いわばエレクトロ・ポップ・デュオである。
Everything/クライミー・フィッシャー
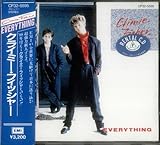
Amazon.co.jp
まず最初にネイキッド・アイズなる
デュオがあった。
バグルズに始まって(異論は認める)
OMDやヒューマン・リーグ、あるいは
ユーリズミックス辺りが押し上げた、
いわば正当な(というのも変だが)
シンセ・ポップの流れに乗ったサウンドを
作り出してくるユニットだった。
ネイキッド・アイズ――剥き出しの眼球。
なんだかダリの絵みたいだけれど、
この彼らの代表曲となったのが、
バート・バカラックの手による
Always Something There to Remind Me
(邦題、以下同じ:『僕はこんなに』)
なる楽曲のカヴァーであった。
このバカラックは、いわずもがなだが、
アメリカの作曲家である。
ディオンヌ・ワーウィックへの
楽曲提供が一番有名なのだけれど、
ほか、メジャーなところを挙げておくと、
カーペンターズの(They Long to be)
Close to You(『遥かなる影』)、
BJ.トーマスのRaindrops Keep
Falling on My Head(『雨にぬれても』)
それからクリストファー・クロスの
Arthur’s Theme(Best that You Can Do)
(『ニューヨーク・シティ・セレナーデ』)
辺りになるだろうかと思う。
まあだから、だいたいこんな感じの、
ある種上品で、叙情にあふれた
甘めのメロディー・ラインを
最も得意とする方である。
で、この彼の旋律を、
彼らネイキッド・アイズは
純正のシンセ・ポップに
仕上げてしまった訳である。
原曲はルー・ジョンソンとか、
サンディー・ショウといった方たちが
歌っていたらしいのだけれど、
何せ64年のことなので、これらは未聴。
そういう、当時からしてもうすでに
20年近く昔の楽曲を、彼らは見事に、
いわば時代のスタイルで解釈しなおし、
甦らせたという訳である。
もちろんこれ、なかなかの名曲である。
あともう一点ここで記しておかれるべきは、
この時代にシンセサイザーが進歩して、
複数の音色を、一つの操作で
鳴らせるという機能が加わっている点だろう
だからユニゾンの旋律であれば、
指一本の操作で生み出すことが
できるようになった訳である。
なるほどこのAlways Something~の前奏、
83年の曲なので、いわれてみれば、
いわゆるオーケストラル・ヒットの
走りであったのかもしれないとも思う。
オーケストラル・ヒットとはだから、
あたかもオーケストラの全体が
一つの音を鳴らしているような音色のこと。
わかりやすいのはたぶん、
マイケル・ジャクソンのBadの
あのイントロであろうかと思われる。
しかし残念なことに、
このネイキッド・アイズは
二枚のアルバムを発表しただけで、
85年には解散の憂き目を見てしまう。
というか、どうやら契約上の問題が起きて、
二人で活動を続けていくことが
できなくなってしまったというような事態が
水面下で起きていたらしいのだけれど、
詳しい経緯まではさすがにわからなかった。
という訳で、その片割れの、
ロブ・フィッシャーなる
サウンド・クリエイターが、
新たにサイモン・クライミーなる
シンガー/ソングライターを
パートナーに迎えて立ち上げたのが、
このクライミー・フィッシャーだったのである。
こちらのネーミングはそのまんまだが。
このユニットのデビューは86年のことである。
まず今回ご紹介のThis Is Meが
本国でシングルとしてリリースされた。
ファースト・アルバムの登場は翌87年。
で、このアルバム、結構出来がよいのである。
その証拠に、という訳でもないが、
何故かはよくわからないけれど、
南アフリカ共和国で、
チャートの一位を獲得したりもしている。
オープニング・トラックは
Love Changes Everything。
一時期車のCMで流れていたので、
あるいはこちらの方に
聞き覚えのある方も
少なくないかもしれないとも思う。
で、今回取り上げたThis Is Meは
B面頭の収録である。
この曲の冒頭の、ギターのパターンが、
極めて気が利いている。
ヴォーカルも、ちょっと前回の
スクリッティ・ポリッティの
グリーンと似た感じのウィスパー・ヴォイス。
クルーナー唱法とは少し違うとも思うけれど、
でも手触りはそんな感じ。
この辺り、好き嫌いが分かれるところ
だろうなあとは、確かも思いもするけれど。
僕はこのサビの、ブラスっぽいパートが、
ヴォーカルを追いかけて鳴る箇所が
なんだかとても好きである。
アルバム全体にアレンジもドラマチックだったし、
ネイキッド・アイズ時代の
アイディアの多彩さもきちんと継承されていた。
ここまでに触れた二曲のほかにも、
Rise to the Occasionとか
Break the Silenceとか
結構好きなトラックが多かったので、
二枚目のCOMING IN FOR THE KILLも
ちゃんと聴いた。
でもこちらは、正直あまり印象に
残るような曲がなかった。
実際、チャート・アクションもセールスも
相当落ち込んだようである。
なるほど特にアルバムの後半になると
いささか黒っぽさを意識し過ぎて、
楽曲がちぐはぐになっている感が拭えない。
批評家にもこの点を指摘され、
アメリカのマーケットに
媚び過ぎなのではないか、くらいに
まあいってしまえば酷評されたようでもある。
確かにこの、どこかディスコっぽい
女声コーラスは余分かもしれない。
その後ユニットはほぼ
自然消滅してしまい、
キー・マンのロブ・フィッシャーは、
この前来日したリック・アストリーの
ソングライターなどとして仕事を続けるものの、
99年には42歳の若さで、大腸ガンのため
急逝してしまっている。残念なことである。
一方のサイモン・クライミーの方は
プロデューサーとしての進路を目指し、
90年代にはあのクラプトンに見出され、
一時期は彼の片腕ともなっているようである。
ちなみにSMAPの「世界に一つだけの花」の
次のシングルとなった
「友だちへ」なるトラックで、
このサイモンはクラプトンとともに、
作曲者の位置に名前を連ねていたりする。
また、ネイキッド・アイズの方の
シンガーだったビート・バーンなる方が、
近年、自身のソロ・プロジェクトとして、
このネイキッド・アイズの名前を
復活させているようでもあるが
もちろんこちらは手が伸びてはいない。
たぶん亡くなってしまったフィッシャーが、
ネイキッド・アイズにせよ、
今回のクライミー・フィッシャーにせよ、
そのサウンドの要を担っていたことは
たぶん間違いがないだろうと
思われるからである。
さて、ではお約束のトリビアである。
村上春樹さんの『カンガルー日和』の中に
「バート・バカラックはお好き?」
なる短編が収録されていたことは、
たぶんここに来てくださっている向きには、
十分ご承知のことなのではないかと思う。
で、今回はこれをトリビアにして
本稿を締めるつもりだったのだが、
どうやら同作品、
現在は「窓」と改題されているらしい。
理由までは残念ながらわからなかった。
タイトルを変えたくなる、
あるいはある種の事情で
変えざるを得なくなることは、確かにある。
でも僕自身は、やっぱり最初につけたのが
一番よかった気がするなあ、と、
後悔してしまう場面の方が
結局は多いように感じている。
いや、もちろん個人的な感想ではあるし、
そんなにしょっちゅうとっかえひっかえ
しているようなつもりも、
まだそんなにないのだけれど。
それでも歯切れが悪くなることは確かか。
ついでなのですみません。
自著の話であれですが、
『追憶の雨の日々』と
『レインデイズ』は同じ作品です。
あと『ビザール・ラヴ・トライアングル』は
文庫化の際に表題作を取り替えています。
不要な混乱をされてしまった方、
あるいは両方買ってしまったという方には
慎んでお詫びを申し上げます。
背景はいろいろあるのですけれど、
最終的にはやっぱり僕がうんといっています。
申し訳ない。