思わないでもないのだけれど、
トーマス・ラングというバンドである。
なお、本記事は、同姓同名の
オーストラリア出身のドラマーとは
まるで関係がないので念のため。
Scallywag Jaz & More/Thomas Lang
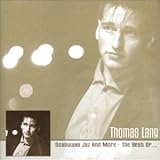
¥1,055
Amazon.co.jp
87年に登場したデビュー・アルバムである。
この作品がとにかくやけに気に入って、
当時結構、というか相当ひいきにしていた。
新譜が出たら無条件でとにかく買ってみる
数少ないアーティストのリストにも入れていた。
もっともその機会は、出会いの一枚を除く
結局一度しか訪れてはくれなかったのだけれど。
さて、このトーマス・ラングなる呼称は、
バンド全体を指しているのと同時に
リード・シンガーのフル・ネームでもある。
ちょっと違うけれど、ボン・ジョヴィとか、
もしくはヴァン・ヘイレンとかと、
ある意味似たアプローチだったといえよう。
ちなみにラングはリヴァプールの出身である。
もちろんあのビートルズを産んだ町である。
しかしながらこのバンドのサウンドは、
マージー・ビートという言葉では形容しがたい。
むしろ明るいという表現からはほど遠い。
収録のどの曲もどの曲も、切なげというか、
物悲しくて、しっとりとしている。
だから当時はこのバンド、男シャーデーなんて
表現のされ方で、レーベルから紹介されていた。
まあ、十分にわかる。
端的にいってそういう音楽なのである。
ところでこのSCALLYWAG JAZというタイトル、
決して僕のスペルミスではない。
あえてjazzという綴りから、
zを一つ落としてあるのである。
ちなみにこのscallywagという形容詞、
ならず者の、とか、手を抜いた、とか、
あるいはぞんざいな、といった意味なのだそう。
しかしながら僕自身は、このアルバム以外で
使われている場面をほぼ目にしたことがない。
だからとにかく、たぶんではあるのだけれど、
気を張ってやったジャズじゃないんだけどさ、
みたいな、ある種の照れといおうかなんというか、
そういうニュアンスが、このタイトルには
込められているのではないかと思っている。
なるほどそういう感じの音なのである。
それこそベースはフレットレスだし、
ドラマーは時折ブラシも使っている。
全編に目立ってくるのは、ギターではなく、
ストリングスとサックスと
それからアコースティック・ピアノである。
ところがこの編成が、彼らの書くトラックに
極めてマッチしているのである。
最早ロックでは絶対にない。
けれどジャズにもなりきれはしない。
結局のところ、ポピュラーミュージックの域から
はみ出してしまうこともしてはいない。
こういうある種の、よくいえばぎりぎりさ、
中途半端ともいいきれない微妙な匙加減が
僕の場合、どうにも琴線に
引っかかってくるらしいのである。
たぶんブロウ・モンキーズに通じるセンスを
潜在的に持っていたバンドだったのではないかと
当時も今も思ってはいるのだけれど。
ただ欲をいえば、少しだけ
華やかさに欠け過ぎた。
レイト・ナイト・ソングスなんてコピーが
スリーブには記載されているけれど、
確かにその通りで、いわばこのアルバム
徹頭徹尾ダウナー系である。
決してチアー・アップはしてくれない。
もちろんこれもあえてなのだろうけれど、
アルバム全編がジャズに寄り過ぎて、
ダンサブル、ファンキーといった要素が
あんまり、というかほぼ聴こえてこないのである
だから夜、それも日付の変わる前後くらいの
深夜に聴くのが
一番似つかわしいように思えてしまう。
それこそ灯りをすっかり落とし
一人で耳を傾けるべき作品なのである。
彼らがいまいちメジャーに
なりきれなかったのには
たぶんその辺の理由も
あるのではないかと思っている。
それでも今回のこのHappy Manは、
やはり名曲なのである。
タイトルとは裏腹に、
曲調は全然ハッピーではない。
明るくなどなりはしない。
ストリングスに寄せた音色の
シンセサイザーが、
冒頭から繰り返してくる、
シンプルなラインが強く印象に残る。
展開も十分にドラマチックである。
そして、サビの歌詞はこんな感じである。
君が僕のアドヴァイスに耳を貸し
賢明さなるものに敬意を持ってくれるのなら
きっと僕は幸福な男になれるのだろうに。
シニカルというかなんといおうか。
最早これはラヴソングですらないだろう。
端的にいって、自由奔放な恋人に
振り回されざるを得ない男の、
ある種の恨み節であろう。
ところが、これがそれなりに
カッコよく聴こえてきてしまうところが
やっぱりシンガーの表現力であり、
このバンドのセンスだったのだと思う。
ほか、タイトル・トラックも秀逸だし、
LP当時にはクロージング・トラックだった
Injuryなる曲もかなり好きだった。
アルバム中唯一のカヴァー作品が
四曲目のMe and Mrs. Jonesで、
オリジナルは、アメリカのビリー・ポールなる
ソウル・シンガーの72年のヒット曲である。
もうずいぶん昔になるけれど、一時期本邦でも、
某オーディオ・メイカーのCMソングに
同曲が起用されていたようにも記憶している。
タイトルからお察しかもしれないが、
これ、人妻との不倫の歌である。
だから、こういうのがハマってしまう
タイプのバンドなのである。
なお、90年のセカンドアルバムでは、
あの007のFrom Russian with Love
(『ロシアより愛を込めて』)の
カヴァーを披露したりもしている。
LITTLE MOSCOWと題されたこちらの一枚は
残念ながらデビュー作の衝撃を
塗り替えてくれるほどの出来ではなかったが。
彼らはさらに、90年代に入ってあと一枚だけ、
カヴァー・アルバムを発表している模様である。
こちらは残念ながら僕は、
手を伸ばすことができなかった。
現在はこのトーマス・ラングは、
バンドではなくシンガーとして、
時折地元リヴァプールで、
ステージに上がっていたりもするようである。
さて、では例によっての横道、
ではなくて、トリビア。
007の主題歌といえば、個人的には
ウィングスのLive and Let Dieと
DDのA View to a killとが
まず真っ先に浮かんでくるのだけれど、
実は95年の『ゴールデンアイ』の
主題歌が少なからず異色である。
シンガーはティナ・ターナーで、たぶん
What Love Got to Do with Itの大ヒットを
受けての起用だったのだとは思うのだが、
驚いたのは、このGoldeneyeなる楽曲、
U2のソングライター・チーム、
ボノとエッジの手によるものなのである。
いや、ボノも007とか見るんだ、と、
違和感というほどでもないが、
ちょっとだけ不思議に感じたものである。
なお、この『ゴールデンアイ』から
ピアース・ブロスナンが
五代目ボンドとして登場している。
やや失速気味だったシリーズの人気を
十分に回復することに成功し、
さらには四作品にわたって出演して、
06年に現在のダニエル・クレイグに
バトン・タッチするまでの期間を
きっちりと支えた形となっている。