当時ブロードウェイを舞台にした作品を
書いてみたいなと考えていて、取材と勉強を重ねていた。
例えば『コーラスライン』とか『フラッシュダンス』とか
あるいは『フェイム』とか、とにかくあんな感じの世界を、
日本語で再現できたら、たぶんかなり新しいし、
何より僕自身が楽しいんじゃないかなと考えていたのである。
――まあ今となってみれば、まったくもって無謀である。
もちろんモチーフはだから、当然ミュージカルである。
そういう訳でレコードショップでも普段は足を運ばない
そのジャンルの作品を集めたコーナーを頻繁に物色していた。
ガーシュイン、ポーター辺りの名前は一応知ってはいたけれど
ソンドハイムなる開祖みたいな存在はこの時期に知ったし、
ロイド=ウェーヴァーの凄さについても
認識を新たにしたものである。
そんな中、棚に面陳されていて僕の目に飛び込んできたのが、
この映画『レント』のサウンドトラック盤だった。
レント/(オリジナル・サウンドトラック)
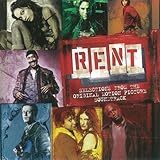
¥1,080
Amazon.co.jp
もちろん店員さんの手書きのキャプションも、確かに
つけられてはいたのだけれど、それだけでなく何故か惹かれた。
何の予備知識もなかったにもかかわらず、
この一枚は絶対に間違いがない気がしたのである。
ある種呼ばれたといってよい。だからほとんど迷いもせずに
気がつけば手に取ってレジへと運んで購入していた。
帰宅して一曲目をかけてすぐ鳥肌が立った。
久し振りにすごい音楽に出会えたと思った。
そのトラックが、このSeasons of Loveなのである。
たぶん皆さんもテレビか何かで
耳にしたことがあるのではないだろうかと思う。
何度か日本語でもカヴァーされているようだし、
何より缶コーヒーのCMソングとして今も頻繁に流れている。
今ザッケローニ監督が出演している、あれです。
ミュージカル『レント』は96年のトニー賞で
作品賞以下四部門を受賞し、当時歴代7位となるロングランを
軽々と成し遂げた作品である。ちなみにトニー賞とは、
ミュージカルの分野のアカデミー賞のようなものである。
だがこの作品が今なお伝説的であるのは、
ほかに大きな理由がある。
同作の全曲を作曲したジョナサン・ラーソンなる人物がいる。
のみならず、脚本もすべて彼の手による。
極めて才能と閃きに恵まれた人だったのだと思う。
『レント』の音楽がすごいのは、それまでミュージカルという
分野とは基本的に無縁だった、ロックンロールやソウル、
リズム&ブルースにゴスペル、フォークロック、
あるいはディスコ・ミュージックなどのエッセンスを
極めて大胆に取り入れているのみならず、タンゴやチャチャ、
そして原典となったプッチーニまでをも踏まえ、時に引用し
かつそれらの音楽の全体を、見事に統御している点にある。
サントラを聴いただけでもそれがわかるし、
映画なり舞台なりでストーリーの進行とともに耳を傾ければ、
一層鮮明に伝わってくるはずである。
『レント』のプロットは、基本的にプッチーニのオペラ
『ラ・ボエーム』を下敷きにしている。
この舞台を90年代初頭前後のニューヨークへと移し、
当時同市が各所で進めていた、不法占拠者への退去勧告、
あるいは強制排除などといった要素を取り入れ
全体を再構築しているのである。
主人公は時にボヘミアンと称される、アーティストを目指し、
貧窮した生活に甘んじている若者たちである。
だからこのレントとは、普通に家賃のことである。
そして、ここからが本当の伝説なのである。
ラーソン自身、作曲家としての大成を夢見ながら
都市の片隅に暮らす、現代のボヘミアンたちの一人だった。
彼はこの『レント』を、実に七年という歳月をかけ
独力で書き上げた。だが完成したからといってすぐ、
無名の新人の作品がステージに上るはずもない。
どのような努力や苦労がそこにあったかはわからないけれど
ついに彼の夢が現実となり、ミュージカル『レント』が
オフ・ブロードウェイのワークショップながらもついに
正式な舞台として上演される、そのまさに文字通り前夜に、
このラーソンは自室で死体となって発見されるのである。
死因は胸部大動脈瘤破裂だった。
享年35歳という若さである。
もちろん僕自身も、こういった内容は
サントラに出会った後から知った。
繰り返し聴きほれながら、命を賭けた作品というのは
あるいはこういうものなのかな、などと
些か在り来たりな、でもほかに形容しようのない
悲痛さとも違う思いさえ頭によぎったものである。
ミュージカル『レント』はこういった背景とも相俟って、
後に「レント・ヘッド」と呼ばれることになるファンにも
強固に支えられ、前述のような金字塔をたちまちに成し遂げ、
幾人かのスターを生み、ついには映画化される運びとなる。
ほどなく僕も、これが日本で06年に公開されることを知り、
当時つてのあった映画雑誌に頼み込んで試写会にもぐり込み、
のみならず同誌に紹介記事を書かせてもらうことまでした。
オリジナル・キャストでは残念ながらなかったけれど、
今はなき東京厚生年金会館での来日公演にも足を運んだ。
だから僕も、間違いなくレントヘッドの一人なのだと思う。
ちなみに作曲家、作曲家といってこそいるけれど、
あちらの場合わりとはっきりと、ソングライターと
コンポーザーとの二種類に区別されている。
一曲ずつの詞とメロディーを作るという行為は
単にソングライティングと呼ばれ、
コンポーズの方は、ミュージカルやバレエ音楽、歌劇、
交響楽や、あるいは映画音楽の全体などの場合に用いられる。
要はある意味、きちんとスコアが書ける人が
ラーソンが目指していたところのコンポーザーなのである。
だから後年あのポール・マッカートニーが
クラシック音楽の発表に取り組んだりしたのは、
ひょっとしてそんな辺りも絡んでいたのではないかと
時に思ったりしないでもない。
まあ、多少穿ち過ぎかも知れないけれど。
あの出会いからもすでに十年近くが過ぎようとしている。
発表からで数えても18年、
おそらく譜面の完成を起点とすれば
たぶん20年以上の歳月が過ぎているのだと思う。
それだけの時間をかけ、このSeasons of Loveという曲が
どうやら一つのスタンダードになりつつあることは、
少なくともこうやって電波に乗せられているのを
今になっても繰り返し見つけられることは、
正直本当に喜ばしい。
それと同時に、まあ多少は自惚れになってしまうのだが、
相も変らぬ自分のミーハーさ加減も、
ひょっとしてまだまだ捨てたものでは
ないんじゃないかな、と鼻を高くしたりもするのである。
余談とは重々承知しているのだけれど。
僕にとって非常に重要だったこの出会いを演出してくれた
駅前のビルに入っていたタワーレコードさんが、先頃ついに
撤退してしまったのは、残念を通り越してただ悔しい限り。
同時に、この事態は決して対岸の火事ではないんだよな、
といったような思いを日々新たにせねばならない毎日である。
RENT/レント [Blu-ray]/ロザリオ・ドーソン,テイ・ディグス,ウィルソン・J・ヘルディア
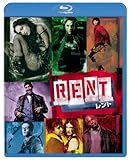
¥2,571
Amazon.co.jp