
等伯 上 (文春文庫)/文藝春秋- ¥756
- Amazon.co.jp
安土桃山時代から江戸時代初期に活躍した絵師、長谷川等伯。
能登で絵仏師として名を成していた等伯が、京で活躍する狩野永徳らの絵に触発され、天下一の絵師になるという野望をを抱いて京へ上るところから始まり、最高傑作とされる「松林図屏風」が生まれるまでの波乱に満ちた半生を描いた作品です。
長谷川等伯というと、狩野派とのライバル関係という一面を抜きにしては語れませんが、それが実際にどのようなものであったのか...
このあたりは、秀吉、千利休、近衛前久など、両派を取り巻く人物との関係をも含めて、少し前に読んだ山本兼一さんの狩野永徳を描いた小説「花鳥の夢」と比較しながら読むと、より立体的に見えてきて面白かったです。
たった一代で狩野派の牙城を切り崩し、肩を並べるほどの絵師にのし上がった等伯。
足利将軍家が没落し、信長、秀吉、家康と、目まぐるしく天下人が変わったこの時代、彼らの栄華を彩った絵の世界でもまた同じような下剋上があったというわけですが、絵画にしても茶の湯にしても、まつりごとと切り離しては考えられないほどに深い関わり合いがあり、そういったところに着目してみると、歴史がまた少し違った風に見えてきます。
そして、この小説の最大の見どころは、牧谿の観音・猿鶴図に魅せられ、その境地に迫ろうと愚直に模索し続けた等伯が、いかにして伝統的な画法の壁を打ち破り、「松林図屏風」という新たな画境に到達したのかというところです。
誰もが心を洗われるこの絵は、気嵐に霞む故郷七尾の松林を牧谿を超える表現力で再現したものあるとともに、日蓮宗に帰依し、春屋宗園や千利休との交わりから禅にも学んだ等伯の宗教的な一つの到達点とも言えるのですね。
ここは作者の等伯観が最もよく出ているところかと思いますが、この絵を描き切った場面の突き抜け感は、初めてこの絵を間近に見た時の感動を思い出させます。
「松林図屏風」には下絵説もありますが、これもこの場面の中で実にうまく落とし込んでいて、ニヤリとしますが、いや、実際、本当にこんな感じだったのかもとも思ってしまいます。
もう一度、「松林図屏風」を観たくなりました。
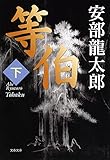
等伯 下 (文春文庫)/文藝春秋- ¥756
- Amazon.co.jp

花鳥の夢 (文春文庫)/文藝春秋- ¥821
- Amazon.co.jp