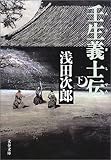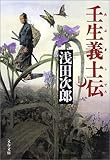
壬生義士伝 上 (文春文庫 あ 39-2)/文藝春秋- ¥700
- Amazon.co.jp
南部の脱藩浪士で新撰組隊士であった吉村貫一郎の半生を描いた浅田次郎さんの代表作の一つ。
北辰一刀流の免許皆伝という剣の腕前を持ち、学問にも秀でており、新撰組の中でも一目置かれる存在であった一方、銭には呆れるほど卑しい。
しかし、そこに私欲はなく、着物が古び、刀が痩せ細っても、手にした銭のほとんどすべてを国許で貧しく暮らす妻子へ仕送りし、目の前の貧しい者、飢えた者には手を差し伸べる。
元新撰組隊士や盛岡での教え子らの証言と、死を目前にした本人の回想によって語られる一人の義士とその子供たちの物語です。
土方歳三も最後まで徳川のために戦うことで自らの士道を貫いた人ですが、妻子を守ることを自らの使命とした吉村貫一郎の生き方もまた一つの士道。
”妻子を養うために主家を捨てる。しかし恩と矜りとは決して忘れぬ。守銭奴と罵られ嘲られても、飢えたものに一握りの飯を施す。一見して矛盾だらけのようでありながら、奴はどう考えても、能う限りの完全な侍じゃった。”
吉村を疎ましく思いつつもその侍としてのあり様を認める斎藤一の言葉が特に印象的でした。
そして新撰組としての最後の戦いに敗れ、満身創痍になりながら駆け込んだ大阪の南部の蔵屋敷。
ここで腹を切るようにと与えられた一間で、薄れゆく意識の中、己の使命から解き放たれ、一人胸の中で後悔や未練を吐露するその姿には、武士としての潔さはなく、もう、どうしようもなく惨めで無様なんですが、最後まで妻子を守るという自らの矜持を捨てぬその姿は、やはり侍。
時代が違えば、考え方を変えれば、もっと楽に生きられただろうに、死なずに済んだだろうに、なんでこんな...という思いが繰り返し押し寄せる悲しい生涯ですが、そういう思いを抱かせるのはやはりそこに完全な侍を見るからなんでしょうね。
討幕だ佐幕だ、尊王攘夷だ開国だと、大義で動いていたような時代ではありましたが、実際、身分が低く、貧しい武士の等身大の姿とはこのようなものではなかったかと想像してしまいます。
余談ですが、この小説、テーマといい、構成といい、百田尚樹さんの「永遠の0」によく似ているなと思ったら、「永遠の0」は、「壬生義士伝」のオマージュなのですね。
「壬生義士伝」を読んだ後で、「永遠の0」を読んでいたら、随分と印象が変わっただろうと思います。
たまたまこういう順番になっただけですが、この順番でよかった...
- ¥700
- Amazon.co.jp