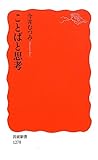
ことばと思考 (岩波新書)/今井 むつみ- ¥840
- Amazon.co.jp
「人間の思考は言語に依存する」ということを提唱した「サピア=ウォーフ仮説」。
エール大学の言語学者エドワード・サピアは、人間は特定の言語の支配を受けている存在であるとした上で、現実世界は集団の言語習慣に基づいて無意識的に構築されたものであり、言語が異なれば、その世界も違ったものになるという考えを示しました。
そして、そのサピアの弟子であるベンジャミン・ウォーフは、アメリカの先住民ホピ族の言語であるホピ語などの実証的研究を通じて、人間の思考が言語と切り離して考えられないものであるということを改めて示しました。
それが「サピア=ウォーフ仮説」です。
この「サピア=ウォーフ仮説」の是非については、これまで多くの研究がなされ、主に言語学や人類学の研究者によって行われたフィールドワーク的研究によって、驚くべき言語の多様性が見出されてきました。
本書でも、この「サピア=ウォーフ仮説」に基づいて、「異なる言語の話者の間で認識や思考が異なるのか」という観点から行われた研究の成果を紹介しながら、人間の認識や思考が言語の影響を受けているということを解説しています。
モノの分け方、動作の分け方、色の分け方、位置関係の表現、数の名前の付け方...などなど、人間の認識や思考が如何に言語に引っ張られてたり、歪められたりしているかということが、具体例とともによくわかります。
ただ、それはそれで面白いのですが、本書においてそれは前振りであり、むしろそれと同時に展開されている認知心理学や発達心理学の観点からのアプローチの方が主題というべき構成になっています。
その中で特に面白いと感じたのは、子供の認識や思考が、ことばを覚えることによってどう変化していくかという点について。
これもまた具体的な調査・実験の成果を交えて紹介しているのですが、異なる言語の話者という、認識や思考のパターンの出来上がってしまった者同士の比較よりも、一人の人間が言語を習得していくことによって起こる認識や思考の変容のほうが、ダイナミックでかつ、ことばと認識、ことばと思考の関係を考える上でも重要な観点なのではないかと思います。
普段何気なく使っていることばが、人間の認識や思考にいかに影響を及ぼしているかについて、様々な視点から解説するこの本、個人的にかなり”アタリ”の一冊でした。