
世に棲む日日〈1〉 (文春文庫)/司馬 遼太郎- ¥580
- Amazon.co.jp
幕末の尊王攘夷思想の源泉である吉田松陰と、その思想の後継者のひとりである高杉晋作を描いた作品です。
「世に棲む日日」というタイトルは高杉晋作の辞世の句から連想してつけたそうですが、内容的にもどちらかというと高杉晋作に重きが置かれているようです。
年代順に当然、松陰の話から入るわけですが、松陰という人物が肌に合っていないのか、松陰という人物に正対してその人生を掘り下げていこうというような熱意があまり伝わってきません。
何か、別のこと(この作品でいえば高杉晋作ということになるわけですが)を書きたいがために、その思想的背景として松陰を描いている、そんな雰囲気が感じられます。
(読みながら感じていたこの疑問は、文庫版あとがきを読んで、なるほどと納得するわけですが...)
方や高杉晋作。
こういうキャラが好きなんでしょうね。
動けば雷電の如く
発すれば風雨の如し
衆目駭然、敢て正視する者なし
これ我東行高杉君に非ずや
という高杉晋作を評した伊藤博文の言葉どおり、期を見るに敏で、動き出せば仲間を巻き込み、「革命を起こすには一旦乱世を演出しなければならない。そのためには長州をつぶしてもよい」という覚悟で苛烈に行動する。
かと思えば、芸者をはべらせ酒に浸るゴロツキのような日々を送ってみたり、突然頭を丸めてみたり、外国へ行くと言ってみたりと、人々から「鼻輪のない牛」と陰口を言われるような放胆な行動をとる。
それでいて藩や藩主、高杉家への忠義は人一倍強く、終生一長州人、一書生として生きた晋作が、実に生き生きと描かれています。
司馬さんは、吉田松陰は、思想的正義を日本の歴史上はじめて完成させ、その思想に殉じた思想家であり、高杉晋作はその後継者と言われながらも、決して思想に殉じた思想家ではなく、現実を冷静に見つめて行動した現実主義者であると見ています。
思想から実行へという継承、そこには元来の個性や発想の違いもありますが、没年にして8年というわずかな時代のずれが織りなす綾でもあるということがよくわかります。
そして、なにより、この2人の傑物を生み出したのが、薩摩や土佐とはまた違ったこの長州の理屈っぽく、かつ寛容な藩風あってこそというところにも、歴史の面白さを感じます。

- 世に棲む日日〈2〉 (文春文庫)/司馬 遼太郎
- ¥580
- Amazon.co.jp

世に棲む日日〈3〉 (文春文庫)/司馬 遼太郎- ¥580
- Amazon.co.jp
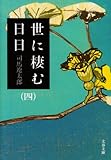
世に棲む日日〈4〉 (文春文庫)/司馬 遼太郎- ¥580
- Amazon.co.jp