アプローチ会の岡本啓二会員による「 人生をなんとか無事にやっていくための爺の戯言 」というメッセージをご紹介いたします。この記事は、改訂版の「しなれんでよ」にも掲載いたします。

生まれて物心がついてきて成長していく過程で徐々に自分の能力とか才能が開花していくわけだけれど同時に周りの優秀な同年代との差という物にも気付かされるよね?学力・運動能力・その他諸々、そして周りの人たちに対しての受け答え、振る舞い方等、嫌われないようにしないとね(これが案外むずかしい)その都度壁に当たった時にちゃんと乗り越えられればよいのだけれど、上手く出来ないとそこから抜け出せないまま年齢を重ねてしまうんだね、これが一番厄介なトラウマになるね、だんだんと自分がイメージしていた未来と乖離してきて、こんなはずじゃなかったと落ち込む日々が続くんじゃないかな?(でもこれってほぼ全員でしょ。)
たとえば、スポーツが得意でどんどん頭角を現してきたときライバルに勝てなくなってくるとか、取り返しのつかない怪我をしちゃったり、学力の場合だと希望する学校に入れない。資格取得の試験に受からない等?優秀であればあるほどショックが大きくて立ち直れない感じかな?しかしこの文章を読んでいるみなさんに伝えたい、夢を見るのはOKだけどだいたい15歳位までには自分のレベルはどのくらいか?自分でわかってくるでしょ。そこからは自分の能力・才能を客観的に自己分析して人生をやっていけば良くない?あのね、大きな意味で人生に失敗は許されないんだよ、そして、全てにおいて賞味期限とか締め切りがあるってことをしっかり踏まえないとね、(今に見ておれ本気出せば私はできる子なんだよじゃないっちゅうのよ)
持たざる者の人生は、出来れば大学まで出て、小さくても良いので福利厚生のしっかりした職場を選んで定年まで勤めあげて、65歳から厚生年金を満額貰うのが王道だね。金額に差はあると思うけど20年貰い続けたら5,000万円に迫るか超えるか?じゃないかな?知らんけど。これって宝くじに当たるのと同じじゃない?しかも超確率の悪い「くじ」じゃなくて自分の努力次第、レールから外れないように気を付ける。それだけでもれなく付いてくるんだよ。だってもう働いてないのに口座に突然入金なってるんだよ、それも定期的にね、配偶者の口座にもね、最高でしょ!そりゃギャンブルみたいな、一攫千金狙うような人生送りたいならお好きにどうぞってなものですけれどね。

「アサーション とは」
松本好恵会員
学校や職場、また地域などさまざまな人間関係の中で、日々言葉を交わしながら私たちは暮らしていますが、「こんなに言っているのにどうしてわかってくれないのだろう」「あの時こんな気持ちを言いたかったのに言えなかった」と思うこともしばしばあるのではないでしょうか。そのコミュニケーションを円滑にするためのスキルとして「アサーション」が重要であるといわれています。アサーションとは、自分も相手も尊重しながら自己主張するコミュニケーション手法をいいます。
アサーションには「非主張型(ノン・アサーティブ)」、「攻撃型(アグレッシブ)」「アサーティブ」の3つのタイプがあります。
「非主張型」は自分よりも他者を優先するなど、自己犠牲的な傾向があり、相手に尽くしがちです。自分のことは後回しになり、嫌なことがあっても、黙ったり我慢したりするのが特徴です。そのため、自尊心が低い・自己否定的・引っ込み思案などの傾向が見られます。アニメ「ドラえもん」で例えると、のび太が非主張型といわれています。
「攻撃型」は、自分のことだけを考える傾向にあります。一方的に主張することが多く、何か失敗をしても強がったり、責任転嫁をしたりするのが特徴です。そして他人のことは無頓着で、話を聞かない・否定する・見下して支配的になる様子も見られます。またいきなり怒鳴ったり、暴力的になったりもします。「ドラえもん」では、ジャイアンのイメージです。
「アサーティブ」は、非主張型や攻撃型と違って、自分・相手どちらも大切にします。そのためアサーションとは、このタイプのことを表しています。アサーティブタイプは自分の行動に責任を持ち、自発的に動きます。また自分の気持ちに正直で、話すべきことをしっかり伝えられるところも特徴のひとつです。相手に対しては、話を聞いて歩み寄ろうとする傾向があります。たとえ意見が食い違っても、柔軟に対応し、解決策を見つけようとします。「ドラえもん」では、しずかちゃんがこれにあたります。
アサーティブになるためのポイントがいくつかあります。
1.自分の気持ちを把握する
アサーティブになれない理由として、自分の気持ちを把握できていない場合があります。無意識のうちに、欲望を抑制してしまっているのです。そのため、まずは怖がらずに自己開示することが大切でしょう。自分の気持ちがわかるようになると、アサーティブな行動もしやすくなります。
2.周囲や結果を気にしない
アサーションで重要なことは、自分の言いたいことを適切に伝えることです。それを受け取るかどうかは相手次第であり、私たちが支配できるものではありません。たとえばずっと相手の顔色をうかがっていると、何も言えなくなってしまうでしょう。またはストレスが溜まって、ほかの人にイライラをぶつける可能性も考えられます。このように周囲や結果を気にしていると、アサーティブな行動はできないので注意が必要です。
3.アサーション権を使う
アサーション権とは、「誰もがアサーションする権利を持っていること」を意味します。この考え方は、自他尊重の自己表現を大切にするアサーションにおいて、とても重要です。
・私たちは誰からも尊重され、大切にされる権利がある
・私たちは誰もが自分の行動を決め、その結果に責任をもつ権利がある
・私たちは誰でも過ちをし、それに責任をもつ権利がある
・私たちには、支払いに見合ったものを得る権利がある
・私たちには、自己主張をしない権利もある
「アサーション」は、言うのを我慢したり、自己中心的になったりするのではなく、自分の気持ちを率直に伝えながら、相手の気持ちも大切にするコミュニケーションのため、良好な人間関係の構築につながるといえます。アサーションを身に付けると、自分に対して正直になれます。これは自己開示を通して、自分が思っていること・考えていることを理解しやすくなるためです。その結果「〜したい」という欲求を、無理に抑制することがなくなります。また相手に「〜してほしい」と、素直に頼むこともできるでしょう。
アサーションを身に付けていく過程で、自分のアサーティブではない考え方にも気づくでしょう。具体的には「〜してはいけない」「〜すべきだ」などです。このような固定概念がなくなれば、自己表現や行動が制限されることもなくなるでしょう。考え方もより柔軟になります。その結果、自信を持ってコミュニケーションができるようになり、自己表現を恐れることもなくなります。
私自身、いきなり身に付けることは難しいですが、3つのタイプを知ることで、今の自分がどれにあてはまるのかがわかるだけでも、自分の気持ちを理解し、相手に言葉を投げかける前に一歩立ち止まって、言葉を選び使うことができるような気がします。しずかちゃんを思い出しながら、人とのふれあいの中でアサーティブを目指していきたいと思います。

「レジリエンス」
徳島文理大学講師 田村幸子
同じストレス状況に置かれても、困難から立ち直る人もいれば、そうでない人もいます。こうしたストレスフルな状況から回復できる力として、近年、レジリエンスが注目されています。この概念が初めて使用されたのは、心理学の分野で、Ruter(1985)の論文です。ネガティブな人生経験やストレスフルな環境において、適応を保つ者もいれば、不適応に陥る者もいるという個人差に焦点を当て、レジリエンスとして捉えられ、精神的回復力とも訳されています。平野(2010)によれば、個人の心理的な強さや成長に焦点を当て、資質的レジリエンス(もともとの特性や資質による)と獲得的レジリエンス(経験や学習から身につける)の 2 つの側面があると指摘しています。
レジリエンスが高い人は、逆境に柔軟かつ建設的に対応し、精神的な健康を維持できると考えられます。逆に、レジリエンスが低い人は、ストレスが精神的な健康に悪影響を与える可能性が高まります。つまり、レジリエンスと精神的健康の間には深い関係があると推察されます。看護系大学の学生を対象に行った自身の研究では、レジリエンスの向上が精神的健康の向上につながる可能性が示唆されました。相談相手の存在と自己理解がレジリエンスを高め、メンタルヘルスの問題に対処するのに有益であることも明らかになりました。
「自己理解」は、獲得的レジリエンスを向上させるために重要であることも分かりました。要するに、レジリエンスを高めるには、自己理解を促進し、個々の強みを活かすサポートが不可欠です。ネガティブな側面も受け入れつつ、リフレーミングを通じて肯定的な視点を持つことが役立ちます。また、自分だけで悩まずに相談できる状況が、レジリエンスを高める一環であると考えます。そして、レジリエンスを高めることにより、メンタルヘルスの問題にも対処していけるのではないかと推察されます。レジリエンスは、人間関係の中で育ちますが、同時に人間関係はストレスの要因ともなり得ます。自分の感情に気づくことは、ストレス対処にもつながります。そして、自分だけで解決しようとせずに誰かに相談できること自体が、レジリエンスが高い状況なのです。
1)平野真理(2010)レジリエンスの資質的要因
獲得的要因の分類の試み‐二次元レジリエンス要因尺度(BRS)の
作成‐パーソナリティ研究 19 巻 2 号

「 ウェルビーイング(志は常に楽しむ)」
中村武光 会員
数年前から「人生100年時代」と言われるようになってきました。男性81歳、女性87歳が平均寿命で、中には100歳まで生きられる方が沢山おられます。人生を座標で表してみると横軸を時間、縦軸を人生の満足度とした時、株価の折れ線グラフのように上げては下げ、下げては上げの繰り返しが想像されます。上げを大きくして、下げを小さくすることの繰り返しであれば、年齢を重ねる毎に自分の人生の満足度は上昇していく事になります。しかし、順風満帆に行かないのが人生です。満足度は物の場合と精神的な面とに分かれると思いますが、自分でコントロール可能なのは、どちらかというと後者の方かと思います。
自分なりに努力はしているのに、一向にいい結果が得られないということも長い人生の中では多々ある事でしょう。そのような時、沈んだ自分の気持ちをどう奮い立たせるか、人によってやり方は千差万別だと思います。私の経験からすれば、「現状をありのままに受け入れる」ということで、自分の精神状態をノーサイドにして、「さあ、これからどうしようかな?」と、進めた方が冷静なポジティブ思考になれると感じました。また、全てを自分1人で解決しようとはせず、周りの意見を聞くことも大事です。身内、親しい友達や先輩等、力を貸してくれる人はいくらでもいるはずだからです。暗いトンネルを過ぎれば、きっと明るい未来に続く道が発見できると思います。
ただし、努力を怠る人に幸せの女神は微笑んではくれません。自分好みの「座右の銘」を脳裏に焼き付けて、目標をもって責任ある行動をし、自分を取巻く人たちには常にリスペクトする気持ちを忘れないことです。
私は、日本という恵まれた環境の中で勉強ができている幸せに感謝しています。月日を重ねる毎に、人生に例える座標の折れ線グラフが右肩上がりに上昇ラインを描いていることを切に願い、今年目標をウェルビーイングといたします。

「不登校の生徒について思う事」
野上和子会員
現在日本をはじめ世界では戦争や災害のため多くの児童、生徒が登校できない状態が続いております。そんな中、学校に行かない、行けない不登校の子供たちに接し、今思う事を綴りたいと思います。
日本では30万人を超える不登校の児童、生徒がおり、その原因はいじめ、ADHD、起立性調節障害、摂食障害、介護問題等様々です。コロナによる長期間の生活環境の変化もこれに拍車をかけ、今やその人数は増加し続けております。LINE相談ではそんな方たちの生の声を聞いており、現在の学校の在り方を考えさせられます。私の回答で少しでも勇気を持ってもらい一日でも多く学校に通ってもらえれば、という思いで行っておりますが、寄り添うつもりが、LINEという限られた枠の中知らず知らずのうちにかえって傷付けてしまったり、余計な事を言ってしまったのではないかと反省することばかりです。
2016年には”教育機会確保法“という法律が制定され、学びの場は学校だけでなくフリースクールや保健室など、様々な取り組みが始まっております。不登校だった生徒がその経験を活かし、養護教諭になったという例もあります。
不登校は学校だけでなく社会全体の問題で、孤立しがちな一人一人に寄り添い決して一人ではない事を伝えないといけません。また、それに伴い保護者への心のケアも必要となり周りの私たちの役割りはとても大事です。LINEによる生の声を、まずは聞く事を意識し、今後は不登校を少しでもなくすべく研鑽を重ね精進して参ります。
アプローチ会に所属しながらあまりお役に立てていない事を心苦しく思っておりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

荒田妙会員
約50年前大学進学の際、福祉を学ぶ道を選んだ。将来、高齢化社会がくるだろうし、色々な人たち人たちが生きている社会、私達は、どう生きていくのがよいのだろうかと思った。選択した心理学では、神谷美恵子氏の「生きがいについて」がテキストでそれを読んでレポートを提出した。先生は、精神科医。ハンセン病療養施設、岡山の長島愛生園で勤務していた。深刻な苦悩を経た人間がどれほどすばらしい精神性、可能性を持っているかを語る。
ハンセン病といえば、何年か前、樹木希林さんの主演の「あん」という映画をみた。差別のこわさ、悪評によって人は人を傷つける。今度「あん」の舞台があるらしいので又、みにいきたいとと思っている。辛い時私は祈る。
社会福祉とは何か、幸せとは何か、生きがいは人によってちがうけれど、日々の個人の生活の中に答えはあると思う。50年考えている。福祉は広範囲であることが生活に直けつしている。災害のニュースをききながら、私は祈った。

「相談して下さいね」の落とし穴
中瀬医院 院長 中瀬勝則
私たち産業医や産業保健師は、職場の自殺予防対策の中で、「何かあったら相談してくださいね」という言葉をよく使う。勿論、私達としては、相談しやすい体制づくりや相談しやすい従業員との関係づくりは、とても重要であると常に認識し、日々の何気ない雑談もできる風通しのよいコミュニケーションの構築を心がけている。しかし、従業員の側では、産業保健職の役割が理解されていなかったり、ひどい時には会社側の人間という見られ方をしている場合もある。実に様々な事情を抱え悩みの中にいる当事者にとって、残念ながら産業保健職である私達は万能ではないし、全ての労働者の自殺を防げるわけではない。防ぎえた自殺と、そうではない自殺の境界は、クリアカットにはいかないのも現実だ。そこで重要になるのが「命の門番」とも位置付けられる現場の支援者である。例えば救命処置で心肺停止時などの緊急時にも、その場に居合わせた現場の人間の行動が、救命の連鎖に繋がり生死を分ける。それと同様に、自殺予防のためには、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)ができる現場の支援者を育てることが重要なのだ。アプローチ会員以外にも、そのような支援者を職場に隈なく配置できる日がくることを夢見て、この活動を続けている。

学校法人野上学園 ブレーメン動物専門学校
理事長 野上 耕一
今、原稿を依頼された瞬間、私はいくばくかのストレスを感じております。
この苦痛は感覚的であり、フィジカルなものとは少し異なる。
それは時間軸の経過と着地点の違いによって左右されますが
今回は比較的短いストレスで終りそうな気がする。
さて
ストレスの語源はdistress(苦痛や苦悩)のDIがなくなった言葉であり
1930年代の研究に起因されている様だ。
あくまで私個人の主観でのお話になりますが
知らぬが仏。知らぬが華。
この言葉に反し、人間というのは色々知ってしまうと、今まで“何となく”だったものが頭の中で勝手にデフォルメ又は増幅されてストレスに感じてしまうようだ。
何事にもネガティブキャンペーンを展開してしまうと、息を吸う事、食事を摂る事
寝る事、等々ジェラシック脳が何も考えず本能のままに行っているフィジカルな事ですら大きなストレスとなってしまっております。
無論何らかの疾病によるものはこれには当てはまりませんが。
ストレスを引き起こすものをストレッサーといいます。
それは“物”であったり、五感的なものであったり、“者”であったり。千差万別です。
人はストレスを少しでも和らげようと人は色々考え故事や格言がうまれました。
万事塞翁が馬。スペイン語のケセラセラ。止まない嵐はない。等々沢山の言葉があります。
人は自分中心。故に自分(細胞)の敵も味方も自分(細胞)であるという事を理解し受け入れる事が肝要かと考えます。
私は老齢期に入りストレスを感じ始めた時、ストレスがあるから生かせれていると
解釈し今に至っております。
そして、書き終えた今、最初に感じた“それ“から解放され様な気がする。

公認会計士 福山正啓会員
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
新年の挨拶を、とのご依頼をいただいたので自分の思う健康と絡めて少しお話をさせていただきます。
「健康」とは?と問われれば人それぞれ答えがあると思いますが、WHOでは「健康」を次のように定義しているそうです。「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。(日本WHO協会訳)」
全てが満たされた状態といわれるとなかなかハードルが高そうですが、当然ながら「肉体的」「精神的」「社会的」の三つの要素はそれぞれに独立したものではなく相互に作用するものであると思います。また、アプローチ会では、上記の三要素を「良い健康」「良いメンタル」「良いコミュニティ」としています。
さて、「良い健康」「良いメンタル」「良いコミュニティ」とはなにか?と少し考えてみました。「良い健康」「良いメンタル」はシンプルに身体的に精神的に健康だということだと思いますが、「良いコミュニティ」とはどんなコミュニティだろうと考えてみました。
「良いコミュニティ」とは「良い健康」「良いメンタル」を持った人の集まり、また、参加者を「良い健康」「良いメンタル」に導くようなコミュニティのことかなというのが自分なりの考えです。そうすると実は健康は自分だけのものではなく、日々接する人たちと共にしていくものなのだと思いました。ということで、自分だけでなく周りの人が元気になってくれるような人間になりたいというのが今年の目標です。

アプローチ会 ✻ 心の相談室
アプローチ会は、LINEで「お悩みの相談」を行っています。
専門的な回答が必要な場合は、専門家(精神科医、看護師、弁護士など)がお答えします。
秘密厳守、無料でのご相談をお受けしておりますので、安心してご相談してください。
ひとりで抱え込まずにご相談してください。
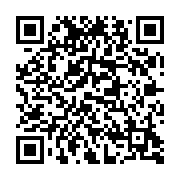
スマホでQRコードをスキャンすると相談業務に入れます。

スマホをお使いの方は、上記ボタンをタップまたはクリックすると相談業務に入れます。
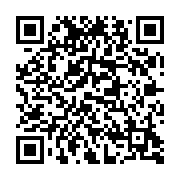
![]()




































