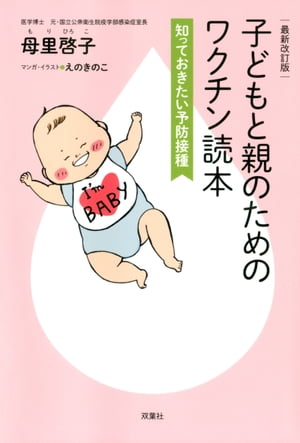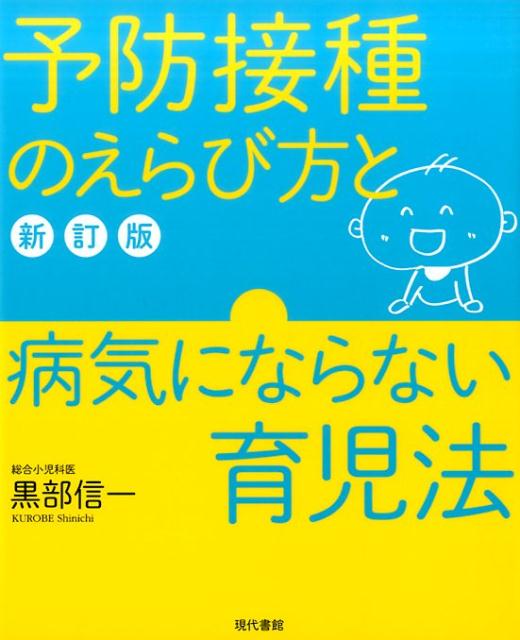生まれた時から歯がある?NICUで発覚した息子の「魔歯」と、その謎の結末
こんにちは、Aoパパです。
NICUで初めてAoと対面した時、ふと口の中に光る小さな白いものを見つけました。
「え、嘘でしょ...歯?」
生まれたばかりの赤ちゃんに歯が生えているという、信じられない光景との出会い。
これは、超レアケースと言われる「魔歯」を持つ息子との、ちょっと不思議な体験談です。
私たちのこと⤵️
息子の口の中にあった謎の"白いモノ"
NICUでの初対面で見つけた異変
432gという超低出生体重で生まれたAo。
保育器の中で小さな体を横たえている姿を見て、愛おしさと同時に不安でいっぱいでした。
面会の際、看護師さんが少しだけAoの口を開けて見せてくれた時のこと。
ふと、口の中に光る小さな白いものが目に入りました。
「これって...まさか歯?でも生まれたばかりなのに?」
信じられない光景に、思わず二度見してしまいました。
この歯、フニャフニャ?普通の歯じゃない違和感
硬くない、不安定な謎の物体
よく見ると、その歯は硬い骨というよりは、なんだかフニャフニャしていて不安定でした。
しっかりと歯茎に根付いている感じでもなく、グラグラしているように見えます。
赤ちゃんの歯といえば、しっかりした乳歯というイメージがあります。
でも、Aoの口にあるものは、そのイメージとは全く違う謎の物体。
「これは一体何なんだろう?」と夫婦で頭にハテナが浮かびました。
主治医からの一言「Aoくんには"魔歯"が生えています」
恐る恐る質問してみると
NICUの主治医の先生に、恐る恐る口の中の白いものについて質問しました。
すると先生は落ち着いた様子で「ああ、これは"魔歯(まし)"ですね」と一言。
魔歯?
初めて聞く言葉に、さらに疑問が深まります。
魔歯(先天性歯)とは
- 生まれた時から生えている歯のこと(医学的には「先天性歯」と呼ばれる)
- 数百人から数千人に1人という、非常に珍しいケース
- 授乳時にママの乳首を傷つけたり、赤ちゃんの舌を傷つけたりするリスクがある
- 自然に抜けることもあれば、グラグラして飲み込んでしまう危険がある場合は、意図的に抜歯することもある
なぜ生まれた時から歯があるのか
先生の説明によると、通常は歯茎の中で成長するはずの歯が、何らかの理由で早く出てきてしまうことがあるそうです。
魔歯は正常な乳歯とは構造が異なり、根がしっかり形成されていないため不安定なのだとか。
超レアケースに遭遇したことに驚きつつも、「また一つ知らないことを学んだな」と思いました。
挿管チューブと魔歯...どうすべきか
邪魔そうに見える魔歯
当時のAoは、呼吸を助けるために口から管を入れる「挿管」をしていました。
そのチューブが魔歯に当たっているのを見ると、「邪魔じゃないかな」「痛くないかな」と親としては心配になります。
先生と「この歯、どうしましょうか?」と話しましたが、特にすぐに抜くなどの具体的な方針は決まりませんでした。
「様子を見ましょう」ということになり、とりあえずそのまま過ごすことに。
魔歯の対応について
授乳に支障がある、赤ちゃんが舌を傷つける、誤飲の危険があるなどの場合は抜歯を検討します。
Aoの場合は授乳もまだ先で、特に問題がなさそうだったため経過観察となりました。
ある日突然、魔歯が消えた!真相は闇の中
謎のミステリー
抜くとも抜かないとも決まらないまま、数日が経過しました。
ある日、いつものようにAoの顔を覗き込むと...「あれ?歯がない!」
きれいさっぱり、あのフニャフニャの魔歯がなくなっていたのです。
結局いつ、どうやって無くなったのかは誰にも分からず。
真相は闇の中へ...なんともミステリアスな結末を迎えました。
魔歯の行方
看護師さんの話では、魔歯は根が浅いため、吸引の際や口の中を清拭している時に自然に取れることがあるそうです。
おそらくそのタイミングで抜けたのではないかと考えています。
育児は"知らないこと"の連続
新しい世界を教えてくれる子どもたち
最初は驚きと少しの不安でいっぱいだった「魔歯」との遭遇。
結果的にミステリアスな結末を迎えましたが、この一件を通して「世の中には自分の知らないことが、まだまだたくさんあるんだな」と改めて実感させられました。
医療従事者の方々にとっては珍しくても既知の現象だったのかもしれませんが、親の私たちにとっては初めての体験。
育児を通して、こうした新しい発見や学びに出会えることは、大変さの中にある小さな楽しみでもあります。
レアケースから得た学び
魔歯というレアケースに出会えたことで、赤ちゃんの体の不思議さや、医療の奥深さを実感しました。
Aoは超低出生体重児で、ダウン症やPVLなど様々な医療的背景を持っています。
その一つひとつが、私たちに新しい知識と経験をもたらしてくれます。
知らないことばかりで不安になることもありますが、一つずつ学んでいけば大丈夫。
子どもが教えてくれる新しい世界を、これからも一つ一つの発見を楽しんでいきたいと思います。
魔歯との不思議な出会い
生まれた時から歯が生えているなんて、普通では考えられないことでした。
でも、そんなレアケースに出会えたこと自体が、Aoとの生活が特別なものであることを象徴しているような気がします。
これからもAoが教えてくれる新しい発見を、家族みんなで楽しんでいきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
※魔歯(先天性歯)については、赤ちゃんの状況に応じて対応が異なります。気になる症状がある場合は、必ず小児科医にご相談ください。