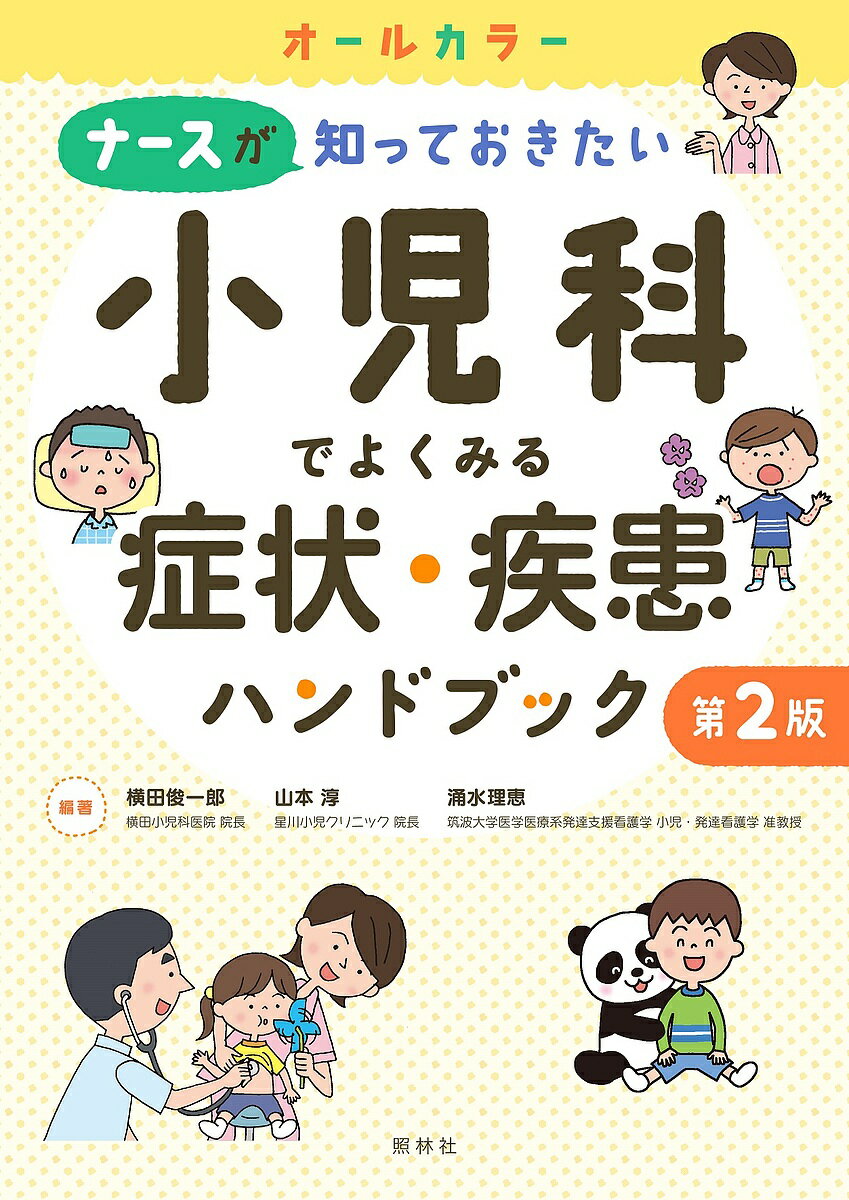🚑 NICU退院指導で学んだ、乳幼児心肺蘇生法
こんにちは、Aoパパです👋
先日のブログで触れた「退院指導」について、今回は特に印象深かった「乳幼児の心肺蘇生法」のDVDについて詳しくお話ししたいと思います。
正直に言うと、Aoを抱っこしながらDVDを観ていて「難しい...😰」というのが最初の感想でした。でも、この小さな命を守るために、絶対に覚えなければならない知識だと強く感じています。
前回のお話⤵️
自己紹介⤵️
🏥 はじめに:退院指導で向き合った現実
📺 DVDを観ながら感じた責任の重さ
NICU(新生児集中治療室)での退院指導では、様々なDVDを観ることになります。前回のブログでは「乳幼児揺さぶられ症候群」と「心肺蘇生法」について簡単に触れましたが、今回は特に心肺蘇生法について詳しく掘り下げていきたいと思います。
約3000gまで成長したAoを腕に抱きながらDVDを観ていると、この子の小さな胸、細い手足を見て「本当にこんな小さな体に、適切な処置ができるのだろうか」という不安が込み上げてきました😢
💭 「もしも」を想像することの大切さ
Aoには21トリソミー(ダウン症)やPVL(脳室周囲白質軟化症)など、複数の医療的背景があります。一般的な赤ちゃんと比べて、リスクが高い可能性があるからこそ、私たち両親がしっかりと知識を身につけることが何より重要だと感じています。
💡 大切なポイント
心肺蘇生法は「使わないことを願う知識」ですが、「いざという時に命を救う可能性がある知識」でもあります。特に医療的ケアが必要な子どもを持つ親にとっては、必須の知識だと思います。
👥 大人の心肺蘇生法との違い
✋ 胸骨圧迫:「両手」から「指2本」へ
大人の心肺蘇生法では両手を重ねて胸骨圧迫を行いますが、乳幼児の場合は中指と薬指の2本の指で行います。この違いだけでも、力の入れ方が全く異なることが分かります。
🎯 正確な位置と深さ
- 位置:胸の中央、乳頭を結んだ線よりもやや下
- 深さ:胸の厚みの約3分の1程度(約4cm)
- リズム:1分間に100~120回のテンポ
DVDを観ながら実際にAoの胸を見て、「こんなに小さな胸に、指2本でも大丈夫なのか...」と心配になりました😰 でも、適切な深さと位置を守ることで、効果的な血液循環を維持できるのだそうです。
👄 人工呼吸:口と鼻を一緒に覆う繊細さ
大人の人工呼吸は「口対口」で行いますが、乳幼児の場合は口と鼻を一緒に覆って行います。この時の力加減が非常に繊細で、「胸が軽く上がる程度に」息を吹き込むのがポイントです。
⚠️ 注意が必要な点
乳幼児の肺はとても小さいため、大人と同じような強さで息を吹き込むと、肺を傷つけてしまう可能性があります。「優しく、確実に」がキーワードです。
🚨 もしもの時に備える、具体的な3つのステップ
1 反応の確認と応援を呼ぶ
まずは赤ちゃんの意識があるかどうかを確認します。DVDでは以下の方法が紹介されていました:
🔍 反応確認の方法
- 大きな声で名前を呼ぶ
- 肩を軽く叩く(決して激しく揺さぶらない!)
- 足の裏を強く叩く
反応がない場合は、すぐに周囲に助けを求めます。「誰か来てください!」「119番に電話してください!」と具体的に指示を出すことが大切だそうです。
2 胸骨圧迫の実施
気道を確保した後、胸骨圧迫を開始します。DVDで学んだポイントを整理すると:
💪 胸骨圧迫のポイント
- 救助者が1人の場合:胸骨圧迫30回 → 人工呼吸2回を繰り返す
- 救助者が2人の場合:胸骨圧迫15回 → 人工呼吸2回を繰り返す
- 圧迫のたびに胸がしっかりと戻るまで待つ
- 中断時間を最小限にする
実際にAoを見ながら想像してみると、その小ささに改めて驚きます。「本当にこの通りにできるだろうか...」という不安はありますが、繰り返し練習することで身につけていきたいと思います💪
3 人工呼吸とAEDの使用
人工呼吸を行う際は、気道の確保が最も重要です。赤ちゃんの頭を軽く後ろに傾け、顎を持ち上げて気道を開通させます。
🫁 人工呼吸の手順
- 口と鼻を自分の口で覆う
- 1回につき1秒かけて息を吹き込む
- 胸が上がるのを確認する
- 2回目の人工呼吸の前に、胸が下がるのを待つ
💡 AEDについて
乳幼児にAEDを使用する場合は、小児用パッドを使用します。小児用パッドがない場合は、成人用パッドでも代用可能ですが、パッド同士が触れ合わないよう注意が必要です。
🌟 まとめ:親としてできること、そして決意
📚 継続的な学習の重要性
正直に言うと、DVDを1回観ただけで完璧に覚えられるものではありません😅 でも、「知っている」と「知らない」では大きな違いがあると思います。
私はこれまで消防署や日本赤十字社が開催している講習会にも参加したことがあるため、実際に人形を使った練習をしたこともあります。Aoママと一緒に学ぶことで、いざという時にお互いが冷静に対応できるようになりたいです。
🏠 日常での備えも大切
心肺蘇生法の知識と合わせて、普段から以下のことも心がけています:
- 近所のAED設置場所の確認
- 緊急時の連絡先リストの作成
- かかりつけ医や病院の連絡先の把握
- Aoの医療情報をまとめた「緊急時カード」の準備
💙 同じ境遇の親御さんへ
医療的ケアが必要な子どもを持つと、不安になることがたくさんありますよね。でも、正しい知識を身につけることで、少しずつでも自信を持てるようになると思います✨
一緒に学んで、一緒に成長していきましょう!Aoと家族の安全を守るため、これからも勉強を続けていきます💪
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙏 次回は、もう一つのDVDで学んだ「乳幼児揺さぶられ症候群」について詳しくお話しする予定です。
※この記事は個人の体験に基づいたものです。実際の緊急時には、速やかに119番通報を行い、専門家の指示に従ってください。