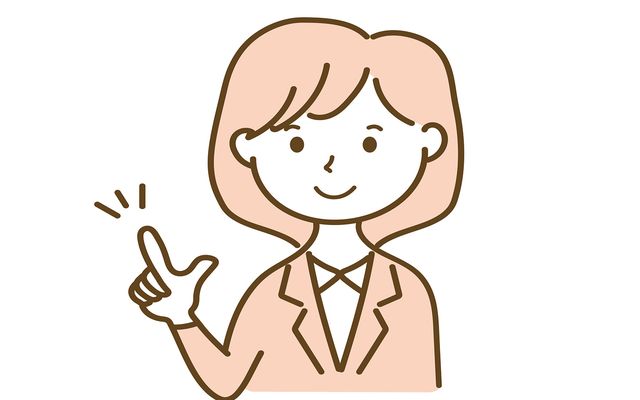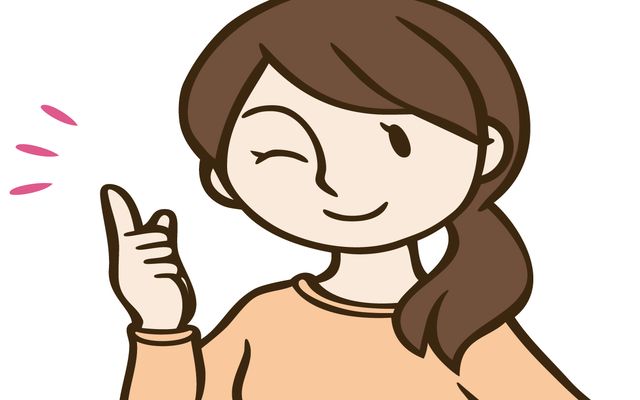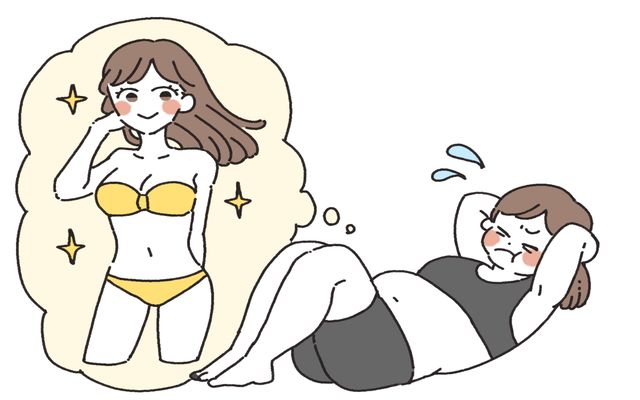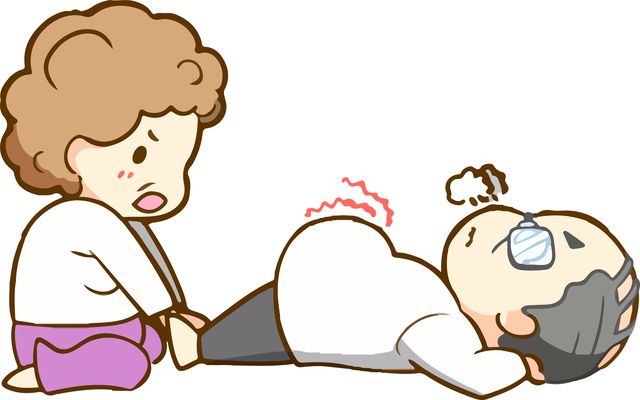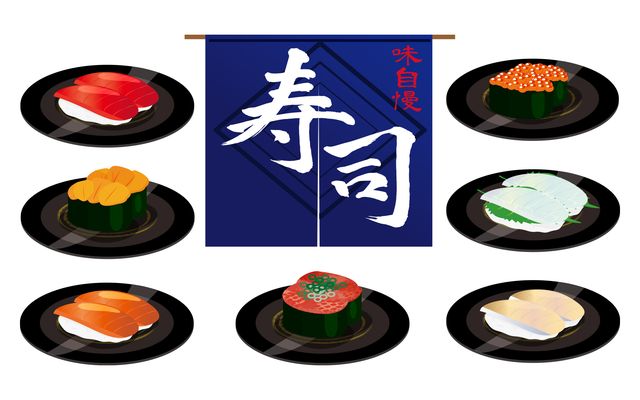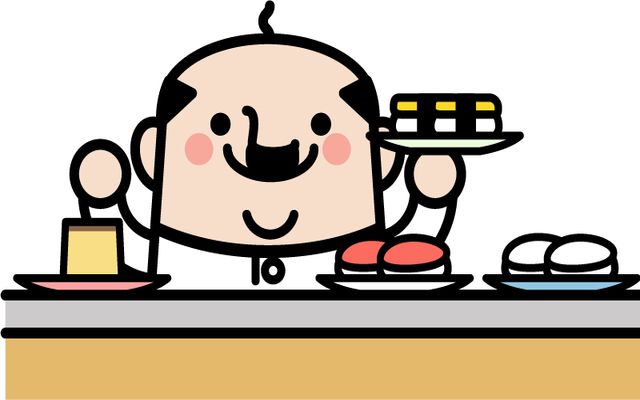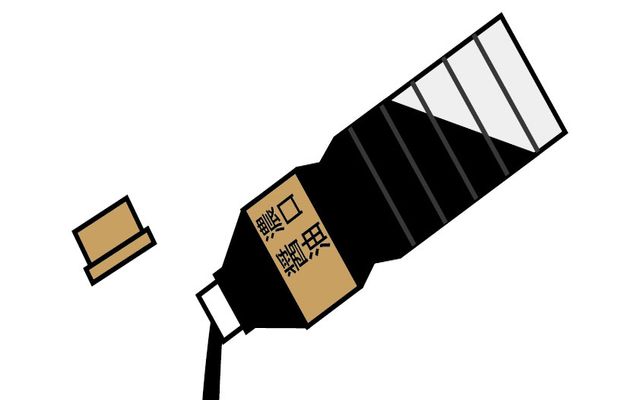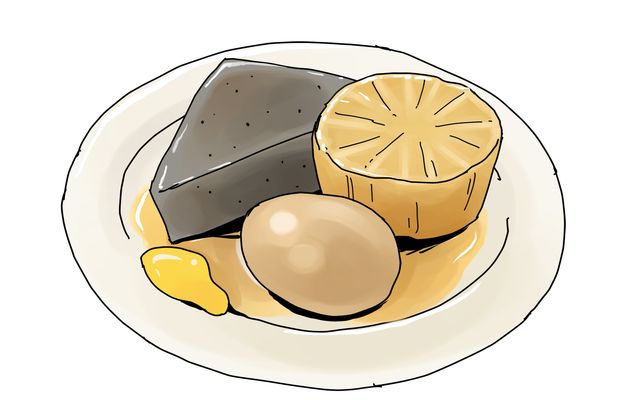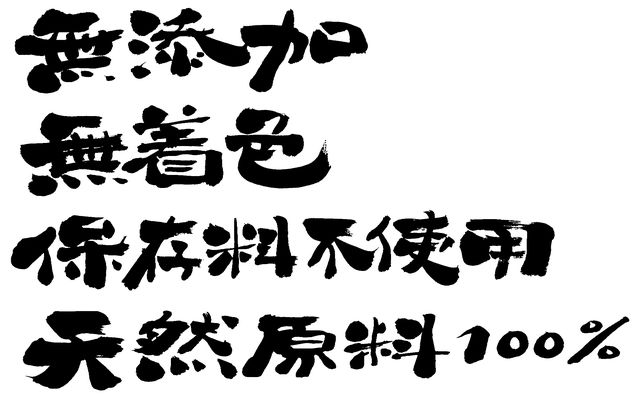アーモンドはナッツの中で最も生産量が多く、その約8割がアメリカのカリフォルニア州で生産されています。
意外かも知れませんがアーモンドはバラ科で、アーモンドの木は春に桃や桜に似たピンクの花を咲かせます。
しかも美容や健康、ダイエットなどに良いと言われているアーモンド。
今回はアーモンドの栄養と効果についてご紹介します。
アーモンドの栄養と効果

アーモンドには、食物繊維、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど、体にうれしい栄養素が豊富に含まれています。
具体的には、次のようなものです。
- 食物繊維:100gあたり6.1g
- タンパク質:100gあたり21g
- ビタミンE:100gあたり25.9mg
- マグネシウム:100gあたり270mg
- カルシウム:100gあたり265mg
- リン:100gあたり540mg
- 鉄:100gあたり3.4mg
これらの栄養素は、心臓病や糖尿病、肥満などの生活習慣病の予防に効果的であるとされていると言われています。
また、アーモンドには抗酸化作用が強く、老化の原因となる活性酸素を除去する働きもあり、アンチエイジングにも効果的です。
アーモンドの1日の適量は、20〜25粒程度です。
食べ過ぎるとカロリー過多になるため、注意が必要です。
アーモンドの食べ方には、いろいろな方法があります。
そのまま食べるのはもちろん、おやつや料理に入れて楽しむのもおすすめです。
ビタミンE
アーモンドに含まれるビタミンEは、約19粒で成人の1日に必要な量を摂ることができるほど、豊富に含まれています。
ビタミンEには抗酸化作用があり、動脈硬化や老化・免疫機能の低下の原因のひとつとなる活性酸素の働きを抑えてくれます。
さらに、免疫機能を高めてくれる働きがあり、体内に侵入してくる細菌やウイルスを撃退してくれます。
食物繊維
アーモンドに豊富な食物繊維は、10粒で1.5g含まれ、これはレタス(大きめの葉)約4.5枚分の食物繊維量に相当します。
食物繊維は、便秘予防や、食後の血糖値が上昇するのを緩やかにしたり、コレステロール・中性脂肪の値を下げたりする効果があります
オレイン酸
オレイン酸は一価不飽和脂肪酸の一種ですが、動脈硬化の原因のひとつとなる悪玉コレステロール(LDL)を下げる効果があります。
アーモンド100gには脂質が55.7g含まれていますが、その内の約3分の2をオレイン酸が占めています。
良く食べられるナッツの中では、ヘーゼルナッツに続き、トップクラスの含有量です。
カルシウム
アーモンド10粒(約16g)にはカルシウムが38㎎と豊富に含まれています。
これは、同量の牛乳の2倍以上の量です。また、ピーナッツ(落花生)の4.8倍、くるみの2.8倍、カシューナッツの6.3倍と、ナッツ類の中ではトップクラスの量です。
カルシウムには丈夫な骨を保つ働きがあるため、骨粗鬆症予防には欠かせない栄養素と言えます。
糖質
GI(グリセミック・インデックス)値とは、血糖値の上昇率を示す数値ですが、GI値が低いと食後の血糖値が上がりにくいと言われています。
アーモンドなどのナッツは低GI食品とされており、インスリン分泌を節約してくれる働きが期待できます。
また、アーモンドに含まれる糖質は100gあたり7.8gです。
ダイエット中の方や、糖質量が気になる方の間食やおつまみにおすすめできると言えます。
他にも、アーモンドには、マグネシウム・鉄・亜鉛・銅・ビタミンB2などが豊富です。
しかし、アーモンド10粒(15g)で92kcalと、少量でおにぎり約1/2個分のカロリーがあります。
栄養を摂るために食べ過ぎると、カロリーオーバーしてしまうため注意が必要です。
アーモンドの美味しい食べ方
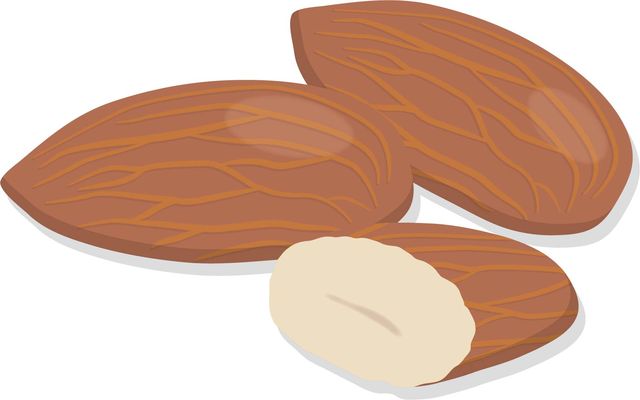
コンビニやスーパーで手軽に手に入るアーモンドは、ほとんどが「素焼き」「ロースト」のものです。
ダイエット中の間食やおつまみとしてそのまま食べる他にも、料理や製菓にも使われます。
例えば、砕いてサラダのトッピングや和え物に、スライスしたものを揚げ物の衣に使う方法などでおいしくいただけますよ。
最後に
アーモンドは、今の食生活にプラスして食べるのではなく、間食の代わりにするなど、置き換える方法で取り入れるようにし、カロリーを摂りすぎないよう気を付けましょう。
つい食べ過ぎてしまうという方は、個包装のものを探してみたり、お皿に決めた数を出したりなど、食べ過ぎないように工夫して活用してみてはいかがでしょうか。