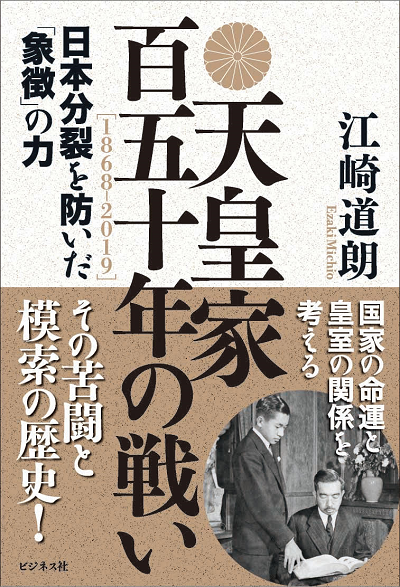以前検索をしていたら、こんな名前の神社を見つけました。奈良県御所市にある国見神社です。国見とは言葉通り、国を見るということ。古来から、天皇が国見をすることで、国が良く治まると言われている我が国ですが、それはもちろん神武天皇から始まるわけです。いえ、正確には神話の時代から始まるわけですが、初代神武天皇ももちろん国見をしたわけで、その地にこうして神社ができているわけです。神社そのものの創建は、ずっと後年なわけですが、それもこうしたことが伝わってきたからこそここに創建されたわけですから、伝承というものはあなどれません。
国見神社が鎮座する掖上の地は、日本書紀、巻第三(神武天皇の巻)に登場する。東征を終え、橿原の地で即位した後、神武天皇は国見山(日本書紀には「腋上の嗛間の丘(わきがみのほほまのおか)」と表現されている)にお登りになり、自分の「国を見」られた。
その時に「なんとよい国を得たものか。狭い国かもしれないが、蜻蛉(とんぼ)がとなめ(交尾)をしているように連なった山々に囲まれた地だ」と発せられたとされる。蜻蛉とは豊作の象徴であり、自分たちが得た地は狭いかもしれないが、稲作が盛んな、恵まれた地であるとの意で神武天皇は発せられたのである。この国見山での出来事が、日本書紀における神武天皇の最後の業績記載となっている。
国見神社では瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)を主祭神としてお祀りしている。この神は天照大神の命により天孫降臨をした神であり、神武天皇の曾祖父でもある。やがて、都が移り変わり奈良、京都へと北上していく中で、いつしか忘れられた、時代に取り残された神社となった。
しかし、神武天皇の御世より掖上に住む氏子たちによって、神武天皇の想いは守られ、ご奉仕、信仰されている。かつて社殿は国見山の山頂にあり、秋津村冨田地区の人も氏子であったが、いつの時代か丘の東麓に移され、今では原谷・今住・上方の三地区の人々の氏神として祀られている。江戸時代には近隣の高取藩や櫛羅藩からの寄進により社殿を改築したとの記録がある他、鰐口には明和5年(1768)9月の刻銘(盗難にあい不明、現在は大鈴を代用)、棟礼に「改築年 天保七年(1836)」の記載がある。
また、当社では瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の他、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)と田心比売命(タゴリヒメノミコト)の二柱もお祀りしている。住古より、国の発展はもちろんのこと、疝気(せんき 腰痛や腹痛)の神としても仰がれ、粟を供え奉って病気平癒を祈願するなど、その御神徳あらたかなるため、遠近より参拝祈願する者多しと伝えられている。
国見神社 御由緒より
こちらが、その国見をされた山、国見山です。
「国見」という言葉に聞き覚えがない、なにそれ?という方でも日本人であれば「民の竈」という言葉を聞いたことがあるのではないかと思います。「民の竈」とは、仁徳天皇が高殿から見渡すと民の竈から煙が上がっていないことから民の窮乏を察して三年間無税にしたお話です。これは天皇の国見として日本で一番有名なお話となっています。つまり、国見をすることで仁徳天皇は、民を知り、その知ったことで無税という政策により生活を改善させたわけです。
「国見」には、古来からの我が国の基本が収まっています。つまり「国見」=「国を知る」=「しらす」です。国を見なくては知ることはできませんから、国見は国を知るためには欠かせないこと、というわけです。
記紀を読むと我が国が「シラス」国であると書かれています。知識がなければ考えることはできません。だからこそ、我が国は「知らす」⇒「知る」ことに重きを置いてきたのだと思います。私たち日本人は、日本人としてもっと我が国への知識を深めていかなければなりません。それが、我が国の国体を護っていく力になっていくだろうからです。国体を守ることで守られるのは私たち自身です。天皇と国民は深く結び合っている紐帯なのです。
かつて、国見を禁じた人がいます。徳川家康です。家康は、天皇を御所に押し込めて、行幸をするには幕府への届け出が必要にしてしまいました。そんなわけで、父である上皇が病でお見舞いに行くためにも届け出が必要ということをお怒りになって長い廊下を作って屋敷を繋げてしまった天皇もいます。
そうした時代を経て、明治時代になって初めて天皇が東北まで巡幸され帰られた時には、それを記念した海の記念日もできました。つまり、これは天皇が東北各地を国見されたということです。天皇が行幸されるたびに各地で歓迎されるのは、それが国見であることに他なりません。日本各地に天皇が行幸されるたびにその地の発展が促進されるようになりました。迎えることで発展が促され、行幸されたことで励まされた人々の力でさらにその発展が後押しされるという良循環になってきたのが、明治以降の御巡幸の数々ではないでしょうか。そうしたことは、あまり知られていませんが、『天皇家百五十年の戦い』には、そうした天皇と皇室がいかに日本の発展に貢献されてきたかが巡幸の面でも記載されています。その御巡幸の力を私は本書発売直後に「国民とともに歩まれた平成の30年展」で確認してきました。巡幸地から献上された各地の献上品の質が物凄かったのですが、中には陛下(現上皇陛下)がいらっしゃるということで出来上がったもの、向上したものもあったりして、その力に驚かされたものです。
つい最近の大きな国見は、なんといっても沖縄です。先月、天皇皇后両陛下が沖縄へ巡幸啓されました。
こちらは1時間以上のバージョン↓
この時期、沖縄に訪問されたことには深い意味があるように思えるのは穿った見方でしょうか?
沖縄は反日の巣窟のように見えますが、実はもしかしたらどの都道府県よりも熱狂的に皇室を慕っていると思えるのが、こうしたパレードです。他の都道府県でここまでやっているところありますか?
今回の沖縄の国見は、沖縄の方々への大きな励みではないでしょうか。
コロナ禍により、天皇皇后両陛下のご予定が随分減ってしまっていましたが、令和の行幸啓がこれから増えていき、日本各地が国見されることを願っています。
神武天皇が願った理想の国を歌う「あめのした」
天皇陛下のように国見的効果が上がっているのが『日本製』。本書で取り上げられた様々なことが、本の出版後に注目されたのは凄いことだと思います。
国力をあげるためにも、天皇陛下の国見の力が必要と考えています。だからこそ、令和の巡幸、巡幸啓が増えることを願うのです。
三浦春馬 & STAFF INFO@miuraharuma_jp
明るみになる事が清いのか、明るみにならない事が清いのか…どの業界、職種でも、叩くだけ叩き、本人達の気力を奪っていく。皆んなが間違いを犯さない訳じゃないと思う。 国力を高めるために、少しだけ戒める為に憤りだけじゃなく、立ち直る言葉を国民全員で紡ぎ出せないのか…❄️
2020年01月29日 01:33
🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎