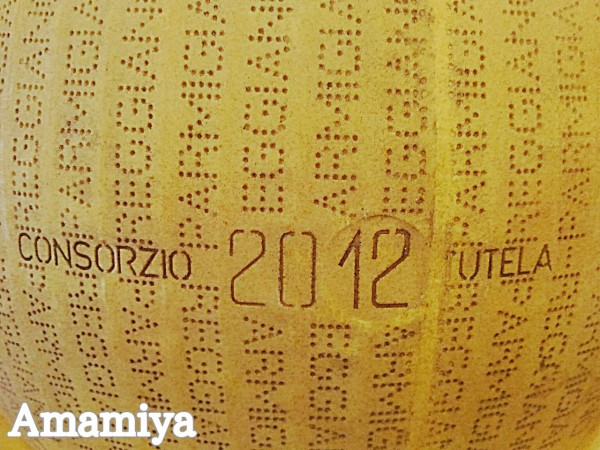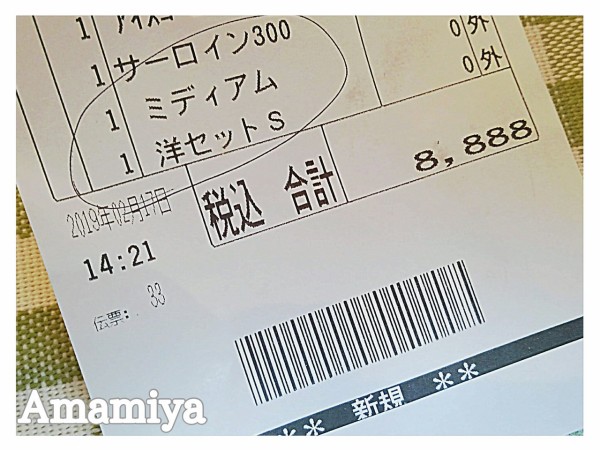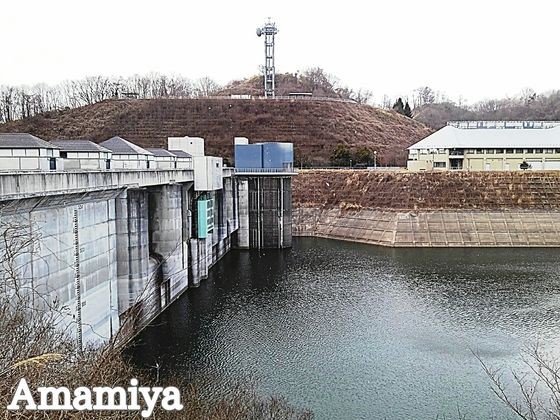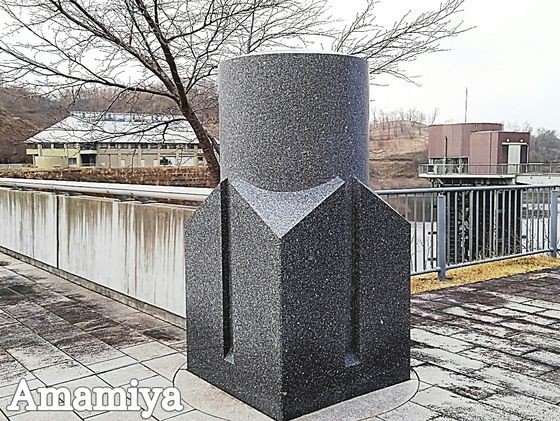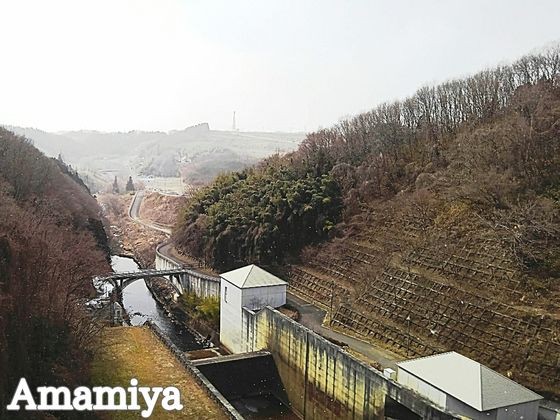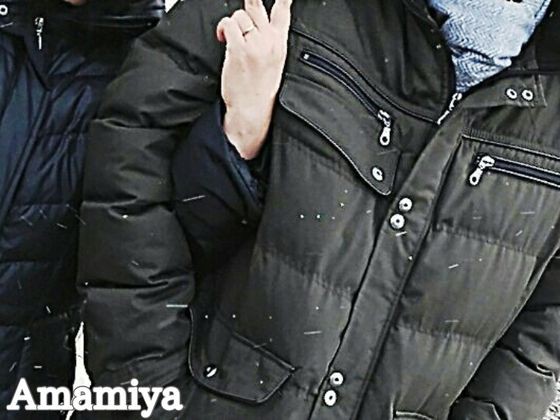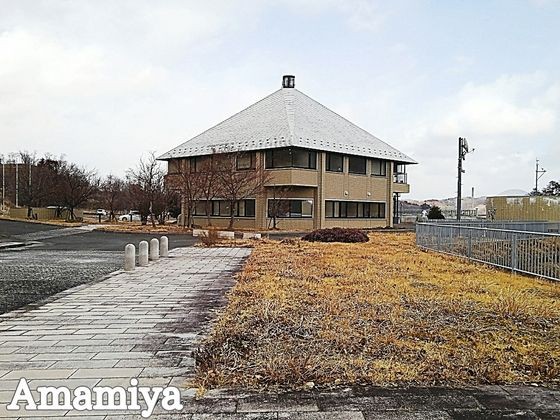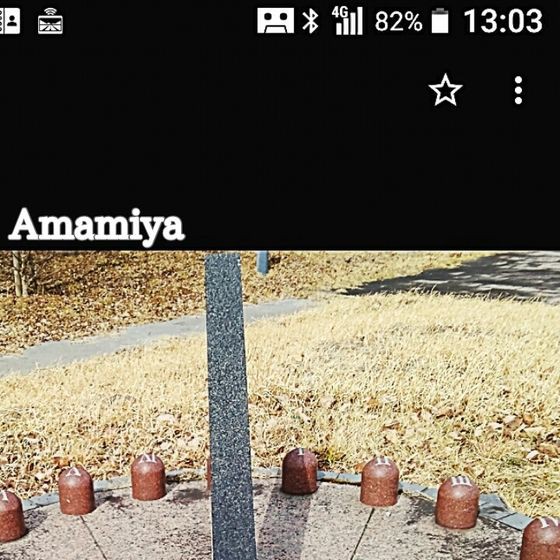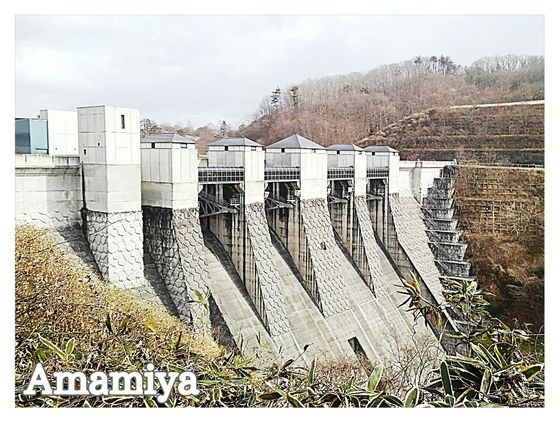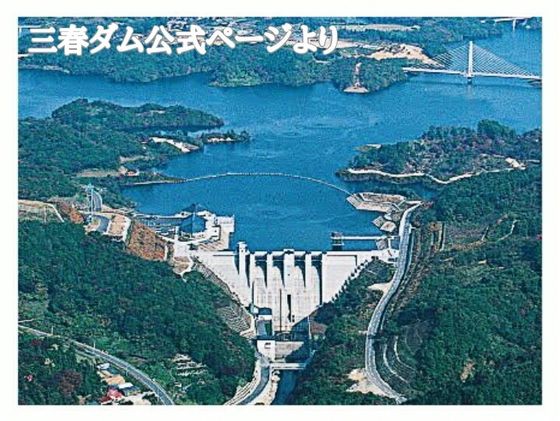おはようございます、ターボなババア天宮です
日付けは飛びまして本日2月14日
今日は何の日❓ワシの日❓(っ・д・)=⊃)゚3゚)'∴:
「世界中でチョコが舞い飛ぶ乱れ飛ぶ2月がやって来たのだ。
そこで私から貴方へ言っておきたいことがある。
容赦なく飛んで来るチョコから頭部を守りなさい。
飛んで来たチョコを正面から迎え撃つようにガッと口で咥えるような無謀な真似はしないように。顔面強打の可能性が高いです。
いや、絶対に強打します!
貴方のカッコいいおでこと鼻を損なうことなかれ。
因みに頭の上に蓋を除いたおでん鍋を括り付けておくといいでしょう。
チョコレートフォンデュの用意をしておきなさい。」
毎度なチョコの日ということで家族に❤
緑🟩が好きな夫氏へ
リーガロイヤルホテルの渋めチョコ
息子は帰省出来ないのでパッケージのみ📸
同じくリーガロイヤルホテルのチョコを
こちらは娘に
白金なんちゃらの可愛いピンク🩷のパッケージ
写真を撮らせて貰いました♪
これはワシの、缶目当てのごでば
このハート缶は二つ目です
こちらも白金なんちゃらのタブレット「クッキーミルク」
タブレットにはいろんな種類がありました
と、ゆーことで
今日はバレンタインデーなのですが‼️
実は‼️
皆様ご存知でしたか❓ワシ、知りませんでした❗
さぁ、チョコをバリバリ喰うぞ‼️