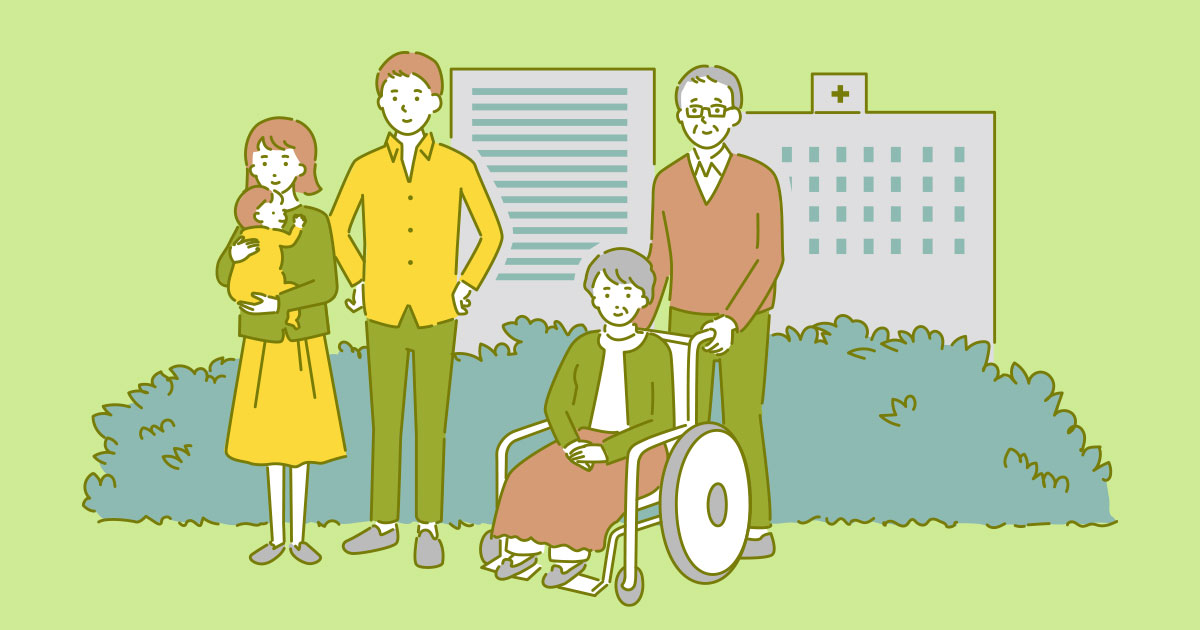こんにちは、東京都議会議員の龍円あいりです。
2017年7月に初当選させていただいてから2期8年が過ぎようとしています。私が掲げているインクルーシブな社会を実現するために邁進してきました!「言いっぱなしにしない」政治にするために、「こうします」とお約束した公約(マニフェスト)に、その後どのように取り組んだのかを報告します。
全98項目のうち、未着手はゼロ。公約進捗率は約95%となりました。
評価方法
公約は5段階で評価しました。
0点=未着手
1点=都に提案するための調査などの準備を進めた
2点=都に提案したものの前進はしていない
3点=都に提案し前進させるための意見交換や議論が進んでいる
4点=具体的に政策が進み出している
5点=大きく前進、達成する見込み、達成
アメブロでは文字数制限があることから数回に分けて評価を掲載していきますね。
龍円あいりの政策2017
2017年の私の政策リーフレットはこちらです↓
こども関連
1. 産みやすい!育てやすい東京に!(5点)
評価:
私が所属する都民ファーストの会では「チルドレンファースト」の政策を進めています。
東京都の子ども・子育て支援政策はしばしば国をリードし、全国されるようになりました。
ワイズスペンディング(限られた財源を有効に活用し、無駄を排除して持続可能な財政運営を実現する取り組み。全事業に終期を設定し、成果を検証して次年度の予算に反映させるサイクル、過去8年間で約7,600件の事業を見直し、累計約8,100億円の財源を確保)によって生み出した財源を、大胆に「子ども・子育て」に振り向けました。8年間で子育て関連予算は倍増を実現。令和7年度(2025年度)予算では2兆円が計上されました。
2. 出産前後のサポート(5点)
公約:出産前後の母親は、身体的にも精神的にも不安定な時期を過ごすことが多いです。身近に頼れる方がいない時、家事育児手伝いや心のケアをする産後ドゥーラのようなヘルパーを派遣するなどして、新しい命を迎え入れるお手伝いをしていきます。
評価:
「とうきょうママパパ応援事業」を2020年度に創設しました。この事業は、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供することを目的とした事業です。各区市町村と連携して実施しています。「ゆりかご・とうきょう事業」という前身の事業を都民ファーストの会のママ議員を中心に東京都に働きかけて本格実施に繋げました。
私が提案した産後ドゥーラやヘルパーの派遣も実現しています。
2021年度には「赤ちゃんファースト事業」を創設しました。この事業は、妊娠期から出産・子育て期までの経済的支援を目的に立ち上がりました。カタログから必要なものを選べるのが大変好評を得ています。毎年拡充を続けていて、2025年度は27万円になりました。
<とうきょうママパパ応援事業>
(赤ちゃんファーストカタログ↑クリックするとご覧いただけます)
「赤ちゃんファースト事業」誕生秘話を、都民ファーストの会の後藤なみ政調会長と、宮本せな都政改革委員と話しました!
3. (赤ちゃんの遺伝子疾患の)出生前診断を健全に運用(4点)
公約:胎児にダウン症などの遺伝子疾患や病気があるかどうかなどを調べる「出生前診断」の運用方法を健全なものにしていきます。医学的情報に偏りがちな現在の体制から、その子がどんな人生を歩むだろうかということ、いかなる支援があるのか、仲間たちが大勢いることなど、親が知りたい「生きた情報」を多面的に提供します。不安を煽るのではなく、安心して両親が診断を受けられるようにします。
評価:
ダウン症児の親として大きな関心を持って取り組んできた政策です。
特に母親の血液検査で実施できる新型出生前診断(NIPT)の運用については、相談支援体制が十分ではない中で、検査だけが先行して普及していることを懸念してきました。
東京都では初めこの課題に対応する部署が存在していませんでした。
都議会議員になった2017年は、まだNIPTの運用については、産婦人科学会が主導して進めていて国による明確な運用方針が存在していませんでした。学会に所属していない医療機関では相談支援をせずに検査体制だけをしているところもあり、都として何ができるのか議論を始めました。
厚生労働省が2019年に「NIPT等の出生前検査に関する専門委員会」を設置したことから、一旦、国の議論を見守りました。
2021年に報告書が取りまとめられましたが、期待していたような法整備はなく、日本医学会の認証制度が立ち上がるに留まりました。認証を受けていない医療機関での検査だけを提供するクリニックも存在を法的に取り締まることができないままになっています。
そこで東京都として新型出生前診断を受ける方への支援を進めたいと、取り組んできました。
●医療機関での相談支援が不十分な中で、自主的に出生前診断で陽性の結果が出た家族に寄り添った相談支援をする「胎児ホットライン」を応援することを進めています。
●ダウン症のある赤ちゃん向けの母子手帳「しあわせのたね」を区市町村の窓口で配布
都議会で提案し、ダウン症のある赤ちゃんの保護者に「しあわせのたね」を配布するための支援制度を立ち上げました。より「生きた情報」を必要としている方へとお届けするためのものです。また「しあわせのたね」は都立病院でも配布を開始しました。
これに合わせて、母子手帳についても、障害児や小さい赤ちゃんなど「多様なお子さんの成長を祝福するもの」に改定していただきました。(東京子供手帳モデル)
NIPTそのものの運用については国の法整備を待つ必要がありますが、東京都でできる支援を進めてまいりました。
4. 育休をフレキシブルに大活用できるようにしよう!(5点)
公約:ライフスタイルが多様化している中で、育児休業をもっとフレキシブルに利用しやすくするほか、非正規雇用の母親でも安心して育児ができるように支援が必要です。雇い主側もサポートすることで、「育休をとるとひんしゅく」という雰囲気を払拭していきます。
評価:
東京都では育児休業の普及啓発のために「ネーミングを変える」ことを提案し、2022年に「育業」と変更されました。育児は「休み」ではなく「未来を育む大切なしごと」だから「育休」ではなく「育業」としたものです。ウェブサイトも立ち上がりました。
また2024年度の東京都の予算に対して「育業を取得する人の同僚への支援」を都民ファーストの会の予算要望として提案し実現しました。これは育休を取得すると周囲に迷惑がかかるからと取得を控えることがないようにと提案したものです。
(都民ファーストの会東京都議団2024年度予算要望)
↓↓その結果、同僚への支援制度が立ち上がりました↓↓
5. パパにももっと育児の喜びを(5点)
公約:男性の育休取得率はとても低いです。父親がしっかりと子育てに関わることは、家族の豊かさにつながるのではないでしょうか。
評価:
私の所属している都民ファーストの会では「男性の家庭活躍」を重要な政策として代表質問でたびたび質疑をしながら後押ししてきました。東京都では男性の育業取得を推進するためのポータルサイトを立ち上げ、TOKYOパパ育業促進企業の登録制度、フォーラム等を実施しています。
男性の育業取得率は、2017(平29)年は12.3%でしたが、2024(令6)年には54.8%に増えました。
6. 不妊検査を助成し早期に不妊治療が
受けられる体制を整備(5点)
評価:
民間でキャリアを積んできた女性議員が多い都民ファーストの会では「キャリアも、妊娠出産も諦める必要がない、女性に人生の選択肢がある社会にしよう」と取り組みを進めてきました。
「不妊検査」は2017年にスタート。当初は年齢制限が35歳でしたが「女性がキャリアを頑張っているとあっという間に30代半ばになってしまう」ことから、年齢要件を引き上げるよう都に対して要望し、2019年には40歳にまで対象拡大。また男性の不妊検査も対象にするなどしてきました。
「不妊治療」については、その金額があまりに高額になることから、2021年1月にはそれまでの所得制限を撤廃しています。2022年4月に国が不妊治療を保険適用とすることにしたことを受け、全額自己負担となる先進医療の治療費への助成も開始しました。
さらに妊娠しても流産を繰り返す、いわゆる「不育症の検査費用」に対する助成も実施しています。
さらにAYA世代のための卵子凍結助成を創設。昨年度からは39歳までの卵子凍結助成も始まり、大変好評をいただいております。
7. 周産期母子医療センターを中心とする
医療機関の連携強化(4点)
評価:
都では、産科・小児科双方から一貫して総合的で高度な周産期医療を「周産期母子医療センター」を29施設設置しています。 ミドルリスク妊産婦に対応する「周産期連携病院」を11施設指定し、それぞれの役割に応じた連携を進めています。厚生委員会に所属し、ハイリスク妊婦への支援体制について質疑をしてきました。
8. 新生児集中治療室(NICU)に長期入院している
小児の円滑な在宅移行の実現(5点)
評価:
ダウン症など障がいのある赤ちゃんにとって出産後にNICUで数カ月を過ごすことはよくあることです。その中でよく聞くのが「情報がなくて孤独だった」ということです。
また障害の診断名はないものの早産で低体重で生まれた赤ちゃんの保護者からは、NICUから在宅へ戻ると支援が急になくなり、情報もなく、途方に暮れると伺ってまいりました。東京都のNICU退院支援手帳「のびのび」の改訂をするように東京都に対して要望。
↑こちらは2024年予算特別委員会での質疑。その結果、NICU退院支援手帳のびのびが改定されることになり、ワーキンググループによる議論が進んでおります。
9. 救命センターを中核とした小児救急医療提供体制の充実(4点)
評価:
子どもの命を守る小児救急体制はとても重要です。東京都では救命治療が困難な小児患者を必ず受け入れ、小児集中治療室(PICU)等での救命治療・専門医療体制を備えた「こども救命センター」を4病院を中心に、迅速かつ適切に救命処置を受けられる体制を確保。さらに二次救急医療体制としては、休日・全夜間診療事業(小児科)に参画する都内 54 病院において、緊急入院のための病床を 79 床確保しております。
10.地域の子ども食堂と連携し
食事提供などを行う居場所作りの拡充(5点)
評価:
●子供食堂は増加
「子供食堂」への支援を創設し、子供食堂の数は確実に増え続けています。令和元年は508箇所でしたが、令和6年には1075箇所へと増えました。
●こどもの居場所を増やす:今年は「朝の居場所づくり」
議員提案で実現したこども基本条例が施行されてからは「こどもの意見を聞きながらこども政策を進める」ようになりました。そのため子供食堂以外にも様々な「子どもの居場所」の創設を進めています。
2025年度、都民ファーストの会の要望で新たに新設したのが「朝の子どもの居場所」づくりです。下記は「こども未来アクション」の資料です。
子供食堂については、子どもたちの声を元に「地域の見守り機能を一層強化できるように、スタッフのスキルアップ促進」がされています。
<次の投稿に続きます> ※文字数制限のため投稿を分けております。
↓↓↓↓↓