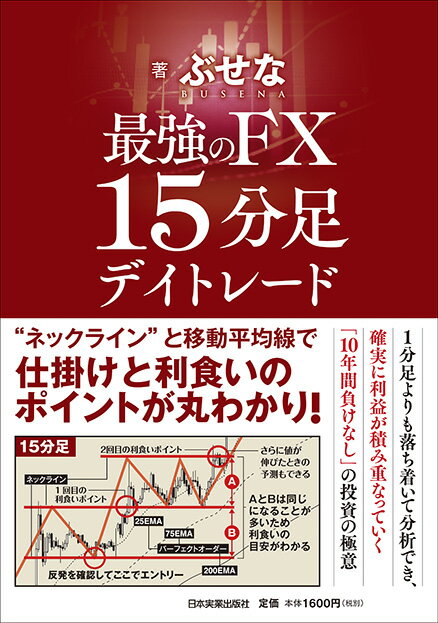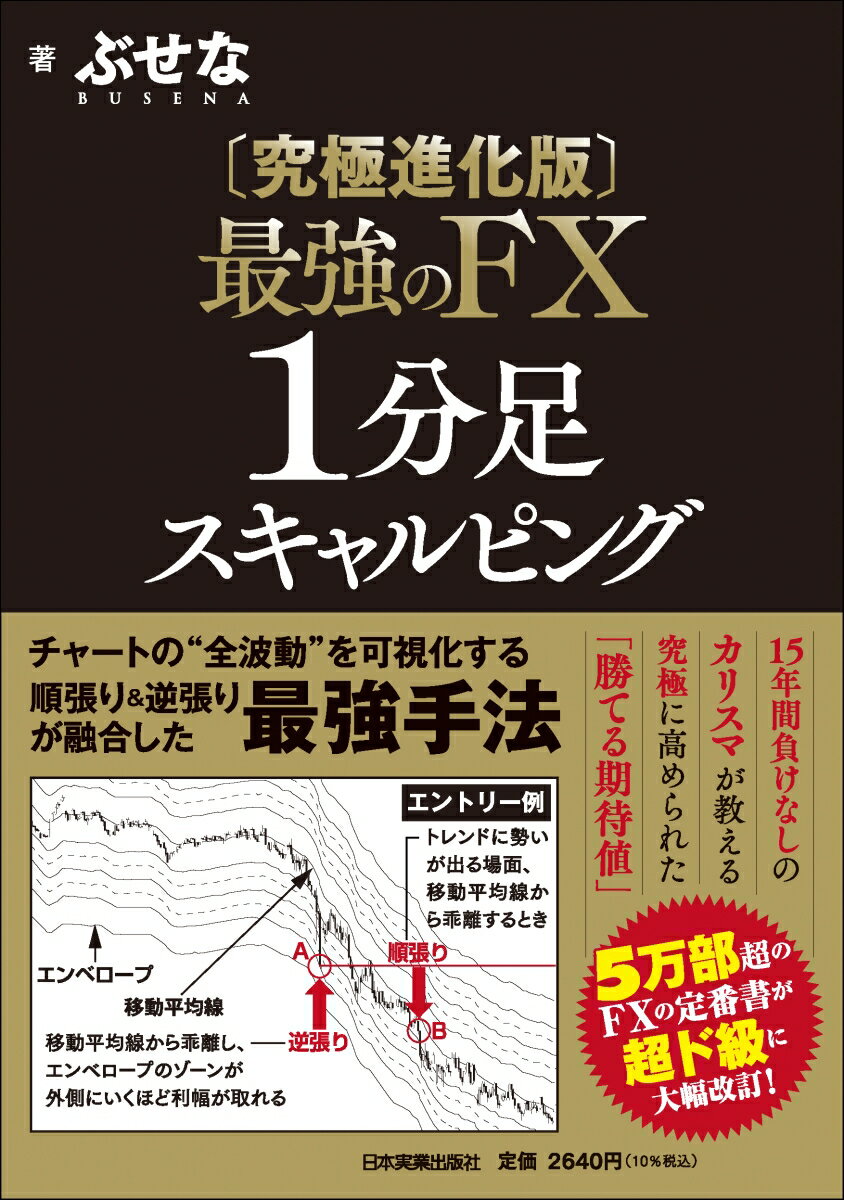6月3日からのペソ大暴落で、かなりの含み損を抱えてしまい、一人大反省会を開いたところ、結論としては、戦略レベルの自分ルールは間違ってなくて、無理にペソスワにしようとして戦略レベルの自分ルールを無視して、戦術レベルで無理をした結果だったという結論に至った。
とはいえ、大失敗は大失敗!
反省しただけで終わらせずに、FXについてもっと深く勉強しなければということで、何冊かFX関連本を買い込んで勉強することにした。
その第一弾。
結論から言うと、凄く良かった。
本当にためになった。お勧めする。
何が良かったかって、テクニカル分析というよりチャート分析のやり方が非常に分かりやすく解説してあって、とってもためになった。
FXを始めるにあたっては、当たり前だが、この本に出てくるテクニカル分析に使うラインの一通りは、辞書的な意味では目を通していたのだが、今一つ、実感が湧かなかった。
ところが、この本を読んで、実際の使い方を解説されて、なるほどこんなふうに使うのね。という感じで、実感できた。
詳しい内容については、当然、本を読んで自分で理解してもらった方がいいと思うのだが、しかし、あえてざっくりこの本の良かったところを上げると
・一つの通貨ペアを監視してトレンドが出た時にエントリーする方法もあるが、著者は、多数の通貨ペアを同時に監視してトレンドが出た通貨ペアにエントリーする方が好き。(これ、私のLightFXの裁量取引と同じ。)
・勝ち続けるにはトレードの手法の引き出しが多い方が良い。(いろんな手法を試している私に通じるところがある。)
・テクニカル分析は必要だがあまり複雑なのは不要。ローソク足、短期・中期・長期の3種の移動平均線、ネックライン(レジスタンスライン、サポートライン、トレンドライン、アウトライン等7種)、フィボナッチぐらいしか使わないけど、使いたおす。(私の場合、フィボナッチは使わず、ボリンジャーバンドとMACDを見てるけど、ストキャスとかRCIとか難しいものは使わない(分からない)のが似てる。)
・トレンドが出たかの判定方法がかなり丁寧に説明されている。具体的には、ゴールデンクロスではなく、パーフェクトオーダーとネックラインを超えたかで判定。(これは本当に勉強になった。)
とはいえ、著者の方法が、そのまま私に合うかというと、そうは問屋が卸さない。
というのは、著者の一番のお勧めの戦略は、レンジ相場がブレークして、トレンド相場が始まった次の押し目でエントリーして、大きく利益を確保するという順張りで、しかも得意なのが売りからエントリーというものなのです。
しかし、これは、基本的にレンジ相場を想定して、レンジの下端で買ってエントリーし上端で売ってエグジット、ついでにスワップも貰えたらいいな。もしレンジブレークしたら、自動取引に任せて裁量取引は行わず、また落ち着いてレンジ相場っぽくなったら、裁量取引でレンジの下端で買ってエントリーし直せばいい。という私の戦略とちょうど真逆なので、ちょっと真似できないのです。
というか、実は、2023年中に売りの方が手早く儲かるということで売りさや狙いを推奨する本を読んだので、実地で売りからのエントリーを試してみました。
その結果、いくらか儲ける取引ができたものの、全くタイミングが読み取れず、トータルでは圧倒的に駄目だったので、自分には向いていないと思いました。
今になって考えてみると、これは、多分、この著者の言う相場のスピード感の違いに、私がついていけてないということだと思います。
つまり、著者曰く、昔からある相場の格言に「上げ100日、下げ3日」というのがあって、下げ相場の方が足が速いので、手っ取り早く儲かる(デイトレードで勝負をつけやすい)ということなのですが、私は逆でこの上げ100日の方で、レンジ相場っぽくコツコツと利益を積み上げることばかり考えているので、動きの速い下げ相場に全くついていけないということかなと思ってます。
そして、これは上げ相場、下げ相場にかかわらず、レンジ相場を狙うのか、レンジブレークしたトレンド相場を狙うのかという違いにも関係しています。
つまり、動きの遅いレンジ相場をじっくり狙うのか、動きの速いトレンド相場で手早く稼ぐつもりなのかとう違いに直結しているのです。
これは、もともとは一分足スキャルピングで大儲けしたという著者の経験があるからこそ、下げ相場の速さに対応できるのであって、私には当面無理だと感じています。
そのほか、気になった点をいくつか挙げると
・V計算、NT計算、N計算、E計算など、イグジットのための値幅の計算方法。(私はこの発想はありませんでした。単純に過去のトレンドの最高値やレジスタンスラインで売値を決めています。計算も複雑だし、将来値の推計で精度がそれほどでもなさそうだし、余裕もないしで、当面は使いませんが、参考にはなりました。)
・フィボナッチで押し目からのエントリーポイントを決定。(私の場合、厳密なフィボナッチに拘らず、アバウトにレンジ内の2割下げ、4割下げあたりのレジスタンスラインに寄せてエントリーしてるので、これを大体同じととるのか微妙に違うととるのか。)
・カウンタートレンドラインの使い方。(私にはちょっと難しすぎる感じです。)
などなど、書き出したらキリがありませんが、これ以上はやっぱり直接本を買って勉強していただいた方が良いのかなと思います。
以上