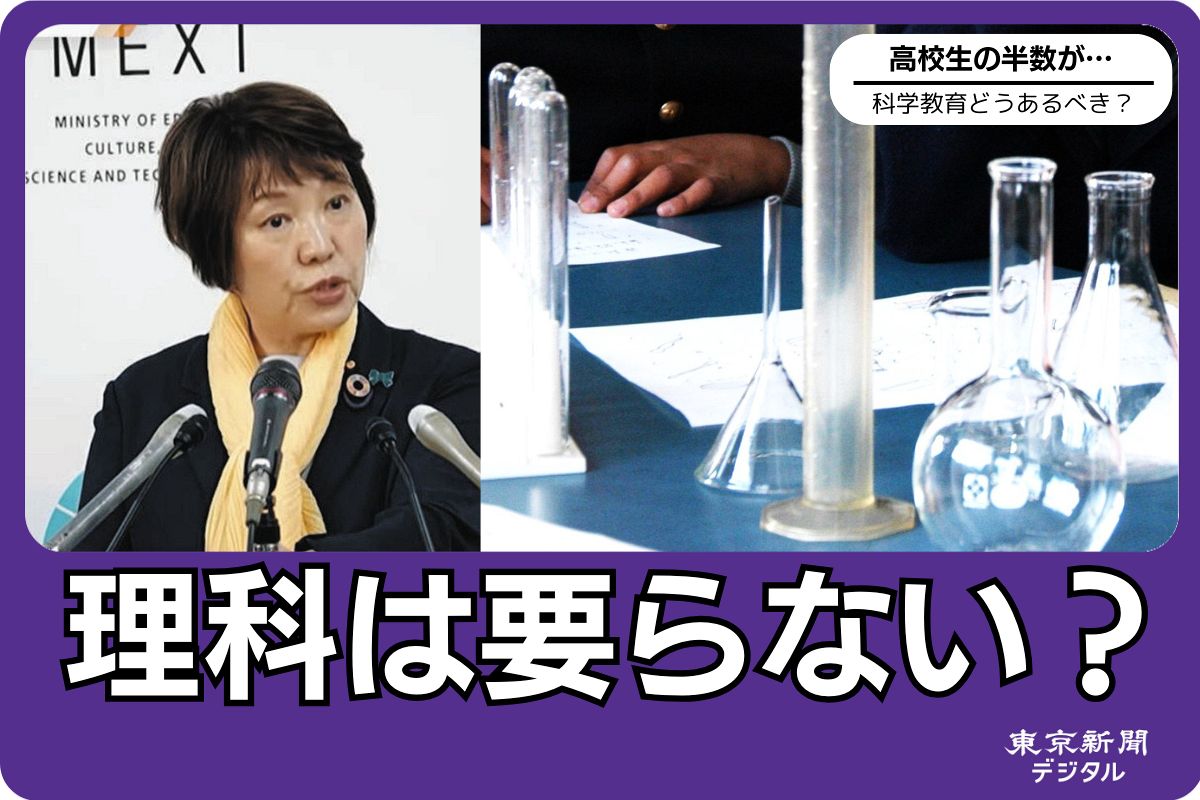いくら注意喚起されても世の中テキトーな言説は増えるばかりで、惑わされる人たちが後を絶たぬのも仕方がないし、何かしら専門知識がかかわってくるような領域では特に、自身の裁量で真偽を見分けるなんてままならぬ者の方が多かったりもする。
しかし、最近になって頓にブイブイ言わせるようになった「サンセーのハンタイのサンセーなのだーっ‼」みたいな名前の党を代表とする「有権者のアホさ加減を自らの力に変えて立ち回るタイプ」の政党に、まんまと利用されて相当にズッコケた社会の片棒を担がされちまうような者が居るとしたら、それは明確に断じて自業自得なのであり、テキトーな言説をテキトーな言説だと見定める能力を「自ら欠いていた罪」に対する「罰」であると考えた方がいい。
生活保護を受給する世帯の3分の1は外国人が占めている--。今年3月ごろから、そんな外国人の生活保護を巡る投稿が交流サイト(SNS)上で散見されるようになり、外国人に関する政策がクローズアップされている参院選の公示直前にも広く拡散された。しかし、実際に受給しているのは全体の3%未満で、この投稿の情報は誤りだ。
この記事に書かれているのは、誤情報の拡散にそもそも発信元のテキトーな言説が最も加担していたという事実なのだが、そんな経緯とは無関係に、「3分の1」という、ただ感情・感性に訴えるがためだけの数値が勝手に広がり、それが好き嫌いでモノを考えるシンプルな者たちによって支持されていくのだ、という悲惨な結論こそが重要なポイントだ。
もちろん、記事中に「どこがファクトでないか」の説明はある。次の部分だ。
厚労省によると、23年度に生活保護を受給した世帯数(23年4月~24年3月の月平均)は全国で165万478世帯で、このうち外国籍の人が世帯主のケースは、4万7317世帯だった。
計算すると、生活保護を受給している全世帯のおよそ2・9%に当たり、指摘されている3分の1には遠く及ばない。22年度も約2・9%と同様だった。
一方、拡散されている投稿の内容を見ると、全体の受給世帯数は約165万という1カ月分の数値なのに対して、受給する外国人世帯数の方は12カ月の延べ数(約56万)で対比されているため、外国人受給世帯の割合が30%を超えているという誤った数字が算出されていた。
つまりこの56万という外国人世帯数は「年間のべ総数」であり、それを1か月分の母数である165万で除算したから30%超=3分の1という数字になっただけ、ということだ。「延べ」の概念を知っていればこんな誤りはすぐにでも判るはずだろう。
ところが、当初の情報源には誤解を招くなりの理由もあったという。
確認すると、一部で出回っているグラフや記事には、生活保護を受給している外国人の世帯数について、「のべ総数」と記した注釈部分がないものがあった。
ニッポンドットコム編集部に取材すると、3月に配信後に読者から指摘があり、誤解を生じさせることから「のべ総数」という注釈を加え、4月に再配信したのだという。
だが、SNSでは古い内容が更新されないまま広まったことで、「生活保護の3分の1は外国人」という数字が独り歩きしていったとみられる。
注釈を載せなかったのなら延べと分らないのだから、それは誤解を招いたのではなくそれ自体が誤情報だったと言うべきだ。もちろん後で訂正を打つのは正しい判断だったし、そもそもの数値は厚労省発表によるものなので、自らデータを参照して事実確認しようと思える者であれば、いつまでもそんな誤情報に囚われ続けるはずはない。
が、そもそも外国人がキライで、外国人の存在によって日本人が損していると考える連中にとっては、それにどういう根拠があるかなんてどうでも良く、3分の1という数字をただ歓迎したいから歓迎し、拡散したいから拡散しているだけ、誤情報であろうが無かろうが、それを都合良く利用しているだけなのだ。
テキトーな言説にしっかりした根拠を求めず、自分の感情・感性に合いさえすればすんなりと受け入れてしまう。
たとえデータが間違っていようが、正しいデータを突きつけられようがそんなことはお構い無しで、自らすすんで誤解の道を歩み続けようと心に決めている。それはあたかも恣意的誤解の実践者のようではないか。
悲しいかな、基本そうした連中に対しては、ファクトチェックなど何の役にも立たないのだよ。
俺はこの話題についていつも疑問に思うのだが、エスカレータを歩くことが転倒事故の主因であるかのような言説は、いったい何処から出てきたんだろうか?「一般に」とか言うからには、ちゃんとしたデータが在るってことなのか?それは参照可能なのか?
・・・という訳で、面倒だが俺が代わりに調べてやったよw
もちろん、過去に書いたこのファクトチェックも、恣意的誤解の前にはまったく歯が立たなくて当然だ。
おそらくは俺がこの国に生まれて以来、社会がもっとも困難を極めている今、参院選を目の前にして億千万の恣意的誤解がうごめくこの状況を見ながら、ああ、やはりこの国は教育を誤ったのだなとつくづく思う。大体こんなふうに「理科が生活に役立つか?」みたいな議論があること自体、とんでもなく失敗してる証拠だろうよw
「科学技術について学んだことを普段の生活に活(い)かすことができる」と思う割合は、日本が44.0%で最少。他の3カ国は6割前後だった。逆に「科学の技術や知識を学ぶことは難しい」と思う割合は、日本が65.6%で最多だった。理科で学ぶ知識は、料理やものづくりなど暮らしや社会のさまざまな場面に関わっている。
物の理を学ぶことは恣意的誤解の排除に役立つ。たいていの人は罪の意識を抱くこともなく恣意的誤解を軽やかに実践しているが、しかしそれは物の理からすれば明確に罪なのである。データに基づかない、事実に即さない判断がそこに介在し、物の理が示す「真」をあえて無視しようとしているからだ。もし物の理を心得ていたら、そんなことは罪悪感にさいなまれて出来なくなるはずじゃないか。
最近になって俺は、「世の中がおかしいのはシステムの問題ではなく、人の考え方がおかしくなっているからだ」と思うようになった。トランプの台頭も、兵庫県知事の居座りも、予言に右往左往する社会も、すべて「おかしな考え方・恣意的誤解」の投影でしかない。そんな考え方する人の激増は、結局のところすべて教育の失敗が生み出しているんじゃないかと思っているんだがな。
知識を教えようと必死になるが、考え方は教えない。上の議論にあるとおり、そもそも考え方を教えていることすら認識していないんだ。そんな教育じゃ、何が正しいかは好き嫌いで判断するという大人に誰もが育って全然おかしくないはずだろう?
(追記)
※これを書いたあとで別の記事がUPされていた。
理科教育は単なる暗記ではなく、“なぜ?”を問い、検証し、論理的に考えるプロセスそのものが重要にもなり、その思考法は、科学だけでなく、人と議論したり、何かを選択したりするときにも大きな力になるのです
その通り。これは極めてまともな評論だ。
日本の子どもたちが理科の重要性を実感できていないという今回の調査結果について、レン氏は「単に理科が難しいと感じていたり、学校教育全般に将来への希望が持てていない可能性もある」と指摘したうえで、「“なぜ?”を問う米国の探究型学習のような姿勢が必要ではないか」と話す。
日本では、受験のための知識偏重の授業によって、「理科=暗記科目」「社会と結びつかない科目」と見なされてしまっている可能性がある。
同感だ。アホみたいに暗記させたがる日本の教育ってマジでどうにかならんもんだろうか。