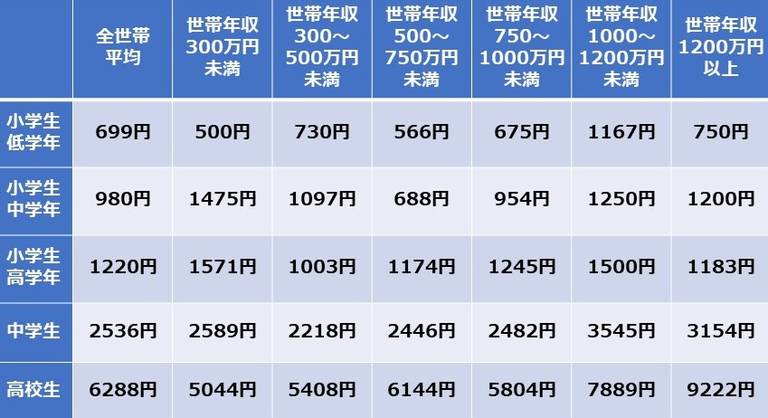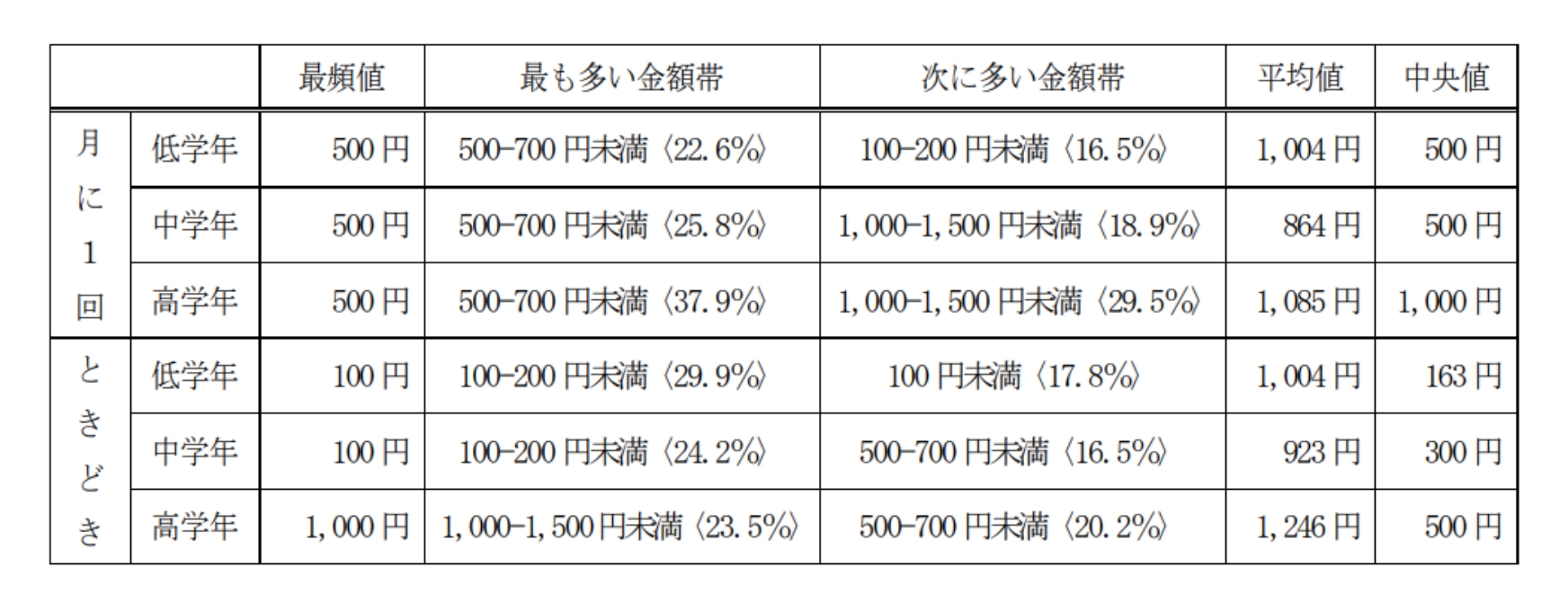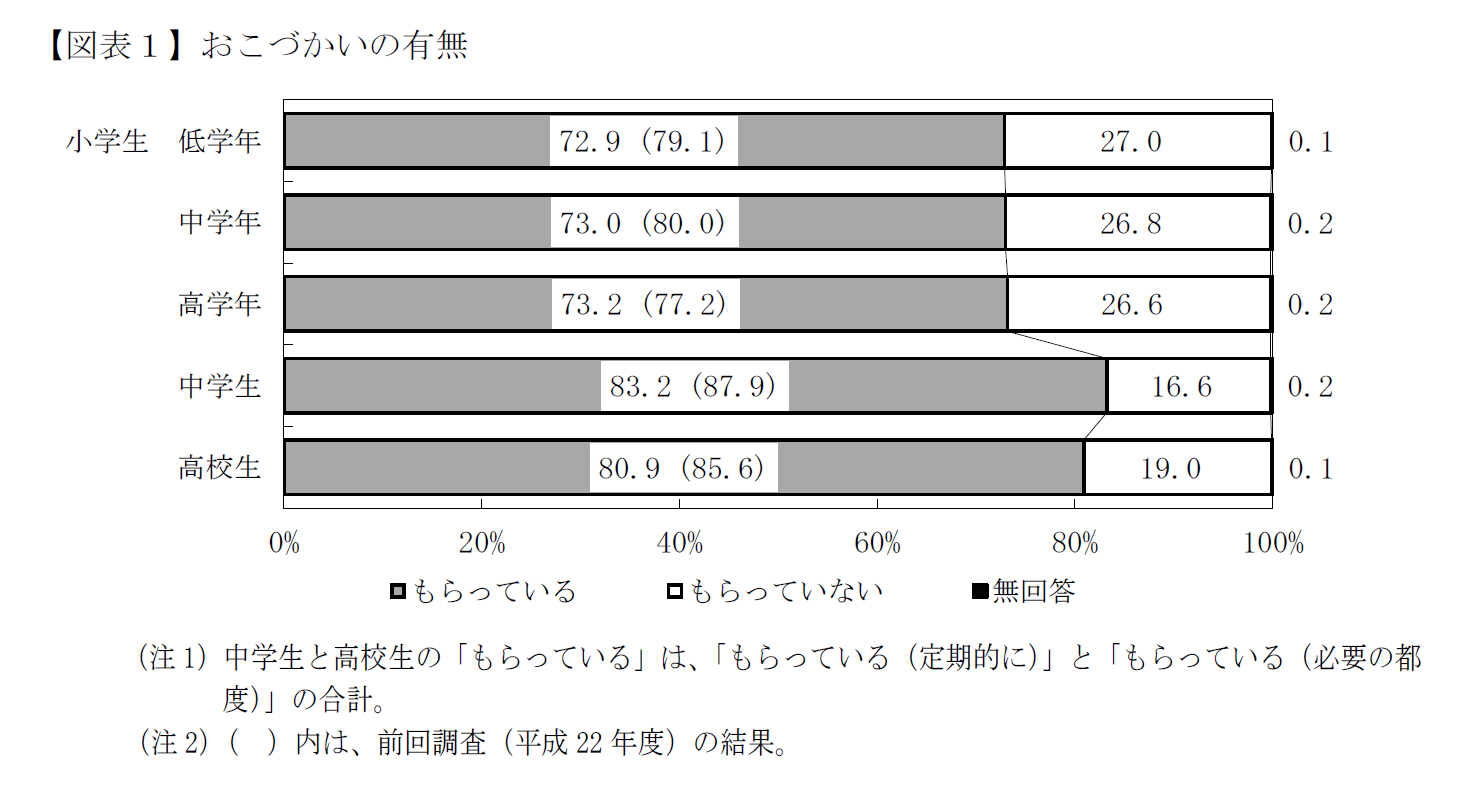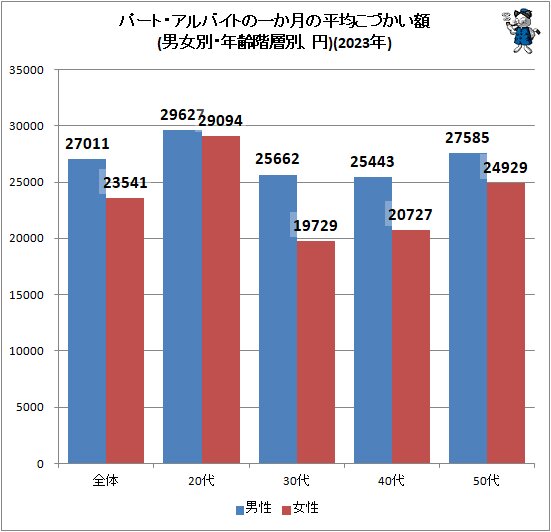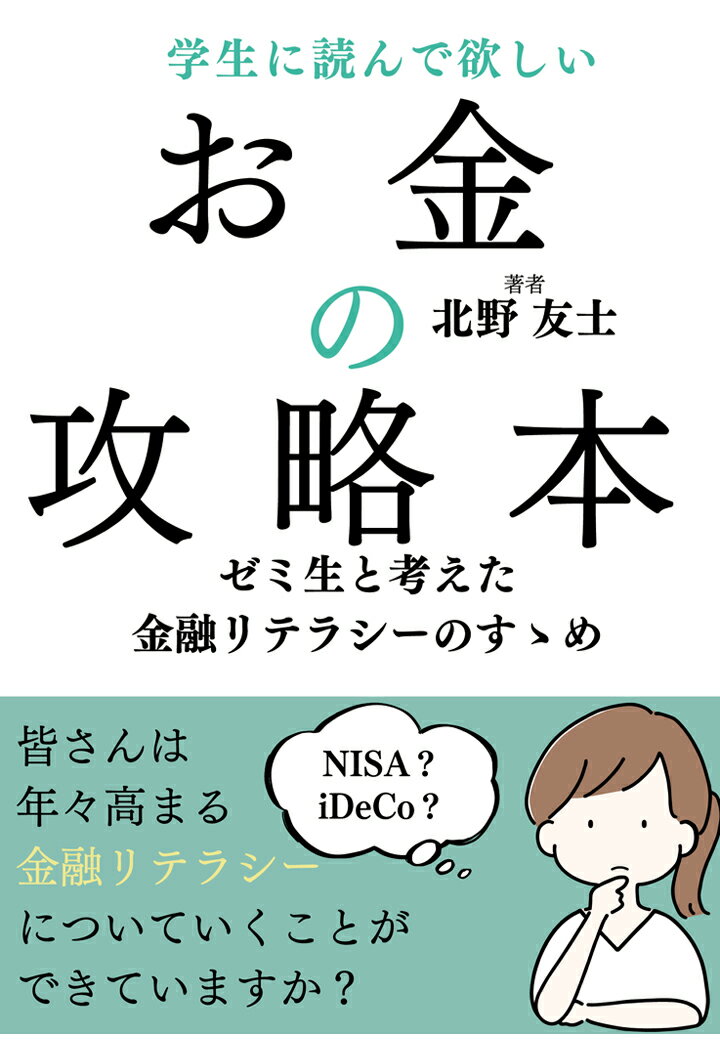子供の頃は1日がとても長く感じられました。夏休みの1ヶ月すら「永遠」のようで、「あと○日で学校だ!」と数えていたものです。ところが大人になり、特に40代後半からは1週間が瞬く間に過ぎ、1年もあっという間。なぜ年齢を重ねると、こんなにも時の流れが速まるように感じるのでしょうか?
今回はその理由について、心理学や人生経験も交えて考えてみたいと思います。
1. ジャネーの法則──「人生の相対的な時間感覚」
その1つ目の理由として有名なのが「ジャネーの法則」という心理現象です。
「人生のある時期に感じる時間の長さは年齢に反比例する」というもので、
たとえば10歳の子どもにとっての1年は人生の10分の1に相当しますが、50歳の大人にとっての1年は50分の1です。
つまり、年齢を重ねるごとに1年が相対的に短く感じられる仕組み。
実際に数式で表すと、
- 子供(10歳)…1年=人生の10%
- 大人(50歳)…1年=人生の2%
過去の人生に「比べて」今年の1年は、50歳の私にとっては10歳の頃の5分の1程度の重さしか感じられないのです。どうりで早く感じるわけですね。
2. 刺激や初めての経験が減ることで「新鮮さ」が薄れる
年齢を重ねると、「新しい経験」「ドキドキする体験」が減ると言われています。
子供や若い頃は、初めて経験することが多く、毎日が新鮮で印象的です。
- 初めての友達
- 初めての学校行事
- 初めての遠足や発表会……
そんな新しい経験は「記憶に残りやすく」、1日が長く感じられます。しかし大人になるとルーティンワークや決まりきった生活が増え、印象の薄い日が多くなってきます。結果、「気づけば1週間終わってる」という現象が起きるのです。
3. 毎日の「生活パターン」が固定化されるから
社会で働き始め、家庭や子育てなどを経験し、気がつけば決まったサイクルで生活している人がほとんど。
特にここ数年はコロナ禍もあり、さらに行動範囲や人間関係が限定されがちでした。
- 朝起きて、仕事に行き、
- 帰宅し、食事や家事、趣味やテレビを少し楽しみ、
- また寝て、翌朝がやってくる──
一見忙しく見えますが、これが変化のない状態だと「1日、1週間、1年がどんどん短く」なっていくのです。
(節目となる行事・イベントが少なくなるのも、加速要素のひとつです)
4. 体力や気力の変化で「消耗しやすい」
年齢を重ねると、体力や気力の消耗が以前より早くなったと感じる人も多いのではないでしょうか。朝は元気でも、仕事や用事が終わる夕方にはドッと疲れを感じ「1日がもう終わった気分…」ということもしばしばです。
そうすると、やりたいことがあっても「また明日でいいか」と先送りし、気づけば1週間、1ヶ月が過ぎていたりします。
5. 情報や刺激が多すぎる現代社会
ここ10年、スマートフォンやSNSの普及により、私たちは膨大な情報や刺激を受け続けています。一見忙しく充実しているようでも、実は「流し見」「受け身の時間」が増えており、振り返るとあまり記憶に残っていない。そのため、「いつの間にか1日が過ぎてしまう」感覚が増幅されています。
6. これからの人生を、どう「濃い時間」にできるか?
時間が早く過ぎていくこと自体は、ある意味「充実している」「忙しい」証拠でもあります。しかし、50歳が目前になると、「このままで良いのか」「もっと1日1日を大切に味わいたい」という気持ちも強まります。
そこで今日から心がけたいことを考えてみました。
新しいことに挑戦する
趣味や学び直し、新しい場所への散歩や旅行など、日常に“新鮮さ”を取り入れることで時間の質が変わります。
1日の記録をつける・振り返る
日記や手帳、スマホアプリなどで、1日のできごとや気持ちを書いてみましょう。意外と「こんなにいろんなことがあったんだ」と気づかされます。
人との出会いや会話を大切にする
たまには昔の友人と連絡を取ったり、家族と深く話したり。新しい人と交流するのも、刺激になります。
自分の心と体を大事にする
忙しさに流されすぎず、好きなこと、リラックスできること、体を気づかうことも忘れずに。
まとめ
「毎日があっという間!」と感じるのは、年齢や環境、社会のせいばかりではなく、私たちの心の持ち方にもヒントがあります。
50歳を目前に、これまでよりも“意味ある1日”を増やし、人生後半戦をより濃く、楽しく過ごしていきたいですね。
みなさんも、もし同じような悩みや思いがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。これからも“今この瞬間”を大切に、一緒に年齢を重ねていきましょう。