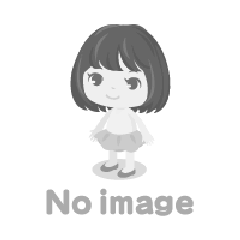新NISA「めんどくさい」は正解! 荻原博子氏、森永卓郎氏、楠木建氏ら経済専門家が手を出さない理由
「みんなにいいさ! NISAがいいさ!!」
日経平均株価が34年ぶりの高値圏となり、盛り上がりに拍車がかかっている「新NISA」。日本証券業協会が冒頭のように呼びかけるほどに、1月に制度が始まるやいなや、日本中を挙げてのお祭り騒ぎとなっている。
いまや “やらなければ損” という風潮の新NISAとは、どういった仕組みなのか。
「通常の投資では、儲かった額に対して約20%の税金がかかりますが、NISAを利用して投資すると、儲かった額が丸々手取りになります」
と話すのは、経済ジャーナリストの荻原博子氏(69)だ。
「さらに、今回始まった『新NISA』では、『つみたて投資枠』が年120万円、『成長投資枠』が年240万円と従来の2~3倍に拡充され、非課税となる期間も無期限となっています」
2022年9月、岸田文雄首相はニューヨークで講演し、「老後のための長期的な資産形成のため、NISAの恒久化は必須だ」とぶち上げている。新NISAに乗り遅れてしまった写写丸世代は、今からでも始めるべきなのか。
■無責任な数字で煽る金融庁は “罪” だ(経済評論家、ジャーナリスト・荻原博子氏)
「いえ、やめるべきです。たしかに、新NISAは株価が上がったときは非課税の恩恵を受けられます。しかし、今は株価が右肩上がりでも、この先、確実に株価が上がっていく保証はまったくありません。それなのに、下がったときはなんの手当てもないのです」(荻原氏)
NISAは通常の投資と違い、納税する際に損失と利益を相殺して税金を減らすことができる「損益通算」や「繰越控除」はできないのだ。
金融庁は、ホームページで子育て世代にNISAの活用を推奨しているほか、毎月5万円、年間60万円を積み立てた場合、10年間で98万7000円の運用収益が出るというグラフを掲載している(想定利回りを3%で計算)。
このシミュレーションを見れば、初心者は “必ず儲かる” という錯覚を起こすだろう。
「こんな無責任な数字を出して、金融庁は罪だなと思います。投資は怖いもので、絶対なんてありません。なのに、国と金融機関が投資の “博打感” を覆い隠し、国民を駆り立てているようにしか見えません。国民に払う年金を抑えたい国が、『自分の老後は自分でやって』と、切り捨てようとしているのでしょう」
荻原氏が警鐘を鳴らすのは、これまでに多数、「投資信託はこりごりだ」と嘆く人たちを見てきたからだ。
「2000年に『ノムラ日本株戦略ファンド』という投資信託を野村證券が売り出し、退職金を注ぎ込んだ方がたくさんいました。ところが売り出した直後にITバブルが崩壊し、6割以上も暴落。値を戻すまでに20年近くかかりました。投資信託は、値上がりも値下がりもするということを理解しておくべきです」
■将来に備えたお金を投資に回すのは厳禁(獨協大学教授、経済アナリスト・森永卓郎氏)
経済アナリストの森永卓郎氏(66)も「新NISAは絶対にやってはいけない」と訴える専門家の一人だ。
「私は、新NISAを始めるのは、今ではないと考えています。投資は、相場が下落したタイミングで、 “ギャンブル” として一気に勝負をかけるべきです。老後や子育てなど、将来に備えたお金を投資に回すものではありません」
森永氏も数年前までは、株価は長期的に上昇していくと予測していたという。
「しかし、今は実力以上の株価をつけている会社が少なくありません。リーマンショック直前にも株価はバブルで、FRBも今と同様に5%超まで利上げを続けていました。その後に利下げに転じ、2%台まで下がったところでバブルが崩壊したのです。今回も、同様の事態が起きる可能性があると考えています」
森永氏は、その対処法として「債券を買うべき」と語る。
「米国債の10年債は、現在も4.3%の利回りがあります。直近の円高リスクを避けるためにも、米国債の20年債や30年債を買うべきです。ただ、債券そのものは新NISAでは買えません。そういう意味でも、いま新NISAをやる必要はないのです」
■お金が減るのはイヤ。利回り1%で十分だ(一橋大学特任教授、経営学者・楠木建氏)
一橋大学特任教授の楠木建氏(59)も、債券に投資しており、新NISAは利用していないという。
「僕の専門は競争戦略で、ある企業が競合会社よりも優位に立ち、長期的な利益を出す論理について研究しています。しかし、そんな僕でも個別株の値動きはわからない。戦争や地震、為替の変動など、競争戦略の外にあるものの影響が大きすぎるからです」
貯蓄以外の金融資産は、信託会社の担当者に運用をまかせている。
「お金のことについて考えるのがとにかく面倒なんです。僕は、年間1%でも利回りが出れば泣いて喜ぶタイプ。担当者には、とにかく低リスクで運用するようお願いしており、ポートフォリオの大半は社債になっています。だって、汗水垂らして働いて得たお金が、いきなり減ってしまうのはイヤじゃないですか。競馬を観るのは好きなのに、馬券は絶対買わないくらいケチなんです(笑)」
今のように株価が急騰している局面でも、楠木氏は焦ることはない。
「なんか儲かりそうだなとは思いますが、高リターンということは必然的に高リスクですよね。個別株はリスクが大きすぎます。損したり得したりというプロセスを、趣味として楽しめる人以外は、新NISAを使ってインデックス投資をするのはいいでしょう。いろいろな銘柄に長期分散投資し、低コストで運用していくぶんには、新NISAは合理的です。面倒なので僕はやりませんけど(笑)」
まわりの誰もが新NISAを始めているからといって、焦る必要はない。あなたが始めようとしたタイミングが、ちょうど買いどきかもしれないのだから。
資本主義の崩壊で日本でも「イモのつる」ばかり食べる時代がこれからやってくる
格差社会、弱肉強食、差別社会、新自由主義のドンズマリで冷酷な99%の国民が1%の奴隷になって働き続ける時代に投入してしまうのか?もう入り口を入ってしまっているのか?
一部の人間に富が集中する経済のあり方が批判されている。特にコロナ禍以降は人々の意識にも変化に兆しがあるという。経済アナリストの森永卓郎氏と、東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏の対談書『国民は知らない「食料危機」と「財務省」の不適切な関係』(講談社+α新書)から一部を抜粋・再編集してお届けする。
これから大変革の時代がやってくる
森永卓郎(以下、森永) 私は昭和32年生まれで、周囲の大人たちはみんな太平洋戦争を経験していました。戦争中は食い物がまったくなかった。サツマイモを植えたけど、イモが大きくならない。だからイモのつるばかり食べたと聞かされていました。サツマイモのつるなんて、まずくて食えたものじゃないですよ。
そういう話を聞かされていましたから、いずれ食料危機が現実になると聞いても、それほど驚きはない。グローバル資本主義の崩壊も迫っているわけですから、そのくらいの大変動は覚悟しています。
大変動は経済だけではありません。政治システムの崩壊ももうすぐだと思っています。明治維新のような大変革の時代がやってきます。
「創業100年企業」が大量に生まれている
森永 実はこの3年ぐらいで、「創業100年企業」が大量に生まれているんです。毎年1000~2000社くらいのハイペースで。なぜかと言うと、いまから100年ぐらい前に創業した企業が大量にあったから。
いまから100年前に何が起きたのか。
そのころはちょうど不況の時代でした。第1次世界大戦が終わり、戦争特需、日本にとっての外需が喪失しました。
そこにスペイン風邪の大流行が発生し、世界経済がダメージを受けた。
その直後、今度はウォール街で大暴落が発生し世界恐慌がはじまった。日本は昭和恐慌に苦しむんですが、その影響で庶民のライフスタイルが大きく変化する。変化を余儀なくされたというか、庶民が初めて積極的にライフスタイルを変えていった時代なんです。
ライフスタイルが根本から変わった
森永 当時の流行語は「和洋折衷」。当時エリートと富裕層は、明治維新以来、欧米の文化をすでに取り入れていた。でも庶民はまだまだ江戸時代の生活を引きずっていたんです。
その庶民も洋服を着て、文字は万年筆や鉛筆で書くようになった。自転車に乗り、椅子に座って生活する。ライフスタイルが根本から変わったんです。
そんな時代にあわせて、万年筆のパイロットとか、椅子のコトブキといった企業が、雨後の筍のように創業した。100年前はそういう時代だったんです。
次のバブル崩壊の後も、同じような大変革が起きると思います。
「1%の富裕層が残り99%を搾取する経済をどう思うか」 東大生の答えは…森永卓郎が「若い世代の価値観が変わった」と言うワケ
森永大変革は3つの軸で起きると思います。すなわち、「大規模から小規模へ」「グローバルからローカルへ」「中央集権から分権へ」の3つ。
日本はずっと中央集権でしたが、次の時代は分権化の動きが進むだろうと思います。
コロナ禍によって、「何か違うぞ」と気づく人が爆発的に増えた。とくに若い世代にそういう人が多い。
田舎に移住するのも、私みたいな年寄りだと、なかなか地域社会に溶け込めなくて大変だったりします。でも若者なら大丈夫です。だから若い人の間で田舎に移住する動きが目立っている。
私は大学でゼミを持っているんですが、若い世代の価値観がものすごく変わったと感じます。
「ついに6000万円の仕事取れました」
森永ゼミを持ったのはいまから18年前ですが、そのころは就職状況が良くなかった。だからどの学生も一部上場企業に入ろうとしていた。もちろん入れなかった学生も多かったのですが、その後転職して上場企業に入っている。それが18年前の価値観なんです。
最近はむしろベンチャー企業に就職する学生が増えましたね。あとは、自ら事業を始める学生が出てきています。
最近一番成功した教え子は、大学在学中にアメリカへ行き、現地で「1人でCM映像を作る」というビジネスを見つけ、日本に持ち帰ってきた。営業もやって、台本を書いて、撮影も編集も一人で行う。最後にBGMを入れて、1本あたり100万円で売る。
彼が卒業するときに「ビジネスの調子はどう?」と聞いたら、「先生、ついに6000万円の仕事取れました」と言っていました。まだ学生なのにですよ。
「1%が搾取する経済をどう思うか」への答え
森永「編集機とかどうやって買ったの?」って聞いたら、「先生、いまはパソコンでできますよ」。「カメラは?」「ハイビジョンのカメラ、いまなら1万円ぐらいですよ」。「カメラマンはどうしてるの?」「ドローンを飛ばしてるんで。360度カメラだから、後で適当に画角を切れるんです」と(笑)。もう時代が違うんだなと思いました。
私がテレビの仕事をはじめたころって編集機が1台2000万円もしましたから。
鈴木東大の学生に、世界の1%の富裕層が、残りの99%から搾取する経済についてどう思うか聞いたんです。すると一部の学生は「その1%になればいい」と答えましたよ(笑)。
それも1つの考え方かもしれません。でも、その1パーセントの富裕層も、世界経済の大転換が起これば危うくなる。
普通の東大生は深く考えていない
森永いやいや。私も東大の理科二類なので、なんとなく雰囲気はわかります。志の高い学生もいるにはいる。でも普通の学生は「理二は受験が楽だからとりあえず入った」という感じです。
鈴木私は文科三類。就職するとなると大手の商社とか、マスコミ、官僚が多い。いきなり起業する学生はいませんでしたね。
森永私の周りは8割がた銀行に就職しました。みんなあまり深く考えていなかった印象です。私もそうでした。
財務省は「れいわ新選組」を相手にしていない
鈴木私は卒業して農水省に入りましたが、古巣の農水省も今後の大転換でガラッと変わるかもしれない。これまでのように仲間うちだけで政策を決めるわけにはいかなくなるでしょう。
森永元農水大臣の山田正彦さんの勉強会に参加して、一緒にお酒を飲んだんですよ。彼は元民主党の人ですが、いまはれいわ新選組の応援をしているそうです。
状況が変わると人も結構変わるものですよね。
ちなみに、れいわ新選組は財務省の支配下になっていない例外的な党です。
財務省は主要な政治家のところに「ご進講」に行く。そうやって緊縮財政と増税が唯一正しい政策だと洗脳するんです。
山本太郎さんに、れいわ新選組には来ないのかと聞いたんですが、一度も来たことがないと言っていました。
その話を財務省OBの高橋洋一さんに聞いてみたんですが、「財務省はれいわ新選組を相手にしてないからだよ」と言っていました。
必ず上がると信じて「FIRE」を目指した人の末路…森永卓郎が勧める「バブル崩壊に強い資産」が「農地」である「納得の理由」
森永 いま「FIRE(ファイア)」という、早期引退して、投資のリターンで左うちわで暮らすのを目指す若者が増えているんですが、私はずっと呆れているんですよ。お前らいい加減にせえよと。
だってこれからエブリシング・バブルが崩壊するんですよ。投資のリターンで左うちわどころか、資産が10分の1になるかもしれないのに、よくFIREなんて目指すよなと。それこそ暴落で焼かれて丸焦げになってしまう。そういう意味のFIREならまだわかりますが(笑)。
鈴木 いまはバブル経済が崩壊する寸前ということですよね。その後は森永先生が実践されているような、より農業を重視する社会に変わってくるでしょう。持続可能で豊かな生き方をしていかないと、地球環境も資本主義ももう持たない。
森永 バブルが崩壊すると、世界からお金が消えてしまう。だから資産をお金として持っている人は危ない。経済評論家の三橋貴明さんは、講演会で「いま、何に投資をしたらいいですか?」と聞かれ、「農地」と答えたそうです。
実際、彼は長野県の飯田市に土地を買って、将来はそこで農業をはじめるそうです。
よく農業委員会を通りましたねと言ったら、農地として買ったわけじゃないので大丈夫なんだそうです。彼はたくさんお金を持っているから買えるんです。
投資商品を買うより、農地を持っているほうが安全です。飢え死にしませんからね。
政府はNISAを拡充して「貯蓄から投資へ」と言っていますが、それに安易に乗っかるとひどい目に遭うと思います。
森永 田舎に行くと、家と畑と山がセットで1000万円以下くらいで買えるんですよ。山なしだと、100坪ぐらいの家が500万円しない価格で売りに出ている。
だから住宅ローンを組む必要さえないんですよ。真面目に貯金すれば、500万ぐらいは貯められるでしょう。
先述した三橋さんの言う「農地を買え」という投資法も、それなりに正しいんじゃないかと思います。
うちは農地を持っておらず、借りています。一応買おうとしたんですが、本物の農地は農業委員会の壁があって買えなかったんです。
ただこの前、長崎在住の女性から、「やる気になれば買えるのよ」と教えてもらいましたけど。「農業委員会にダメって言われても、乗り込みなさい」と(笑)。その人はそうやって農地を買ったそうなんです。
「マイクロ農業」に広い畑はいらない。先に触れたように日当たりが良ければ30坪もあれば十分。だからわざわざ農地を買う必要もない。しかもうちの近所だと1500万円もあれば住宅地を買えるんです。
鈴木 三橋さんは、「鈴木さんのお話を聞いて、自分でもやろうと思った」とおっしゃってました。
森永 じゃあ、三橋さんに指南したのは鈴木先生だったんですね(笑)。