水曜日のカンパネラ『聖徳太子』
2023.10.18 配信
2&2&3&1&1&8=17・・・1&7=8
水(4)曜(18)日(4)=26(4&9=13 9&4=13)・・・2&6=8(4 4)
538年 仏教伝来
574年(6/2) 厩戸皇子誕生 「聖徳太子絵伝」 四天王寺所蔵
604年 憲法十七条
622年(2/22) 聖徳太子死亡 49歳
5&7&4&6&2&2=16&10=26・・・2&6=8
太子には「豊聡耳(とよとみみ)」というお名前があります。
よきさとい耳を持っておられたという意味です。また一度に
8人の訴えを聞かれたので「八耳(はちじ)」の王ともいわれました。
夢殿 八角堂

夢殿(奈良時代)
西暦601年に造営された斑鳩宮跡に、行信僧都という
高僧が聖徳太子の遺徳を偲んで天平11年(739)に
建てた伽藍を上宮王院といいます。その中心になる建物が
夢殿です。(パンフから)
737(天平9)年、都で天然痘が流行し、藤原氏など政治の中枢
にいた人物が相次いで亡くなった。これを聖徳太子の怨霊の仕業
だと考えた人々は、太子が亡くなってから100年以上を経てから、
夢殿を建て、太子の供養をしたのではないかという推論がある。
それほど太子の霊が強力で、何らかの形で強い影響力が残って
いたということなのだろうか。この時に夢殿に祀られた救世観音
は、太子の等身であると伝えられており、太子は当時としては
かなりの長身だったということになる(像高は178.8cm)。
つまり、太子の怨霊を恐れた人々が、太子を神として祭り上げて
夢殿の扉を閉ざし、更なる災難を繰り返さないように、太子の
等身像を白布で巻いて封印したというストーリーが浮かび
上がってくるのである。
フェノロサの貢献
メモ:救世観音のお開帳は、毎年4月11日から5月5日と、10月
22日から11月22日の年2回である。
4&1&1&5&5&1&2&2&1&1&2&2&2=16&11&2=29・・・2&9=11
【法隆寺お会式 歴史・簡単概要】
法隆寺お会式(おえしき)は夢殿(ゆめどの)が建立された後の
748年(天平20年)から行われていると言われています。748年
(天平20年)2月22日、行信僧都が第45代・聖武天皇の勅許を
得て法要を行ったと言われています。ちなみに夢殿は739年
(天平11年)に行信僧都が聖徳太子(しょうとくたいし)を偲び、
聖徳太子一族の住居であった斑鳩宮(いかるがのみや)の旧地に
建立した言われています。その後1121年(安元2年)からは聖徳
太子摂政像が安置されている聖霊院でお会式が行われるように
なりました。なおお会式は622年(推古天皇30年)2月22日に
亡くなった法隆寺の開基・聖徳太子の命日に遺徳を偲ぶ法要です。
お会式ではお仏飯・重ね餅・黄の小判餅・ネコ耳・白の小判餅
・ケイピン・三輪素麺・金柑・青豆・カヤの実・ホオズキ
・ミズクワイ・白豆・ネズミ耳・クワイ・干柿・八角柱の切餅
・紅白寒天・黒豆・銀杏が供えられます。供物は古い記録に則って、
1か月ほど前から僧侶などの手作りで準備されるそうです。
2&2&2&2&=8(4 4)(11×4)
お供え物20種類=2(1 1)
ネコ耳&ネズミ耳=12&17=29・・・2&9=11
太子の正式な名前である「厩戸皇子(うまやどのみこ)」の
名前も、このエピソードから来ているとされています。この
出生時のエピソードのあった橘の宮を、のちの聖徳太子が
橘寺に改めたことから、橘寺が聖徳太子の生誕地と呼ばれる
ようになったのでした。
「厩(14)戸(4)皇(9)子(3)」=30
「和(8)」
30&8=38・・・3&8=11
「橘(16)寺(6)」=22(11×2)
2015/01/21
聖徳太子の愛馬の像です。太子が27歳の時、甲斐国から黒駒
が献上されました。空を駆ける天馬とされ、太子はこの黒駒
に乗り、空を飛んで富士山の山頂に立ったという伝説があります。
また太子は仏教を学ぶために郊外の斑鳩の宮に住みましたが、
そこから飛鳥まで続く太子道(たいしみち)と呼ばれる道を、
この黒駒に乗って通ったともいわれています。
黒(11)駒(15)=26
太(4)子(3)道(11)=18
26&18=44(11×4)

御祭神:
幣立神社(九州)・・・神漏岐命、神漏美命、大宇宙大和神、天御中主神、天照大神
石鎚神社(四国)・・・石鎚毘古命(いしづちひこのみこと)
大剣神社(四国)・・・安徳天皇 大山祗命 素盞嗚命
天河神社(近畿)・・・市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)
伊勢神宮(近畿)・・・天照大神 豊受大神
諏訪大社(中部)・・・建御名方神 とその 妃 ・ 八坂刀売神
氷川神社(関東)・・・須佐之男命(すさのおのみこと)稲田姫命(いなだひめ
のみこと) 大己貴命(おおなむちのみこと)
橋広バロン幸之助![]() MJGA💫@hasibiro_maga
MJGA💫@hasibiro_maga
七星剣 中国の道教思想に基づき北斗七星が意匠された刀剣
法隆寺の銅七星剣(七星文銅太刀) 丙子椒林剣とともに
聖徳太子の佩刀である
2021/11/30
👆
北斗七星&北極星(一)=8

👆
黒駒に橘の家紋![]()
橘寺(たちばなでら)は、明日香村(飛鳥宮跡の近く)にあり、
聖徳太子建立七大寺の一つに数えられとともに、聖徳太子生誕
の地ともいわれますが、創建については、よく分かっていません。
飛鳥の謎の石造物の一つである「二面石」も橘寺にあります。
橘(16)寺(6)=22(11×2)
七&一&一&二=11
明日香村は、飛鳥時代に都がおかれ、日本初の律令国家体制
が築かれたところです。渡来人がもたらした高い文化が栄え、
日本の仏教が興隆したところでもあり、当時の史跡が数多く
発掘されています。
なお、橘という名の由来は、『日本書紀』にあります。
太子を身ごもっていた穴穂部間人皇女が橘の宮の敷地を散策
していた際、厩(馬小屋)の入口付近で産気づき出産したと
されています。
非時香菓(ときじくのかくのみ)=「常世の国に生える不老長寿の実」
「昔の恋を思い起こさせる花」として、平安の昔から存在して
いる花がある。それが、橘の花。花言葉は、「追憶」。
晩春から初夏にかけて、小さな白い花を付ける。

(コバルトブルー地 橘尽し模様 塩瀬染名古屋帯・菱一)
五月待つ 花橘の香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする
(古今集・巻3 夏歌139)
橘は、「追憶」あるいは「不老不死」の花として、人々が愛しみ、
今に至っている。なお、キモノや帯の文様としては、不老不死の
意味合いが強く、「吉祥文」として位置付けられている。

コウライタチバナCitrus nipponokoreana は萩市と済州島のみに自生する。
聖徳太子磯長墓(叡福寺北古墳)
叡福寺は、推古天皇30年(622年)旧暦2月22日(太陽暦4月11日頃)、
太子が49歳で薨去された後、前日に亡くなった妃 膳部郎女(かしわべ
のおおいらつめ)と、2か月前に亡くなられた母 穴穂部間人(あなほべ
のはしひと)皇后と共に埋葬され、推古天皇より方六町の地を賜り、
霊廟を守る香華寺として僧坊を置いたのが始まりです。
神亀元年(724年)には聖武天皇の勅願により七堂伽藍が造営されたと
伝えられます。
3&3&2&2&4&9&2=11
六&七=13
11&13=24・・・2&4=6







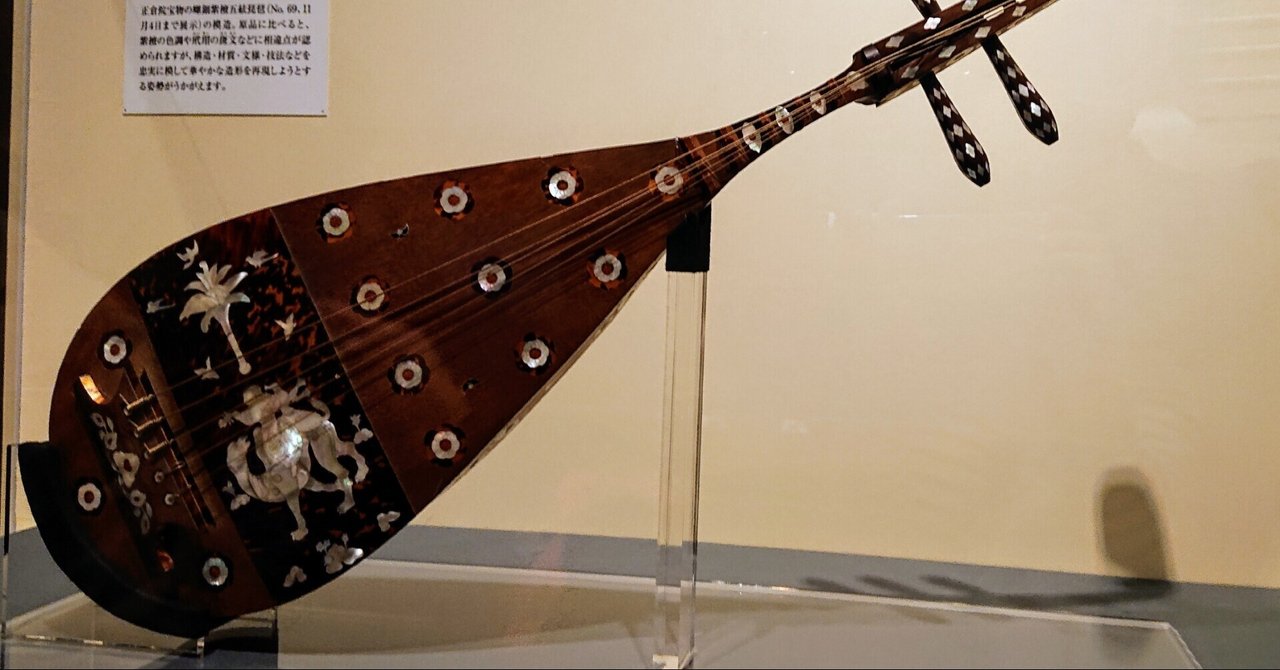






![聖徳太子と斑鳩京の謎ミトラ教とシリウス信仰の都[久慈力]](https://shop.r10s.jp/book/cabinet/7684/76846957.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)