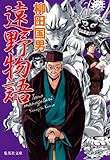民俗学者 柳田国男 『涕泣史談』② | ドット模様のくつ底
- 遠野物語 (集英社文庫)/柳田 国男
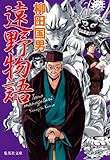
- ¥540
- Amazon.co.jp
長くなりましたが、
ようやく本題です。
「泣く」ことの歴史。
このことに氏が問題として提出されたことは、
あまりに最近五十年の社会生活において、
激変した一事項であり、
各々が関心を持たずにには居られない
一現象であり、
しかも、記録文書の自然の登録に任せておいては、
誤った推量に導かれると言う経験を持っているからとしています。
人が「泣く」ということは、
近年著しく少なくなっていると氏は言います。
このことを五木氏が現代に取り上げられた通り、
72年たった今でもそれほど大きくは
変わらないことであるように思いました。
当時の例でいうと、
『婦人之友』か何かの雑誌で、
子どもを泣かせぬようにするのが育児方法の理想であると、
論じていた夫人がいたそうです。
そしてこのことは現代の公論であり、
有力に結果の上にも顕れているのかと思うと言います。
しかし、「泣く児は育つ」「泣く児は頭堅し」という類の諺や、
子どもは泣くのが商売だからと平気でそう言っている母親もあり、
実際には、夜泣きに閉口するけれども、
生まれたばかりの赤ちゃんはあまり泣かぬと気にかける母親もいます。
そして
今日の有識人に省みられていない事実の中、
泣くということが一種の表現手段であったのを、
忘れかかっているのではないかとしています。
この点に立脚して考えると、
同じ一つの「ナク」という動詞を
もって言い表されるもう一つの行為、
「涙をこぼす」「悲しむ」「哀れがる」行為、
すなわち忍び泣きと呼ばれる方の「ナク」は、
単語としては同じでも全然別種のものであって、
しかも現在はこの両者間に大きな混同が生じていることが
認められ、
そして、
表現は必ず言語に依るということは
これは明らかに事実と反していて、
特に日本人は眼の色や顔の動きで、
かなり微細な心のうちを表現する能力を備えているので、
「泣く」という表現方法でしか表せないものが
あるのだということなんですね。
言語以外の表現方法は、
総括してこれを
「しぐさ」または挙動と言っています。
この語では狭きに失して
「泣く」までは含まないように感じるそうです。
言葉をもってする表現技能の進歩と反比例に、
泣くという表現方法が退却していくのは、
子どもから少年、青年へとだんだん泣かなくなっていくのが
よい証拠で、誰だって自由に思ったことが言えるならば、
物好きに泣いてみるということはないこと。
しかし、氏の観測する通り、
老若男女通じて泣き声の少なくなってきた時代とすれば、
それは何らかの他の種の表現手段、
その中でも主として言い方の
大いに発達した結果と推定して間違いはなく、
なお一方に、泣くことは、
人間交通の必要な一つの働きであることを認めずに、
ただひたすらにこれを嫌い憎み、
または賤しみ嘲るの傾向ばかりが強くなっていたり、
表現手段として他の方法がなくても、
なお泣くまいと努力する人が見られると
このように氏は人間を観察しています。
「男は泣くものでない」
いう教訓があったものの、
葬式では儀式として「泣女」という
上手に泣く女性に頼み泣いてもらっていたと
いう風習があったこともあり、
また自然に泣きたくなり涙がこぼれたことからも、
儀式としてそうした人を使うことは、
心から泣く人と少しも差別されなかったことは、
女は特にその古い仕来たりに背くに忍びない
やさしさをもっていたのかと思われるといい、
これがいつのまにか廃れたのは一種の覚醒としています。
弁慶は一生泣かなかった。
もしくは弁慶でも泣くだろうなどと、
非凡の例としてよく人が引くのも、
裏を返せば、平凡人は時々泣いていた証拠であるとし、
今日、一様にめったに泣かなくなったことは、
これが変遷でなくて何であろうかと問いかけます。
ということで、
ここでは泣きの歴史は近年で大きく変わったことを
科学的な分析のされていない時代から
氏独自の主眼によって書かれているのです。
氏の旧友、国木田独歩などは、
あまりに下劣な人間の偽善を罵る場合に、
よく口癖のように
「泣きたくなっちまう」と言ったそうです。
氏も時折、その口癖を真似するそうです。
そのくせお互いに一度たりとも、
声を放って泣いてみたことはなく、
泣かずに済ませようとしている
趣味となっているのだそうです。
ここまでは氏の体験談を中心とした
「泣く」ことの歴史考察の勉強でした。
長文となりました。
ここまで読んで頂きましてありがとうございました!
③につづきます。