今日もお越し下さりありがとうござゐます☆
カタカムナってなんなの~?
というまったくの初心者の方向けの
かんたんカタカムナ入門のおはなしの二回目です。
一回目を読んでゐない方は、お読みになってから、
この記事を読んでね~(*'▽')
⇒【かんたんカタカムナ入門】ひとつの巻
【かんたんカタカムナ入門】ふたつの巻
ひふみよい
まわりてめくる
むなやこと
あうのすへしれ
かたちさき
そらにもろけせ
ゆゑぬおを
はえつゐねほん
日本の和歌の形式とされる五七調で詠まれた、
この『カタカムナ四十八音』といわれる歌は、
〇と一と│の三種類の図形の組み立てで
造られた図象(カタカムナ文字)として残されてゐました。
四十八音の図象を用い、四十八音とは別の図象を中心に
渦を巻きながら、八十首もの歌が詠まれてゐます。
その八十首のうち、五首、六首が、四十八音が重ならず、
まるでいろは歌のように詠まれてゐるのです。
(六首の末尾のみ「カタカムナ音」が再び詠まれてゐます)
〈カタカムナウタヒ五首〉

〈カタカムナウタヒ六首〉

〈カタカムナ文字の発見はいつ、どこで、だれが?〉
このカタカムナ文字は、昭和24年に兵庫県神戸市にある
六甲山系金鳥山で、電位学者の楢崎皐月氏により、発見されました。
第二次世界大戦中から、鉄の専門家として、
満州で働いてゐた楢崎氏は、枯れ葉5~6枚に火をつけただけで、
あっという間にお湯が沸いてしまうという不思議な鉄釜を
持ってゐた蘆有三(ろゆうさん)という老人に出逢います。
蘆有三より、「古代日本にはとても高度な文明を築いた、
八鏡文字(はっきょうもじ)という文字を使うアシア族がゐて、
その民族がこの鉄釜をつくり、日本から伝わってきた」
ということを聞いた楢崎氏。
終戦で日本に帰国後、日本各地の電位を測定する中で訪れた金鳥山で、
父親がカタカムナ神社の宮司をしてゐたという、
平十字(ひらとうじ)という人物より巻物を見せてもらう。
その巻物に書かれてゐた図象が、ひょっとすると
満州で聞いた「八鏡文字」なのではないか?とピンッときて、
渦巻状に図象が描かれてゐた「文書」をすべて書き写させて戴いたそうです。
そして、楢崎氏はその後の人生をこの巻物に描かれてゐた図象の解読に専念し、
何十年もの研究の末、図象が文字であること、日本語の四十八音の文字であること、
カタカナの源流であることを突き止め、そして、渦巻状に描かれてゐる文字で
歌を詠んでゐることを読み解きました。
その内容は、一見、現代のわたしたちが使ってゐる日本語の単語
(たとえば、「トキ」「トコロ」「クニ」「アメ」「ヒメ」など)の
羅列なのですが、興味深いのは、その羅列する単語をつなぎ合わせると、
古事記に出てくる神さまの名前だったり、日本の土地の名前になるのです。
神さまの名前も、古事記に登場する順番に出てくることから、
わたしたち日本人の祖先の人々が詠んだとしか考えられないほどです。
このカタカムナ文字が描かれてゐる文書は、
楢崎氏が巻物から模写したものしか残っておらず、
遺跡として発見されてゐないため、
縄文時代以前の時代の文明につくられた文字と推測されてゐます。
また、このカタカムナ文字が発見された六甲山系金鳥山の近くには、
現在、芦屋市があることから、満州で蘆有三が語ってゐた、
「古代日本で文明を築いてゐたアシア族」と重なること、
また、アシア族⇒アジアの名称の源流ではないかと推測されてゐます。
8月21日表参道ハピ女カレッジ文化祭、参加者募集中☆


⇒〇〇〇カタカムナ四十八音ヨソヤコト思念表〇〇〇
カタカムナのLINE@配信
ご登録者募集中◎
友だち検索で、@katakamunaを検索の上、友だち追加すると登録できます♪
カタカムナ 言霊の超法則: 言葉の力を知れば、人生がわかる・未来が変わる!/徳間書店

¥1,728
Amazon.co.jp
ブログランキング《エッセイ・随筆》/ブログ村《潜在意識》、皆様のお蔭様で上位キープ☆大感謝☆
引き続き一日二回ポチポチッと応援して戴けましたらうれしいデス☆ありがとうございます~☆


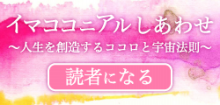
また、ご縁がありましたらうれしいです

