2014年7月に、生命保険と破産、とくに生命保険が成立したものの、その後に保険金受取人に対して破産手続開始決定がなされ、さらにその後に被保険者の死亡などの保険事故が発生した場合に、保険金請求権が破産財団に帰属するのか、あるいは保険金受取人に帰属するのか、についてブログ記事を書きました。
・生命保険と破産/解約返戻金・保険金請求権の帰属
その後、まさにこの論点が争点となった平成24年の高裁判決があることを知ったので、紹介します。
■追記(2016年6月)
最高裁判決に関するブログ記事もご参照ください。
・【最高裁】破産手続開始後に生じた死亡保険金請求権は破産財団に帰属するとされた判例
2.事実の概要
Yは破産手続開始決定前から長男Aを保険契約者兼被保険者、保険金受人をYとする生命保険会社Bの生命保険などに加入させていました。ところがその後、Yは破産手続開始決定を受け、その後にAが死亡するという保険事故が発生しました。
Yは保険会社Bに対して保険金の支払い請求を行い、保険金の支払いを受けました。これに対して、破産管財人Xがその金銭を引き渡すよう求めたのですが、Yが拒んだため、訴訟となりました。
3.判決の概要・東京高裁平成24年9月12日判決(確定)
Yの抗告を棄却
「一般に、保険金請求権は、保険契約の成立とともに保険事故の発生等の保険金請求権が具体化する事由を停止条件とする債権(以下、具体化事由の発生前の保険金請求権を「抽象的保険金請求権」という。)であって、抽象的保険金請求権のまま処分することが可能であるのみならず、法律で禁止されていない限り差押えを行うことも可能であるところ、破産手続開始決定が、破産者から財産管理処分権を剥奪してこれを破産管財人に帰属させるとともに破産債権者の個別的権利行使を禁止するもので、破産者の財産に対する包括的差押えの性質を有することに鑑みると、その効果が抽象的保険金請求権に及ばないと解すべき理由はない。」
「したがって、破産手続開始決定前に成立した保険契約に基づく抽象的保険金請求権は、「破産手続開始決定前に生じた原因に基いて行うことがある将来の請求権」(破産法34条2項)として、破産手続開始決定により「破産財団に属すべき財産」(同法158条1項)になるというべきである。」
「生命保険請求権が、死亡事故が発生するまでは具体化する確率の極めて低い権利であり、受取人変更の余地もある不安定な権利であることなどを考慮しても、破産手続開始決定時において、将来の発生が予想され一定の財産的価値をもつことは否定できないのであって、これを破産債権者のための配当財源とすることが合理性を欠くものということはできない。」
「破産者の経済生活の再建の機会の確保を図ることは破産制度の目的のひとつであるが、これは自由財産の拡張の決定(同法34条4項)において考慮、対応すべき事柄であり、当該財産が破産財団に帰属するか否かの判断に関わるものではない」
4.検討
(1)学説
私の2014年7月のブログ記事でもふれたとおり、受取人の破産手続開始決定後に保険事故が発生した場合の保険金が保険金受取人のものになるのか、破産財団のものになるのかについては、学説上の争いがあります。
そのひとつは、破産手続開始前に発生済の停止条件付請求権で破産手続開始時に条件未成就のものは、破産手続開始前に「成立」していれば、保険金請求権者は停止条件付請求権としての抽象的保険金請求権を有するので、保険事故の発生が破産手続開始決定後でも保険金請求権は破産財団に帰属するという、破産法・民事訴訟法の学者の先生方にオーソドックスな考え方です(伊藤眞『破産法 第4版補訂版』171頁など)。
これに対して、保険事故発生前の抽象的保険金請求権は保険事故の発生により具体化するまでは具体化する確率の非常に低い権利であり、保険金受取人変更がなされる可能性があることから抽象的な権利であって、財産的価値も小さいから破産者の債権者としては責任財産として期待すべきではないので、抽象的保険金請求権が停止条件付請求権であるとしてもそれに関する一般原則をそのまま適用すべきでないとする反論が商法・保険法の学者の先生方からなされています(山下友信『保険法』544頁)。
そして、この商法・保険法の学者の先生方の学説の側に立つと解される裁判例として、大阪高裁平成2年11月27日判決(判例タイムズ752号216頁)があります。なおこの事件は上告されましたが、最高裁は原審の判断は是認できるとして上告棄却としました(最高裁平成7年4月27日判決・生命保険判例集8巻123頁)。(私の2014年7月のブログ記事をご参照ください。)
このような商法・保険法学者の学説(あるいは保険会社の考え方)の背後には、保険金請求権という債権の特殊性に対する価値判断があるものと思われます。
つまり、保険金請求権ももちろん金銭債権の一種ではありますが、しかし、保険契約は、銀行の預金債権などとは異なり、いったん解約されると、被保険者の健康状態や年齢によって、再度加入できなくなってしまうおそれがあります。そのような事態は、被保険者や保険契約者、その家族である保険金受取人の保護のために望ましくありません。
現在の東京地裁の実務取扱においても、生命保険契約の解約返戻金の金額が原則として20万円以下であれば、その保険契約は破産財団に属さないという取扱をしており(「20万円基準」)、また、破産管財人と協議のうえ、保険契約者側が解約返戻金相当額を支払う代わりにその生命保険契約を破産財団から離脱させて保険契約を存続させる、という和解的な方法が採られることがあります。
(2)東京高裁平成24年9月12日判決
しかし、このたび出された東京高裁平成24年9月12日判決は、うえであげた、破産法・民事訴訟法的な考え方に全面的に立つことを示しました。
そして、商法・保険法学者や保険会社が懸念する、保険契約者やその関係者の保護の問題に関しては、本判決は、「破産者の経済生活の再建の機会の確保を図ることは破産制度の目的のひとつであるが、これは自由財産の拡張の決定(同法34条4項)において考慮、対応すべき事柄であり、当該財産が破産財団に帰属するか否かの判断に関わるものではない」と判示しました。
また、この東京高裁平成24年9月判決の弁論においては、被告Y側が、大阪高裁平成2年11月27日判決などを持ち出して抗弁を行いました。しかし、裁判所は、この平成2年判決は、あくまで裁判時点においては被保険者が高度障害状態になっていなかったことを判断したにすぎないなどとして、その主張を退けました。
このように、この平成24年の東京高裁判決は、下級審判決であり、また、ややマニアックなものではありますが、保険に携わる人間にとっては注目すべき判決です。今後、学者の先生方の新しい論文なども出されるものと思われます。
■参考文献
・田中秀明「破産手続き開始後に生じた死亡保険金請求権の破産財団への帰属の要否」『保険判例の研究と動向2014』73頁
・判例時報2172号44頁
・山下友信『保険法』543頁
・中尾正浩「保険契約者の破産」出口正義・平澤宗夫など『生命保険の法律相談』192頁
・伊藤眞『破産法 第4版補訂版』171頁
・西謙二など「特集 新破産法実務の展開を語る」東京弁護士『LIBRA』2005年08号2頁
 |
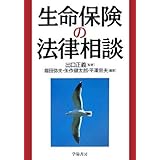 |
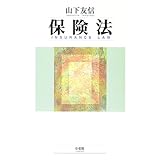 |
法律・法学 ブログランキングへ
にほんブログ村