-----------------
「そして二人だけになった Until Death Do Us Part」
森博嗣 著 出版社:新潮社
ISBN:9784101394312 値段:705円(税別)
- そして二人だけになった―Until Death Do Us Part (新潮文庫)/新潮社
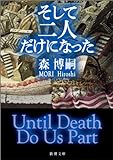
- ¥788
- Amazon.co.jp
あらすじ:「全長4000メートルの海峡大橋を支える巨大なコンクリート塊。その内部に造られた「バルブ」と呼ばれる閉鎖空間に科学者、医師、建築家など6名が集まった。プログラムの異常により、海水に囲まれた完全な密室と化した「バルブ」内で、次々と起こる殺人。残された盲目の天才科学者と彼のアシスタントの運命は……。反転する世界、衝撃の結末。知的企みに満ちた森ワールド、ここに顕現。」
-----------------
Vシリーズ「黒猫の三角」の直後に出されたシリーズ外長篇小説。今までもシリーズ外はいくつか紹介しました(探偵伯爵と僕、カクレカラクリなど)が、この作品が初シリーズ外というものになります。シリーズ外ということでS&MやVとはまた一味違った雰囲気になっているなと感じました。
天才と聞くと、森博嗣作品で行くと、どうしても真賀田四季を連想してしまいますが、彼女よりかはカリスマ性が低い天才科学者を扱っています。ただ、性格がクール(淡泊?)であるだとか、「個」としてのヒトではなく「人類」という大きな目線で我々を見ている部分など、「天才」の描き方に関しては相変わらずな気がする。
初めて読んだ時は、結構退屈しながら読んでいた気がしますが、再読したら、二回目の方が面白く読む事が出来ましたね。おそらく物語の構造が理解できたからなのでしょう。初めて読んだ時は構造を解き明かすのに精いっぱいだった印象があるので、きっとそこがなくなった分物語にすんなりと入ることができたのだろうと思います。
-----------------
解説の方も書かれているのですが、何度も読んでしまいたくなる、そんな「魅力」をもった作品のような気がします。今回のタイトルなんてもう某有名推理小説にオマージュささげたようなものになっています。でも、森さんの作品は英題も意外と物語の根幹を表している時が多く、今回の英題、「Until Death Do Us Part」というのは「死が二人を分かつまで」という意味。これはこの作品のキーワードと言っても過言ではない。一体、これがどこで使われているのか、それが意味する所は?なんて考えていくとかなり面白い。読み終わった後、英題を見返して「ふ~ん、なるほどねぇ」となってしまうか、「ちくしょう!そういう意味かよ」となるか。どっちだろうねぇ。
-----------------
森さん独特の言葉のチョイス。それは正に「シンプル」かつ「無駄がない」。ミステリィ要素だとかトリックはS&Mには負けるかもしれないが、物語の深みというのは断然今作の方が良いだろう。S&Mシリーズは本当に森博嗣入門編だと思う。今作はその入門編をある程度読んだ人が読めば「あれ?なんかいつもと違うぞ?」というのが分かると思う。
森作品は、V含めてここら辺から「一定の解答」はなく、「考えるな、感じろ!」というのが強くなっている気がしました。Vにしてもそうなんですが、謎を解き明かそうとはしなくなってくるし、今作にしても「真実」については一応提示されます。しかし、それを額縁通りに受け取るか、「一部は真実、あと虚言」と取るか。正に「それは君が、決めるんだ」という状態になってきている気がしないでもない。
今作のラストは特に紛らわしく、「え?そうだとしたらこの時はどうなってんの?」とか色々と出てくるかもしれない。それを自分の中でどう消化するのか、読後も色々と考えさせる辺りが、森さんらしいが、不親切と言えば不親切なんだろう。だから、これを「アンフェア」というならばそれはそれで良いと思うし、「許容範囲内だ」というのであればそれも正しい。「すべては君が、決めるんだ」(何度も言うな!)
-----------------
答えとか内容をつらつらと書くことは簡単です。そう、解説の方も書いているが、簡単なのです。ですが、それではなんていうか味気ない。もしかしたら、今後も森さんの作品を紹介していくれけど、内容を描くというよりはこういう感じが描かれていたなぁとかこう感じたなぁというのが多くなりそうな気がします。特にGになってからはそういうミステリよりもドラマ性がますます強くなっていきますからね。ミステリの解答をかくというよりは、もう本当に「ココが良かったんだよォ~」とかになりそう。
ミステリィなのにね。トリックが凄かったとかそういうのがおそらく出ない気がします。うん、出ないな。多分。
それでは、こんかいはここまで。
=================
次回は、
夏の物語を、冬に紹介するという
季節感0で御免なさい。
「真夏の方程式」
=================