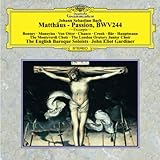プールでリハビリ→リハーサルその①→フラメンコ修行という日程。
移動中はAMね。
で、ちょっと面白い話を聴いたので、思い出してみる、・・・と。
N村雅俊さんの番組にて、恐らくクラシック関係者のゲスト氏が色々とお話を。
オーケストラと指揮者の関係について、裏話をしてはりました。
ある指揮者が○○オーケストラに招聘されたとします。
そうしますと、初回のリハーサルにおいて、その後の出来は9割がた決まってしまうとか。
指揮者を迎え撃つオーケストラの受け入れ態勢としてはいくつかの段階があって、
まずは団員の方々はとりあえず、「お仕事」をしようという構えでそこに挑むと。
与えられたことを確実にこなせばそれで良いと、そういう意味での「お仕事」です。
この段階では指揮者が誰であろうと一緒というわけです。
「与えられたこと」
これすなわち受動的な関り方であります。
ところが、リハーサルにおいて、楽曲に対するイメージ等、「そんな解釈があったのか」「そんな演奏法があったのか」、というような、類まれなエッセンスを提示されますと、団員達は「是非この作品を創ることに参加したい」と思うようになるのだとか。
カリスマといわれた指揮者、例えばカラヤンのような人は、本番はただ指揮棒を音楽の上に添えていただけだったそうです。
すなわち、リハーサルの段階で全てが完成され、闘魂が注入されつくされた状態のため、オケが勝手に音楽を奏でてくれていたと。
これは関係がうまくいっている例。
いっていない例はどんなんかといいますと、
何かいやな指揮者がきたとします。
今日は地方公演。
もう少し速く終演できれば一本早い新幹線に乗れるのにな・・・。
という雰囲気がオケに漂いますってぇと、コンサート・マスターはその空気を敏感に感じ取り、全ての曲を「ちょい速めに」弾くそうです。
そうすると、早く帰れるから。
コンマスが速めに弾けば、オケは付いていかざるを得ず、指揮者はオケに追随するしかないと・・・。
あ~あ。
な展開。
大きな声ではいえませんがね。
とは、ゲスト氏。
・・・これラジオなんですけど。
願わくば、そんなコンサートには居合わせたくないものです。
さて、直前の「指揮者が嫌われた例」は極端なバッド・エンディングとして、成功例の方も、それはそれで「?」な部分は残ります。
というのは、ラジオのゲスト氏は、「リハで全てが出来上がっている」ので、「指揮者は何もせんでも良い」ということを言っておられたので。
この字面を真に受けますと、
本番はリハの模倣、或いは再現か?
という話になってきませんか?
私の考える「ライブ」的では無いな、と。
これを字面どおりととって巷の音楽に当てはめると、「面白い」という感覚には程遠いものになるかと思いますが、こと、クラシックの話ですから、何かもう一山ありそうな気もするんですね。
その「もう一山」の可能性としては、キリスト教などが絡んでくるかもしれないな、と思いつつ、詰めが甘い私はそろそろ休もうかと思います。