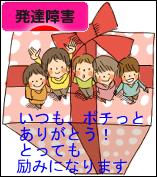特別支援教育部門 第9位
自閉症育児部門 第8位
子どもの発達障害の受容が進み、理解が高まってくると、母親の子供へのかかわり方にも変化が現れます。子どもの特性を踏まえた教え方や、叱り方がわかってくるのでしょう。しかし、その姿が、世間からは「躾の甘さ」と映る事があります。世間の不理解で、折角進んだ障害理解が裏目に出るわけです。今日はそんなお話です。
【理解が進むと、子どもに無理強いが無くなる】
親の側に発達障害への理解が高まってくると、教育熱心な親であっても、子どもの特性や状態を見極め、無理な指導を控えるようになっていくようです。
また、発達障害児の精神安定をもたらす為には、周囲環境を構造化するなどの整備が大切です。こうした配慮は、基本的に先回りの支援と言う性格を持っています。子どもの阻害要因となりそうな環境を除いたり、子どもに予定をしっかりと明示する事で、彼らの安心を担保します。しかし、こうした事も理解の無い周囲から見ると、過保護と映ってしまうことがあるようです。
発達障害に関しては、当事者が大人であっても、子どもであっても、ひとつ言えることは、この障害を、自分の周囲にカミングアウトするメリットが、この日本では余り無いという現実です。世間や社会にこの障害に対する理解は少なく、障害に関する啓蒙も進んでいません。また最近は少しマシになってきたようですが、一時期犯罪報道などでショッキングに取り上げられたことで、余り良くないイメージが定着した事実もあります。
本来は、周囲の理解者を増やすことが一番大切な障害なのですが、現在の社会理解ではそうした効果を期待できない現状があります。
こうした現実と、前述の「過保護ではないか」という周囲の目には、大きな関わりがあり、現在の発達障害の親子をめぐる不幸のひとつといえると感じます。つまり、周囲にカミングアウトできない現実があり、啓蒙が進んでいないことが、こうした厳しい視線を生んでいる訳です。
そして、追い込まれた母親は、結局、周囲の目を気にする余り、子どもに対して厳しく叱っていくしかないような状況があるように感じます。
【叱らない母親に向けられる厳しい世間の目】
こうした発達障害児に適した教え方、叱り方のところで、僕は最近あるブログを見つけました。申ももこさん の記事です。その記事 では、ご自身が当事者でもある申ももこさんが、母親として、発達障害児の息子さんにどのように物事を教えたり、叱ったりしているかが示されています。しかし、そのやり方は世間には理解されず、周囲からももこさんご自身が怒られるようなことがあったそうなのです。
さて、記事からのエピソードの紹介です。
申ももこさんは、お子さんが2歳の頃に「異食」に苦労したそうなのです。
「異食」とは、家では本や紙を食べたり、
公園では砂や土を食べてしまう行為のことです。
異食をする度に「食べないでね」と伝えたそうですが、
お子さんはニコニコしながら、食べる事をやめなかったそうです。
そうした様子を見た周囲の人たちは、
「子どもをしっかり叱らないから、なめられているんじゃないか」
と言ってきたそうです。
また、別の日に、お子さんがバス内でパニックを起こした際には、
泣き叫ぶ子どもさんと申ももこさんに、
周囲は厳しい視線を送ったと聞いています。
【マナーが悪いのと、パニックとは、見た目に判らないのだろうか?】
確かに、僕自身も街を歩いていたり、電車に乗っていたりして、
明らかにマナーの悪い親子は居るように感じます。
悪ふざけの度が過ぎたり、不真面目だったり、
他人の迷惑を気にかけない態度が、目に付くことはあります。
しかし、そうした行動と、発達障害の問題行動は、
良くみれば違いが分かると思うのです。
それは、障害に知識がなくとも、何となく感じると思うのです。
ましてや、パニックを起こして泣き叫んでいる子どもと、
それを賢明に諌めようと対処している母親に対して、
迷惑そうな視線を周囲が投げかけるならば、
世間のどこに一体バリアフリーがあるのだろうと言いたくなるのです。
僕自身も、子どもがこういった状態になったときに、
周囲から厳しい視線を向けられた時は、ただ謝るしかありません。
ただ、その一方で、自分たち親子のこのつらさは、
結局、誰にもわかってもらえないばかりか、
こうして非難の目まで向けられてしまうのだと悲しくなります。
障害の啓蒙も大事だとは感じますが、
社会全体で、子ども達をノビノビと育てるようなところがもう少しないと、
子どもの情緒も育まれないのではないかと、僕は思います。
ももこさんは、ご自身の障害特性からか、
どう叱ってよいか思い浮かばず、
世間から見て叱っているように見える方法ではなかったのですが、
彼女なりに息子さんに適していると考える方法で、
教えたり諭したりしていたようなのです。
彼女がどんな考えで息子さんに対応していたかは、
別の記事で、また詳しく述べるつもりなのですが、
こうしたことに周囲の理解は中々得られなかったようなのです。
世間は「定型発達の子達にやるような方法」を躾と考えており、
そのやり方とは違っていると、
「しつけが甘い」と厳しい目を向けてくるそうなのです。
「不真面目だったり、マナー違反はダメ」でよいと思いますが、
困っている親子に非難の目が向かないような包容力が、
社会にはもう少しあって欲しいとおもうのです。
皆さんのクリックがとっても励みになります!
【告知です!】
日頃の生活を離れ、ゆったりと過ごすお時間はいかがでしょうか
同じ境遇を持つもの同士、悩みを語ったり、
判らないことを聞いてみたり、
互いの経験を交換し合って、問題をひとつひとつほどいていく・・・・
そんなグループを目指して、開催しています。
2011.04.08(金) 10:00~14:00
大阪市北区・中央区の貸し会議室にて開催!
少人数(10人)制 要予約