- フリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略/クリス・アンダーソン
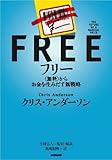
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
昨今、こんな高機能なものまで無料なの?ってサービスも多かったりしますが、当然そういうのはからくりがあるわけで、そのフリーのからくりを解き明かしてくれる本です。
フリーの歴史、そして無料のものに触れた場合の人間の心理、無料への一般論への反論、フリーのビジネスモデルまで、様々な観点でフリーの裏側を解説しています。
期間限定で無料で使用できる、機能限定版は無料で利用可能、学生など特定の条件に合えば無料で開放するといったソフトウェアやサービスを目にしたことは多いと思いますが、それらをより多くの人に関心を持ってもらい、そこから一部の人に対して料金を徴収するといったモデルで成り立っていたりします。
フリーミアムと呼んでるそのモデルを通し、試用期間が過ぎた後の有償版への乗換えや、より高度で多機能な有償のサービスプランの利用、そのソフトウェアに対して昔から馴染みを持つことで社会人になってからも継続して利用してもらうなどなど、現在では多くの企業がそういったフリーの特性を活かしてサービスやソフトウェアの提供を行ってたりしてるんだなと。
特にサービスやソフトウェアというのは、一つを作ってしまうと簡単にコピーができるため、日用品に比べて一人一人に割り当てるコストが気にしなくても良いレベルまで下がっている、というところがフリーミアムのモデルの根本であると解説されています。
逆にそこをついて海賊版が横行している結果を招いたりもしますが、中国やブラジルでの例を取り上げながら、横行している違法コピーをうまく利用したビジネスモデルなども紹介されていて、企業(個人)として何を売るのかという対象が変化していっている現状を目の当たりにさせられます。
現在の若い人たちは多くの無料のソフトウェアやサービスを使うことに慣れていることもあるため、有償版のみの提供だけだとそれがよっぽど優れたもので、自分の日常に必要なものでないと利用もしてくれなかったりします。
フリーというのはその垣根を極端に低くしてくれるので、その認知性を活かして利用者を増やし、その一部に課金したり、大規模なプラットフォームを持つことで広告などメディアとしての収入を得たりと、既存のビジネスモデルからの脱却というのも過渡期として迫られている時期なのかもしれないと感じます。
目次
第1章 フリーの誕生 第2章 「フリー」入門 - 非常に誤解されている言葉の早わかり講座 第3章 フリーの歴史 - ゼロ、ランチ、資本主義の敵 第4章 フリーの心理学 - 気分はいいけど、よすぎないか? 第5章 安すぎて気にならない - ウェブの教訓 = 毎年価格が半分になるものは、かならず無料になる 第6章 「情報はフリーになりたがる」 - デジタル時代を定義づけた言葉の歴史 第7章 フリーと競争する - その方法を学ぶのにマイクロソフトは数十年かかったのに、ヤフーは数ヶ月ですんだ 第8章 非収益化 - グーグルと二十一世紀型経済モデルの誕生 第9章 新しいメディアのビジネスモデル - 無料メディア自体は新しくない。そのモデルがオンライン上のあらゆるものへと拡大していることが新しいのだ 第10章 無料経済はどのくらいの規模なのか? - 小さなものではない 第11章 ゼロの経済学 - 一世紀前に一蹴された理論がデジタル経済の法則になったわけ 第12章 非貨幣経済 - 金銭が支配しない場所では、何が支配するのか 第13章 (ときには)ムダもいい - 潤沢さの持つ可能性をとことんまで追求するためには、コントロールしないことだ 第14章 フリー・ワールド - 中国とブラジルは、フリーの最先端を進んでいる。そこから何が学べるだろうか? 第15章 潤沢さを想像する - SFや宗教から、<ポスト希少>社会を考える 第16章 「お金を払わなければ価値のあるものは手に入らない」 - その他、フリーに対する疑念あれこれ
各章に挿入されている、米国を中心とした実際のフリーのビジネスモデルに関するコラムも必読です。