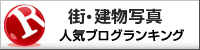今回からは足利氏館(鑁阿寺)の紹介
です。2020年8月6日に訪問しました。
最初はその歴史からです。
元足利氏館の鑁阿寺南山門と太鼓橋です。
現在地にある案内板です。
現在地の周辺案内板です。(上が北)
渡良瀬川の北側に立地しています。
平安時代に河内源氏の棟梁:源義家
(八幡太郎義家)の四男:源義国は、
下野国足利荘(栃木県足利市)を相続
して本貫とし、源義国次男の源義康
(1127~1157年)以降の子孫が
足利氏を称しました。この頃に足利
氏の館として成立します。1142年
に鳥羽上皇が建立した安楽寿院に
足利荘を寄進、義康は下司となりま
す。久安の頃に上洛し、所領の寄進
が機縁となって鳥羽上皇に北面武士
として仕え、蔵人や検非違使に任官
します。また陸奥守にも任ぜられて、
「陸奥判官」とも呼ばれました。
将来を嘱望されますが、31歳で病
没します。
足利氏略系図です。
約4万平方メートルに及ぶ敷地は、
元々は足利氏の館(やかた)であり、
現在でも、四方に門を設け、土塁
と堀がめぐらされており、平安時代
後期の武士の館の面影が残され
ています。またこの事から「史跡
足利氏宅跡」として、大正10年3
月に、国の史跡に指定されており、
現在では「日本の名城百選」にも
なっています。
寺院としては、鎌倉時代初期の、
1196年(建久7年)源姓足利氏
2代目の足利義兼(よしかね)が
発心得度し、邸宅内に持仏堂を
建てたのが始まりとされます。
義兼死後、その子義氏が建立
した本堂は、1229年に落雷
により焼失したが、足利貞氏
が禅宗様式を取り入れ改修し
ました。日本としては禅宗様式
への転換期の最初期にあたり
ます。
国宝の鑁阿寺本堂です。
本堂の解説板です。
徒然草216段にある鑁阿寺紹介
「最明寺入道(五代執権北条時頼)が、
鶴岡八幡宮に参詣のついでに、足利
左馬入道のもとへ、前もって使いを
遣わして、立ち寄られた時に、主人
として接待されたその様子は、最初
の膳にはのし鮑、二番目の膳には
えび、三番目の膳にはかいもちひ
で終わりになった。その座には亭主
である足利夫婦と、隆弁僧正が主人
側の人としてお座りになっていた。
さて、「毎年いただいています足利
の染物が、待ち遠しいです」と申さ
れたので、「用意してございます」
といって、色々の染物を三十疋、
最明寺入道らが並み居る前で、
女房たちに小袖に仕立てさせて、
後からお届けになったといいます。」
このことから織物が盛んだったよ
うです。
鎌倉時代から室町時代にかけて
寺院として次第に整備され、室町
将軍家、鎌倉公方家などにより、
足利氏の氏寺として手厚く庇護
されました。
境内には本堂のほかにも、鐘楼
、一切経堂が国の重要文化財、
東門、西門、楼門、多宝塔、御霊
屋、太鼓橋が栃木県指定の建造
物です。
鑁阿寺の周囲をめぐる堀です。
今回はここまでで、明日に続きます。
読者募集中ですので、読者登録はここのリンクです。
希望があれば、読者相互登録します。
毎日午後8時半頃に更新しています。
「相手わかるように」に設定して読者登録してください。
読者のブログ村・ブログランキングは出来るだけ押しに行きます。
Ctrlキーを押したままで、ポチしたら画面が飛ばされません。
お手数ですが、よろしく。![]()
![]() ぽちっと
ぽちっと![]()
![]() 押すだけ
押すだけ