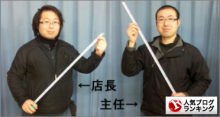冬は天気の良い日の方が寒いですよね。
どうも、主任の平田敬(たかし)です。
本日は昨日の続きで、カーテンの歴史というか、豆知識をお届けしますね。
前回はカーテンそのものの始まりについてお話しましたので、今回は「カーテン」って日本にいつ入ってきたんでしょう?というお話を主任と一緒に見ていきましょう。
いつ入ってきたかお話しする前に、そもそも「カーテン」が入ってくる前って日本では何を使っていたんでしょうか?
日本でカーテンの原点といえるものは、平安時代(794年~1192年頃)にまで遡ります。
几帳(きちょう)という絹の織物で作られた衝立(ついたて)が間仕切りのように使われていたり、
御簾(みす)という竹製のすだれや、壁代(かべしろ)という絹の織物で壁面に掛けられた布が使われていました。それがカーテンの原点だと言われています。
几帳について詳しいページはこちら
御簾について詳しいページはこちら
壁代について詳しいページはこちら
これらが武家時代になると、壁や襖(ふすま)や障子(しょうじ)に代わっていきました。
ちなみに武家時代というのは鎌倉時代(1185年~1333年)から江戸時代(1603年~1867年)の末までの約680年間のことを言うようです。主任は初めて知りました(笑)
そして日本でカーテンが使われるようになったのは、江戸時代初期に長崎の出島にある外国公館で使われたのが初めてだ、というのが通説のようです。
でもそれはあくまで「日本国内でカーテンが使われた」のが初めてってだけでまだまだ日本人が使うのは後になります。
実際に日本人が使ったのは江戸時代末から明治(1868年~1912年)にかけての時代だったんじゃないか、と考えられています。
その頃は「カーテン」ではなく「窓掛け」と言われていて、ほとんどが輸入品で高価なものだったようで、庶民の方々にはまだまだ使われてはいなかったようですね。
「カーテン」という言葉が使われるようになったのは明治末期になってからのようです。
大正(1912年~1926年)に入って徐々に広まって行き、関東大震災後は建物の近代化・洋風化が進んだようで、カーテンは増えていきました。でもまだ一部の上流階級のものだったようです。
それから昭和30年代(1955年~)に入ってから、ようやく一般住宅に本格的にカーテンが普及し始めました。それはアパート建設や、住宅産業が盛んになった影響のようですね。
その後昭和40年(1973年)の第一次オイルショックを境に、省エネへの関心が一般の人々にも広まって、カーテンは家庭の必需品として定着していったようです。
日本にカーテンが入ってきて広まったのはこういう流れのようです。やはり、日本の住環境の変化とともにインテリアも近代化・西洋化してきたんでしょうね。
ずっと身近にあったカーテンにもこういう歴史があったんですね。こういうことを調べるのもなかなかオツなものです。特に主任の勉強になりました(笑)
それでは今回はこの辺で。
↓なるほど~、という方は是非クリックお願いします♪↓