
監督:原恵一、声の出演:杏、松重豊、濱田岳、高良健吾、美保純、清水詩音、筒井道隆、麻生久美子、立川談春、入野自由、矢島晶子、藤原啓治のアニメーション映画『百日紅~Miss HOKUSAI~』。
原作は杉浦日向子の同名漫画。
主題歌は椎名林檎の「最果てが見たい」。
文化十一年(1814年)、両国橋から望む江戸の町を舞台に葛飾北斎とその娘・お栄や居候の池田善次郎(のちの渓斎英泉)ら、此岸と彼岸のあわいを往き交う浮世絵師たちが織りなす人間模様。
まず、僕は日頃から日本製のアニメをまったく観ていなくて(僕の最近の日本アニメへの偏見は『サカサマのパテマ』というアニメ映画の感想をお読みいただければわかると思います。※ファンのかたは要注意)、良い印象を持っていません。
映画館でよく目にする日本アニメの予告篇には虫唾が走るほどで。
ところが、TVでこの映画の紹介をやっていたのを偶然目にして興味をそそられました。
原作は未読だったし、僕は原監督の『カラフル』を劇場公開時に観ていて、あの作品は世間一般では高く評価されてますがこれまた僕はまったく受けつけなくて、「この監督のアニメは自分には合わない」と思ったのでした(『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』は面白かったですが)。だからこれはまったく予想だにしていなかった。
何よりもまず、主人公のお栄さんの「顔」のインパクトに魅せられて。
僕は浮世絵のことや江戸文化などについてはまるっきし無知で、北斎に娘さんがいて彼女も浮世絵師だったことすら初めて知ったんですが、Wikipedia読むと実際のお栄さんはアゴがしゃくれてて父親からは「アゴ」と呼ばれていたそうで(まんまじゃねーか^_^;)容姿も色黒であまり美しくなかったとのこと。
原作でも「化中(ばけじゅう)」と呼ばれて男たちには不美人扱いされているが、特にブサイクに描かれているわけでもなく、これといって特徴のない顔つきをしている。
というか、漫画的には充分美人だ。

基本的にアニメの方も他のキャラクターたちは原作の絵柄を踏襲しているんだけど、このお栄さんの顔だけは多少アニメ用にデザインし直されていて、目尻は上がって気の強さが強調されて、受け口を表現しているのか下唇が若干前に出ている。


いわゆる流行りのアニメ絵美人の顔じゃないのが、逆に妙に気になって。
背筋の伸びたスラリとした体躯や大きな瞳などからも、どこか声を演じる杏さんを思わせる。
まるで「ごちそうさん」のヒロインがアニメになったみたい。
また、僕は原作についてもほとんどなんの予備知識もなかったんだけど、映画を観ながら「あぁ、この映画の原作は多分短篇集なんだろうな」と思ってたら、その通りだった。いかにも短篇を繋げたような作りだったから。
映画は原作漫画上下巻全30篇の中からエピソードを抜き出して1本の長篇に仕立ててある。
原作漫画は映画の鑑賞後に買って読んだんですが、原作と映画が互いにうまい具合に補完しあっていて、両方に目を通すことでより深くこの「百日紅」の世界を味わうことができます。
そもそも原作ではお栄さんは主要登場人物ではあるが「主人公」といえるかどうかも微妙で、エピソードによっては北斎や善次郎、歌川国直が主役の時もあるし、お栄がまったく登場しない話もある。
北斎の末娘のお猶(おなお 演:清水詩音)は映画では重要な存在だが原作では1つのエピソード「野分(のわき)」に登場するのみで、彼女と姉のお栄のふれあいのシーンを映画用に付け加えて膨らませ、それを主軸にお栄をヒロインとすることで江戸に生きた一人の女絵師の物語になっている。

お栄さんのあの面妖な顔立ちや妖怪変化の類いの描写など、ちょっと高橋葉介の漫画「夢幻紳士」を思いだしたりした(好きなんですよねー)。
劇中にたびたび登場する筆による絵の数々が目に心地良くて、できればああいう絵柄で全篇通してほしかったぐらいなんだけど、多分それは技術的にも面倒で金もかかるんでしょうね。製作費50億の高畑勲監督の『かぐや姫の物語』じゃないんだから^_^;

雲から龍の姿が覗く場面は『かぐや姫』にも同様のシーンがある。「百日紅」の方が先なんだけど。
『かぐや姫』は1枚1枚を紙に手描きしたようなその手法と内容が合致していて、現在のアニメが古くは絵巻物から始まることを語っていたが、この『百日紅』もまた、アニメ映画の中で浮世絵を通してアニメについても語っている。
北斎が善次郎の描く絵を評する、現実にはありえない体つきのリアリティのない絵はフニャフニャしていてすぐ崩れてしまう、というくだりとか、そのまま「アニメ」についての言及とも取れる。
この映画の舞台となる1814年は「北斎漫画」が発行された年で、劇中でも北斎が善次郎をモデルにしてスケッチしているのが映しだされる(これも映画オリジナルの描写)。
ちょっと前に観た「華麗なるジャポニスム展」という展覧会に「北斎漫画」の一部が展示されていて、映画では善次郎がやっていた、鼻息でろうそくの炎を揺らしたり鼻の穴に棒を入れてドジョウすくいみたいな顔したり、顔を横に引っぱって伸ばしたりするあの百面相もありました。

「北斎漫画 十編二十丁表 百面相(部分)」
限られた線を駆使して確かなデッサン力によって描かれた誰にでもわかる「北斎漫画」には、それが今のアニメーション(それ以前に“漫画”があるけど)に繋がっていることがハッキリとうかがえたのでした。
この映画は「浮世エンターテインメント」と銘打っているけれど、それでもディズニーの長篇アニメなどとは対極にある小さな世界を描いたもので、男女のちょっと艶っぽい場面もあるし(滑稽でもあるが)、正直映画向きの題材ではないな、と思います。
原作自体が大人向けの短篇の連作で、どこから読み始めても構わないしどこでやめても困らないような作品だし(だから映画のラストのような明確な最終回もない)。
物の怪(もののけ)やデッカい仏様まで出てくるけど、「妖怪ウォッチ」みたいな(って観たことないけど)ファミリー向けのファンタジー映画ではまったくないです。
アニメだからってんで小さい子どもさんと観にいくと気まずい思いをすることになるんでご注意を。
だから誰にでもお薦めできる作品ではないんですが、ほんの少しだけ「江戸」の空気に触れた気がしてちょっと癖になる映画でした。
少なくとも『カラフル』の時のような不快感はまったくなかった(どちらも脚本は同じ人が担当しているのだが)。原作の魅力に負うところが大きいでしょうね。
自分が知らない時代を眺める楽しさがあった。
というわけで、これ以降はストーリーに言及しますので、映画をまだご覧になっていないかたはご注意ください。
お栄は父・北斎の絵の才能と性格を受け継ぎ、描く絵は父の弟子たちや町の人からも一目置かれると同時に本人はがさつな娘でもあって、煙管の火で父の絵を焦がしたのは史実らしい。
原作では絵の師匠であり実の父である北斎を普通に「鉄蔵」と呼び捨てにするところなど、まるで「じゃりン子チエ」のチエちゃんみたい。
春画も描くが、生娘なので男の絵は不得手で北斎の絵をそのまま引き写している。
現代でいえば、男性経験はないのにエロ漫画描いてる若い女の子みたい(そんな人がいるのかどうか知りませんが)w
男を知らないが春画を描き、家には若い男が居候していても平然としている。自分のことを「オレ」と呼び、男言葉を使う。一方で北斎の弟子の初五郎(魚屋北渓 演:筒井道隆)に岡惚れして幼い妹にそれを見抜かれてドギマギしたりウブなところもある。かと思えば突然男娼に抱かれたりする。ファンキーな人だ^_^;

演じる杏さんはこの映画のインタヴュー記事でその口からスラスラと当時の浮世絵師たちの名前が出てくるのでやけに詳しいなぁ、と思ったんだけど、そういやこの人、筋金入りの「歴女」でした。
彼女の若々しい声と竹を割ったような小気味良い姐さん口調が、この火事見物が趣味で普段は紙くずだらけの部屋の中で黙々と絵を描いているちょっと風変わりなヒロインを魅力的な女性に見せている。
北斎の声を担当している松重豊さんは、最近では映画やTVドラマなどで「飄々とした上司」みたいな役がテンプレ化してきていて、失礼ながらぶっちゃけいつも同じような役だなぁ、と思っていたんだけど、この作品ではこれまでのどの作品とも異なる声(ナレーションの時とも違う)を聴かせてくれた。
やたらと巻き舌でべらんめぇ調の(片岡鶴太郎が喋るような)耳障りな江戸弁ではなくて、一見ぶっきらぼうだが時に饒舌にもなり、わざとらしくないがボソボソと聞き取りにくくもないハッキリとした口跡。若い男たち(善次郎役の濱田岳や国直役の高良健吾など)は高めの薄っぺらい声のため、松重の落ち着いた声が実に耳に心地良い。
怪異の噂を聞きつければまるで妖怪ハンターみたいに(ハントはしませんが)出張っていく北斎が頼もしくて、その食えない親父ぶりには憧れもする。
お栄は時々人に憎まれ口を叩くところなど、父・北斎とよく似ている。時に言ってることと思っていることが裏腹なところも。
娘は父のことを「いくじなし」と言う。なぜ病気の末娘を見舞ってやらないのか、と。
このあたりのやりとりも映画オリジナルのものなので、原作漫画ではよくわからなかった家族関係が(映画でもあまり細かい説明はないが)おかげで多少わかりやすくはなっている。
これは北斎とその娘・お栄の、父と子、師匠と弟子の物語だ。
父は娘を半人前扱いしながらもじっと見守っている。女の絵を描かせたら「時によっちゃあ俺もかなわねぇと思うよ」と認めるところはしっかり認めてもいる。
自分の絵を代筆させたり春画まで描かせる父親。
破天荒な職人親子だが、お栄にはそんな生活もまんざらではなさそうに見える。
現実のお栄さんは一度結婚したが結婚相手の絵師の絵を笑って離縁されたそうで、『百日紅』の中でも善次郎を「ヘタ善」呼ばわりして彼の絵を容赦なくコキ下ろすけど、ほんとにそういう人だったんだなw のちに仏門に入り、北斎の死から8年後に消息を絶ったといわれる。
恥ずかしながら僕はこれまでこのお栄という女性の存在を知らなかったのだけれど、こういう魅力的な“ヒロイン”が現実にいたのだということ、そこになんともいえない感動を覚えるんですね。
僕が不勉強なだけでこのような女性を描いた小説や戯曲、漫画などは数多くあるんだろうけど、特にアニメで目にすることってあまりないので。
等身大の女性が描かれること自体が劇場アニメでは珍しいような気がする。
再三言ってるようにこの作品は別にヒロインが大冒険したり大恋愛するような派手な物語ではないので観る人を選ぶと思うんだけど、お栄さんにちょっと萌えちゃう人はいるんじゃないかな。
「離魂病」のエピソードに登場する花魁“小夜衣”の声は『カラフル』に続いて麻生久美子が担当。出番は短いが、『カラフル』の母親役とはまったく違う「ありんす」言葉の妖艶な美女役がハマっている。
“花魁”と椎名林檎の主題歌、という組み合わせは蜷川実花監督の『さくらん』を思わせるが、原監督は意識していたんだろうか。

「クレヨンしんちゃん」繋がりか、矢島晶子と藤原啓治(※ご冥福をお祈りいたします。20.4.12)が端役で参加している。
また、この作品は原作での登場人物たちの江戸弁の独特の言葉遣いが実際に耳で聴ける快感もある。
昔、漱石の小説などでよく見た「剣呑」って言葉、好きなんだよなぁ、とか。
「言っつくんな」みたいな言い回しとかもそうだけど、僕は江戸っ子じゃないから劇中で使われている江戸言葉がどれほど正確なのかはわかりませんが、なんだか新鮮で。
専門の声優を使ってほしかった、という意見もあるけれど、僕は杏さんや松重さんなど、声優じゃない人たちの起用はよかったんじゃないかと思います。
プロの声優さんならもっとこなれた声の演技ができたかもしれないけど、おかげで既成の声優にはない生っぽいリアリティが出たから。
これまでの原監督のアニメ作品を観ても、その声のキャスティングからはいわゆるアニメ作品にありがちなアニメの世界だけで閉じた演技ではなくて、生身の人間が演じているようにキャラクターを動かし喋らせたい、という狙いを感じる。
また悪口になっちゃうんだけど、『カラフル』では逆にアニメでやる必然性をまったく感じなくて、実写でやりゃあいいじゃん、と思ったのだった。
でも実写だったらもっとつまらなかったと思うけど。
それが今回の『百日紅』では、先ほど書いたようにアニメでやる意味が大いにあったし、あるかたがTwitterで呟かれてましたが、「江戸が関東平野に作られた町だということがよくわかる」。
江戸の空の広さを表現するにはアニメでやるしかなかっただろう、と。
妖怪変化や巨大な仏様の描写なんかも、アニメだからこその表現だと思ったし。
もしこれをCGを駆使して実写でやっていたら、技術的には不可能ではなくても作品として魅力的なものになったかどうかは疑わしい。
なぜなら、江戸の空気感や浮世絵の世界を実写で撮れる監督は今の日本にはいないから。
漫画やアニメーションならそれは可能だと思うのです。
僕が期待していたものがこの映画にはあった。
お栄とお猶が乗った舟を揺らす波が北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」のようになる映画独自の場面なども、やはりアニメならではの楽しさだ。

お猶の死を予感したお栄が町を疾走する場面の躍動感もそう。
そして木造家屋の影の部分の処理。
漫画でいう「ベタ」の部分の闇は観る者の想像力を刺激する。
この映画では萬字堂役で声の出演をしている立川談春がTVで語っていた「粋(いき)か野暮(やぼ)かというのは、カッコイイかカッコ悪いか、ということとは違う。もう“粋”としかいえないもの」というのは、明らかに野暮な人間の部類に属する僕にはその違いがちゃんとわからないのだけれど、浮世絵の世界もまたそういう「粋」だったり「野暮」だったり、あるいは「本物」と「贋物」の違いを見極めるようなまさしく「芸」の世界であり、『百日紅』もまたそういうものについてかすかに触れている。
お栄の実の母“こと”と北斎はなぜ別居しているのか。
北斎は盲目で身体の弱い末娘のお猶にどうしてなかなか会いにいってやらないのか。
お栄は北斎を「長生きしたいから病人の近くに居たくないのだ」と言うが、それは本当なのか。
原作でも映画でもいちいち説明しないので想像するしかない。
いちいち説明するのは「野暮」だということだろうか。
江戸文化の研究家でもあった原作者の杉浦日向子さんは当然この漫画では触れられていない細かいところまで知った上でフィクションとして表現したのだろうし、ともかく映画の中には僕などにはわからないことも含めて紛れもなく「江戸」という異世界が広がっていました。
そして妖怪変化や地獄極楽、春画をはじめ男女の「色」等々を通して、何か「人生」の断片を見ているようだった。
「死んだら地獄へ行くよ」と言うお猶。男娼が語った夢の中で現われた巨大な仏様は、自分を拝む人間どもなどお構いなしにゴジラのようにみんな踏み潰して歩き去っていく。
地獄はあるかもしれないが、「極楽」なんかないんじゃないかという乾いた絶望感。
最後の最後に幼いお猶は、一陣の風とともに姉とかつて雪景色の中で見た赤い椿の花びらを父・北斎に届けて去っていく。
お栄は、妹は地獄ではなく極楽に行ったのだ、と思う。
これも映画オリジナルのエンディングだが、原作に流れている無常観の上に原監督がほんのちょっと加えた「希望」に思えた。
最後に実写で現在の両国橋と隅田川が映る。
父親の死後、消息不明になったお栄。
実は生没年は不詳のため、映画では23歳とされる1814年のお栄の正確な年齢も定かではない。また彼女の実母で北斎の後妻“こと”(演:美保純)の本名もわかっていない。四女のお猶の存在についても諸説あるようだ。
原作者の杉浦さんはさまざまな説を参照しながら、想像力を駆使して“お栄”という現代にも通じる若い女性像を描き上げたのだろう。
庭の百日紅(原作では木瓜)を見て、母に「長ぁい祭りが始まったね」と呟くお栄。
人生は「祭り」。
過ぎ去っていくものもある人生をそれでもどっこい生きていく、そんな女丈夫の矜持を両国橋は今日もみつめている。
最後の両国橋の実写ショットについては「不要ではないか」という意見もあるのだけれど、あのワンショットで原監督がこの作品に込めたものがわかりやすくなっている。
もっともそれをあえて説明しない方が「粋」だった気もしないではないが。
1本の長篇にまとめられて見やすくなった分、まだその時点で原作を読んでいなかった僕には正直「あ、もう終わりなんだ」というちょっとした物足りなさがあったのも確かで、これはせっかくなら原作通りに短篇の連作として全エピソードを観たかった気はする。
たとえば善次郎は映画でも「女好き」ということになっているけど、原作での女がらみのエピソードが入っていないのでまったく女好きには見えないし、やはり原作ではちょくちょく顔を出す北斎の女弟子で愛人でもある井上政女(葛飾北明)は最後に初五郎と歩いているところをお栄が見かける、という出番のみ。
だから原作のファンの人がこの映画版をどう評価するかはわかりませんが、ただ、僕はお猶のエピソードを膨らませて姉妹を映画の中心に持ってきたことでよりこの作品に愛着が湧いたので、やっぱりこういう形で長編映画化してくれてよかったと思います。
何よりも、僕はこの映画の世界にもっと浸っていたかったから。物足りない、というのは「もう終わってしまうのが惜しい」ということです。
結論としては、僕の最近の日本アニメに対する偏見はこの映画でほんの少し修正されましたね。
いい作品だってあるんだよ、と教えられました。
7月公開の細田守監督の最新作『バケモノの子』も観にいく予定ですが、さていかが相成りますか。
関連記事
原作漫画「百日紅」感想
『バケモノの子』
『この世界の片隅に』
『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』
百日紅~Miss HOKUSAI~ [DVD]/杏,松重豊,濱田 岳

¥4,104
Amazon.co.jp
百日紅 (上) (ちくま文庫)/杉浦 日向子

¥734
Amazon.co.jp
百日紅 (下) (ちくま文庫)/杉浦 日向子

¥734
Amazon.co.jp
最果てが見たい/椎名林檎
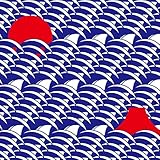
¥250
Amazon.co.jp
北斎娘・応為栄女集/久保田 一洋

¥2,160
Amazon.co.jp