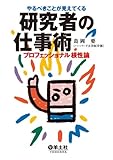【書評】やるべきことが見えてくる研究者の仕事術
小飼弾さんの書評記事 に触発されて読んでみた本。
僕は研究者ではなくビジネスパーソンであるが、十分に示唆に富んだ内容だった。
というよりも寧ろ、「研究者の」という形で限定する必要は無く、副題になっているプロフェッショナル根性論をメインタイトルに据えても良かったのではないかと思う内容だ。
本書のエグゼクティブサマリー的な位置づけとして著者の島岡さんが書いているのが、「研究者として仕事をすべき10の原則(研究者としての仕事力をつけるための成長の10のステップ)」という箇所。
step1. 興味を持てる得意分野を発見する
step2. 最初は自分で学ぶ
step3. 師匠を持つ
step4. 現場で恥をかく
step5. 失敗を恐れつつも、果敢に挑戦する
step6. 自分の世界で一番になり成功体験を得る
step7. 研究者としての自信をつける
step8. 井の中の蛙であったことに気付き、打ちのめされる
step9. すべてを知ることはできないことを理解する
step10. それでも、自分の新しい見識を常に世に問うていく
この中から取り入れていきたいポイントなどを見ていきたい。
「好き」よりも「得意」にこだわる仕事術(step1)
かの有名なドラッカーの教えや、それに基づくバッキンガムの主張(SBA仕事術)を拠り所としているため、ベースはビジネスパーソンに求められる仕事術にある。
つまり、本書では「研究者は「長所の強化」に専心してこそ、生産的な”強い”人生を送ることができる」(P.29)と書いていることは、そのままビジネスパーソンにも当てはまる。
もちろん、SBA仕事術の重要性については、今更繰り返すまでもないだろうが、「人は強みのある分野に最大の成長の可能性がある」という考え方に基づいている。
また、これに関して引用されている中村うさぎさんの言葉は秀逸。
「(人は)好きだったことを嫌いになることはあるが、得意なことが突然苦手になることはめったにない」(本書P.16、CW編集部「執筆前夜-女性作家10人が語る、プロの仕事の舞台裏。」より)
そして、こうした「強み」に偏った代表的な職人として僕の頭に浮かぶのは、かの名探偵シャーロック・ホームズ氏である。
特定分野に突き抜けた強みを有することで、プロフェッショナルとして活動するホームズは、憧れの存在として今尚僕の中にあり続ける一人だ。
この考え方の実践例になるだろうと思われるのが『奇跡の営業所 』。
※ご参考: 【書評】奇跡の営業所
モデルとなった吉見さんは、それぞれの強みを伸ばし、それらを組み合わせることで成果を得たとおっしゃっていた。
批判され/批判して自分を磨く「フィードバック力」(step4)
研究の場においては、研究成果を雑誌であったり学会であったりといった様々なところで発表し、それらに対する批判や意見を受けて、さらに突き詰めていくというプロセスが繰り返される。
他人の研究を正しく評価する能力をつけることは、他人に自分の研究を正しく評価してもらうための能力をつけることに他ならないのです。他人の研究を客観的に評価することができて初めて、客観的に他人の視点から自分の研究をみることができ、自分の研究が正当に他人から評価されるためにいかに修正や調整をすべきかを理解することができるのです。(p.75)
ここで「研究」を「ブログ」や「書評」に置き換えてみると、僕自身がフィードバック力を身につける必要性が実感できる。
また、コメントのやり取りや、書評紹介、書評コンテストなどによって、批判され/批判することを続けていくことの大切さを再認識し、これからも続けていく励みになる。
※したがってご意見、ご批判歓迎しているので、是非お願いしたい。
自分のストーリーを語る「物語力」(step7)
ビジネスシーンにおいても、「物語力」「ストーリー」の重要性は至るところで指摘されている。
今の時代、例えアカデミックな世界の研究者といえども、「異なった価値観を持った人々にメッセージを伝えるためには、専門的な詳細を抑え、相手の価値観に戦略的に”Framing(調整)”したストーリーを語ることの必要性」(p.106)が提示されているという。
もちろん、これはビジネスシーンでも同様であり、どんなに優れた製品やサービスでも、それらの持つ効用などを一生懸命説明するだけでは、お客様の心には響かないし、伝わらない。
ここにストーリーを以ってして語ることの重要性があるのである。
このあたりは以下の書評でも触れているので、併せて参照して欲しい。
【書評】価格、品質、広告で勝負していたら、お金がいくらあっても足りませんよ
この他にも、様々なビジネス書でも採り上げられている理論などが紹介されており、研究者達の間では浸透していないビジネスシーンでの王道的な仕事術を取り入れるという発想が見受けられる。
したがって、ビジネスパーソンにも該当する箇所が随所に見られるので、同様の書籍を好まれる方には幅広く手にとっていただける本になっている。
ただ、正直言えば、お値段がちょっと理系専門書の常識から設定されているような気がしてならない。
ビジネスパーソン向けの仕事術の本であれば、1,000円台半ば、1,200円から1,500円くらいがボリュームゾーンではないかと思うのだが、2,800円(税別)はちょっと手を出しにくい価格帯かもしれないと、個人的には感じた。
有名な書籍などでの考え方などがバランスよくまとまって体系化されているため、得られるものは間違いなくあると思うし、「研究者の」と銘打たれているだけに、新鮮な角度からの発想も見られる。
お値段の問題はあるものの、これからプロフェッショナル人生を歩む若手ビジネスパーソンにお薦めしておきたい。
もちろん、タイトルどおり、アカデミックな世界に生きる研究者の方には必読の一冊になり得るほど、よくまとめられた本である。
【関連リンク】
【基礎データ】
著者: 島岡要
出版社: 羊土社 2009年8月
ページ数: 178頁
紹介文:
「研究者に必要なのは知識や実験技術だけではない!」
プレゼン力・時間管理術・コミュニケーション力など、10年後の自分に自信が持てる『仕事術』を身につけよう!
研究が思うように進まず途方に暮れた時、進路に不安を覚えた時、評価されてないんじゃないかと不満を感じた時… 本書を読めば、今起こすべき行動が見えてくる。
羊土社
売り上げランキング: 3353
【他の方々による書評記事】
404 Blog Not Found: プロフェッショナル根性論 - 書評 - 研究者の仕事術
5号館のつぶやき: 研究もビジネスである: 島岡要著「研究者の仕事術」
企業研究者の日々: 「やるべきことが見えてくる 研究者の仕事術」 著:島岡 要
新・むかろぐ: やるべきことが見えてくる研究者の仕事術--プロフェッショナル根性論
大隅典子の仙台通信: プロフェッショナルとは:『研究者の仕事術』【追記あり】