有限と微小のパン―THE PERFECT OUTSIDER (講談社文庫)/森 博嗣
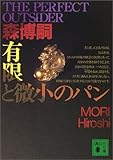
¥1,200
Amazon.co.jp
☆☆☆
いよいよシリーズ10作目。
これで犀川&萌絵ともお別れかと思うと悲しいですね。
個人的には愛着を持ったキャラクターの成長を見続けられるシリーズ物はとても好きなので10作も続くこのシリーズにはとても楽しませてもらいました。(途中飛ばしているので半分の5作しかしか読んでないけど)
さて本作はシリーズ1作目で登場した最高の頭脳を持つ真賀田四季と再び合間見えることになります。
ストーリーは真賀田四季を擁するソフトメーカーが作り上げた巨大なテーマパークで次々起こる不可思議な密室殺人事件に2人が挑むと言うものです。しかし真賀田四季が出てくると言うことは当然、リアルとバーチャルの境界が曖昧になり、その辺が作品としてのテーマにもなってくるわけです。
さてさて書評なのですが、ストーリーに関することはこの後ネタばれを含めて書きますが(書く前に予告するのでご安心を)850ページもある今作はまたも冗長です。事件のほとんど重複する内容を複数人の視点から描いたり、ニュースで報じさせたり。しかもその後でニュースの内容を登場人物が批判したりして。
はっきり言って無駄に長いです。まあ100ページは削れるでしょうね。
またミステリーとしては正直3流の出来です。ある意味では前作に近い、ミステリーという土台そのものをひっくり返してしまうトリックを使用しているのですが、その演出があまり上手くないです。唯一衝撃を受けるのはラスト数ページですが、これはある意味事件のトリックとは直接関係のない部分です。しかもかなりルール違反の書かれ方をしています。
私が感じた本作で楽しめるポイントは2つです。
1つ目はこれまで愛着を持ってきたキャラクター達の活躍を目一杯楽しめる点。特に最終作を向かえ再び真賀田四季との対決が見れるのはここまで付いてきた読者にはそれだけでおなかいっぱいと言うネタでしょう。
2つ目は、森博嗣流の哲学が披露されており、その点を文学的に楽しめると言うことでしょうか。また本作はテクノロジーの発展と嫌でも向かい合わねばならないストーリー展開となっているので、その点も考えさせられます。
例えばここ数年、携帯の普及に伴う問題が指摘されていますよね?「心の交流があ~だこ~だ」みたいな。でもこれって携帯を子ども時代から使っていなかった世代のノスタルジーな思いでしかないと思うんです。携帯電話が当たり前じゃなかった世代にとってはメールや電話なんてどこかむなしい、心のつながりを感じられないツールなんでしょう。でもそれを当然のものとして使用している世代にとってはきっとそんなこと無いんじゃないでしょうか?
私は本は紙媒体で読みたいです。いくら資源を節約できようとモニタで本を読みたいとは思いません。でも今から30年後に生まれる子ども達は紙に印刷するなんてナンセンスだって思うでしょう。ipodで育った世代はレコードには戻れません。
話が大分それましたね。要は古いものも新しいものもそれぞれ良い点悪い点あるが、新しいものを身体から受け入れられた世代にとっては、それを旧世代の理屈で批判するのはあまり意味が無いことだって思うわけです。真賀田四季が作品内で語るのはその極限とも言える思想です。
話を元に戻します。
本作は、ミステリーとしては2流以下です。それでも読ませてしまうのは、キャラ物として完成度が高いことと、ある種の文学的哲学的な要素を備えた作品だからだと思います。
以下ネタばれです。
さて、本作ではミステリーの禁じ手である「事件の大部分が狂言」でその一部にのみ本当の事件が混ざっていた、というストーリーでした。
これは前作「数奇にして模型」に近い構図だと思います。
前作では事件の大部分はミステリーでは禁じ手とされる「最も怪しい者」が本当に犯人で、その事件の一部に別の犯人が混ざっていた、というものでした。
で、突っ込みどころは前回同様です。どう考えてもあり得ない事件で、実際問題それが嘘だったじゃあ通常はミステリーとして成り立たないわけです。それを成り立たせるのが、混ざっていた本当の事件のはずなんですが…、どうもそっちが雑なんですね。これじゃあただ嘘だったってだけで何の面白さもない、とうか腹立たしいだけです。
これが映画であればそれもありなんだと思います。
実際「ユージュアルサスペクツ」や「ゲーム」は全てが嘘だった話と、全てが狂言だった、にも係わらず非常に良作なエンタテインメント作品に仕上がっていますから。この理由は、複線などが見事なこともありますが、映画の場合ミステリー以外の要素、例えば「映像としての格好良さ」や「映像による衝撃」を加味できるという特徴を思っているからだと思います。ところが活字の場合、一生懸命考えて想像して、その結果が全部嘘でしたじゃあ最も根幹で唯一の楽しみである部分が壊されてしまうため全部台無しになってしまいます。
とは言え上で書いたようにそれ以外の部分で随分楽しめる作品ですから、それでも良作の体をギリギリ保っていますが。
さてさて最後にどうしても言っておきたいところがあります。
本作で最も衝撃的なラスト数ページ、冒頭で出会っていた瀬戸千衣が真賀田四季であった、と言う点についてです。
そもそもそれに気づいた犀川の論理がかなり怪しいものでしたが、それはいいとしても、ラストシーンを読んだ後、当然前半に戻ってあのシーンを読み返したんですが、犀川先生、真賀田四季の顔見てません?百歩譲ってすぐ後ろを向いたとしても声聞いてますよね??
これ非常に残念です。苦しい解釈として顔は見られないように動いて声は意図的に変えていた、と考えることも出来なくはないです。でもこれってアンフェアですよね?読者が無理矢理解釈しなきゃいけないなんて。上手く顔を見られずに動く描写かなんかを入れておくべきでしょう。そんな描写を入れたって誰もあの時点で気づきはしないし、100人に1人気づく人がいるかもしれませんが、それがミステリーの醍醐味なわけだし。
あまりに気になってmixiのコミュティなどを覗いたら案の定同じ疑問を持った方が何人もいらっしゃいました。そこで1人の方が回答されていたのが「四季シリーズを読めば理由が分かりますよ」というものでした。(その点についても言及した「四季 冬」の書評はこちら)まだ読んでいないので本当に分かるかは分かりませんが、これもルール違反ですよね。何故あそこに住んでいたのか?どんな暮らしをしていたのか?これは完全なサイドストーリーですから別の本で書かれてしかるべき内容です。
でもあそこで犀川先生が彼女だと気づかなかった理由が別の本を読まないと分からないなんて…。
というか場合によっては、出版年が随分ずれている2冊ですからあの時点で作者自身気づいておらず、後で誰かに指摘されてその作品で無理矢理帳尻合わせたなんて可能性も。
いずれにせよ、最後の最後でひどくがっかりさせられました。
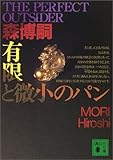
¥1,200
Amazon.co.jp
☆☆☆
いよいよシリーズ10作目。
これで犀川&萌絵ともお別れかと思うと悲しいですね。
個人的には愛着を持ったキャラクターの成長を見続けられるシリーズ物はとても好きなので10作も続くこのシリーズにはとても楽しませてもらいました。(途中飛ばしているので半分の5作しかしか読んでないけど)
さて本作はシリーズ1作目で登場した最高の頭脳を持つ真賀田四季と再び合間見えることになります。
ストーリーは真賀田四季を擁するソフトメーカーが作り上げた巨大なテーマパークで次々起こる不可思議な密室殺人事件に2人が挑むと言うものです。しかし真賀田四季が出てくると言うことは当然、リアルとバーチャルの境界が曖昧になり、その辺が作品としてのテーマにもなってくるわけです。
さてさて書評なのですが、ストーリーに関することはこの後ネタばれを含めて書きますが(書く前に予告するのでご安心を)850ページもある今作はまたも冗長です。事件のほとんど重複する内容を複数人の視点から描いたり、ニュースで報じさせたり。しかもその後でニュースの内容を登場人物が批判したりして。
はっきり言って無駄に長いです。まあ100ページは削れるでしょうね。
またミステリーとしては正直3流の出来です。ある意味では前作に近い、ミステリーという土台そのものをひっくり返してしまうトリックを使用しているのですが、その演出があまり上手くないです。唯一衝撃を受けるのはラスト数ページですが、これはある意味事件のトリックとは直接関係のない部分です。しかもかなりルール違反の書かれ方をしています。
私が感じた本作で楽しめるポイントは2つです。
1つ目はこれまで愛着を持ってきたキャラクター達の活躍を目一杯楽しめる点。特に最終作を向かえ再び真賀田四季との対決が見れるのはここまで付いてきた読者にはそれだけでおなかいっぱいと言うネタでしょう。
2つ目は、森博嗣流の哲学が披露されており、その点を文学的に楽しめると言うことでしょうか。また本作はテクノロジーの発展と嫌でも向かい合わねばならないストーリー展開となっているので、その点も考えさせられます。
例えばここ数年、携帯の普及に伴う問題が指摘されていますよね?「心の交流があ~だこ~だ」みたいな。でもこれって携帯を子ども時代から使っていなかった世代のノスタルジーな思いでしかないと思うんです。携帯電話が当たり前じゃなかった世代にとってはメールや電話なんてどこかむなしい、心のつながりを感じられないツールなんでしょう。でもそれを当然のものとして使用している世代にとってはきっとそんなこと無いんじゃないでしょうか?
私は本は紙媒体で読みたいです。いくら資源を節約できようとモニタで本を読みたいとは思いません。でも今から30年後に生まれる子ども達は紙に印刷するなんてナンセンスだって思うでしょう。ipodで育った世代はレコードには戻れません。
話が大分それましたね。要は古いものも新しいものもそれぞれ良い点悪い点あるが、新しいものを身体から受け入れられた世代にとっては、それを旧世代の理屈で批判するのはあまり意味が無いことだって思うわけです。真賀田四季が作品内で語るのはその極限とも言える思想です。
話を元に戻します。
本作は、ミステリーとしては2流以下です。それでも読ませてしまうのは、キャラ物として完成度が高いことと、ある種の文学的哲学的な要素を備えた作品だからだと思います。
以下ネタばれです。
さて、本作ではミステリーの禁じ手である「事件の大部分が狂言」でその一部にのみ本当の事件が混ざっていた、というストーリーでした。
これは前作「数奇にして模型」に近い構図だと思います。
前作では事件の大部分はミステリーでは禁じ手とされる「最も怪しい者」が本当に犯人で、その事件の一部に別の犯人が混ざっていた、というものでした。
で、突っ込みどころは前回同様です。どう考えてもあり得ない事件で、実際問題それが嘘だったじゃあ通常はミステリーとして成り立たないわけです。それを成り立たせるのが、混ざっていた本当の事件のはずなんですが…、どうもそっちが雑なんですね。これじゃあただ嘘だったってだけで何の面白さもない、とうか腹立たしいだけです。
これが映画であればそれもありなんだと思います。
実際「ユージュアルサスペクツ」や「ゲーム」は全てが嘘だった話と、全てが狂言だった、にも係わらず非常に良作なエンタテインメント作品に仕上がっていますから。この理由は、複線などが見事なこともありますが、映画の場合ミステリー以外の要素、例えば「映像としての格好良さ」や「映像による衝撃」を加味できるという特徴を思っているからだと思います。ところが活字の場合、一生懸命考えて想像して、その結果が全部嘘でしたじゃあ最も根幹で唯一の楽しみである部分が壊されてしまうため全部台無しになってしまいます。
とは言え上で書いたようにそれ以外の部分で随分楽しめる作品ですから、それでも良作の体をギリギリ保っていますが。
さてさて最後にどうしても言っておきたいところがあります。
本作で最も衝撃的なラスト数ページ、冒頭で出会っていた瀬戸千衣が真賀田四季であった、と言う点についてです。
そもそもそれに気づいた犀川の論理がかなり怪しいものでしたが、それはいいとしても、ラストシーンを読んだ後、当然前半に戻ってあのシーンを読み返したんですが、犀川先生、真賀田四季の顔見てません?百歩譲ってすぐ後ろを向いたとしても声聞いてますよね??
これ非常に残念です。苦しい解釈として顔は見られないように動いて声は意図的に変えていた、と考えることも出来なくはないです。でもこれってアンフェアですよね?読者が無理矢理解釈しなきゃいけないなんて。上手く顔を見られずに動く描写かなんかを入れておくべきでしょう。そんな描写を入れたって誰もあの時点で気づきはしないし、100人に1人気づく人がいるかもしれませんが、それがミステリーの醍醐味なわけだし。
あまりに気になってmixiのコミュティなどを覗いたら案の定同じ疑問を持った方が何人もいらっしゃいました。そこで1人の方が回答されていたのが「四季シリーズを読めば理由が分かりますよ」というものでした。(その点についても言及した「四季 冬」の書評はこちら)まだ読んでいないので本当に分かるかは分かりませんが、これもルール違反ですよね。何故あそこに住んでいたのか?どんな暮らしをしていたのか?これは完全なサイドストーリーですから別の本で書かれてしかるべき内容です。
でもあそこで犀川先生が彼女だと気づかなかった理由が別の本を読まないと分からないなんて…。
というか場合によっては、出版年が随分ずれている2冊ですからあの時点で作者自身気づいておらず、後で誰かに指摘されてその作品で無理矢理帳尻合わせたなんて可能性も。
いずれにせよ、最後の最後でひどくがっかりさせられました。