ルーシー・M・ボストン『グリーン・ノウの子どもたち』
イギリスの寄宿舎に入っている七歳のトーリー少年は、
クリスマス休暇を過ごしに
ひいおばあさんのオールドノウ夫人の家に行くことになりました。
洪水で川があふれていたため、汽車を降りてから
迎えのボートに乗ってたどり着いたのは
オールドノウ家の人々が代々暮らしてきた
古い石造りの「がんじょうで、あたたかく、力があふれている(p.20)」家でした。
お茶のあと、ろうそくを手に螺旋階段を上って案内されたトーリーの部屋には
たてがみがほんものの馬の毛でできている「うつくしい古いゆり木馬」や
鍵のなくなってしまった古いおもちゃ箱、それに鳥かごなどが置いてあり
すべてが居心地のいい雰囲気をかたち作っていました。
両親はミャンマーに住んでおり、しかも二番目のおかあさんに
あまりなじめずひとりぼっちだったトーリーは、
ひいおばあさんと暖炉のそばでお茶を飲み、
パッチワークのかかったベッドに入るときには
すでに「しみじみと、じぶんの家にいる気がした(p.30)」のでした。
年はとっているけれど、どこか若々しくて
トーリーの気持ちをちゃんとわかってくれる
「遊び友だちの男の子のように思われ(p.34)」るひいおばあさんと
これまた代々仕えている気のいい農地頭のボギスと一緒に、トーリーは休暇を満喫します。
さらに、トーリーは暖炉の上に飾ってある油絵に描かれている
三人の子どもたち――トービー、アレクサンダー、リネットと知り合いになります。
彼らは三百年前にこの家に住んでいた子どもたちでした。
トーリーの本名はトーズランド(Toseland)で、代々オールドウ家に伝わる名前でした。
トービーも同じトーズランド、ひいおばあさんのオールドノウ夫人の名前もリネットです
ノアの方舟のような古くてあたたかな家と
イチイの木のトピアリーや大きな石像のあるすばらしい庭を背景に描かれる、
トーリーと過去の子どもたちとの交流がとても気持ちがいいです。
・・・・・・・・・・
グリーン・ノウと呼ばれているオールドノウ夫人の家は、
作者のルーシー・M・ボストンが住んでいた
ヘミングフォード・グレイのマナーハウスと庭がモデルになっています。
ルーシーは1892年、イングランド北西部のランカシャー州サウスポートで生まれました。
六人きょうだいの五番目(姉兄姉兄弟)、父は市長をしており
乳母が子どもたちの一切を取り仕切っていました。
その頃住んでいた家の庭が灰色の砂地で
何も植物が育たなかったことがずっと引っかかっており、
のちにマナーハウスを手に入れた際、庭作りに邁進する一因になったそうです(①p.33)
十歳の時、母の健康回復のために
母方の祖父の地元、アーンサイドのケント川のほとりの家で一年を過ごすことになりました。
ここで美しい自然に囲まれて過ごした
「よろこびはいたるところにあり、尽きることがなかった(①p.77)」日々は深く印象に残り、
毎年夏をここで過ごすようになります。
川の流れをせき止めてよく遊んだことから
「シャベルを手ににぎることが私の第二の天性となった(①p.79)」とも言っています。
オックスフォード大学に進みますが、第一次世界大戦が始まると
退学してVAD(Voluntary Aid Detachmentの略。志願救護隊およびその隊員)となり、
看護婦としてフランスに渡ります。
研修を受けてフランスに行く前、待機状態だったとき
ほかの兄弟や従兄弟たちがケンブリッジに在学&駐留していたため
ルーシーはしばらくケンブリッジに住んでいました。
そのころ、はじめてケンブリッジから北西に10㎞ほどのヘミングフォード・グレイ村を訪れています。
何度か平底舟で川下りをしているうちに、途中に古いマナーハウスがあることに気付き、
「舟で通りすぎるうちに、親近感を持つようになった(①p.231)」と述べています。
1917年に従兄弟のハロルド・ボストンと結婚し、一人息子のピーターが生まれますが
35年に離婚します。
離婚前から、ルーシーはイタリアやオーストリアで絵画の勉強をしていました。
36年に帰国し、ピーターがケンブリッジに在学中だったこともあって
ケンブリッジの以前の下宿先の隣のアパートを借りましたが、そのうち
「ヘミングフォード・グレイ村でマナーハウスが売りに出ている」と聞いてキュピーン!
どこかに潜んでいた過去の力が大きかったのか、
それとも運命の磁力が働いたのか知るべくもなかったが、
それ以上の質問をしたり深く考えたりもしないで私はタクシーに乗って、
以前と寸分違わぬ場所に立っているあの陰気な家に向かったのだった。
「この家が売りに出ていると聞いたのですが」と私は戸口のところで言った。
どうしてご存知なのですが、と相手はたずねた。
売却するつもりではあったが、まだ広告を出していなかったのである
(売りに出ていると聞いたのは、私が全く気づかなかった別の家だった)。(①p.233)
こうして、運命的な出会いを経てルーシーはこのマナーハウスを購入します。
1120年に建てられたノルマン時代のもので、イギリスで最も古い家の一つでした。
日本だと平安時代末期の家が昭和12年に売りに出て(平成25年現在も人が住んで)ることになります。
そこから二年かけて修復し
「永続的な挑戦である、深い落ち着いた力強い静けさがある(①p.282)」この家で
ルーシーは暮らすことになりました。
自伝には修復の過程がbefore→afterの間取り図付きで書かれていて、ほんとにおもしろいです。
人に貸せる離れもあり、1988年の夏から8ヶ月ほど林望氏が滞在していました。
「クラシック音楽の熱烈な愛好家だった(①p.219)」ルーシーは
ヨーロッパにいるあいだにレコードを集めており
蓄音機でレコードが聴けるよう、二階にミュージックルームを作りました。
第二次大戦中は、近くの空軍基地に駐留している兵士を週末ごとに招いて
レコードコンサートを開いていました。
イギリス人だけでなくさまざまな国の青年がやって来ましたが、
「最も頻繁に聞かれた言葉は『家に帰ったみたいだ』というものだった(①p.303)」そうです。
そして、「そのなかの一人から、私の「グリーン・ノウ」シリーズに出てくる家族のために、
オールドノウという名前を借りた(p.331)」のだそうです。
彼はアメリカ人で、マナーハウスを上手に写真に収めてくれました(①p.355に写真掲載)。
1950年、58歳の時に、ルーシーは初めての著作『イチイの館』という本を書きます。
それを「書いて出版社に送るまでのあいだ(p.378)」に書きあげたのが
『グリーン・ノウの子どもたち』でした。
一つには収入に困っていたからでもあるが、それよりも、私自身のために、
この場所に誰かを住まわせたかったからである。
書き手が自分自身のために書いているのでなければ、
人にその内容の良し悪しがどうしてわかるだろうか。(①p.378)
出版社に送ったところ、二作とも受け入れられ、54年に出版されました。
ただ、イチイの方は文字だけだったのに対して
グリーン・ノウには、息子のピーターが挿絵を描いてくれていました。
物語の雰囲気にぴったりの、ほんとに息が合っている落ちついた絵です。
当初、出版社は二冊とも大人向けの本のリストに入れていたそうなのですが、
「ピーターの挿絵つきで、と私が言い張ると、
挿絵というものは子どもの本のためにしかつけないのが決まり、ということで、
私は子どものための作家になった。
それがどんなに作家としての地位を下げることになるか、
そのときの私にはわかっていなかった(①p.379)」。
たしかに原書を読むと、一文が比較的長めで(冒頭の段落は一つのセンテンスがほぼ三行以上)
章立てもされておらず、最後のページまでそのまま物語が続いていきます。
(和訳では21章に分けられています)
この文章が、ほんとに見事です。
心のこもった真摯な文章は、底のところでは届ける相手の年齢を問わないのだろうと思います。
J. R. タウンゼントは、以下のように言っています。
ボストン夫人は、ある場所を描写したり、ある雰囲気をつたえたりする場合に、
最高の美しさと正確さをともなったことばを駆使することができる。
いろどりのある文体というよりはむしろ明確だと言うべき彼女の文体には、
ひややかできよらかな美しさがあり、川の水がたえず形を変えながら、
きらきらと流れていく趣があって、イギリスの全ての児童文学作家を抜いている。(②p.62)
また、ジル・ペイトン・ウォルシュも、自伝の前書きで
「ボストン夫人を本質的な児童文学作家たらしめている[姉補足:三つの]要素」のうち、
文章の美しさを最初に挙げています。
第一は、彼女の散文の持つ透徹した明快さと透明な平易さである。
これにより、思想の繊細さや感情の細やかさが容易に読者に伝わるのだ。
音楽に対する彼女の愛情と関連してのことだと思うが、
ルーシー・ボストンは言葉の音と響きに鋭い耳を持っていた。(①p.8)
彼女が述べているとおり、文章の流れのこころよさは
ルーシーが音楽に親しんでいたことと深く関連していると思います。
作中にもフルートを吹いて小鳥を呼ぶ場面や、歌をうたう場面がたくさん出てきます。
父が音楽評論家だった松田瓊子 もそうでしたが、一文の長さにかかわらず
物語全体がどことなく一つの曲のようになっていて、
呼吸が自然なまま、こころよく進んで行ってふわりと着地して余韻を残す感じを受けました。
こうしてルーシーは62歳で「子どものための作家」となり、
マナーハウスの食堂で、87歳頃まで精力的に書き続けて
1990年に97歳で亡くなりました。
その後の著作にも一貫して言えるのは
基本的にはユーモアにみちたあたたかなまなざしで描かれているものの
子ども用に都合よくぼかした感じが一切ないことです。
トーリーはなかなか三人の子どもとちゃんと会うことはできず
(最初は声だけとか、かくれんぼのような感じで
面と向かって会話ができるのは物語の半分をすぎてから)、
グリーン・ノウにまつわる恐ろしい話も出てきます。
また、リネットが「あたし、死んでるんですもの(p.167)」とあっけらかんと言うように
三人の子どもはペストが大流行した時(おそらく1665-66年頃)に
亡くなっていると明言されていますし、
ボギスの息子二人は第一次大戦で、孫の男の子は第二次大戦で戦死していることも語られます。
ルーシーも弟を戦争で亡くしていますし、レコードを聴きに来ていた兵士たちの中には
飛行機で出発したまま帰ってこない人も何人もいました。
訳者の亀井俊介氏があとがきで書いているとおり
物語の中には「真実の人生のきびしさがおりこまれて」おり、
「この小説には、明るくたのしい夢がいっぱいにみちていながら、しかも同時に、
あまえた態度をゆるさない、人生に対する真剣さがあふれています(p.265)」。
・・・・・・
それ[姉注:家]は、ここにやってくるほとんどすべての人が感じるある力を持っている。
だが、どんな力を、どんなふうに?霊媒力のある私のアンテナは役に立たない。
おそらくそれは、そこで営まれた生活の稀に見るような密度であろうし、さらに重ねられて、
ついには一種のはっきりした沈殿物を形成するのだろう。さまざまな層があるのだ。(①p.273)
とルーシーが言っているとおり、長いあいだ住み込まれた家には
密度の高い時間と生活とが何層にも重なって堆積しているのでしょう。
うれしいこともつらいことも同じように受け入れて、それでも続く生活の静かな強さが
長い年月のあいだに深みを増しながら備わっていくのだと思います。
(「○○様式」を模して建てた新しい建物にどうやっても不自然さが残り、
底が浅い感じを受けるのも結局はこういうことなのかなと思います)
こうした「説明のつかない包みこむような親愛の雰囲気を、あるがままに持っている(①p.303)」
マナーハウスと、その庭の描写がほんとうによくて
読むととても落ちつく本です。
<おまけ その①>
お茶に関する場面がよく出てくるのが楽しいです。
トーリーが家に着いたとき、オールドノウ夫人が用意してくれたのは
「卵サンド、チキンサンド、砂糖をまぶしたオレンジケーキ、ゼリー、
それに棒チョコ・クッキー(p.24)」でした(おいしそう。
お茶の時間が、トーリーが気持ちを整理したり考えたりする
節目の役割をしているのも奥が深いです。
普段のお茶菓子は基本的にバターを塗ったトーストとはちみつ。
仕度を手伝い、トーリーは休暇中にトーストの達人になります。
ずっとあとに、大原照子さんの本でボストンさんとのお茶のエピソード(■ )を読んで
小鳥にえさをあげる場面もそうですが、
ご自分の生活がそのまま物語の中に描かれているんだなぁとしみじみ思いました。
上の写真は最近のお茶、ボストンさんのトーストです。簡単ですがとても和みます
また、ある日のお茶の場面には
「オールドノウ夫人は、茶わんと受け皿を下においた(p.56)」という記述が出てきます。
(原文だと Mrs. Oldknow put down her cup and sauser.(p.35)
繰り返し読んでいるうちに
受け皿は最初から置いてあるんだから、下に置くのはカップだけでいいんじゃないのかなと
うっすら違和感を覚えておりました。
このとき、「オールドノウ夫人は、暖炉のそばのお茶のテーブルのまえに、
このまえとおなじようにすわっていた(p.55)」のですが
ここは以下のようになっており(太字は私が変えています、
Mrs. Oldknow was sitting in front of a tea-tray by the fire, . . .(p.35)
「お茶のテーブル」ではなくて、ティートレイ(■ )と書かれています。
「このまえ」というのは、トーリーがこの家に来た最初の日です。
このときは「おばあさんは、トーリーのために食器棚に用意しておいた盆を持ってきて、
暖炉のまえのひくいテーブルにおいた(p.24)」のでした。
ここは原文ではこうなっています。
She brought a tray theat was laid ready for him on the sideboard,
and put it on a low table in front of fire.(p.17)
おそらくこの部分を踏まえて(暖炉のそばに低いテーブルがあることがここでわかっているので、
ティートレイをお盆ではなく
「暖炉のそばのお茶のテーブル」と訳してあるのでしょう(スバラシイ。
オールドノウ夫人は、お茶の道具がのったティートレイを運んできて
暖炉のそばの低いテーブルに置いたと考えられます。
ローテーブルでお茶を飲むときは、ソーサーごと持ち上げて
ソーサーを左手、カップを右手に持ってお茶を頂くのが正解です。
オールドノウ夫人もおそらくソーサーとカップを持ち上げていたと思われるので、
「茶わんと受け皿を下におい」た となっているんですね。
17世紀半ばに生きていたリネットのままごと道具に
紅茶茶碗がなくてマグとボウルだけだったり(持ち手付きのティーカップは18世紀に入ってから登場
フォークがなかったり(一般に使われ出すのは18世紀に入ってから、
歴史的な事実との兼ね合いも興味深かったです。
<おまけ その②>
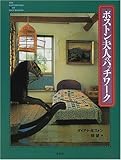 ボストン夫人のパッチワーク
ボストン夫人のパッチワーク
ルーシーはパッチワークも得意だったそうで、
息子のピーターの妻であるダイアナさんがまとめられた本です。
マナーハウスの離れに住んでいた、林望氏の翻訳です。
ルーシーがはじめてパッチワークを作ったのは1938年ですが、
最も多くの作品が作られたのは70年代、80歳代の時でした。
パッチワークは、1インチあたり20針で縫うのが基本なのだそうですが
(1インチ=2.54㎝なので、÷20で一針1.27㎜Σ(・ω・ノ)ノ!
それに忠実に、細かい針目で仕上げられているそうです。
ダイアナさんは「それはまるであのベアトリクス・ポッターの『グロースターの仕立て屋
』に出てくる
ねずみが縫ったような精密さです(p.18)」と書いています。
デザインや色あわせがほんとにきれいで、写真をずっと眺めてしまいます。
ヴィンテージのローラ・アシュレイの布なども使われていて楽しいです。
クリスマスプレゼントにもらった絵をモチーフにデザインされていたり、
お人形用に数年後にミニバージョンを作ってあげていたり、
四人のお孫さんのために作ったキルトがどれもほんとに壷でした。
日本語版の見返しが、初孫ケイトちゃんのために作ったパッチワークの図案になっています。
・・・・・
ボストンさんのマナーハウスには、現在ダイアナさんが住んでらして
予約を取れば見学することもできるのだそうです(サイトはこちら:■
トーリーの部屋の様子も見られます:■ )
この本や③にも写真が収められていますが、いつか行けると嬉しいな。
<参考文献>
ルーシー・M. ボストン『メモリー―ルーシー・M・ボストン自伝 』(評論社、2006年)①
J. R. タウンゼント『子どもの本の歴史―英語圏の児童文学 (下) 』(岩波書店、1982年)②
小峰和子『大人のためのイギリス児童文学 』(NHK出版、2009年)
さくまゆみこ『イギリス7つのファンタジーをめぐる旅 』(メディアファクトリー、2000年)③
(英語の引用部分のページ数はパフィン版のペーパーバックのものです)


