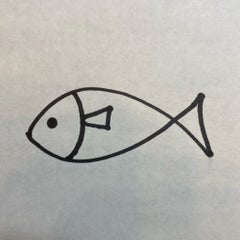支援措置に関する判例のご紹介です。
支援措置がとられていても弁護士なら住民票がとれるかのように宣伝している弁護士がいらっしゃるようです。弁護士倫理がどうかしているのでしょう。DV被害者支援を続けてきた私の立場からは決して承服できません。
本日、ご紹介するのは、加害者に依頼された弁護士への不交付の流れを決定的にした高裁判決(最高裁で確定)です。事務処理要領どおりにやることが法的に求められていることを明示しています。
この判決の後、平成30年3月28日総務省通知によって、「特定事務受任者から加害者の代理人として住民票の写しの交付等の申出があった場合、又は、住民基本台帳法第12条の3第2項の規定により、受任している事件又は事務の依頼者が加害者である特的事務受任者から住民票の写し等の交付の申出があった場合、加害者本人から当該申出があったものと同視し、・・・」とはじめて明確に通知され、加害者が依頼した弁護士からの住民票などの請求は不交付とすることとなりました。
さらには、同年11月30日には、最高裁事務総局民事局・家事局・総務局の各課長から、高裁・地裁・家裁各事務局長に、「住居所不明の訴状が出てきたら、裁判所が市町村に住所の調査して嘱託を行うように」とする関連通知が出されています。
DV被害者と申告した人の住所が明らかにならなくても調停はできるわけだし、そこまでして住所を暴きたい動機って何ですか? 超キショいんですけど。と思っています!
* * *
平成29(行コ)第158号 行政処分取消請求事件
控訴人 橋本市
被控訴人 〇〇〇〇
平成30年1月26日
判決
主文
1,原判決を取り消す
2,被控訴人の請求を棄却する
3,訴訟費用は第1・2審とも被控訴人の負担とする
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1、控訴人
主文同旨
2、被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する
(2) 訴訟費用は控訴人の負担とする
第2 事案の概要
1、本件は、弁護士である被控訴人が処分行政庁である橋本市長に対し、住民基本台
帳法20条4項に基づき、Aが記載されている戸籍の附票の写しが必要である旨の申出をしたところ、控訴人市長から、戸籍の附票の写しを交付しないとする処分の取り消しを求めた事案である。
2、原判決は被控訴人の請求を認容した
そこで控訴人が原判決を不服として控訴した
3、関係法令等
(1) 住基法
ア 住基法 20条3項
イ 住基法 20条4項
ウ 住基法 12条の3第3項
エ 住基法 20条5項
(2) 住基事務処理要領
ア 申出の受付
イ 支援の必要性の確認
ウ 支援措置
4、前提事実
5、争点
6、当事者の主張
第3 当裁判所の判断
(1) 事務処理要領上の支援措置の運用について
住基法は、市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理を基礎とするとともに、住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適切な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳事務の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。(同法1条)住民に関する記録の適正な管理を図り、住民のプライバシー保護に配慮することは市町村長の基本的な責務であり、市町村長は、その責務を果たすため必要な措置を講ずるように努めなければならない。(同法3条1項)そして住民票は住民の居住関係を公証する唯一の公簿であり、戸籍は、国民の身分関係を公証する唯一の公簿であるところ、戸籍と住民票とも連携させるため、住所を記載した戸籍の附票が戸籍を単位として作成され、この附票上の住所の記載は、住民票の住所地の市町村長からの通知に基づいて修正される(同法19条)ことから、戸籍の附票についても、住民票と同様に、住民のプライバシー保護に配慮するという観点から、住民に関する記録の適切な管理が図らなければならない。
他方、国は、市町村に対し、住基法の目的を達成するため、同法の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとされている(同法31条1項)ところ、支援措置の運用に関しては国により事務処理要領が定められているのであり、各市町村長は、その定めが明らかに法令の解釈を誤っているなど特段の事情がない限り、これにより事務処理を行うことが法律上求められているといえる。
そして、事務処理要領第6の10によれば、市町村長は、DV等の加害者から戸籍の附票の写しの交付等の制度を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的として、住基法20条4項等の規定に基づき、支援措置を講ずるものとされている。この支援措置は、DV被害者等及び加害者について、申出に基づきあらかじめ把握し、住基法20条4項等の運用に反映させようとするものであり、事務処理要領に定める手続により把握された加害者とされている者からの被害者に係る戸籍の附票の写しの交付申出については、原則として同法3条各号に掲げる者に該当しないとして、同法に基づきこれを拒むとするものである(質疑応答の問1)。このような定めは、住民に関する記録の適正な管理を図り、住民のプライバシー保護に配慮するという住基法の目的に合致するとともに、国及び地方公共団体は、配偶者暴力防止法に基づき、DV被害者の適切な保護を図る責務を果たす(同法9条)という観点からも合理性を有するものであるから、住基法の解釈を誤ったということはできない。
以上によれば、市町村長は、DV被害者等の保護のための支援措置を講ずることにした場合には、被害者に係る戸籍の附票の写しの交付については、事務処理要領第6の10に従って運用し、裁量権を行使すべきことになる。
(2) 本件処分の違法性の有無について
事務処理要領第6の10によれば、戸籍の附票の写しの交付については、加害者が判明しており、加害者から申出がなされた場合には、住基法20条3項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否することとされ、利用目的の厳格な審査の結果、特別の必要があると認められる場合にも、加害者に交付しないで目的を達することが望ましいとされている。このような取り扱いは戸籍の附票の写しが交付されることで、被害者の住所等の情報が加害者に知られるという事態を可及的に抑止しようとするものであるから合理的のあるものであることは明らかである。
また一般に加害者の代理人に被害者に係る戸籍の附票の写しを交付した場合、代理人を通じて被害者の住所が加害者に知らされるおそれがあることは否定できないことからすれば、加害者の代理人からの申出も、原則として、加害者本人からの申出に準じた処理がされるのもやむを得ない。
本件において、被控訴人は離婚訴訟代理業務についてBから依頼を受けた代理人として、住基法20条4項に基づき、Aに係る戸籍の附票の写しが必要である旨の申出をしたこと、本件申出書の「利用目的の内容」欄には「大阪高等裁判所平〇(〇)第〇号〇号の後処理のため相手方であるA氏と連絡をとる必要があるが、所在不明になってしまった」との記載がされていたこと、他方、控訴人市長は、本件申出がされるまでにAからBを加害者として、A自身をDV被害者とする事務処理要領第6の10に基づく支援措置の実施を求める申出を受け、支援措置の必要性について第三者機関から意見を聴取して確認した上、AにつきDV被害者に対する支援措置を開始していたことは、前記認定のとおりである。そうすると本件申出は加害者とされているBの代理人からの申出であるが、本件処分はB本人からの申出があった場合に準じて事務処理要領第6の10の定めるところに従い、Bが住基法20条3項各号に掲げる者に該当せず、かつ、本件申出が相当なものと認められないとして、これを拒否したのであるから裁量権の逸脱、濫用の違法があるとはいえない。
(3) 被控訴人の主張について
被控訴人は、本件申出は、本件和解で定められた義務を履行するために、Aの住所を確認する必要があるものであり、何ら不当な目的はなく、正当な理由に基づくものであったが、控訴人市長は事務処理要領に従い、利用目的について必要な審査を怠り、被控訴人がBからの依頼を受けて申出をしていることだけをもって、不当な目的があるものと判断し、これを拒否したものであるから、本件処分は裁量権の逸脱・濫用の違法があると主張する。
ア、被控訴人は市町村長が戸籍の附票の写しの交付申出を拒否できるのは当該申出に不当な目的がある場合であると主張する。
しかし事務処理要領の6の10のコ(イ)(A)によれば、戸籍の附票の写しの交付について、加害者から請求又は申出がなされた場合には、不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は住基法20条3項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否するものとされている。そうすると、住基法20条4項に基づく本件申出は、被控訴人の依頼者であるBが事務処理要領に定める手続きにより加害者と把握されていることが、同条3項各号に掲げる者に該当しないとして拒否されることはあっても、不当な目的があるものとして拒否されるということはない。
イ、被控訴人は事務処理要領によれば加害者からの申出の場合でさえ、利用目的等を審査した結果、当該申出に特別な必要が認められる場合には、当該目的を達成するように定められていると主張する。
前記の事務処理要領第6の10のコ(イ)(A)は戸籍の附票の写しの交付につき、加害者からの申出に対しては住基法20条3項各号に掲げる者に該当しないとして、これを拒否するとしながら「ただし、申出に特別の必要があると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受ける…(中略)…などの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい」としており、事務処理要領に付加されている質疑応答では、この「特別の必要」の意義について、当該戸籍の附票の写し自体が請求における利用目的のために必要不可欠であり、他の手段では代替できない場合とされている(問13)。この点、訴訟の提起等の法的な手続きをとるためには、戸籍の附票の写しの提出は必要ではないが、相手方に訴状等の送付をするためには送達場所を知ることが必要不可欠であり、この場合に戸籍の附票の写し等を全く利用できないとすると、法的手段をとることが困難となることは否めない。
特に被控訴人のように高い倫理性が要求される弁護士が代理人となって申出をした場合には、代理人弁護士に対して、交付を受けた戸籍の附票の写しの記載を本人に秘匿する旨の誓約を求めるなどの秘匿措置をとり、代理人弁護士がこれに応ずるのであれば、誓約等の遵守を期待することができる場合もあるから、当該戸籍の附票の写しそれ自体が必要でない場合でも、戸籍の附票の写しを交付すべき場合がないとはいえない。
しかし、本件申出書に記載された利用目的は、訴訟事件の後処理のためにAと連絡をとる必要がある。(具体的には本件和解で定められた仏壇等の引取りのための協議をする必要がある)というにすぎず、本件申出時以降の確認では、Aは被控訴人からの連絡を受けることすら拒否しており、Aの意思は本件申出時においても変わらなかったと推認されることに鑑みれば、Aに係る戸籍の附票の写しを交付することは相当でないとして、被控訴人に対して、これを交付しないとした本件処分が、控訴人市長の裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものということはできない。
なお、被控訴人は代理人弁護士から申出がされた場合には、加害者及び支援措置者以外の第三者から申出がされた場合に該当するとも主張するが、加害者から依頼を受けたことが明らかな代理人弁護士からの申出は、加害者本人から申出がされた場合に準じて扱われるべきであることはこれまで述べたとおりである。
また加害者の代理人弁護士からの申出に対する以上のような制約は、支援措置の必要性がある場合に、戸籍の附票の写しの記載が、加害者に知られることにより、支援対象者の生命又は身体に危うさが及ぶ可能性をできる限り排除するためのものであるから、目的達成の手段として不相当な制約ということはできない。
以上によれば、被控訴人の請求は理由がないから、これを棄却すべきである。よってこれと結論を異にする原判決は相当でないから、本件控訴に基づく原判決を取り消した上、被控訴人の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 田川直之
裁判官 安達玄
裁判官 高橋仲幸