写真は昭和20(1945)年4月12日に、知覧航空基地から特別攻撃隊「第二十振武隊」が飛び立つときのものです。
桜のひと枝を手に見送る知覧高女の女生徒達が手前に写っています。
いままさに飛び立とうとしているのが、穴沢利夫大尉の隼です。
機体の下に、250キロ爆弾が見て取れます。
この日、穴沢機を含む第二十振武隊は、沖縄洋上で見事、米駆逐艦に体当たりを果たされました。
出撃の模様を、この写真で手を振って見送っている前田笙子さんが、日記に遺されています。
~~~~~~~~~
昭和20年4月12日
今日は晴れの出撃。
征きて再び帰らぬ神鷲と私達をのせた自動車は、誘導路を一目散に走り飛行機の待避させてあるところまで行く。
途中「空から轟沈」の唄の絶え間はない。
先生方と隊長機の偽装をとつてあげる。
腹に爆弾をかかへた隊長機のプロペラの回転はよかつた。
本島さんの飛行機も、ブンブンうなりをたててゐる。
どこまで優しい隊長さんでせう。
始動車にのせて戦闘指揮所まで送られる。
うしろを振り返れば可憐なレンゲの首飾りをした隊長さん、本島さん、飛行機にのつて振り向いていらつしやる。
桜花に埋まつた飛行機が通りすぎる。
私達も差上げなくてはと思つて兵舎へ走る。
途中、自転車に乗つた河崎さんと会ふ。
桜花をしつかり握り、一生懸命馳けつけた時は出発線へ行つてしまひ、すでに滑走しやうとしてゐる所だ。
遠いため、走つて行けぬのが残念だつた。
本島機が遅れて目の前を出発線へと行くと隊長機が飛び立つ。
つづいて岡安、柳生、持木機、97戦は翼を左右に振りながら、どの機もどの機もにつこり笑つた操縦者がちらつと見える。
二〇振武隊の穴沢機が目の前を行き過ぎる。
一生懸命お別れのさくら花を振ると、につこり笑つた鉢巻き姿の穴沢さんが何回と敬礼なさる。
パチリ・・・・・・後を振り向くと映画の小父さんが私達をうつしてゐる。
特攻機が全部出て行つてしまふと、ぼんやりたたずみ南の空を何時までも見てゐる自分だつた。
何時か目には涙が溢れ出てゐた。
~~~~~~~~
文中にある穴沢利夫大尉(出撃時少尉、没後二階級特進で大尉)は、会津(福島県那麻郡)の出身です。
大正11(1922)年2月12日生まれで、幼い頃からたいへんな読書好きだったそうです。
彼の幼いころの夢は、故郷に児童図書館を作ること。
そのために彼は、文部省図書館講習所を卒業し、中央大学に進学しました。
穴沢利夫大尉

当時、親の仕送りで遊んで暮らせる学生なんていうのは、まずいません。
穴沢大尉も、お茶ノ水にある東京医科歯科大学の図書館で司書としてアルバイトをしながら、勉強していました。
昭和16年夏といいますから、穴沢大尉が19歳になったばかりの頃です。
バイト先の図書館に、図書館講習所の後輩たちが実習にやってきました。
その中に、後に婚約者となる孫田智恵子さんがいました。
これが運命の出会いでした。
お二人は、昭和16年の暮れ頃から交際をはじめられたそうです。
けれど当時は、大学生の男女が付き合うなどということは「はしたないこと」とされた時代です。
ですからデートなんてできない。
お二人は、もっぱら手紙のやりとりばかりをされていたそうです。
~~~~~~~
智恵子様へ
半年前、あなたがグラジオラスを持ってきて図書館の花瓶に生けてくれた日の夜、僕は誰もいない図書館でそれを写しました。
~~~~~~~
手紙には、繊細なタッチで模写したグラジオラスの絵が添えられていました。
お返しに智恵子さんが、手紙で
たまゆらに
昨日の夕(ゆふべ)
見しものを
と上の句を手紙にしたためます。
すると穴沢大尉が、
今日(けふ)の朝(あした)に
恋ふべきものか
と下の句を返す。
この歌は、柿本人麿呂の歌です。
意訳すると、
~~~~~~
あなたとは、
昨夜、お会いしたばかりなのに、
一夜が明けると
もうこんなにもあなたが恋しい。
~~~~~~
となるのでしょうか。
お二人は一緒に歩いたこともない。デートしたこともない。手も触れたことがない。
けれどお二人の心と心、情感と情感、教養と教養がお二人の愛をはぐぐみました。
二人は結婚を望みました。
穴沢利夫さんと智恵子さん(昭和17年春)
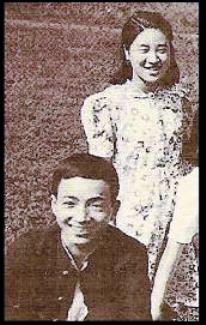
けれど、穴沢大尉の郷里の兄が猛反対しました。
当時は、よくあったのです。都会の娘なんて信用できないというのです。
それにひきずられて両親も結婚に反対しました。
時は大東亜戦争の真っ只中です。
穴沢大尉は、昭和18年10月1日、戦時特例法によって大学を繰り上げ卒業となりました。
そして陸軍特別操縦見習士官第一期生として、熊谷陸軍飛行学校相模教育隊に入隊します。
穴沢大尉は、入隊の時点で死を決意されていたようです。
~~~~~~~~~~
智恵子様へ
僕が唯一最愛の女性として選んだ人があなたでなかったら、こんなにも安らかな気持ちでゆくことはできないでせう。
どんなことがあっても、あなたならきつと立派に強く生きてゆけるに違ひないと信じます。
昭和18年9月6日夜
~~~~~~~~~~~
穴沢大尉が、まだ内地で厳しい訓練にいそしんでいる頃、
昭和19年7月に、サイパンが陥落しました。
同年10月、神風特別攻撃隊が編成されました。
そして、昭和19年12月8日、飛行第二四六戦隊に配属されていた穴沢大尉のもとに、特別攻撃隊第二〇振武隊員選抜の知らせが届きます。
そのとき、大尉の任地である三重県の亀山兵舎に、智恵子さんが訪ねて来てくれました。
東京から、夜行列車に乗っての旅です。
当時は、そうやってやってくるだけでも、たいへんなことでした。
同僚達は気をきかせて、二人を旅館に送りだしました。
けれど穴沢大尉は、連日の猛訓練の疲れで、寝てしまったそうです。
二人は清い交際のままででした。
~~~~~~~~
わかれても
またも会ふべく思えば
心 充たれて
わが恋かなし
智恵子
~~~~~~~~~~~
昭和20年3月8日、穴沢大尉は、隊長から出撃前の特別休暇をもらって帰郷します。
彼は、両親を説得しました。
私は、特攻隊として、この戦争で死にます。
けれど、死ぬ前に、どうしても智恵子さんと一緒になりたいのです。
覚悟の出征です。
「利夫がそこまでいうのなら、先様さえそれで良いのなら・・・」
ご両親は、穴沢大尉の説得に応じます。
穴沢大尉は、翌9日には、さっそく東京の智恵子さんの家を訪ねました。
そして、智恵子さんのご両親にも結婚したい旨を告げ、ご了解をいただきました。
喜んだ穴沢大尉は、その日は、目黒にある大尉の親戚の家に泊まりました。
翌朝の明け方、大事件が起こりました。
東京の3分の1を焼き尽くした3月10日の東京大空襲です。
死者は、8万人以上となりました。
東京大空襲

智恵子さんの無事を心配した穴沢大尉は、まだ夜が明けないうちに親戚の家を飛び出し、智恵子さんの実家へと焼け跡も生々しい町を、徒歩で向かいました。
ちょうど同じ頃、穴沢大尉の身を案じた智恵子さんも、夜明けとともに目黒に向かっていたのです。
いかなる偶然なのでしょう。
それともお二人の引き合う気持ちがなせるわざだったのか、二人は、大鳥神社のあたりで、バッタリと出会いました。
互いに生きていた。
いまどきなら、そこでハグでもしそうなところですが、当時はそんなんじゃありません。
互いの姿を見て、互いに生き残ったことを喜び合った。
それだけです。
穴沢大尉は、そうした戦火の中にあっても、当日は任務で大宮の飛行場に帰らなければなりません。
智恵子さんは、穴沢大尉を送って、二人で国電に乗りこみました。
ところが空襲の直後のことです。
国電は空襲のあとで避難する人があふれかえって超満員です。
あまりの混雑で智恵子さんは息苦しくなり、穴沢大尉の勧めもあって池袋駅で電車を降りました。
そしてこれが、二人の永遠の別れとなりました。
ひと月後、穴沢大尉から手紙が届きました。
~~~~~~~~
二人で力を合わせて努めて来たが
終に実を結ばずに終わった。
希望も持ちながらも心の一隅であんなにも恐れていた
「時期を失する」ということが実現してしまったのである。
去月十日、楽しみの日を胸に描きながら池袋の駅で別れたが、
帰隊直後、我が隊を直接取り巻く情況は急転した。
発信は当分禁止された。
転々と処を変えつつ多忙の毎日を送った。
そして今、晴れの出撃の日を迎えたのである。
便りを書きたい、書くことはうんとある。
然しそのどれもが今迄のあなたの厚情に御礼を言う言葉以外の何物でもないことを知る。
あなたの御両親様、兄様、姉様、妹様、弟様、みんないい人でした。
至らぬ自分にかけて下さった御親切、
全く月並の御礼の言葉では済み切れぬけれど
「ありがとうございました」と
最後の純一なる心底から言っておきます。
今はいたずらに過去に於ける長い交際のあとをたどりたくない。
問題は今後にあるのだから。
常に正しい判断をあなたの頭脳は与えて進ませてくれることと信ずる。
然しそれとは別個に、
婚約をしてあった男性として、
散ってゆく男子として、
女性であるあなたに少し言って征きたい。
あなたの幸を希う以外に何物もない。
徒に過去の小義に拘るなかれ。
あなたは過去に生きるのではない。
勇気をもって過去を忘れ、将来に新活面を見出すこと。
あなたは今後の一時々々の現実の中に生きるのだ。
穴沢は現実の世界にはもう存在しない。
極めて抽象的に流れたかも知れぬが、将来生起する具体的な場面々々に活かしてくれる様、自分勝手な一方的な言葉ではないつもりである。
純客観的な立場に立って言うのである。
当地は既に桜も散り果てた。
大好きな嫩葉の候が此処へは直に訪れることだろう。
今更何を言うかと自分でも考えるが、ちょっぴり欲を言って見たい。
1、読みたい本
「万葉」「句集」「道程」「一点鐘」「故郷」
2、観たい画
ラファエル「聖母子像」、芳崖「悲母観音」
3、智恵子
会いたい、話したい、無性に。
今後は明るく朗らかに。
自分も負けずに朗らかに笑って征く。
昭20・4・12
智恵子様
利夫
~~~~~~~
これが穴沢利夫大尉の最後の手紙です。
手紙の書かれた日付と、利夫さんの戦死の日付は、同じです。
おそらく、出撃の直前に、書かれたのでしょう。
智恵子さんは、穴沢大尉との面会の折とき、
「いつも一緒にいたい」と、自分の巻いておられた薄紫色のマフラーを渡しました。
穴沢大尉は、その女物のマフラーを首に巻いて出撃されました。
その様子が、次の写真です。
マフラーが首に二重に巻かれているので、他の隊員よりもマフラーが膨らんでいるのがわかります。

愛する利夫さんを失った智恵子さんは、悲嘆の底に沈みました。
そんな智恵子さんを支えたのは、やはり穴沢大尉の、入隊二週間前の日記でした。
大尉の死後に、届けられたものです。
~~~~~~~~
智恵子よ、幸福であれ。
真に他人を愛し得た人間ほど、幸福なものはない。
自分の将来は、自分にとって最も尊い気持ちであるところの、あなたの多幸を祈る気持のみによって満たされるだらう。
~~~~~~~~
ある本の記述を転載します。
~~~~~~~~
その女性は、手のひらに乗るほどの小さな箱を箪笥から取り出すと、
「大切なものが入っているの」
そう言って微笑み、私の前へ静かに置いた。
見事な寄木細工の小箱だった。
一体、何が入れられているのだろう。
そっとふたを外してみると、タバコの吸殻がふたつ、綿に包まれて入っていた。
銘柄も判別できないほどに変色し、指で触れれば崩れてしまいそうな。
「彼の唇に触れた唯一のものだから」
八十四歳になる伊達智恵子さんにとって、六十年以上も前の吸殻は、婚約者であった穴沢利夫少尉(享年二十三)の遺品だったのである。
「女物のマフラーを巻いたまま、敵艦に突っ込んでいった特攻隊員がいる。しかも、その隊員の婚約者だった女性は、未だに健在でいるらしい」
特攻隊の取材をしている知人からの情報で、都内で一人暮らしをしている智恵子さんを訪ねたのは、平成十八年一月十三日のことだった。
寂しいご婦人なのだろうか。
そんな私の予想は裏切られ、実際の彼女は明るく、力強く生きていた。
「利夫さんは生きたくても生きられなかったけど、残された私や彼の家族、それに未来に続くあなたたちのために特攻隊として身を投じたの。
私はその遺志を受け継いで、できることなら利夫さんの思いを果たしていきたい」
小柄でチャーミングな笑顔を絶やさない智恵子さんだが、彼女が語る利夫さんとの「物語」は、切なく、苦しい。
智恵子さんの記憶は鮮やかだった。
生への願望を持ちつつ、二十歳そこそこで死を覚悟しなければならなかった利夫さんの無念と、彼と結婚の約束をしていた自分が受け入れなければならなかった現実が、彼女の心に痛ましいほど深く記憶を刻みつけたのだろう。
「利夫さんが私だけに残してくれたものを公にしていいのかとずいぶん悩みました。
だけど、彼の日記や手紙を見て、そこから何かを汲み取ってくれる人もたくさんいるでしょう。
私自身もそれを何度も読み返して、利夫さんへの理解を深めることができたから」
こう言って彼女は、しまい込んでいた利夫さんの日記や手紙、写真を見せてくれた。
言うまでもなく、これらは特攻隊に参加した若者たちを理解する上での貴重な「資料」である。
しかし、私が目にしたのは資料という無機質なものではなく、人の心を打つ「作品」であった。
「死」が前提にありながらも、利夫さんの書く言葉に愚痴めいたものは見つからない。
ただ、智恵子さんへの思いやりと、国家に危急が逼り来るときに青年として何をすべきなのか、という熱い思いが綴られている。
その隙間に、さらりと挟まれている利夫さんの若者としての本音が、智恵子さんの話と共に私の心を打った。
しかし、智恵子さんは時折、私に戦時中のことを話すのをためらうことがあった。
特にその時々の彼女の気持ちを話す際、戦後三十年近く経って生まれた私がよく理解できないことに、もどかしさを感じるようだ。
「あなたたちは、命は尊いものだと教えられているでしょうけれど、あの時代は、命は国のために捨てるべきものだったの。
今とは、あまりに価値観が違うから、わからないと思うことも当たり前かもしれないわね」
それでも、丁寧に話せば若い人にも伝わるはずだと、智恵子さんの下へ通い続ける私に、彼女は根気強く話してくれた。
そんな智恵子さんだが、最近まで思い出を胸に秘めたまま、誰が来ても取材に応じることはなかったという。
彼女の考えを変えたのは、こんな思いだった。
「最近は、戦争が美談とされることもあるし、特攻隊を勇ましいと憧れを持つ人もいる。
でも、私たちは戦争がいかに悲惨なものかを知っています。
間違った事実が伝わらないように、今、話しておかないと、と思ったのです。
あの時代を生きて、身をもって体験したことを語る人は、毎年少なくなっている。
長く生かされていることに、何らかの使命が課せられているとしたら、それは語り部の役割かもしれませんね」
~~~~~~~
この文は、水口文乃著「知覧からの手紙」 (新潮文庫)の前書きにある文章です。
日本人というのは、魂を親から子、子から孫へと伝達し、縦の命のつながりをつなげる民族です。
愛する人のために、命を捧げる。
その命は、短い一生だったかもしれないけれど、肉体なんていうものは、魂を入れておくための殻でしかない。
魂は生き続け、後々の日までも人々に生きる勇気を与え、愛する人を生かしてくれる。
戦後教育は、私達に「命が終わったらおしまいだ。生きているうちが花なんだ」と教えます。
本当にそうなのでしょうか。
人を生かすために、自ら進んで死地に赴くという心は、究極の「思いやり」の心なのではないのでしょうか。
日本の文化は「つながり」と「共生」の文化です。
そして究極の愛は、誰かのために自らの命を捨てることを厭わない。
穴沢利夫大尉の肉体は、昭和20年4月12日に沖縄の海に散りました。
しかし、穴沢利夫さんの心は、智恵子さんに生きる勇気を与え、そして未来永劫、世界の人々の魂をゆさぶる愛の物語として、語り継がれています。
靖国に祀られる英霊は、236万柱です。
その236万柱の英霊、おひとりおひとりに、すべてドラマがあり、人生がある。
そして彼らは、間違いなく、自分のためではなく、他人をきづかう思いやりの心から、勇敢に戦い、散華されたのです。
その御柱をないがしろにする者は、もはや日本人ですらない。
日本の内閣総理大臣が、日本中のどこに行こうが、外国にとやかく言われるいわれはありません。
そのとやかく言うことを、内政干渉と言います。
日本は、支那や朝鮮の属国ではない。
総理が靖国に公式参拝することを咎めることの方が精神異常であり精神破綻者です。
出撃前の穴沢大尉のお写真、もう一度ご覧になってみてください。
首には、愛する智恵子さんからもらった女物のマフラー、そして手には日本刀風の立派な軍刀を下げています。
特アにとって武は、敵対する者への威嚇や殺戮のためのものだけれど、日本にとっての武は、愛する者への究極の思いやりです。
それが日本の武というものなのではないかと思います。
水口文乃さんが智恵子さんを取材されたとき、智恵子さんは84歳。
穴沢大尉がお亡くなりになって61年です。
その61年間、彼女は、指一本触れられたことすらない穴沢大尉を、その笑顔を、ずっと胸に抱いておられました。
ぞのことはきっと、お二人が戦後もずっと一緒にすごされていたということなのではないかと思います。
人の心は、そうやって愛を抱き続けることができる。
なぜなら日本人は縄文以来、愛と思いやりを大切に育くんできた民族だからです。
そして私達は、その日本人なのです。
昭和20年4月12日
今日は晴れの出撃。
征きて再び帰らぬ神鷲と私達をのせた自動車は、誘導路を一目散に走り飛行機の待避させてあるところまで行く。
途中「空から轟沈」の唄の絶え間はない。
先生方と隊長機の偽装をとつてあげる。
腹に爆弾をかかへた隊長機のプロペラの回転はよかつた。
本島さんの飛行機も、ブンブンうなりをたててゐる。
どこまで優しい隊長さんでせう。
始動車にのせて戦闘指揮所まで送られる。
うしろを振り返れば可憐なレンゲの首飾りをした隊長さん、本島さん、飛行機にのつて振り向いていらつしやる。
桜花に埋まつた飛行機が通りすぎる。
私達も差上げなくてはと思つて兵舎へ走る。
途中、自転車に乗つた河崎さんと会ふ。
桜花をしつかり握り、一生懸命馳けつけた時は出発線へ行つてしまひ、すでに滑走しやうとしてゐる所だ。
遠いため、走つて行けぬのが残念だつた。
本島機が遅れて目の前を出発線へと行くと隊長機が飛び立つ。
つづいて岡安、柳生、持木機、97戦は翼を左右に振りながら、どの機もどの機もにつこり笑つた操縦者がちらつと見える。
二〇振武隊の穴沢機が目の前を行き過ぎる。
一生懸命お別れのさくら花を振ると、につこり笑つた鉢巻き姿の穴沢さんが何回と敬礼なさる。
パチリ・・・・・・後を振り向くと映画の小父さんが私達をうつしてゐる。
特攻機が全部出て行つてしまふと、ぼんやりたたずみ南の空を何時までも見てゐる自分だつた。
何時か目には涙が溢れ出てゐた。
~~~~~~~~
文中にある穴沢利夫大尉(出撃時少尉、没後二階級特進で大尉)は、会津(福島県那麻郡)の出身です。
大正11(1922)年2月12日生まれで、幼い頃からたいへんな読書好きだったそうです。
彼の幼いころの夢は、故郷に児童図書館を作ること。
そのために彼は、文部省図書館講習所を卒業し、中央大学に進学しました。

当時、親の仕送りで遊んで暮らせる学生なんていうのは、まずいません。
穴沢大尉も、お茶ノ水にある東京医科歯科大学の図書館で司書としてアルバイトをしながら、勉強していました。
昭和16年夏といいますから、穴沢大尉が19歳になったばかりの頃です。
バイト先の図書館に、図書館講習所の後輩たちが実習にやってきました。
その中に、後に婚約者となる孫田智恵子さんがいました。
これが運命の出会いでした。
お二人は、昭和16年の暮れ頃から交際をはじめられたそうです。
けれど当時は、大学生の男女が付き合うなどということは「はしたないこと」とされた時代です。
ですからデートなんてできない。
お二人は、もっぱら手紙のやりとりばかりをされていたそうです。
~~~~~~~
智恵子様へ
半年前、あなたがグラジオラスを持ってきて図書館の花瓶に生けてくれた日の夜、僕は誰もいない図書館でそれを写しました。
~~~~~~~
手紙には、繊細なタッチで模写したグラジオラスの絵が添えられていました。
お返しに智恵子さんが、手紙で
たまゆらに
昨日の夕(ゆふべ)
見しものを
と上の句を手紙にしたためます。
すると穴沢大尉が、
今日(けふ)の朝(あした)に
恋ふべきものか
と下の句を返す。
この歌は、柿本人麿呂の歌です。
意訳すると、
~~~~~~
あなたとは、
昨夜、お会いしたばかりなのに、
一夜が明けると
もうこんなにもあなたが恋しい。
~~~~~~
となるのでしょうか。
お二人は一緒に歩いたこともない。デートしたこともない。手も触れたことがない。
けれどお二人の心と心、情感と情感、教養と教養がお二人の愛をはぐぐみました。
二人は結婚を望みました。
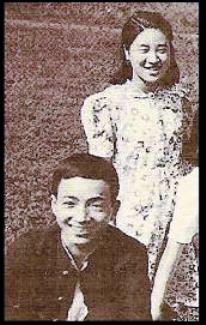
けれど、穴沢大尉の郷里の兄が猛反対しました。
当時は、よくあったのです。都会の娘なんて信用できないというのです。
それにひきずられて両親も結婚に反対しました。
時は大東亜戦争の真っ只中です。
穴沢大尉は、昭和18年10月1日、戦時特例法によって大学を繰り上げ卒業となりました。
そして陸軍特別操縦見習士官第一期生として、熊谷陸軍飛行学校相模教育隊に入隊します。
穴沢大尉は、入隊の時点で死を決意されていたようです。
~~~~~~~~~~
智恵子様へ
僕が唯一最愛の女性として選んだ人があなたでなかったら、こんなにも安らかな気持ちでゆくことはできないでせう。
どんなことがあっても、あなたならきつと立派に強く生きてゆけるに違ひないと信じます。
昭和18年9月6日夜
~~~~~~~~~~~
穴沢大尉が、まだ内地で厳しい訓練にいそしんでいる頃、
昭和19年7月に、サイパンが陥落しました。
同年10月、神風特別攻撃隊が編成されました。
そして、昭和19年12月8日、飛行第二四六戦隊に配属されていた穴沢大尉のもとに、特別攻撃隊第二〇振武隊員選抜の知らせが届きます。
そのとき、大尉の任地である三重県の亀山兵舎に、智恵子さんが訪ねて来てくれました。
東京から、夜行列車に乗っての旅です。
当時は、そうやってやってくるだけでも、たいへんなことでした。
同僚達は気をきかせて、二人を旅館に送りだしました。
けれど穴沢大尉は、連日の猛訓練の疲れで、寝てしまったそうです。
二人は清い交際のままででした。
~~~~~~~~
わかれても
またも会ふべく思えば
心 充たれて
わが恋かなし
智恵子
~~~~~~~~~~~
昭和20年3月8日、穴沢大尉は、隊長から出撃前の特別休暇をもらって帰郷します。
彼は、両親を説得しました。
私は、特攻隊として、この戦争で死にます。
けれど、死ぬ前に、どうしても智恵子さんと一緒になりたいのです。
覚悟の出征です。
「利夫がそこまでいうのなら、先様さえそれで良いのなら・・・」
ご両親は、穴沢大尉の説得に応じます。
穴沢大尉は、翌9日には、さっそく東京の智恵子さんの家を訪ねました。
そして、智恵子さんのご両親にも結婚したい旨を告げ、ご了解をいただきました。
喜んだ穴沢大尉は、その日は、目黒にある大尉の親戚の家に泊まりました。
翌朝の明け方、大事件が起こりました。
東京の3分の1を焼き尽くした3月10日の東京大空襲です。
死者は、8万人以上となりました。

智恵子さんの無事を心配した穴沢大尉は、まだ夜が明けないうちに親戚の家を飛び出し、智恵子さんの実家へと焼け跡も生々しい町を、徒歩で向かいました。
ちょうど同じ頃、穴沢大尉の身を案じた智恵子さんも、夜明けとともに目黒に向かっていたのです。
いかなる偶然なのでしょう。
それともお二人の引き合う気持ちがなせるわざだったのか、二人は、大鳥神社のあたりで、バッタリと出会いました。
互いに生きていた。
いまどきなら、そこでハグでもしそうなところですが、当時はそんなんじゃありません。
互いの姿を見て、互いに生き残ったことを喜び合った。
それだけです。
穴沢大尉は、そうした戦火の中にあっても、当日は任務で大宮の飛行場に帰らなければなりません。
智恵子さんは、穴沢大尉を送って、二人で国電に乗りこみました。
ところが空襲の直後のことです。
国電は空襲のあとで避難する人があふれかえって超満員です。
あまりの混雑で智恵子さんは息苦しくなり、穴沢大尉の勧めもあって池袋駅で電車を降りました。
そしてこれが、二人の永遠の別れとなりました。
ひと月後、穴沢大尉から手紙が届きました。
~~~~~~~~
二人で力を合わせて努めて来たが
終に実を結ばずに終わった。
希望も持ちながらも心の一隅であんなにも恐れていた
「時期を失する」ということが実現してしまったのである。
去月十日、楽しみの日を胸に描きながら池袋の駅で別れたが、
帰隊直後、我が隊を直接取り巻く情況は急転した。
発信は当分禁止された。
転々と処を変えつつ多忙の毎日を送った。
そして今、晴れの出撃の日を迎えたのである。
便りを書きたい、書くことはうんとある。
然しそのどれもが今迄のあなたの厚情に御礼を言う言葉以外の何物でもないことを知る。
あなたの御両親様、兄様、姉様、妹様、弟様、みんないい人でした。
至らぬ自分にかけて下さった御親切、
全く月並の御礼の言葉では済み切れぬけれど
「ありがとうございました」と
最後の純一なる心底から言っておきます。
今はいたずらに過去に於ける長い交際のあとをたどりたくない。
問題は今後にあるのだから。
常に正しい判断をあなたの頭脳は与えて進ませてくれることと信ずる。
然しそれとは別個に、
婚約をしてあった男性として、
散ってゆく男子として、
女性であるあなたに少し言って征きたい。
あなたの幸を希う以外に何物もない。
徒に過去の小義に拘るなかれ。
あなたは過去に生きるのではない。
勇気をもって過去を忘れ、将来に新活面を見出すこと。
あなたは今後の一時々々の現実の中に生きるのだ。
穴沢は現実の世界にはもう存在しない。
極めて抽象的に流れたかも知れぬが、将来生起する具体的な場面々々に活かしてくれる様、自分勝手な一方的な言葉ではないつもりである。
純客観的な立場に立って言うのである。
当地は既に桜も散り果てた。
大好きな嫩葉の候が此処へは直に訪れることだろう。
今更何を言うかと自分でも考えるが、ちょっぴり欲を言って見たい。
1、読みたい本
「万葉」「句集」「道程」「一点鐘」「故郷」
2、観たい画
ラファエル「聖母子像」、芳崖「悲母観音」
3、智恵子
会いたい、話したい、無性に。
今後は明るく朗らかに。
自分も負けずに朗らかに笑って征く。
昭20・4・12
智恵子様
利夫
~~~~~~~
これが穴沢利夫大尉の最後の手紙です。
手紙の書かれた日付と、利夫さんの戦死の日付は、同じです。
おそらく、出撃の直前に、書かれたのでしょう。
智恵子さんは、穴沢大尉との面会の折とき、
「いつも一緒にいたい」と、自分の巻いておられた薄紫色のマフラーを渡しました。
穴沢大尉は、その女物のマフラーを首に巻いて出撃されました。
その様子が、次の写真です。
マフラーが首に二重に巻かれているので、他の隊員よりもマフラーが膨らんでいるのがわかります。

愛する利夫さんを失った智恵子さんは、悲嘆の底に沈みました。
そんな智恵子さんを支えたのは、やはり穴沢大尉の、入隊二週間前の日記でした。
大尉の死後に、届けられたものです。
~~~~~~~~
智恵子よ、幸福であれ。
真に他人を愛し得た人間ほど、幸福なものはない。
自分の将来は、自分にとって最も尊い気持ちであるところの、あなたの多幸を祈る気持のみによって満たされるだらう。
~~~~~~~~
ある本の記述を転載します。
~~~~~~~~
その女性は、手のひらに乗るほどの小さな箱を箪笥から取り出すと、
「大切なものが入っているの」
そう言って微笑み、私の前へ静かに置いた。
見事な寄木細工の小箱だった。
一体、何が入れられているのだろう。
そっとふたを外してみると、タバコの吸殻がふたつ、綿に包まれて入っていた。
銘柄も判別できないほどに変色し、指で触れれば崩れてしまいそうな。
「彼の唇に触れた唯一のものだから」
八十四歳になる伊達智恵子さんにとって、六十年以上も前の吸殻は、婚約者であった穴沢利夫少尉(享年二十三)の遺品だったのである。
「女物のマフラーを巻いたまま、敵艦に突っ込んでいった特攻隊員がいる。しかも、その隊員の婚約者だった女性は、未だに健在でいるらしい」
特攻隊の取材をしている知人からの情報で、都内で一人暮らしをしている智恵子さんを訪ねたのは、平成十八年一月十三日のことだった。
寂しいご婦人なのだろうか。
そんな私の予想は裏切られ、実際の彼女は明るく、力強く生きていた。
「利夫さんは生きたくても生きられなかったけど、残された私や彼の家族、それに未来に続くあなたたちのために特攻隊として身を投じたの。
私はその遺志を受け継いで、できることなら利夫さんの思いを果たしていきたい」
小柄でチャーミングな笑顔を絶やさない智恵子さんだが、彼女が語る利夫さんとの「物語」は、切なく、苦しい。
智恵子さんの記憶は鮮やかだった。
生への願望を持ちつつ、二十歳そこそこで死を覚悟しなければならなかった利夫さんの無念と、彼と結婚の約束をしていた自分が受け入れなければならなかった現実が、彼女の心に痛ましいほど深く記憶を刻みつけたのだろう。
「利夫さんが私だけに残してくれたものを公にしていいのかとずいぶん悩みました。
だけど、彼の日記や手紙を見て、そこから何かを汲み取ってくれる人もたくさんいるでしょう。
私自身もそれを何度も読み返して、利夫さんへの理解を深めることができたから」
こう言って彼女は、しまい込んでいた利夫さんの日記や手紙、写真を見せてくれた。
言うまでもなく、これらは特攻隊に参加した若者たちを理解する上での貴重な「資料」である。
しかし、私が目にしたのは資料という無機質なものではなく、人の心を打つ「作品」であった。
「死」が前提にありながらも、利夫さんの書く言葉に愚痴めいたものは見つからない。
ただ、智恵子さんへの思いやりと、国家に危急が逼り来るときに青年として何をすべきなのか、という熱い思いが綴られている。
その隙間に、さらりと挟まれている利夫さんの若者としての本音が、智恵子さんの話と共に私の心を打った。
しかし、智恵子さんは時折、私に戦時中のことを話すのをためらうことがあった。
特にその時々の彼女の気持ちを話す際、戦後三十年近く経って生まれた私がよく理解できないことに、もどかしさを感じるようだ。
「あなたたちは、命は尊いものだと教えられているでしょうけれど、あの時代は、命は国のために捨てるべきものだったの。
今とは、あまりに価値観が違うから、わからないと思うことも当たり前かもしれないわね」
それでも、丁寧に話せば若い人にも伝わるはずだと、智恵子さんの下へ通い続ける私に、彼女は根気強く話してくれた。
そんな智恵子さんだが、最近まで思い出を胸に秘めたまま、誰が来ても取材に応じることはなかったという。
彼女の考えを変えたのは、こんな思いだった。
「最近は、戦争が美談とされることもあるし、特攻隊を勇ましいと憧れを持つ人もいる。
でも、私たちは戦争がいかに悲惨なものかを知っています。
間違った事実が伝わらないように、今、話しておかないと、と思ったのです。
あの時代を生きて、身をもって体験したことを語る人は、毎年少なくなっている。
長く生かされていることに、何らかの使命が課せられているとしたら、それは語り部の役割かもしれませんね」
~~~~~~~
この文は、水口文乃著「知覧からの手紙」 (新潮文庫)の前書きにある文章です。
日本人というのは、魂を親から子、子から孫へと伝達し、縦の命のつながりをつなげる民族です。
愛する人のために、命を捧げる。
その命は、短い一生だったかもしれないけれど、肉体なんていうものは、魂を入れておくための殻でしかない。
魂は生き続け、後々の日までも人々に生きる勇気を与え、愛する人を生かしてくれる。
戦後教育は、私達に「命が終わったらおしまいだ。生きているうちが花なんだ」と教えます。
本当にそうなのでしょうか。
人を生かすために、自ら進んで死地に赴くという心は、究極の「思いやり」の心なのではないのでしょうか。
日本の文化は「つながり」と「共生」の文化です。
そして究極の愛は、誰かのために自らの命を捨てることを厭わない。
穴沢利夫大尉の肉体は、昭和20年4月12日に沖縄の海に散りました。
しかし、穴沢利夫さんの心は、智恵子さんに生きる勇気を与え、そして未来永劫、世界の人々の魂をゆさぶる愛の物語として、語り継がれています。
靖国に祀られる英霊は、236万柱です。
その236万柱の英霊、おひとりおひとりに、すべてドラマがあり、人生がある。
そして彼らは、間違いなく、自分のためではなく、他人をきづかう思いやりの心から、勇敢に戦い、散華されたのです。
その御柱をないがしろにする者は、もはや日本人ですらない。
日本の内閣総理大臣が、日本中のどこに行こうが、外国にとやかく言われるいわれはありません。
そのとやかく言うことを、内政干渉と言います。
日本は、支那や朝鮮の属国ではない。
総理が靖国に公式参拝することを咎めることの方が精神異常であり精神破綻者です。
出撃前の穴沢大尉のお写真、もう一度ご覧になってみてください。
首には、愛する智恵子さんからもらった女物のマフラー、そして手には日本刀風の立派な軍刀を下げています。
特アにとって武は、敵対する者への威嚇や殺戮のためのものだけれど、日本にとっての武は、愛する者への究極の思いやりです。
それが日本の武というものなのではないかと思います。
水口文乃さんが智恵子さんを取材されたとき、智恵子さんは84歳。
穴沢大尉がお亡くなりになって61年です。
その61年間、彼女は、指一本触れられたことすらない穴沢大尉を、その笑顔を、ずっと胸に抱いておられました。
ぞのことはきっと、お二人が戦後もずっと一緒にすごされていたということなのではないかと思います。
人の心は、そうやって愛を抱き続けることができる。
なぜなら日本人は縄文以来、愛と思いやりを大切に育くんできた民族だからです。
そして私達は、その日本人なのです。




