いや、しかし、実際はどうなんでしょう。過去の名作大河ドラマというのは、そんなに再放送のハードルが高いものなのでしょうか。『相棒』なんか、年がら年中再放送されている気がします。まぁ、通常のドラマと違って第二期という概念がない枠なので、新シリーズの番宣のために再放送されるケースは考えられませんし、再放送してしまうとセル&レンタルDVDでも稼げないし、版権の問題などが山積みなのかも知れませんが、それでも、視聴者が過去の名作に触れる機会は何処かで継続して欲しいとも思います。
『伊達流へそ曲がり』というサブタイからして、主人公が持ち前の頓智で将軍家をやり込めるという『一休さん』のような内容になるかと思えば、さにあらず。確かに硬軟織り交ぜた外交姿勢で謀叛の嫌疑を晴らしたばかりか、忠輝と五郎八姫の離縁で疎遠になっていた将軍家との新しい姻戚を結ぶことに成功するなど、まさに災い転じて福と成していましたが、全編を通じて主人公にはアンニュイな影が漂っていました。今回もいい意味でサブタイ詐欺。ポイントは4つ。
1.これも成長?
伊達家謀叛の風聞が囁かれる中、江戸屋敷に住まう愛姫母子の元に政宗の『イザって時は見捨てるからヨロシク!』という手紙が届きます。ドンびきする五郎八&忠宗姉弟ですが、愛姫は泰然たるもの。ちゃんと予告してくれる分、昔よりマシだとでも思っているでしょう。秀吉の元に人質に出された時には何の断りもなしで叛乱を起こそうとしたからね、政宗の奴。
愛姫「世継ぎは生き永らえてこそ、家名を守ることができる。父上はその修羅場を幾度となく潜り抜けてこられた。忠宗、男というものはのぅ、首級を刎ねられるまで『負けた』と思うてはならぬ」
つまり、世継ぎが諦めたら、そこで御家終了だよというコトですね。実際、乱世には世継ぎの不慮の死で歴史が変わった事件がボコボコと発生しています。本能寺の変もそう。あれは信長が討たれたということよりも、信長と信忠の二人がほぼ同時に討たれたということに意味がある。どちらかが生き延びていれば、ああも容易く織田政権が崩壊することはなかったでしょう。世継ぎが生き延びるということは現在の価値観からは想像もできないほどに重要な要素であったのです。流石に愛姫は判っている。まぁ、彼女が『ダテに修羅場を潜っていない』と評した旦那ですが、その修羅場とやらの半分は政宗本人が自分で撒いた種であったりします。本人は『災い転じて福と成す! これぞ、伊達流へそ曲がり術の極意じゃ!』とドヤ顔で自慢していましたが、少なくとも若い頃の彼の言動は藪をつついて蛇を出すという言葉のほうが似あうでしょう。
2.MVP
今回は柳生宗矩の独壇場でした。聡明でも経験に乏しい秀忠を巧みに懐柔して、政宗との対立の間に妥協点を図るように仕向ける手腕は何処か家康の影を感じます。そういえば、柳生宗矩が主人公の大河ドラマ『春の坂道』の原作も山岡荘八氏。こういう点でも影響が出るものなのでしょうか。
今回の柳生宗矩は家康の代弁者であると同時に、伊達政宗の代弁者でもありました。煎じ詰めると将軍家と伊達家の間で諍いが起きるのは、両家の紐帯が脆弱であるため。それゆえに幕閣の間で伊達潰しの議論がでるし、政宗も幕府の姿勢に不安を覚える。その両勢力を見事に橋渡したのが宗矩でした。
伊達政宗「ほらさぁ、俺もいい加減ヤンチャやらかす年齢じゃないんだけどさぁ、幕府の連中がトヤカクいうからさぁ、色々とアレなんだよねぇ。何つぅかさぁ、将軍家と何かしらの縁ができれば、そういうコトに気を揉まなくてもすむと思うけれども、俺っちが将軍の風下にたつような形式は納得できないよ? 判る? 判るよね?」チラッチラッ
柳生宗矩「あぁ、判った判った。上様の孫を養女に迎えてから送り出してやるよ。それでいいよな? その代わり、領内の切支丹はキチンと取り締まれよ」
だいたい、こんな感じでしょう。政宗にはメンツ。将軍家には実益。双方が必要なものを入手できる落としどころを探りあう政宗と宗矩は、ある意味、政宗と成実以上の関係といえます。それでいて、重要なのは両名が親友でも主従でもないこと。多分、自分の存亡に関わる状況になれば、相手をハメることに何の躊躇いも覚えないでしょう。しかし、そうであるからこそ、お互いの手のうちを読みあい、双方の利害を調整するのは逆に容易なのです。政治に必要なのは人間性に対する信頼ではない。相手の欲望を理解すること。これが大人の関係というものです。
3.本音と建て前
逆にいうと、簡単に本音が出てしまうのは若さの証明。今回だと忠宗と秀忠がそうですな。相手の利害よりも己の矜持、幕府の体面が優先してしまう辺り、まだまだ若い。まぁ、若いというても秀忠は充分に大人なのですが、そこは物語上の演出という奴でしょう。
しかし、両名共に単純に若いというだけでは終わらせないのが本作の凄味。忠宗は政宗の命令と己の面目で将軍家との縁談を(一度は)蹴りますが、仲介の労を取ってくれた今井宗薫にはキチンと頭を下げる。秀忠は秀忠で『別に憎くはない』思っていた政宗に足元を見られてブチぎれたにも拘わらず、宗矩の進言を容れて縁談を成立させた際には、本音を隠して政宗と対峙する。二人共、今回の話で地味に成長しているんですね。本音と建て前。感情と礼節。これらを状況に応じて使いあわせてこその大人。
徳川秀忠「今後は父同様、この秀忠も昵懇に頼むぞ」
伊達政宗「ありがたくも身に余る御言葉。政宗、終生肝に銘じて、天下泰平のために身命を擲つ覚悟にございます」
もうね、この場面のこやつめハハハ感は異常。登場人物が皆、礼儀正しいのに人間のドス黒さが垣間見られるシーンでした。
4.寂寥感
そうはいっても、全ての状況が政宗の機嫌に適うワケではない……というか、明らかに不本意なシチュエーションでしょう。幕府の警戒心を解くために阿房の如き振る舞いに勤しむ政宗ですが、福島正則相手の相撲(史実だと酒井忠勝)といい、能楽の途中で転げる様子といい、可笑しみの影に寂寥感を禁じ得ません。
理由としては膝を屈した相手が自分よりも器量に劣る(と少なくとも政宗は思っている)ことでしょう。秀吉の時のように力に捻じ伏せられたワケではない。家康相手のように器量に心服したワケでもない。そんな相手の御機嫌を取らなくてはいけないワケですからね。現在の政宗にできるのは酒の席での諫言という形式に託けて、幕府の施政を当て擦る&己の器量の大きさをアピールすることのみ。これは相当のフラストレーションでしょう。五郎八姫といい、支倉常長といい、自分の見に降りかかる災難の多くが自分で蒔いた種ということも、政宗の憂鬱の原因。他人の所為にしてくても出来ないというのがツライですな。そして、それらと同時並行で起こる腹心の逝去。今回の鈴木重信の死は作中の政宗には特に堪えた筈です。初登場の回でも書いたように、重信は政宗が自ら見出した家臣第一号なので、小十郎の死とは別の痛みがあったでしょう。
これらの中で今回一番印象に残ったのは、支倉常長の口から出た密約の件に、
伊達政宗「何の話だ? そのような話をした覚えはない。夢でも見ているのか?」
と返答する場面。ここのナベケンが怖いのよ。口調は穏やかそのものですが、明らかに目がそれ以上喋ったら殺すと告げているんですね。ちょっと勝新秀吉を思い出してしまいました。そう考えると天下人の気まぐれで政宗の生殺与奪を楽しんでいたように見えた本作の秀吉も、実は内面では様々な苦悩があったのではないかと深読みしてしまいそう。権力の座にある者は確信犯であることから免れ得ない。その苦悩を押し隠して、傍目には冷酷な権力者として振る舞わなければならない。全く、人の上にたつというのは心に潤いを望めないということなのでしょう。
今回、改めて見返すと、結構シビアな内容でした。確か次回は政宗の日常から始まる内容であったと記憶していますが、そういう点からも終盤はアットホームな印象を抱いていたんだよなぁ。何だ、この『太平記』ばりの鬱展開。
ちなみに、
仁に過ぎれば弱くなる。
義に過ぎれば固くなる。
礼に過ぎれば諂いとなる。
智に過ぎれば嘘をつく。
信に過ぎれば損をする。
というのは伊達政宗の五常訓として伝わるものです。これを元に非常にうまくフィクションを構成していたよなぁ。大意としては『何事も程々に』ということなのでしょうが、万事、自重という言葉と無縁の生涯を送ってきた政宗にいわれたくはありません。
『おまえがいうな』
とはまさにこのことでしょう。教訓。歴史上の偉人の言葉は存外、アテにならない。
アルビレックス新潟あるある/TOブックス
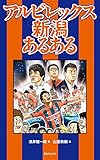
¥1,080
Amazon.co.jp
あまちゃん 完全版 Blu-rayBOX1/TOEI COMPANY,LTD.(TOE)(D)

¥18,576
Amazon.co.jp
NHK 大河ドラマ 武田信玄 完全版 第壱集 [DVD]/中井貴一,平幹二朗,若尾文子
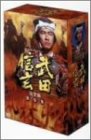
¥45,360
Amazon.co.jp
柳生宗矩(1) (山岡荘八歴史文庫)/講談社

¥799
Amazon.co.jp