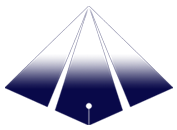先ほどのこれ
この差はなんなのか。
考えるのが好きな子達というのは、考えるってことを楽しんでいる。
たぶん、考えるのが当たり前の中で育ってきて
考えた結果あっていたり間違っていたりという経験を積み
考えたらあってた、出来たという経験がどんどん蓄積されていっているのだろう。
だから、考えることは苦ではないし、考えることで切り開けると心が知っている。
そんなところだろう。
では、そういう子になるにはどういう環境が必要なのか。
いくつかあるだろうけれど
親がなんでもやってしまうような環境は良くないだろう。
自分で考える前にお膳立てされてしまってはね。
それから
待ってもらえないのも良くないのだと思う。
考えるってのは時間がかかること。
なのに、すぐに答えを求められたり
考える間もなく「いやだからさ」と外部から介入される。
考える気にならないですよね。
他にはなんだろう?
たぶん、細かいこと言えばいくらでもある。
でも、結局は幼少期から形成されてきていることなんだろう。
ところで、ちょっと話はズレるけどこういう子もいる。
考えはするんだけど、めっちゃ浅い子。
考える力はありそうなのに、深くいく手前で必ず止まってしまう子。
解説とか読んでも上滑りしやすい。
きっと、簡単な問題に慣れすぎてるか、めどくさがりなんだろう。
考えることは嫌いじゃないんだけど、めんどくさいが先行してくる感じ?
考えるって言葉一つにも、いろいろなレベルがある。
どういうレベルでやれているのかは、かなり大きく影響する。
その差は、中学2年生あたりから、如実に現れてくる気がするな。