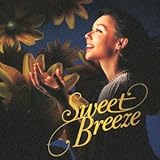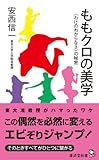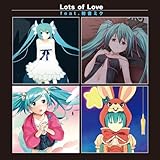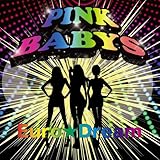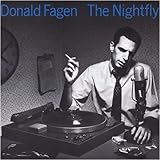昨日の日曜日はウチのスタジオに若いミュージシャンたちが集まりました。秋に発売予定の某アルバムのレコーディングです。
僕(右から3番目)以外はハーフやクォーターばかりだったのでスタジオでは英語が飛び交うことに…。ネイティブ同士の会話は聞き取りにくいですね(^_^;)。
一番左と一番右は去年亡くなったジョー山中さんの息子&娘で、赤ちゃんの頃からよく知ってます。歌の上手いDNAを引き継いでるので楽しみな二人です(^_^)。
↑モデル&シンガーとして活躍している山中マイちゃん。
今回はラフな服装ですが、モデルの時はものすごく綺麗に変身します。
ピアノは地下スタジオのスタインウェイ。
(もちろん僕の所有物ではありません)
↑オーストラリア&ジャパニーズのミッシェル。メチャクチャ歌が上手いです。
まだデビューはしてないけどセッションは色々やってるのでご存知の音楽関係者もいるかも。
外国育ちなので、写真の時は恋人みたいにくっつきますが怪しい関係ではありません(笑)。
(ずっと前のブログでも書いたけど、マイちゃんの友達。ルームメイトです)
18~25才の若いミュージシャンたちに囲まれてると気分が若くなりますね。
もちろん「気分だけ」ですが…(^_^;)。
それと写真撮るの忘れたけど、初めて会ったギタリストのタカシ・シナガワもとても優秀でした。
まだ20才なのにいろんなプロ・ミュージシャンとセッションしてるとか。
彼らと話してると、音楽をやっていく上で日本という国がすごく特殊だということがよくわかります。ある意味、鎖国状態というか、ヒットチャートにあふれている音楽が世界のレベルから考えると「…???」と疑問符が付く印象です。
もちろん、僕からみても「素敵だな」と思える音楽を作ってるミュージシャンもいるのですが、
「ザ・芸能界」といえるような大手プロダクションの力が絶大すぎて、ビジネスとしては成立しにくい時代ですね…。
以前からそういうことは考えていましたが、前回のブログのコメントで「匿名ファン」の方から、
佐久間正英さんの記事 を紹介していただきました。35才以上のプロ・ミュージシャンならほぼ全員が同意できる内容だと思います。
佐久間さんは仕事をしたことはないのですが尊敬する大先輩ミュージシャンのひとり。
80年代から現在まで数々の大ヒット・アルバムをプロデュースしておられます。
ずっと前に取材させて頂いた時、ぺーぺーの馬の骨の僕に対しても優しく丁寧に話をしていただきました。アナログもデジタルもすごく詳しく、とてもクレバーな方ですね。
(ドラムマシンの名機・ローランドTR-808を開発し、世界で初めて使ったのも佐久間氏)
そんなプロ中のプロの方が「音楽を諦める時」と書いたものだから、すでにネット中のいろんな所でコピペされ、論評されています。中でも
BLOGOSの記事 は主題とズレつつも比較的まともだったので僕も読みました。
批判的な意見として「時代錯誤だ」とか「音楽なんて元々タダなんだから諦めて廃業しろ」みたいな酷いものも。
あとは「2億円かけたスタジオで作られた音楽もPC1台の音楽も需要があれば価値は同じ」とか(これは当たってますけど…)。
佐久間氏は時代変遷のこととか、PCやネットの進歩で音楽が無料化に近づいてることなどは百も承知です(初音ミクの曲まで作ってますし)。
その上で、ああいう記事を書かれてるので、「音楽家が食えなくなった」ことが主題ではないと思います。
(佐久間氏の文章より) 40年かけて地道に築き上げて来たノウハウが『伝承しようの無い』ものになってしまった現状を自省も込めて嘆いておられます。ここがこの記事の主題だったのではないかと思われます。
ご本人も「タイトルが誤解を招いた」と仰ってますし…。
そういう現況が「日本固有の状況に思える」と書かれていますが、僕もそう思います。
このブログでも何度か書いてますが、去年1700万枚もCD売ったアデルや、今年大ブレイクしたゴティエのことを大々的に取り上げたマスコミはごくわずか…。
レディー・ガガなども音楽性のことより奇抜な衣装やメイクばかりが取り上げられてますね。
K-POPにしても、美脚だとかセクシーダンスがどうとかいう記事ばかり。
僕の青春時代には『ベストヒットUSA』という素晴らしい洋楽紹介番組があって、同級生はみんな見てました。ああいう番組があれば、もっと若い人がいろんな音楽に触れる機会が増えるのに。
(もちろん、洋楽が上で日本が下だなんて単純には思ってません…)
ただ、日本の音楽業界はリスナーを育てて来なかった、とは思います。90年代のCDバブルの時代は宣伝さえすれば、あるレベル以上の音楽ならなんでも売れてましたし。
僕が外国人ミュージシャンと一緒にやってて一番楽しいのは、音楽の原点に帰れる気がすることです。YouTubeで世界ヒットも狙える時代ですから、インターナショナルな視点はいつでも持ちたいし、古き良き時代を継承する新しい才能にも出会いたい。
名曲に出会う率が少なくなった昨今ですが、ゴティエの
コレ はやっぱり良いですね。
VIDEO オリジナルバージョンはYouTubeで2億回の再生ですが、日本語字幕で聞きましょう。
歌モノはやっぱり意味がわかったほうが魅力倍増しますから(^_^;)。
男女掛け合いの歌詞が面白いし、それで話題になった部分も大きいです。
音楽的にはまさに80年代のポリス(スティング)の再来ですね!
歌い方もアレンジも絶対影響受けてると思います。
ただ、昔の焼き直しに終わってないのが彼の素晴らしさです。ギターのサンプリングとか、Pro Toolsによる細かい編集とか、しっかり現代的な意匠があります。
だから音数が少なくても、声量が小さいパートても淋しさは全く感じられない。
このへんはアデルの「Rolling In The Deep」などにも通じるところ。
それと僕の最近のイチオシバンド、カナダのWalk off The Earthが
この曲をカバー してるのでご存じない方は是非見て下さい。「ギター1本を5人で演奏して歌う動画」として、1億回も再生されてます。
VIDEO 奇しくもこの3組はみんなアコースティック中心で、しかもインディーズから、音楽性が認められて大ブレイクした人ばかり。アメリカ出身ではないけどアメリカで売れたことも共通してます(英語圏の強み、ですね)。
オーストラリア出身のゴティエが売れたので、上記のミッシェルには「世界がオージーミュージシャンに注目する今がチャンス」とハッパかけました(笑)。
ちなみに、ゴティエにフィーチャリングされたKimbraはニュージランドからワールドワイドでブレイクした数少ないシンガーです。彼女のアルバムも良かった(^_^)。
佐久間さんの記事にはかつてのレコーディングの経費の話が出ていて、それが誤解されたのかもしれません。1枚のアルバムで1500万から2000万かけたのは昔の話で、録り音にこだわってた時代の費用です。
今の技術を使えばゴティエみたいな音は1曲10万でもギリギリ作れます。
もちろんドラムは全部打ち込み&サンプリング。
ピアノはIvoryなどのソフトで充分(正直、地下スタジオのスタインウェイより良い音で録れます)。
ベースもTrillianという恐ろしいほどリアルなソフトがあるし、ストリングスも歌のバック程度なら充分通用する音源があります。
ギターだけは未だに人間のプレイのほうが絶対イイです。それでも、アンプのシュミレーション・ソフトが素晴らしいのでライン録音で行けます。
あとはひたすたメロディー、歌詞、アレンジ、そしてボーカル・パフォーマンスにこだわれば最小限の経費で良い音楽は充分作れます。
そのためのスキルを僕も25年くらい磨いてきて、若いミュージシャンにもまだギリギリ信頼されてるようです(^_^;)。
今は小規模なプライベート・スタジオで充分良い音が作れる時代。
ボーカルだけは、しっかりしたマイク・プリ&アウドボードを使う必要がありますが、「ドラムやストリングス・セクションをどうしても生で録りたい!」という場合以外、レンタル料が数十万円もする商業スタジオは要りません。
「SSLやNEVEもデカいミキサー卓を前にするとミュージシャンやシンガーの気分が高揚してマジックが生まれる」という効果はありますが、費用対効果が割に合わな過ぎますね(^_^;)。
佐久間氏のおっしゃる内容は全部当たってるけど、時代の流れば誰にも止められません。
悲しいけど、スタジオ技術を尽くしたサウンド&演奏が200%完璧な『ナイトフライ』みたいな名盤は、永遠に作られることはないですね。
それでも、僕は音楽を諦められません…。
ナイトフライ/ドナルド・フェイゲン ¥1,800
Amazon.co.jp