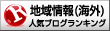岸田内閣の株式市場浮揚政策に対する、韓国専門家の見解
https://sincereleeblog.com/2023/06/12/yoon-nantokasite/
2023年6月12日 尹政権の大冒険 シンシアリーのブログ, 韓国情報 0件
最近、日経平均が大幅に上昇し、バブル後最高値とされています。そんな中、韓国の大手資産運用企業「未来エセット」の年金・株式部門担当者イサンゴン氏が、経済メディア「アジア経済」寄稿文で、「それは単に企業の株価が上がったとかそういう側面だけでなく、高齢化社会対策でもある」という分析を載せました。韓国経済も似たような趣旨の記事を載せており、日本の家計金融資産は2023兆円だが、多くが預金・現金であり、 岸田政権は家計金融資産を証券市場などに積極的に誘致し、資産所得を増やす計画であり、上場企業も配当も15兆円を超える見込みだ、などと伝えています。最近、日本経済、及び岸田総理の政策に対して「見習うべきだ」とする記事が増えていますが、その中の一つとしてエントリーしてみます。以下、各紙、<<~>>が引用部分となります。
[論文]なぜ日本は株価を上げようとするのか?
https://v.daum.net/v/20230610100717883
入力 2023. 6. 10. 10:07
バブル経済が崩壊し、日本は投資家にとって墓のような場所になった。 日本証券市場は30年余りの歳月の間、後ろ歩き、または歩き回り、住宅は投資対象リストから消えた。 日本企業の経営方式も新しい時代に合わない古いものとされた。 日本式経営に関心を持つ国内企業は減り、グローバルスタンダードは英米式資本主義を意味した。 1980年代が日本経済の勝利だったら、1990年代からは米国経済の時代だった。
ところが数年前から日本市場に関心を持つ投資家が多くなった。 決定的転換点の主人公はウォーレン・バフェットだった。 2020年8月、バフェット会長である投資会社バークシャー・ヘサウェイは、日本の5大総合商社株式を買い入れて世間の話題になった。 その後、バフェットはこれらの株式を追加で買い入れ、日本を直接訪問した。 今アジア地域で日本証券市場は最もホットな市場になった。
投資家から免れた失われた30年の歳月の間、日本に対する関心を置かなかった人々がいた。 主に人口構造の変化に関心を持つグループだった。<<・・日本は世界で初めて超高齢社会になった。国民5人のうち1人が65歳以上の最初の国家だった。 今、私たちがその道をたどっている。日本の高齢化経験は、生きている人類学教科書の役割をするというのが人口学者たちの考えだ。
デフレと高齢化が一つになり、巨大な日本の家計金融資産は、主に預金として眠っていた。個人の立場としては合理的な選択だったとも言えるだろう。物価が下落して現金の価値が上がっていたからだ。高齢化も関連がある。高齢者が家計金融資産の60%以上を持っているので、安全性を中心に資産を運用したわけだが、これは資本市場の活力を下げた。
株式市場の停滞は、単に株価の下落しただけの意味ではない。夢を持って創業した若い人たちは、証券上場を通じて補償される必要がある。投資家も、上場しなければ投資金を回収することは困難だ。証券市場の低迷は、創業から上場までの『企業生態系』の形成に思わしくない影響を及ぼす。証券市場の低迷が、経済全体、さらには社会全体の活力を下げる理由がここにあるのだ。
岸田文雄首相は「資産所得の2倍増加」を政策として掲げた。2000兆円を超えるお金が、投資に回って、資産が2倍になれば、経済への影響は想像もできない。以前の政府でも支配構造改善のため、2014年に「スチュワードシップコード」を導入し、2015年には「企業ガバナンスコード」を制定した。前から、構造を改善するための努力をしてきたのだ。
日本中央銀行は日本国民年金に続き、日本証券市場の2大株主である。中央銀行が直接買い入れる前例のない政策を展開したのだ。今回は東京証券取引所が、東京証券市場に上場した3300社に「株価純資産比率(PBR)が1倍を下回る上場会社は、株価水準を引き上げるための具体的な案を公示して実行してほしい」という内容の公文を送った。株式の低評価を解消し、家計資産の収益を引き上げるという、強力な信号を送ったのだ。
高齢化に備える道はいろいろある。福祉も必要で、教育も必要で、雇用も必要だ。それらいくつかの代替案のうち、過小評価されているのが、資本市場のワイルドさを回復することだ。高齢化とデフレという長いトンネルを通ってきた日本が、資本市場を生かすためにここまでの政策を出した理由を、私たちも考えてみるべき時だ。・・>>
(アジア経済)イ・サンゴン未来アセット投資と年金センター長
株価扶養圧迫に… 日商長社、15兆円歴代級配当
https://v.daum.net/v/20230611180559004
チョン・ヨンヒョ入力2023. 6. 11. 18:05 修正 2023. 6. 12.
上場会社30%配当拡大
昨年より1000億円増えた
3年連続「史上最大」金額
東京取引所還元要求に
上司が続々と呼応
日経指数9週連続上昇
この記事は、国内最大の海外投資情報プラットフォームハンギョングローバルマーケットに掲載された記事です。
日本上場会社が今年歴代最大規模の15兆円(約139兆ウォン)を超える配当をする見通しだ。 日本政府と東京証券取引所が上場会社に「株価を上げろ」と圧迫したのが効果を出しているという分析だ。
日本ゲイザイ新聞が去る9日、東京証券市場上場会社の2023会計年度(2023年4月~2024年3月)配当計画を総合した結果、予想配当金総額は15兆2200億円と集計された。 昨年より配当規模が1000億円ほど増え、3年連続史上最大記録を立てる見通しだ。 世界景気見通しが不透明な渦中にも日本上場会社のうち30%が昨年より配当を増やす計画だと把握された。
自社株買い規模も史上最大記録を新たに使う可能性が高いと分析される。 5月末までに日本上場会社が発表した自社株買取規模は5兆1600億円だ。 この傾向が続くと、歴代最大規模で自社株を買い入れた昨年(9兆4000億円)記録を上回る。
<<・・(※配当金が15兆円を超える見込みだ、という内容のあとに)日本企業が株主への還元に積極的に乗り出したことには、東京証券取引所の圧迫が大きな役割を果たしたという評価だ。東京証券取引所は去る4月、東京証券市場に上場した3300社余りの企業に「株価純資産比率(PBR)が1倍を下回る上場会社は株価を引き上げるための具体的な案を公示して実行してほしい」という内容の公文を 送った。PBRは株価を1株当たり純資産で割ったもの。PBR 1倍未満は時価総額が会社を清算した価値より低い状態で、低評価状態であることを意味する。取引所が市場で決定される株価を、人為的に浮揚するよう企業に要求したのは、世界的にも珍しいことで、当時、論議になった。
取引所の圧迫に上場会社は積極的に呼応し、日経225指数はこの日、1.97%上がった32,265.17だった。9週連続上がり、2017年以降最も長い上昇傾向を続けた。
東京証券取引所は最上位市場であるプライム市場上場会社だけPBRを1倍以上に改善しても、現在700兆円の時価総額が850兆円に増えると推算した。
取引所の株価浮揚圧迫は、岸田文雄内閣の看板政策である「資産所得の倍増」政策とも関連が深いという分析だ。昨年末、日本の家計金融資産は2023兆円で初めて2000兆円を超えた。しかし金融資産の54%は預金と現金の形だ。株式の割合は10%に過ぎない。 岸田内閣は家計金融資産を証券市場などに積極的に誘致し、資産所得を2倍に増やす計画だ。・・>>
(韓国経済)東京=チョン・ヨンヒョ特派員 hugh@hankyung.com
9日の「日本の経済好調に凄い関心(?)を示す韓国メディア~」というエントリーでも紹介しましたが、すべてを「地政学的な理由で~」にしようとする記事も多い中、珍しいとも言える内容の記事、でした。でも、こういうのは『オチ』を書くのが難しいのが短所です(笑)。