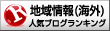日本の経済好調に凄い関心(?)を示す韓国メディア・・『新冷戦構造のおかげ』から『企業の堅実さによるもの』まで
https://sincereleeblog.com/2023/06/09/kotti-minaide/
2023年6月9日 尹政権の大冒険 シンシアリーのブログ, 韓国情報 0件
半導体関連で特にそうですが、最近日本経済の好調を伝えるデータに、韓国メディアが凄い反応を示しています。感覚的な話ですが、日経平均の好調以外は、日本メディアよりも韓国メディアのほうが多くの記事を載せている気がします。ほとんどは、地政学的なこと、いわゆる米中による『新冷戦構造』のおかげだ、という主張です。これは、日本の経済発展において随分前から韓国側では定説になっていたもので、日本の経済発展は冷戦構造のおかげだ、朝鮮戦争のおかげだ、それ以外は認めない、そんな風潮がありました。ただ、今回はそれほどではなく、どちらかというと「外交路線がよかった」というニュアンスもあります。
「いままで堅実に積み上げたものがあるから」という分析もあります。たとえばイジピョン外国語大学教授は、日本では物価上昇率以上に賃金を上げる動きが出ており、今年後半部には実質賃金も上昇するだろうと分析しながら、これは今まで各企業が積み上げた資産(資金)があるからだ、としています。先の記事もこのイジピョン教授の記事も、おなじソウル経済です(記事1、記事2)。さて、先も書きましたが、地政学的なんとかも、結局は『政策が一貫したおかげ』と言えるだろうし、少なくとも米中対立が明らかになってから日本の外交がこの方向から外れたことは無いので、これも堅実さと言えるでしょう。以下、<<~>>で引用してみます。
[課題レポート]日本賃金引き上げ・攻撃投資で堅実な成長傾向・・・「先端産業回復」期待も高く
https://v.daum.net/v/20230609060215988
世論読者部入力 2023. 6. 9. 06:02 修正
イ・ジピョン韓国外国語大学特別教授
日証を生きる理由
日経20ヶ月で3万線を超えて
1990年以降33年ぶりに最高値記録
第1四半期実質GDP成長率2.7%「宣伝」
岸田内閣新資本主義政策
企業の物価より高く賃金を上げる
デジタル革命に合わせて構造改革に注力
トヨタの遅れた電気自動車戦略に拍車
「中牽制」美と半導体協力など強化
TSMCイヤーミクロン日投資から
「不況」を抜け、強力に成長するか注目
[ソウル経済]
今年に入って日本証券市場が目立った上昇傾向を見せ、関心が集中している。 今年2万5834で出発した日経指数は先月17日1年8ヶ月ぶりに3万線を超え、世界で上昇率が最も高い指数で記録された。 その後も高空行進を続け、今月に入っては3万2000選を回復し、泡経済時期の1990年7月以降約33年ぶりに最高値を更新した。 8日、日経指数は小幅下落したまま締め切った。
<<・・日経平均の好調は、日本経済が相対的に堅実な成長を見せている中で現れている。日本の輸出は全体的に不振だが、新型コロナ緩和とともに「対面」消費が活発で、内需が生きている。日本は韓国と違って、輸出が国内総生産(GDP)で占める割合が10%%台だ。対面サービス需要拡大が日本内需景気を支え、経済成長を促進しているのだ。これにより、1~3月期の実質GDP成長率が前四半期比2.7%(年率基準)を記録した。・・>> 潜在成長率が0%台と評価される日本経済としては宣伝した。
日本ではこれまで賃金が停滞し、消費と経済成長に否定的に作用した側面があった。 しかし<<・・最近、賃金がはっきりと上昇傾向を見せ、内需主導成長に対する期待を高めている。昨年以降、日本も3%を超える消費者物価上昇率を記録し、実質賃金は2022年度比1.8%減少した。 しかし、物価上昇率の鈍化とともに、2023年後半には実質賃金が増加傾向になると期待される。
今年の春闘時の加重平均賃金上昇率は3.67%に達した。民間調査機関のミズホリサーチ&テクノロジーによると、3%台後半の賃金引き上げ率であれば、2023年度の個人消費を0.6%ポイント、GDPは0.4ポイントほど引き上げる効果がある。・・>> もちろん一度だけの賃金引き上げには限界があるが、<<・・岸田文雄内閣は、新たな資本主義政策を強調しながら賃金上昇を誘導している。経団連の十倉雅和会長も物価上昇を上回る賃金引き上げは「企業の社会的な責任であり続けなければならない」と強調した。・・>>
日本企業の立場では賃金引き上げが収益を圧迫する要因でもある。 しかし、人材不足で倒産する企業事例が増える状況を考慮すると、生産性と収益性を高める努力が重要になっている。 実際、日本企業は過去20年ほどの賃金凍結など長期的な構造調整の効果で収益性が改善されており、賃金引き上げ余力がある。 日本企業の内部留保(利益剰余金)は2022年12月末基準で536兆円に達した。 世界経済が不振な中でも日本企業の今年3月に決算結果は相対的に良かった。
<<・・日本企業の内部留保(利益剰余金)は2022年12月末基準で536兆円に達した。 世界経済が不振な中でも日本企業の今年3月に決算結果は相対的に良かった。
日本企業はこれまで、拡大した収益と内部留保を海外投資と海外企業買収に活用する傾向が強かった。しかし、今後、相対的に不振だった賃金を引き上げる一方、新しいイノベーション時代に対応するという姿勢も明らかにしている。既存の製造業がデジタル革命、グリーン革命で革新される時代に対応し、日本企業も構造転換に注力するということだ。日本企業としてもこれまでの防御的経営から抜け出して攻撃的な投資が必要であることを認識している。今年第1四半期実質GDP成長率で設備投資の成長寄与度が0.6%ポイントに達するほど日本経済の成長を支えた。・・>>
トヨタ自動車の場合、これまで遅滞した電気自動車(EV)戦略に拍車をかける方針であることを明らかにした。 トヨタの2022年電気自動車販売実績は2万4000台に過ぎなかったが、2026年まで年間150万台、60倍以上増やすという覚悟を示した。
米中覇権競争という不確実性の高まりは、日本企業にも負担として作用する。 しかし、日本企業はこれに対応しながら有利な環境を造成することに注力している。 中国は既存産業で世界最大級の輸出実績を上げているだけでなく、バッテリー・太陽電池など次世代産業でもサプライチェーンの中心的な地位を高めており、米国はこうした中国への依存度を減らそうとする戦略に力を入れている。 日本はこれに対応しながら先端産業サプライチェーンの中心的な地位を回復することに注力しており、米国も日本との協力を拡大している。
特に次世代半導体分野で日米間の協力が強化されている。 米国IBMは日本の国策半導体企業でトヨタ自動車・ソニー・NTTなど8社が出資したラピダスに先端微細加工技術である2nm(ナノメートル・10億分の1m)の基礎技術を移転して量産を推進中だ。 米国商務省と日本経済産業省はすでに2022年5月「半導体協力基本原則」に合意しており、両国の国策半導体研究機関間の協力体制の構築及び強化に乗り出している。
これと共に台湾のTSMCに続き、米国の半導体メモリメーカーであるミクロンも日本広島に大規模な投資方針を明らかにした。 日本には世界有数の半導体関連素材・部品・装備企業が密集しており、これらと緊密に協力して次世代半導体技術を開発するためだ。
もちろん、日本半導体産業の微細加工技術は、2世代以前の40nm程度の水準にとどまっており、ラピダースが2027年の予定通り2nm半導体量産に成功しても、韓国・台湾企業との格差を狭めることは容易ではない。 しかし、米国が過去とは異なり、日本半導体産業を育成しようとする姿勢に変わったことによる影響を無視することはできないだろう。
全体的に回復している日本経済に影響を与える主な変数は、2013年以降10年間続いた大規模金融緩和政策だ。 日本の実質賃金回復は下半期に消費者物価が2%台に落ちることを前提とする。 しかし、最近円が1ドル当たり130円台から140円台に価値が再び落ち、輸入物価の下落に負担になることもある。
日本経済はすでにデフレから外れた。 2022~2024年の平均で、消費者物価が日本銀行の政策目標である2%を超える可能性もある。 このような状況で短期政策金利をマイナスとし、10年満期長期金利を0.5%に抑えるために無条件に本願通貨を大量に放出する金融緩和政策は副作用を高めることができる。 最近、日本証券市場だけでなく不動産価格も明らかな上昇傾向を見せている。 ここに本願通貨大量放出まで加わると円安の下落の可能性に備えた逃避心理が作用して波長が大きくなることがある。
今年4月に就任した上田一雄新任日本銀行総裁は、長期金利まで中央銀行が統制することについて否定的な発言もするなど常識的な姿を見せた。 したがって、これまでの金融緩和政策の点検後に苗の政策変化がある可能性がある。
日本経済はグローバル経済不安の中でも先方を放つなど、過去の長期不況期と変わった姿を見せているが、より強力な成長のためには低出生や人口高齢化など構造的問題を解決しなければならない。 日本企業がこれまで蓄積してきた現金性資産も活用し、イノベーション投資を拡大し、持続的な賃金上昇の中で物価と円を安定させ、今後構造革新課題にも肯定的な効果を出すか注目される。
イ・ジピョン特任教授は・・・日本東京出身の韓国国籍の日本経済専門家だ。 日本法政大学経済学科を卒業し、高麗大学経済学の修士課程を修了した。 1998年、LG経済研究院に入社した後、33年間勤務し、経済研究部門首席研究委員、未来研究チーム長、産業研究部門エネルギーグループ長などを経た。 現在、韓国外国語大学融合日本地域学部で後学を指導している。
(ソウル経済その1)世論読者部 opinion2@sedaily.com
笑顔冷戦の時笑った日本経済、新冷戦の時も笑うか[裏北グローバル]
https://v.daum.net/v/20230609070228850
イ・テギュ記者入力 2023. 6. 9. 07:02
タイムトーク
米貿易赤字増加率8年來最大
輸入中比重も17年ぶりに最低値
産業サプライチェーンを備えた親西方日脚光
日成長率 2.7% びっくり好調
「短期弾力であるだけ」慎重論も出てくる
[ソウル経済]
米国と中国の地政学的リスクに日本経済が反射利益を見る兆しだ。 日本経済は地政学的リスクが最高潮に達した米国とソ連の冷戦時代である1960~1980年代超好況を享受したが、一部では現代の新冷戦時代に似た恩恵を享受するのではないかという観測も出ている。
まず、米国と中国の貿易指標が同伴悪化し、米中紛争が結局両方にブーメランになっているという分析が提起される。 7日(現地時間)ロイター通信によると、米国の4月商品・サービスなど貿易収支赤字は746億ドルで前月より23%急増した。 前月比の赤字増加率は2015年3月以降8年ぶりに最高だ。 絶対貿易赤字規模も昨年10月以降6ヶ月ぶりに最大だった。 詳細には輸入が3236億ドルで前月より1.5%増えた反面、輸出は世界経済鈍化とドル強勢の余波で2490億ドルを記録して3.6%減った。
特に米国の輸入で中国産が占める割合は17年ぶりに最低水準に落ちた。 4月基準で最近1年間、米国全体の商品輸入で中国産の割合は15.4%で、2006年10月以降最低値を見せた。 ドナルド・トランプ専任行政府時代に導入した全防衛大衆関税措置をジョバイデン政権が引き継ぐなど、両側の葛藤が結局このような結果として現れたという評価だ。 一方、米国の輸入で日本・インド・ベトナムなど25カ国の製品が占める割合は24.7%で、2018年の20%台前半で着実に上昇した。
中国の貿易指標も良くなかった。 中国海官総書によると、5月の輸出額は前年比7.5%急落した2835億ドルにとどまった。 特に米国への輸出が18.2%も急減した。 米国国内の需要が堅調な姿を見せているにもかかわらず、中国の対米輸出は大きな減少を記録したのだ。
<<・・(※米中対立について書いた後に)これに対し、日本は反射的利益を享受している。1990年代初頭、冷戦時代が幕を下ろし、グローバル企業はコスト効率化を最優先にして人件費の安い中国などに大規模に工場を建てた。しかし、新型コロナでサプライチェーン問題を経験し、米中の対立が強くなり、コストが増えても安定したサプライチェーンを構築することが重要だと企業の考え方が変わっている。そんな面で政治・外交的に完全に西側にありながら、製造能力にも優れた日本は、最適な国だ。最近、ファイナンシャル・タイムズ(FT)は「中国と距離を置く方式でグローバルサプライチェーンを再編しようとする動きが、日本製造業に対する外国企業の買収の波を呼ぶ可能性がある」と診断した。
日本が中国と相当な経済・貿易関係を維持しているため、日本に投資すれば中国に直接投資するリスクは避けながらも中国に対するエクスポージャーを適度に維持できるという点も、日本が浮上する理由だ。 最近ゴールドマンサックスは「米国と同盟国は希土類を含む中国のサプライチェーン支配力を弱めることを目指している」と診断し、オーストラリア・カナダ・スウェーデンなどとともに日本がさらに重要な国になると予想した。・・>>
日本経済内部の事情を見ても夢のような姿が明確だ。 8日、日本内閣府は第1四半期の国内総生産(GDP)成長率が2.7%(年率基準、前四半期比)を記録したと明らかにした。 年率基準は、このような傾向が1年間持続する場合の成長率である。 これは先月出てきた速報値(1.6%)はもちろん専門家予想値(1.9%)を大きく上回るものだ。 速報値で設備投資は前四半期より0.9%増えたことが分かったが、今回は1.4%と大きく上方修正された。 ブルームバーグ通信は「世界経済の鈍化の懸念にも日本企業の心理が依然として弾力的に維持されている」と評価した。
これと関連して、上田一雄日本銀行(BOJ)総裁は6日、「賃金・物価が上がりにくい環境に少しずつ変化がある」と評価した。 数十年間、賃金・物価が停滞するデフレを経験した日本経済に変化が現れているという診断を中央銀行総裁が出したのだ。
ただし、日本経済の弾力性が短期的である可能性があるという慎重論も出ている。 オックスフォードエコノミックスの山口紀弘選任エコノミストは「これまで抑えられた需要が生き続け、企業も投資機会を覗いている状況なので、今後数カ月間経済が回復力を維持するだろう」としながらも「これまで断行された米国やヨーロッパなどの 金利引き上げ効果が現れ、今年後半と来年上半期に日本の輸出に悪影響を及ぼすだろう」と見通した。 予想より早い高齢化、莫大な国家負債なども日本経済には構造的障害だ。
(ソウル経済その2)イ・テギュ記者 classic@sedaily.com
引用部分にはありませんが、記事2は冷戦構造だから~をメインにしていますが、イジピョン教授は「米中対立は、どちらかというと日本にとっても大きな負担になる」としており、今の「日本が最適」とする風潮は、決してただで手に入ったものではない、という趣旨を書いています。それはそうでしょう。さて、サプライチェーン再編、強いて言うなら「大再編時代」は、まだまだ始まったばかり。しかし、その流れは決まっていると言えるでしょう。頑張れ、日本。