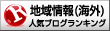韓国が反日没頭していた2019年、米-日-台湾半導体同盟開始
http://monthly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=&nNewsNumb=202304100031
文:パク・ジョンギュ漢陽大学未来自動車工学科兼任教授
⊙ 美、中国牽制のために半導体戦争を繰り広げながら政治的・軍事的リスクのある韓国の代わりに日本をパートナーに選定?
⊙ ▲米国のファーウェイ制裁 ▲IBM、日に2ナノ半導体試製品の製作要請 ▲TSMC、日東京大デザイン研究所設立支援(2019年)
⊙アマリアキラ自民党議員、半導体戦略推進議員連盟設立… 日本政府、半導体産業再建に10年間10兆円投資約束(2021年)
⊙日本国策半導体会社ラピダース設立… トヨタ、デンソー、NTT、ソニーなど民間企業8社が10億円ずつ出資(2022年)
⊙ラピダース、最先端ロジック(Logic)半導体を少量でも早く生産することが目標… トヨタ生産方式(TPS)の半導体板
朴正圭
1968年生まれ。 漢陽大学機械工学科卒業、韓国科学技術院機械工学科修士、日本京都大学精密工学科博士/起亜自動車中央技術研究所研究員、日本京都大学精密工学科助教授、LG電子生産技術院、現代自動車自動車産業研究所・海外工場支援室勤務。 現漢陽大学未来自動車工学科兼任教授、グレンデールホールディングス副代表/翻訳書《実践モジュラー設計》《トヨタ製品開発の秘密》《モノづくり》

バイデンアメリカ大統領は2022年12月7日、アリゾナ州フェニックスにあるTSMC工場建設現場を訪問した。 右はマークリウTSMC会長。 写真=AP/ニューシス
半導体戦争が激化している。 中国は2001年にWTO(自由貿易機関)に加入して以来飛躍的な経済成長を遂げた。 しかし、強力になった経済力をもとに中国が作る位階秩序に周辺国を編入させようとする。 特に長期執権時代を開いた習近平は、2027年までに台湾攻撃準備を終えろと軍に指示したと言われている。
半導体は米中覇權競争の核心である。 今、米国は本格的に最先端の半導体装置の中国流入を阻止し始めた。 そしてチップス法(CHIPS and Science Act)を作って米国内半導体工場を作る企業に生産補助金390億ドル(50兆ウォン)を支払う予定だ。 補助金を申請した企業は今後10年間、中国投資が制限されるなどの制約が続く。
韓国はこれまで「安保は米国、経済は中国「安米經中」」という両足戦略を駆使してきた。 しかし今、半導体ではそれほどこの戦略は使用できません。 半導体技術の変化に伴って発生した半導体サプライチェーンの変化は、半導体産業の新たな競争構図を生み出している。
このような状況で日本の動きが注目される。 サムスン電子に代表される韓国半導体の発展の歴史は、日本半導体敗亡の歴史でもあった。 日立、NEC、東芝などの半導体名家はすでに20年前にDRAM生産を放棄している。 そんな日本が米国IBMと手を取り、最先端半導体(2nm工程)を作るという。 台湾企業(TSMC)は日本の熊本に半導体工場を建設している。
アメリカ - 日本 - 台湾は今何が見えますか? 韓国企業が孤独になるのではないだろうか? 今、半導体産業の変化を日本を中心に見て、今後韓国半導体産業がどのように対応すべきかについて議論してみよう。
中国産スパイチップ事件
誰もが大きなことをする時は、あるきっかけがあるはずだ。 そして仕事をすることに気をつけて一定の準備期間を経て実行することになる。 企業と国家も同じだ。 今、半導体戦争が起きた直接的なきっかけと意思決定が起きた時点をもう一度振り返る必要がある。 正確にはわかりませんが、過ぎた新聞を見直すと推定することができます。 いくつかの出来事を見てみましょう。
2018年10月4日、米国「ブルームバーグビジネススウィーク(BBW)」は中国で作られ、米国の主要企業に納品したコンピュータサーバー用回路基板にスパイチップが装着されていると報じた。 アップル、アマゾンを含む米国主要IT企業だけでなく、米国中央情報局(CIA)、国防部データセンターなどに納品したサーバーでも使用されたと報じた。 このチップは、通常の認証手続きを経ずにコンピュータや暗号システムなどにアクセスできるようにする役割(バックドア/後扉)をする。
以後、2019年5月15日、トランプ当時、米国大統領は「情報通信技術およびサービスサプライチェーンの確保に関する行政命令」を発動した。 米国の国家安全保障を侵害して米国企業の技術流出を試みる他国企業との取引を全面禁止する内容だった。 その後、米国商務省は、中国のファーウェイが米国企業との取引を行うことができないようにする行政命令を施行した。 いくつかの理由があるが、この時から米国が中国を制裁しなければならないという決心をしたと見られる。
IBM、日本に2ナノ半導体製造を要請

「日本半導体最後のギャンブル」記事が掲載された日本雑誌《週刊ダイヤモンド》
一方、2019年夏、米国IBM幹部のジョン・ケリー(John Kelly)が東哲郎に電話をした。 東は1996年、当時46歳で世界3位の半導体装備会社である東京エレクトロニクスの社長となった人物だ。 電話の内容は驚きました。 2ナノ最先端半導体生産をIBMの技術ライセンスを活用して日本が生産してほしいという要請だった。 IBMは半導体技術を提供してライセンス費用を受ける会社で、すでに2ナノ半導体試作品を持っていた。 サムスン電子が2022年から作る3ナノ半導体もIBMの技術に基づくものだという。 このように2019年、米国のIBMは技術協力の対象を韓国から日本に変更した(「週刊ダイヤモンド」「日本半導体最後のギャンブル」、2023年2月25日)。
しかし、日本はすでに半導体集積化競争から脱落した国だ。 半導体微細化技術は40nmで止まっている。 そんな日本で2ナノ半導体を作ることは可能だろうか? 日本はまずIBMの意図を把握することが必要だった。 そして日本半導体メーカーの中で2ナノ半導体生産をする意志があるところを探さなければならなかった。 IBMは本物でした。 今後詳しく言及するが、韓国の地政学的問題かもしれないし、サムスン電子が大きすぎる企業に変身したので、他の競争候補を作りたかったかもしれない。
東は先に日本の半導体企業である東芝とソニーにIBMの意思を打診したが拒絶された。 日本企業は巨額を投資する余力がなかった。 東は結局政府の助けが必要だと判断し、自民党の甘利明衆議院に連絡した。 その後、日本政府の積極的な協力のもと、2022年8月にラピダス(Rapidus)という日本国策半導体会社が設立された。 ラピダースが追求する半導体ビジネスモデルは後述する。
TSMC、東京大学とつかむ
2019年、日本政府は半導体問題に没頭していた。 IBMから2ナノ半導体生産を依頼されたまさにその時点で、日本政府は台湾の半導体ファウンドリ(委託生産)メーカーであるTSMCと工場誘致のための交渉中だった。 そのきっかけは五神眞東京大学総長と張忠謀TSMC会長の出会いだ。 2018年末、物理学を専攻した東京大学の小野上誠総長は台湾に渡り、TSMCのモリス窓会長と会った。 その場にはモリスの窓に続き、TSMCの会長となるマーク・リュウ(劉德音)、そしてスタンフォード大学教授であり、TSMCの研究開発部門を担当するフィリップス・ウィング(黃漢森)も共にした。
ここでモリス・チャンはTSMCと東京大学が共に興味深い研究をしていこうという提案をする。 新しい変化を直感した河野東京大総長は、慶應義塾大学に勤務する黑田忠應教授に連絡し、TSMCとの共同研究責任者になるよう要請した。 黒田は東芝で20年以上半導体開発を担当していた経歴の人物だ。 彼は2019年8月に東京大通りを移し、10月にTSMCの支援を受けてシステムデザイン研究センター(ディラップ/d.labと略称)を設立した。 ディラップは会員制で、どの半導体チップをどのような技術にしてどこに使用するかを東京大学電子工学と各研究室と企業が互いに討論する方式で運営される。 そしてTSMCは導出されたアイデアを基に直接半導体試作品を作って提供した(「日経ビジネス」2021年12月、「東京大+TSMCの求心力、日本の半導体が覚醒する」)。 TSMCは半導体の将来の変化に適応するために日本技術が必要だったのだ。 一言で言えば、2019年は国家間連合戦線を形成する時期と見ることができる。
2019年の韓国状況は
米国-日本-台湾間の半導体連合戦線が形成され始めた2019年、文在寅(ムン・ジェイン)政権チハの韓国は、日本政府の「ホワイトリスト」排除措置を口実に反日に没頭していた。 写真=朝鮮DB
2019年韓国の状況を振り返ってみよう。 2018年10月、韓国最高裁判所は強制徴用被害者4人に1人当たり1億ウォンを賠償するように判決した。 日本は韓日協定違反だと反発した。 2019年7月、日本政府は半導体核心素材であるフッ化水素など3品目の韓国輸出を規制し(「ホワイトリスト」排除措置)、韓国政府高位関係者はソーシャルメディアサービス(SNS)に竹倉家を上げた。
SKハイニックスがインテルの中国工場買収契約に署名した時点が2020年10月だ。 半導体分野で中国を孤立させようとする米国の意図をインテルが知っていたのか分からない。 しかし、結果的にIntelは中国内の半導体工場を韓国企業に引き渡してしまった。 今振り返ってみると、2019年の大韓民国は世界の物情をあまり知らなかった。 米国-台湾-日本間にこのような連合戦線が形成されているとは想像もできなかった。
季節産業と半導体産業には同様の点がある。 「何が太ったのか」という人もいるだろうが、産業の形が似ている。
自動車産業は、様々な部品を持って一つの製品を作る組立産業(Assembly Industry)である。 これと対比する概念であるプロセス産業(Industry)は原材料を一連の工程(プロセス)を経て所望の形態の製品にしていく産業である。 旬、化学産業が典型的な例だ。 半導体産業はプロセス産業に近い。 プロセス産業は膨大な設備投資費を必要とする。 それで国家政策と多くの関連性を持っている。
TSMCは台湾国家政策の産物
今、半導体製造部門で世界トップの座を占めている台湾TSMCの設立過程は、韓国の浦項製鉄(ポスコ)のそれに似ている。 私たちはしばしばモリス・チャンが50代の年齢でTSMCを創業したと知っている。 しかし、ある個人が巨大資本が入る半導体会社を設立することは可能だろうか?
TSMCの胎動は1969年にさかのぼる。 当時、台湾の経済部長(長官)にいた孫運璿が朴正熙元大統領が設立した韓国科学技術研究院(KIST)を訪問して衝撃を受けた。 彼は台湾も何かしなければ韓国に遅れるという危機感を持って帰国し、海外専門家の意見を聞き始めた。 そうして1973年に台湾工業技術研究院(ITRI・Industrial Technology Research Institute)が設立された。
事実、台湾の半導体産業はITRI(工業技術研究院)と共にいる。 現在サムスン電子に続き、半導体ファウンドリ部門で世界3位を占めている台湾半導体メーカーの聯華電子も1980年、ITRIで創業(スピンオフ)した会社だ。
モリス昌は1987年、ITRIの3大院長として迎え入れられた人物だ。 彼は工業技術研究院長として出勤してから2週間で、当時台湾の李国政政務委員からミッションを与えられた。 政府が出資する方式で大型IC(集積回路)会社を作ろうとするので、事業モデルを組むということだった。 台湾半導体メーカーのUMCが高度な半導体会社に成長できないと、台湾政府が下した決断だった。 こうして作られた会社がTSMCだ[《TSMC発展の謎を解く》、朝元照雄教授2013年論文]。
TSMC設立時、台湾政府が48.3%の資本を出資し、オランダの会社であるフィリップスが27.5%、残りの24.2%を台湾の複数の民間企業が出資した。 つまり、TSMCという会社は台湾政府の強力な意志と財源支援、フィリップスの技術提供、そしてモリス・チャンという慧眼を持ったリーダーがいたから可能だった。
朴泰俊という顕著なリーダー、日本製鉄の技術支援、政府の強力な意志と財源支援で設立された浦項製鉄(ポスコ)とほぼ同様の創業ストーリーだ。
モリス・ウィンドウが考えたビジネスモデルは、設計と製造を分離して半導体製造だけの企業を作るというものだった。 この概念は、米国ミシガン大学のコンウェイ(Lynn Conway)とミッド(Carver Mead)教授が集積回路(VLSI)設計時にデザインルール(Design Rule)を設定したことで可能になった(1978~1979年)。 建築設計と施工が分離され、本を企画・編集する出版社と印刷所が分業化されたように半導体産業でも設計と製造が分業化された。 活版印刷を考案したグーテンベルクの名を借り、半導体業界では「グーテンベルクモーメント(Gutenberg Moment)」と呼ぶ(「チップ戦争(Chip War)、クリスミラー、2022年)」。 モリス・チャンが提示した半導体ファウンドリ(委託生産)モデルは成功し、今TSMCは最高の半導体会社になった。
半導体再建に飛び込んだ日本
1970年代、韓国が浦項製鉄を建設する時の姿のように、今日本は政府、企業、学者たちが混연一体となって半導体産業の再建に乗り出している。 前述の自民党のアマリ・アキラ衆議院は、他の数名の議員とともに2021年5月、半導体戦略推進議員連盟を設立した。 そして日本政府は半導体産業の再建のために10年間10兆円(100兆ウォン)を投資するという約束をした。
2021年10月、日本政府はTSMCの誘致を発表した。 岸田首相は記者会見を開き、TSMCに対する支援を表明した。 実際、日本政府は2021年に7740億円、2022年に1兆3000億円の予算を策定して執行した。 当初、TSMCは熊本に22~28ナノ半導体工場を建設する予定だったが、日本経済産業省の強力な要請により12ナノ半導体工場も作ることにした。
先に述べた東越郎東京エレクトロニクス社長及びその意志を共にした半導体生産技術専門家の小池淳義は、アマリ・アキラ衆議院の事務所で経済産業省幹部らに半導体再建の必要性を力説した。
日本政府はIBMの2ナノ半導体を量産するために直接会社を設立することに決め、2020年春にプロジェクトメンバーを結成した。 2022年ロシア・ウクライナ戦争勃発後、中国の台湾侵攻の可能性が台頭し、日本政府の動きは加速した。 2022年5月、経済産業省幹部が米国IBMのアルバニー研究所を視察し、IBMのダリオ・ギル(Dario Gil)首席副社長が日本で岸田首相と面談した。 半導体戦争に日本も国家的なレベルで競争に飛び込んだのだ。
ラフィダス、少量でも早く生産

ラピダースのホームページ。 「世界と協力して日本の開発・製造力を結集し、世界最先端のロジック半導体開発、製造を目指す」と宣言している。
このような過程を経て、2022年8月に日本国策半導体会社であるラピダス(Rapidus)が設立された。 哲郎東京エレクトロニクス社長が会長を、小池が社長を務めた。 トヨタ、デンソー、NTT、ソニーなど民間企業8社が10億円ずつ出資した。
ラフィダスに投資したトヨタ、デンソー、NTTなどは最先端の半導体が必要だという点で共通点がある。 トヨタ、デンソーは自律走行用半導体が必要だ。 NTTは通信用半導体が必要です。 多品種 少量生産を追求する日本メーカーは、TSMCに半導体注文をしてもいつも賛美のお世話だった。 TSMCのトップ顧客はアップルです。 AppleはiPhoneを年に2億個販売する。
全世界の自動車1位メーカーであるトヨタは1年に1000万台の車両を販売する。 しかも車種も多様だ。 未来自動車が自律走行をするためには先端半導体が必要だ。 しかし、TSMCが必要なときに作ってくれるという保証はない。 近年、車両用半導体が不足して自動車工場が停止し続けた。 家電・電子産業が没落した日本の立場で自動車工場が止まっているというのは想像もしにくいことだ。 日本政府は何とかこの問題を解決したかった。
ラピダースは、最先端のロジック半導体を少量でも早く作ることを目指している。 ラピダースという会社名はラテン語で「速い」という意味だ。 つまり会社が追求する目標を社名に定めた。
「競争で勝利するための秘策」
ラフィダスが追求する生産方式は、自動車生産方式の典型であるトヨタ生産方式(TPS・Toyota Production System)と似ている。 TPSは、自動車の車体が溶接され、塗装された後、さまざまな部品を組み立てて完成車を作り出すまでにかかる時間(Lead Time)を減らすことを目指しています。 そして、さまざまな顧客にさまざまな車両を供給するために、異なる車両でも同じコンベアベルトの上で生産できるようにした。
しかし、半導体生産の場合にはトヨタ生産方式と逆に動いた。 生産コストを減らすために、可能であれば一度に同じ半導体をたくさん撮り出そうとした。 このような方式をバッチ方式(Batch Wafer Processing)という。
ラフィダスはバッチ生産とは逆にウエハ一枚ずつ少量で生産する方式(Single Wafer Processing)を採用したことが知られている。 これにより、少量の注文でも高速な時間内に半導体を供給することができる。 半導体業界ではこのような方式を短TAT生産システムと呼ぶ。 ここで、TATはターンアラウンドタイム(Turn Around Time)の略で半導体製造時間を短縮するという意味である。 ラフィダスが追求する半導体生産方式は、トヨタ生産方式(TPS)の半導体板と見ることができる。
東京大黒田忠弘教授はこの生産方式が「競争で勝利するための秘策」と表現した。 彼は2023年1月「日本経済新聞」とのインタビューで「半導体が20年、30年間でコストを下げる競争が進んだが、今や半導体はコストとともに性能も重要な時代に変わっている」とし「ラフィダスが追求 という短TAT生産システムがこれから有効になるだろう」と話した。 ファウンドリ産業に遅れて進出した日本がサムスン電子、TSMCと同じ方式のビジネスモデルでは勝てないため、生産方式の革新を通じて新しいビジネスモデルに勝負を掛けるということだ。
台湾の半導体専門家Lucy Chenは、2023年2月20日「日本経済新聞」とのインタビューで、ラピダスが2ナノ半導体量産に成功すると見た。 米国のIBMとベルギーimec(世界的な半導体研究機関)が技術的な支援をしてくれるという点、そして日本は半導体材料と機器分野で世界最高水準だという点が理由だ。 ただし、量産に成功してもビジネスを持続させることができるほど顧客を確保できるかどうかについては疑問を提起した。
IBMはなぜ日本を選んだのか?
IBMは2014年、米国の半導体製造工場を売却し、半導体量産業務を放棄した会社だ。 しかし、最先端の技術力をもとに新しい半導体プロセス技術のノウハウを提供し、ライセンス費用を受けるビジネスは持続した。
今、IBMは3社とパートナー関係を結んでいる。 サムスン電子が最高のパートナーとして、2022年からサムスンはIBM技術を基に3ナノ半導体の量産に着手した。 そしてインテルもIBMと提携関係を結んだ。 2021年、インテルのCEOであるPat Gelsingerは、就任初期に事業戦略説明会をしながら「IBMと先端半導体研究開発を行うだろう」と発表した。 3番目のパートナーとなったラピダスは、技術的に最も難易度の高い2ナノ半導体量産を担当することになった。
米国のIBMはなぜ日本を新しいパートナーとして決めたのか? 正確にはわかりませんが、推定してみることはできます。 上の図は、米国と中国の半導体戦争の様相を表現した図である。 半導体が設計と製造の分業現象が発生し、専門化が行われた。 半導体プロセスの微細化が進んで、最先端の半導体を作ることができる半導体会社は、今はほとんど残っていない。
このような状況で、米国のIBMは台湾のTSMCと対抗する半導体会社を勢力化する必要があった。 Intelの半導体製造技術は、温かくないレベルでした。 2019年に韓国の状況を見ると、政治的・軍事的リスクが相変わらずだった。 そしてサムスン電子も半導体業界で大きすぎる存在なので、新しい対抗馬として日本を打ち出すのではないだろうか?
米国は日本半導体製造会社の中国への半導体輸出を禁止し、日本政府はこれを迅速に受け入れた。 米国が中国を牽制し、中国の半導体産業を枯死させるためには、半導体装置と材料が中国に入るのを防ぐべきである。 日本はその役割を忠実に履行してくれ、2ナノ半導体という先端半導体技術の提供を受ける機会を取ったかもしれない。 一方、半導体プロセスの微細化が進むにつれて、半導体装置と材料処理技術がさらに重要になった。 結局、IBMは2ナノ半導体を量産するためには日本技術が必要だと判断したかもしれない。
海外技術動向に鈍感な韓国企業
今私たちは何をすべきか。 反省が必要です。 国際情勢の変化に暗すぎたという点で反省しなければならない。 私たちは名分が先に実際の状況を正確に見られない傾向がある。
21世紀の戦争は銃と大砲にするのではなく、半導体、バッテリー、自動車で進んでいる。 それなら、関連する海外競争会社の動向を綿密に把握することが基本だ。 しかし、なかなかこんなことをしない。 特に技術的動向に対して関連する仕事を着実に持続した人はあまりない。 企業経済研究所に行ってみれば勤務経歴が数年になっていない顔が多い。 工場や研究所で仕事をしたことがないので、エンジニアと会話ができない経営陣がほとんどだ。 このような状況で技術変化の意味を把握するのは無理だ。
半導体産業が水平分化し、個々の企業だけの能力で最高水準を達成することは困難になった。 例えば、半導体超微細加工に必要なEUVという露光装置は、オランダのASMLという会社だけが作ることができる。 しかし、そのEUVに入る光源は米国のサイマーという会社が独占している。 このように最高の技術であるほど、独占企業同士が尾に尾を噛んでいる。 したがって、技術を持った国・企業と円満な関係を維持することはあまりにも重要だ。 シリより名分を重視する民族性なので、さらにシリを名分より重視しなければならない。
戦略的支援が必要
2022年3月10日、ジョーバイデン大統領はホワイトハウスサウスコートで開かれた半導体サプライチェーン対策会議で「サムスンがテキサスに170億ドル規模の半導体工場を建設することにした」と明らかにした。 写真=AP/ニューシス
半導体の微細化が進むにつれて、膨大な投資費は不可欠です。 しばしば「台湾は中小企業が発展した国」という。 だが半導体産業においては、台湾のように国家主導で企業を成長させた国はない。 今や日本も米国も自国半導体産業のために莫大な補助金を支払っている。
韓国も積極的に半導体技術の確保に乗り出さなければならない。 ただメモリ、非メモリという二分法的区分にとどまってはならない。 半導体の種類は過去に比べて多くなり、ビジネスタイプも多様化した。 どこにどのくらいの資金を支援するかが重要になった。 あらゆる分野にまんべんなく支援するより戦略的な分野を決めて集中的に支援するほうが良い。
一方、今政府補助金を受けながら建てている数多くの半導体工場は、今後供給過剰という新たな逆風を作り出すこともできる。 半導体企業は成長とともにサバイバルという観点からの備えも備えなければならない。
過去、米国が日本を相手に半導体と自動車の両方で制裁を加えたことがある。 米国が自動車産業の組立生産性指標を本格的に測定し始めたのもこの時からだ。 以後、日本の半導体(DRAM)は没落の道を歩んだ。 しかし、自動車産業は依然として堅固に生き残り、米国市場に位置している。 その理由は何ですか? 綿密な調査が必要と思われる。
長期的に半導体分野で中国という競争者の成長が遅れたという点は韓国企業に肯定的に作用する。 この記事で述べたように、近隣国家日本は半導体産業が新しい形に変化することを期待して総力を傾けている。 韓国も半導体産業の成功体験に陶酔されず、今後産業様相が変わる可能性を念頭に置いて備えなければならない。 こういう時ほど興奮は禁物だ。
Copyright ⓒ 朝鮮ニュースプレス - 月刊朝鮮