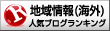韓国メディアが見た日台半導体協力・・「日本と台湾が積み上げてきた『恩』について語られたとき、日台の関係者たちは涙をうかべていた」
https://sincereleeblog.com/2023/04/07/switch-on/
2023年4月7日 2023年4月7日 尹政権の大冒険 シンシアリーのブログ, 韓国情報 0件
半導体関連記事がまた急に増えました。目新しい内容はこれといってありませんが、やはり日本・米国・台湾の半導体協力に関する記事が多く、気のせいか、日本と台湾の協力を論ずる記事が目立ちます。中には、TSMCは米国のスタンス(補助金などに条件が多い)に完全には同調しないでおり、米国よりは日本との協力を望んでいるという記事もありました。ほどの差はあれど、概ね、日台協力をもっと重く見る必要がある、危機感が足りない、とする内容は各記事に共通していました。その中でも、東亜日報系列の『新東亜』というメディアの記事をピックアップしたいと思います。こちらは3月30日の記事ですが、記者さんが日本まで来て取材したもので、他の記事よりユニークな内容です。
記事は、日本、米国、台湾の半導体協力は、韓国側が考えているよりずっと本格的に進んでいるとします。記事によると、TSMCが熊本に工場を作るという話が初めて出てきたのは2020年頃。公式発表されたのが2021年、工場から半導体が量産される時点は2024年。工場の公式発表があってから、20社以上の日本企業が熊本への新規進出、または既存インフラの増強を発表。ソニーの場合スマートフォン用イメージセンサー工場を2024年に着工すると発表。経済産業省が2ナノチップ生産のための米国との先端半導体協業プロジェクトを発表したのが2022年5月、日米共同研究センターLSTCを2023年に設立すると発表されたのが2022年7月、2022年11月「ラピダス」設立。すでに法人登録は2022年8月にできていた、とも。
記事は、取材の際に聞いた話として、LSTCはすでに日米で2020年から会議を続けてきたとし、『いったい、どれだけ大勢の日米の関係者が、どれだけ会って会議をしたのか、想像もできない』としています。ラピダスがヨーロッパ最大の半導体研究所「IMEC」との協力を発表したのが2022年12月、IBMとの2ナノ研究・開発を発表したのが2023年1月。記事は、特に日本と台湾の協力は、想像を超えていると書いています。そして、去年6月、つくば市にオープンしたTSMC研究センターの開所式での、あるエピソードを紹介しています。以下、<<~>>が引用部分です。
[日本半導体復活現場に行く①] 美・台湾と集まらなければ生きる、今回が最後の機会だ
https://v.daum.net/v/20230330100113747
東京=許文明記者入力 2023. 3. 30. 10:01 修正 2023. 3. 30. 15:15
日半導体業界に吹く新風
●復活の象徴、熊本TSMC工場
● すべてが遅い日西半導体は速転速決
●民間ではなく政府主導で米・台湾と団結
●「メイドインジャパン」のために集まったドリームチーム
●屈辱的な技術条件も受け入れる
●半導体がなければ日生き残ることができない
24時間稼働中の熊本TSMC工場。 [東京=許文明記者]
半導体覇権競争が国家間戦争に広がっている。 米国は政府が直接出て産業秩序を再構築し、ゲームのルールを変えようとする。 同盟国に補助金にんじんを出し、技術と利益共有まで要求している。 ここに日本は1980年代半導体覇権国の地位を取り戻すために安堵力を使っている。 莫大な補助金で外国企業工場を誘致し、何より米国・台湾とまともにまとめて協業体系を作っている。 私たちは果たしてそれらほど切迫して走っているのか。 日本半導体復活現場の声を専門家インタビューを中心に連載する。 <編集者の週>
投稿の順序
①「美・台湾と集まらなければ生きる、今回が最後の機会だ」
②技術・人材がなくなったが、日が半導体復活に切迫した理由
③永遠の一等はない、日半導体墜落師が与える教訓
④ 半導体1等 韓、素材装備1等日まとめれば美怖くない
2016年に大地震が発生した日本熊本のある九州は、古代時代から私たちと縁が深い。 地理的に東京より釜山が近く、韓国の祖先が三韓時代から渡って住んでおり、三国時代の時は百済・新羅住民たちが大々的に渡って定着した。 稲作はもちろん仏教、文字など様々な文物が伝わり、百済滅亡後は王族、貴族、学者などエリート層が大挙移住した。
記者は2015年「日本の中に残っている韓国の古代跡」を取材し、九州一帯を巡ったことがある。 九州の中心である熊本では、かつて姫武霊王陵や益山入店里百済古墳物と非常に似た遺物が大量発見された。 亡命した百済貴族たちの技術で築いたという記録が伝わる城でも百済仏像が発見(2008)され、日本社会を興奮させたことがある。
冬の寒さが真っ最中だった2023年2月7日、福岡博多駅から熊本へ向かう新幹線に乗って40分余りを走る間、記者は熊本という地名の漢字の名前「熊本」を掛けてみた。 「熊熊」者は百済の旧首都熊津・姫に由来したという説があるが、その昔百済人たちが「熊津の根」という意味の名前を作ったのではなかっただろうか。
今回再び熊本を訪れた理由は「半導体取材」のためだった。 日本の平凡な大都市であるここは最近世界の注目を集めている。 2年前、台湾のファウンドリ(半導体チップ委託生産)企業TSMCが大規模半導体工場を建設し始めたからだ。 工場建設現場を直接行ってみたかった。
新幹線熊本駅に降りて再び地下鉄に乗って原水駅に降りてバスで乗り換える日程だった。 バス終点名は「ソニーセミコンダクト」。 TSMCが工場を建てている一帯がソニーなど半導体部品工場が密集した場所であることを推測する名前だった。
原水駅に降りた時間は午前8時。 田舎の簡易駅のように厳しかったが会社員らしい100人余りが並んで立っていた。 万ウォンバスに乗って約30分後、終点駅に到着すると広大な大地の上に大規模な工場が散在しており、巨大な産業団地を連想させた。
実際にバス駅のすぐ前にはソニーの半導体専門企業である「ソニーセミコンダクタソリューションズ」工場があり、ここでさらに歩くと世界的半導体機器メーカーである「東京エレクトロン九州」工場がある。 熊本市内でもさらに参入するここをなぜ人々が日本のシリコンバレーと呼ぶのか分かった。
TSMC工場建設現場は終点駅から10分余りを歩かなければならなかったが、あまりにも大きくて遠くからもすぐ目に入った。 計21万平方メートルに達する広い敷地に約2mの高さの壁に囲まれた現場では、数十台のクレーン、掘削機、大型トラックなどが精神なく動いていた。 24時間稼働するという現場周辺は遮蔽幕が張られていたが、工事現場の機械音と人々の足で忙しい。
すべてが速戦速決
熊本は日本が半導体覇権国だった1980年代関連産業をリードしてきた中心都市だった。 かつて1960年代からNECと三菱半導体工場が建てられ、続いてソニーセミコンダクタソリューションズ工場と東京エレクトロン工場が建てられた。 九州一帯はかつて全世界の半導体生産量の10%を占めて「シリコンアイランド」と呼ばれたが、日本半導体が没落し地域経済も没落し始めた。 熊本も同様だった。 それから電撃的にTSMC工場が入りながら注目され始めたのだ。
今日本は政府を中心に1980年代の半導体栄光を取り戻そうという声が大きい。 熊本こそ半導体復活の象徴的現場であるわけだ。
時間を3年前に戻してみよう。
TSMCが日本に工場を建てるという記事がメディアに上がった時期は2020年からだった。 当時だけでもTSMCは記事内容を否定したが、経済産業省が2021年6月4日TSMC誘致を公式宣言し、既定事実となった。 それと共にすべてが約束もしたように速戦속決で進行された。
経済産業省発表4ヶ月ぶりの2021年10月、TSMCは公式に日本内ファウンドリ進出計画を発表し、工場が建てられるところは「熊本県」になると発表した。 これに答えるように岸田文夫首相は直接記者会見を開き、工場建設費用の40%水準である4760億円(約4兆550億ウォン)を補助金として支給すると言った。
熊本TSMC工場でチップが量産される時点は来年の2024年12月だ。 ウェーハの場合、12インチ月5万5000枚を生産する計画だという。 速度よりも安全を重視し、すべてが遅く慎重な日本で3~4年かかる半導体工場建設を2年ぶりに終え、3年以内に製品を生産するという自体が異例だ。
現在、日本の半導体チッププロセス技術は40nm(1nmは10億分の1m)まで実装された。 熊本工場から出てくるチップは28~22ナノ技術で作られる。 現在、サムスン電子とTSMCが3ナノチップを量産しているのと比べると、道が遠くても遠い。 だが熊本発風は日本半導体産業界の雰囲気を変えている。
熊本TSMC工場の波及効果をお金で計算すれば、今後10年間で約4兆3000億円(41兆ウォン)に達するという分析もある。 工場建設に悩んだ人々も、いつも量産時点が近づくと期待する雰囲気が力強かった。 周辺の地価は上がっており、材料や装備会社も徐々に工場周辺に集まる態勢だ。
実際、TSMC進出以来20を超える日本素材装備企業がここに既存施設の増強や新規進出を発表した。 代表的なメーカーがソニー(Sony)だ。 ソニーグループは熊本県に進出したTSMC新工場近くに2024年スマートフォン用イメージセンサー工場を着工し、2025年以降稼働を目指している。
ソニーはイメージセンサ(CMOS)市場で世界市場シェアを40%ほど占めているグローバル1位企業だ。 すでに熊本で工場を運営しているソニーは、TSMCの熊本工場が戻ればここでロジック半導体を供給され、イメージセンサーの生産に活用するという大きな絵を描いている。 最近需要が増えているスマートフォン用イメージセンサーを「メイドインジャパン」にして次世代イメージセンサー市場で2位のサムスン電子を含む他企業との格差を広げるという戦略だ。
人も技術も足りない日本の半導体産業が復活に成功できるだろうか。 ここへの答えをする前にまず目を向けるテーマがある。 日本の場合、徹底的に政府が立ち上がって米国、台湾と協業体系を作っているという点だ。
政府主導米国・台湾とコラボレーション
熊本でTSMC工場が初のシャベルを開けて真っ最中工事が行われた2022年。 経済産業省は先端半導体技術開発のための米国とのコラボレーションプロジェクトを次々と発表した。 5月、ハイウダ・コイチ当時、経済産業省長官とジーナ・レイモンも米国商務長官は共同記者会見を開き、「日米首脳合意に基づくもの」とし「両国間半導体サプライチェーンに協力し、市場を透明に開放し、双方が認めて 補完する形で半導体製造能力強化、労働力開発促進、透明性向上、半導体不足に対する緊急対応協力及び研究開発協力を強化する」とした。
当時発表された協力案の中で最も注目を集めた点は、両国が今後半導体チップパラダイムを変える「2ナノ」チップ量産のために手を握るということだった。 2ナノは、まさにチップ微細化の「終板王」と言える先端の中で先端技術だ。
米日両国は協力案を発表してわずか2ヶ月ぶりの7月になると、共同研究開発組織である「技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)」を2023年内に設立すると明らかにした。 そして日本政府は11月になると2ナノチップを生産する会社として「ラフィダス」を立てたとし、8月にすでに設立登録まで終えたと発表した。
LSTC設立の議論は、3年前の2020年から水の下で行われたという裏話だ。 米国と日本の間でどれだけ多くの政財界の挨拶が、最後に頻繁に会って緊密にコミュニケーションしたかどうかを推測する主題だ。

2022年12月東京で開かれたセミコンジャパンディナー。 東越郎ラピダース会長が舞台で演説している。 [東京=許文明記者]
2022年が暮らしていた12月14日。 韓国のCOEXといえる東京ビッグサイト。 半導体国際展示会「セミコンジャパン」が開かれた。 半導体材料機器展示回路は世界最大規模のイベントだ。 コロナ19の終わりを歓迎するようで賑わった。 12月16日までたった3日間行われた行事に、なんと6万人余りが参加するほど盛況を成し遂げた。
今回のイベントには前年比50%が増加した673社が参加した。 もともと参加を希望していた企業は700社を超えたという。 今年はさらに規模を育てるというのがイベント関係者の伝言。 今回のイベントは、最初から最後まで「ラピダースによる、ラピダースのためのもの」だったというのが、東京で出会った参加者の評価だ。
「2ナノを越えて(Beyond 2nano)」
初日には岸田文夫首相が日本の半導体産業をなぜ復興させなければならないのかをテーマに開幕演説(Opening Speech)をして雰囲気を浮かべた。 それとともにラピダスを「未来次世代半導体量産拠点」と話した。 続いて、自民党半導体戦略推進議員連盟会長を務めている天井明議員は「なぜ今、日本が先端半導体をしようとするのか、台湾海峡が封鎖されれば最先端ロジック半導体供給が70~80%止まる。中国とは連携できない。 企業と政府レベルで価値観を共有できる米国・ヨーロッパと提携していくことが重要だ」と話した。
同日夕方開かれた晩餐会場には、日本の主要装備材料メーカーの主要経営幹部(会長および社長級)はもちろん、半導体関連の定在界、学界関係者など400人が集まった。 イベントに参加した業界関係者は「彼らが一度に晩餐席に総出動したのは非常に異例のことで、経済産業省が出席を促したという裏話もあった」と伝えた。
「ラピダース」の英語表記「Rapidus」はラテン語で「速い」という意味だ。 韓国語で打つと会社名を「早く早く」で建てたのだ。 それだけ切迫感と意欲を表わしたものといえる。
ラピダスは政府が主導するが、日本代表企業が出演金を出した民官合同企業だ。 企業の面を見れば、むしろドリームチームといえる。 世界15位圏の日本の唯一の半導体製造会社で、NANDフラッシュメモリ分野で世界2位圏のキオキシアをはじめ、トヨタ、ソニー、NTT、ソフトバンク、NEC、デンソー、三菱UFJ銀行などが参加した。 同社の初期実弾(資本金)は8社がそれぞれ出した出資金73億4600万円(約702億5000万ウォン)に政府支援金700億円(約6650億ウォン)が投入された。
会場として迎え入れられた東大津郎は半導体プロセス分野のスーパー級エンジニアで、世界的先端製造装置企業である東京エレクトロン社長も務め、定在界に厚い人脈を持っている人物としても知られている。
ラピダースは「2ナノを越えて(Beyond 2 nano)」というプラカードを掲げ、初の試作品が出る時期を2027年にとった。 だが日本内では「サムスンもTSMCもできずにいる2ナノをやるという夢もヤムジだ」という冷笑的な世論も多い。 なお、「2027年ごろになると、サムスン、TSMCともに2ナノをする可能性が高いため、奇跡的にラピダスがやっても遅い」という声も出ている。 だが、ラピダース経営陣は気にしない雰囲気だ。
2ナノチップ工場敷地も日本北部北海道中心都市札幌から近い千歳に建てることが分かった。 小池泰吉社長は「水や電気などのインフラが安定的で国内外の人材が集まりやすいところに工場に建てる」とし「最先端半導体をカスタマイズ型で迅速に供給する高収益ビジネスモデルを採用すれば、サムスンやTSMCなどと差別化できる」 と言った。

IBMと2ナノ半導体技術提携するラピダース。 左から2回目が東越郎会長。 [ラフィダスホームページ]
しかし、最も重要な要素はやはり人と技術です。 日本政府はラピダス設立に続き、技術と人材育成に関する「ビッグニュース」2つを連続で発表した。 1つ目は米国IBMからIP(知的財産権)導入であり、2つ目はヨーロッパ最大総合半導体研究所IMEC(アイメック)とのコラボレーションだ。
IBMからの技術移転は日本人を興奮させるのに十分だった。 IBMは2021年2ナノ半導体試製品の生産に成功した会社だ。 ラピダースとIBM経営陣は、新年の壁頭である1月5日、米国ワシントンで米日政府関係者が参加した中で2ナノ先端半導体を共同研究・開発すると公式発表した。 ラフィダスがIBMに職員を派遣し、必要な基礎技術の熟練を進めるという計画だ。 小池社長はメディアとインタビューしながら「IBMから技術供与がなければ日本と世界的な技術格差を埋めることができない」とした。
また、ラフィダスが昨年12月6日に技術協力を推進する了解覚書を締結したIMECは、現在半導体技術に関する限り、世界最大のシンクタンクといえるところだ。 ヨーロッパ、アジア、北米全域で7カ所に研究所を置いており、100カ国以上から数千人の研究者が半導体技術を研究している。 イ・ジェヨンサムスン電子会長が昨年6月本部のあるベルギーを訪問して話題になった。 IBM、IMECとのコラボレーションは40ナノをスキップして2ナノに行くという日本政府の構想が始まりは微弱だが、ただ「夢」ではないことを示す事件で、現地では受け入れる雰囲気だ。
技術を得ようと屈辱もつかない
<<・・日本の(※米国以外に)もう一つの友軍は、台湾だ。現場で感じた日本と台湾の間の半導体協力は、想像以上のものだった。・・>> 台湾は日本の植民地を経験したが、親日意識が基底に敷かれている国家だ。 実際に台湾に行ってみると、日帝植民地時代の建物がそのまま残っている。
<<・・台湾と日本の友好的関係は、半導体競争において光を放っている。グローバルファウンドリ最高企業TSMCは熊本工場に続き、昨年6月、茨城県つくば市に次世代半導体技術を共同研究する研究開発センターを設立した。TSMCは技術移転にすごく慎重な会社で、他の国に研究センターを作ったこと自体が初めてだ。「魏哲家」最高経営者は開所式で、「日本と台湾は世界半導体サプライチェーンで重要なつながりがある」とし「この研究所で結ぶ協力関係がさらに革新につながると確信する」と話した。
この日の開所式では、日本と台湾の人的関係がどれほど強いかを示す象徴的なことがあった。TSMCとの産学協力を導いている黒田忠広東京大学教授の演説だった。以下、イベントに参加した日本の半導体企業関係者の言葉だ。
「黒田教授は、過去、日本が台湾のある田舎の村に、洪水と干ばつを備えるためにダムを建てたという話をしてくれました。そのダムで土地が豊かになり、いまは台湾を代表する穀倉地帯になったという話です。台湾の関係者たちは、この内容をよく知っている、という表情でした。黒田教授は『それから80年余りが過ぎた今日、台湾会社であるTSMCが日本に来て先端パッケージ研究センターの起工式をするとは、実に感慨深いこと』、『農業の根幹だったダム建設同様、デジタル/AI社会の核心である半導体関連研究開発施設が日本に入る。日本は恩を重視する国だ。台湾も同じであり、長い間、共にしてきた日台両国がもう半導体でつながっている』と話しました。台湾と日本の出席者の中には、涙を浮かべる人もいました」
日本政府が190億円を支援する研究所では、半導体後工程(ウェハーカット後の製品化)に強みを持つ日本の素材・部品・装備企業との共同研究が推進される。これまで半導体業界の技術進化はチップをどれだけ小さくするかという微細化がカギだったが、最近では、後工程技術も非常に重要になっている。チップが分子より小さい10ナノサイズになり、これを製品化する後工程技術が半導体性能を左右しているからだ。
日本の素材装備企業は、後工程分野で実に大きなな影響力を持っている。・・>> インテル、TSMC、サムスン電子などはチップパッケージング技術の強者である日本のレゾナク、シンコ、イビデン、味の素、ディスコ、アドバンテスト、JSR、TOKなどの小部長企業に絶対に依存している。 これらの企業がなければいくら先端半導体チップ製造技術を持っていてもチップを作ることができない。 ところがこれらの小部長企業がTSMCと研究・開発(R&D)段階から協力すれば大きな相乗効果が出るというのが専門家らの一貫した指摘だ。
日本政府は研究センターを開きながら屈辱に近い条件にも合意したという後門だ。 日本政府のお金で日本の先端装備を活用して日本の企業と共同研究開発したにもかかわらず、台湾がこの技術を台湾に持ってきて先端半導体工場を建設する場合、日本政府が制動をかけられないということだ。 ある韓国素材装備企業関係者の言葉だ。
「筑波研究センターには日本人職員が自尊心が傷つくほど工場出入りに制限を受けているという話を聞きました。 誘致をするというのが私たちとしては非常に緊張する大木です」
アメリカが円低容認している?
日本政府の半導体復活プロジェクトに市場はどのような分析を出しているか。 記者は長い間半導体分野を引き受けてきたアナリストや業界関係者たちを東京現地で多様に会ってみた。 興味深いことに、彼らの視線は極端に肯定論と否定論が交錯した。 「今回が最後のチャンス」と言う人もいて、「遅すぎる」と言う人もいた。 まず肯定論の代表走者二人に会った。

グローバル市場調査会社オムディアジャパンのシニアアナリスト南川明。 [東京=許文明記者]
最初の主人公はグローバル市場調査会社オムディアジャパンのシニアアナリストである南川明(66)氏だ。 彼は日本の代表的な半導体アナリストで業界に身を置いてから32年になるとした。 大学電気工学科で自動制御を専攻した後、モトローラジャパン、モトローラ香港でエンジニアとして働いてアナリストに人生軌道を変えた。東京と香港・台湾のガートナー、IDCジャパン、HIS、オムディアなど主要市場調査会社で働いており、現在日本特許庁の半導体関連特許審査委員であり国策研究機関である新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)の研究課題評価 委員でもある。 日本のイノベーション企業に対する予算支援を審査する反官の性格の仕事をしていることを勘案すれば、多分親の性向を持った人物と見ることができる。 逆に言えば、日本政府の計画を最もよく知っている人という話にもなる。
彼に会ったのは東京秋葉原のあるビル講演会場であった。 テクノロジー専門媒体山橋タイムズ主催で開かれた「半導体の未来、どうなるか」という彼の講演には企業関係者など250人が参加して盛況を成し遂げた。 彼と席に座るやいなやラフィダス設立をどのように見るかから尋ねた。 彼は「一言で米中の葛藤に伴う全体的な大きな絵で見なければならない」とし、このように運を上げた。
「米国商務省が2022年10月、新たに中国対策を発表した。米国企業が中国ビジネスを減らす代わりにインド・東南アジアに移すという。メディアは報道していないが、実際に米・中間のビジネス規模は減っている。 今でも中国のスマートフォン製造工場を持続的に他の国に移転している。 米国はこれをさらに増やすという考えだ。 日本の強みをさらに強化し、これを元に協力しようとするのが米国の立場だ。
彼はこの台目で「最近エンジャーを'サポート'している米国の立場に注目してみなければならない」とした。
サポート? 米国がエンジャーを容認しているというのか。
「そうだ。実は長い間持続した円高で日本の製造業競争力は持続的に低くなってきた。しかし、2014年から平坦に円底になって緩やかな成長が加速する姿だ。ドル当たり130円を長期間維持すれば日本製造業 これはまさに日本政府と日本銀行の戦略であり、これを米国がサポートしていると思う。
彼の言葉は米・中覇権の戦いで米国と日本の緊密な絆関係を注目するという意味で聞こえた。
為替レートの問題は複雑に見えます。 まず、日本内の半導体復活の動きについて聞きたい。 ラフィダスは果たして成功できるだろうか。
「ラフィダス自体の成功の可否が重要だというよりも、企業を作らなければエンジニアを集めることが重要である。 ラピダース設立は、当時の利益よりも人材を育てる場所が作られたという点で大きな意味を持つ。 東会長や小池社長は誰よりもこれをよく知っている。 それは日本が何かを始めたということであり、これは米国との緊密な協力の中で進行されるということだ」
米中の葛藤で私たちが大きな影響を受けているとはいえ、どういうわけかこれは外部要素だ。 外の状況とはいつも変わるのではないか。 工場設立に一、二銭が入るのではなく、半導体産業に日本政府が持続的に予算を投入できるだろうか。
「今、日本政府は半導体技術がなければ国家が生き残ることができないと認識している。 したがって、国際情勢が変わっても半導体の育成を続けるだろう。 2022年から小池社長と様々な議論をしてきた。 最初は製品量産ではなく研究開発(R&D)だけすることも考えてみたが、今後半導体需要はますます増えるだろうので生産工場が必須だという意見一致を見た。 なければ、人材の育成もできず、素材機器メーカーとの協力も限界があるので、日本政府は継続的に支援するだろう」
米国の役割を大きく強調しているが、もしかしたら1980年代に日本半導体を屈服させた日米半導体協定のトラウマのためではないか。
「アメリカの力は強い。全世界唯一の基軸通貨がドルだという点だけ見てもそうだ。 GAFA(GAPA、Google、Amazon、Facebook、Apple)がリストラクチャリング(Restructuring)しており、新しいビジネスモデルを作っている。 行く力、つまり人と想像力がある。日本の半導体産業はこのような米国と手をつなぐことだ。
半導体市場2024年から急成長
GAFAはどのように戦場を変えようとしているのか。
「広告や購読を通じた有料会員としてお金を稼いだが売上が停滞している。今後は2次元ではなく3次元すなわちメタバス世界が広がるだろう。サイバー空間でプラットフォームビッグチェンジが起こるだろう。この過程で強力な処理パワー 2024年からはデータセンターへの投資も大幅に増えるだろう。 コンピューター、テレビなど個人が消費する製品が半導体市場を牽引した。今後はDX(Digital Transformation)、GX(Green Transformation、脱炭素)など政府が投資をリードする。
米・中摩擦はいつまで行くと見るか。
「米国は過去に日本を10年以上苦しめた。(米日半導体協定)米国は相手の力を完全に欠かすまで行く。中国が最近油絵ジェスチャーを見せているが、米国は変わらないだろう。 30年前、日本も非常に強かったが、結局アメリカの圧力にひざまずいた。 覚えている」
韓国の話をしましょう。 一部では韓国が米中紛争で中国の先端製造技術開発速度を遅らせることで時間を稼いだと言う人もいる。 米・中紛争が続くとすれば、日本もそのような点で利益を得る面もないだろうか。
中国はおそらく米国の妨害で最先端のDRAMは作れないだろう。 韓国としても時間をかけて合う。
日本もそうだが、韓国も中国に半導体工場がある。 米中葛藤が長期化すれば、中国市場から足を抜かなければならないが、どうすればいいのか。
「非常に難しい質問だ。現状で維持し続けるのか、売って出るのかは全く該当会社の経営判断だと思う。韓国としても中国ビジネスが重要だから閉鎖や売却よりは現状維持の方へ行かないか? 中国も(韓国の会社が )生産を止めれば、該当会社に強硬に警告することができるので、大変行動させられないことだ。
日本と台湾との協力も緊密に見える。
「そうだ。台湾との関係はとても良い。両国が国交はないが人的交流は多い。今後、グローバルファウンドリ3位企業UMCや他の会社も日本に研究所や設計センターを開設するなど日本進出が増えるものと見られる。 」
韓国企業とのコラボレーションは?
「日本としてはウェルカムだ。今日本には半導体人材とマーケティングが不足しているが、これを韓国企業が助けてほしい」
長期的にインド市場を注目してみようという世論が多かったが。
「それも米国が関与することなのに中国市場がなくなってインドと東南アジアを育てようとしている。インドも半導体を自国でやりたくなる。 インドにはまだ半導体生態系が造られていない、エンジニアもなく、電力やインフラも揃っていないが、政府も企業も頑張っている。 おそらく28〜40ナノロジック半導体になるでしょう」
韓国はどこに行きますか

MUFGモーガンスタンレー証券で働くワダキデツヤ。 [東京=許文明記者]
2番目の主人公はMUFGモーガンスタンレー証券で働く和垣哲也さんだ。 2000年にアナリストとして初足を踏み入れた野村証券で2016年から2021年まで働いて今年1月からMUFGモーガンスタンレー証券で働いている。 証券街ビルの森を構成する東京市内大手町駅近くのオフィスで彼に会った。 彼は過去6年間、日本の機関投資家が1位に選んだアナリストでもある。
落ち着いて静かな印象とは異なり、いざインタビューが始まると、声に確信が満ちていた。 日本半導体復活と関連して初めての質問を投げると「確かに雰囲気が以前とは違う」とした。
日本の半導体復活を見る目が肯定的視線と否定的視線が交錯しているが、あなたはどのように見えるか。
「私はポジティブだ。 大きな問題がないと考えている。小池社長が描く戦略は超特急ラインを作るということだ。 ラインを作り、一般的な量産ラインはTSMCにすればいいのではないか。
今、ラフィダスの戦略は米国とTSMCのコラボレーションであり、サムスンやTSMCとの競争ではない。 ラピダースは非メモリなので種類がすごく多いだろう。 政府支援も700億円で終わらないだろう。 半導体企業と資本提携をするか、いろいろなことがあるだろう。 実際、日本政府の半導体復活措置は遅すぎた。 すでに半導体は成熟段階なので投資する必要がないと言って、米国がするから従うのだ。 日本政府が独自にするわけではない。 日本のこのような精神状態は明治維新以後変わらない。
とにかく熊本TSMC工場に1兆円を投資するのも初めてはみんな批判的だったが、今そんな世論は消えた。 熊本県GRDP(地域内総生産)が6兆円なのにTSMC熊本工場誘発効果は1兆円程度になると思う。 新規半導体工場が入るというのは途方もない意味がある。
米中の対立はどのように見えるか
「最近中国が和解ジェスチャーをするが、中国に対する米国の半導体封鎖は続くだろう。ウクライナ事態を見ると分かるが、サプライチェーン(Supply Chain)が不安定になる時代だ。 米国は半導体自給率を現時点で10%程度上げることが目標だ」
それでも日本は意志があると思う。
「日本政府はここ数年間、独自に何をするのに自信を失った。米国がしようとすれば国民も説得になり、米国に従うことに慣れている。 しかし今こそ国内で「しよう」という雰囲気がある。 半導体関連の人々が「いよいよもうやっと私たちの時代が来るな」と思う雰囲気がある。一人当たりGDPも台湾・韓国に落ちているので危機感が大きい。
韓国についてアドバイスするなら。
「サムスン電子やSKハイニックスも心を置いてはならない。SKが第4四半期の赤字だが、もう一度赤字が出れば技術的に難しい。サムスンは数回にわたって危機があった。 技術)産業は変化が多い。アメリカ・日本も同じだ。
今年のメモリ半導体の市況をどのように見るか。
「半導体はオリンピックサイクルだからといって4年周期で好況と不況が交錯する。今はマクロ経済が良くなく、すぐ下半期は難しい。
半導体について韓国と日本の強みと弱点を挙げるなら。
「私が一番に挙げる韓国の強みは、人々が頭が良いのに勉強まで頑張るということだ(笑)。
小部長事態により日本人の韓国に対する不信が高いのか。
「私は日本政府の輸出規制にとても反対した。日本企業が打撃を受ける措置だ。輸出を規制すれば韓国が国産化をしたり海外取引先を探すのになぜわざわざそのような反日を作るのだが、こうした現場の声は反映されなかった。 」
将来の半導体で最も重要な条件は?
「高速メモリだ。半導体は多く不足するだろう。 右上向きに成長していくしかない。
[イ・ゴンヒ半導体戦争] 3高経済危機時代、「イ・ゴンヒリーダーシップ」を読むべき理由
(新東亜)東京=許文明記者 angelhuh@donga.com
記事には「東京都茨城県つくば市」という初めて見る表記もありますが、それはともかくして・・このように、日米台半導体協力は、いまのところ、早いスピードで、技術的交流、人的交流、そして心的交流もまた、順調に進んでいるようです。だからといって油断していいわけではないでしょうけど。数年後、良い知らせが届くことを願います。