リフレッシュ
blogスキンに関して言えば、ただの衣替え。
ここ数日集中しているのでPCを開く時間が短いです。
学習メモ
・自分の答えに納得がいくまで解答を見てはいけない(英・古典)
・わからないor知らない は恥ではなく明示された課題である
もうちょっとで何かが掴めそうなんだけどなあ。
ここ数日集中しているのでPCを開く時間が短いです。
学習メモ
・自分の答えに納得がいくまで解答を見てはいけない(英・古典)
・わからないor知らない は恥ではなく明示された課題である
もうちょっとで何かが掴めそうなんだけどなあ。
物欲
今まで他のものに使っていたお金を参考書やら机周りやらにつぎ込んで、そろそろ当面はこれでいいかという感じになってきました。選択科目に迷ったのが痛かった……。
片づけたり、物を探したりする必要が少しでもあると萎えてしまうので“座って1秒で勉強が開始出来る”机周りが必要だったというか、そもそも自分用の机が無かったのでそこから作る必要があったのでなかなか大変でした。
もう勉強することは無いと思っていたというか、勉強することを諦めたのがやっぱり裏目に出てしまったのですね。いや、諦め切れてなかったというべきか。
とにかくようやく環境が整ったので、やーっと服やら本が買えます。秋服だいすっきー。この微妙にあれこれ重ねて着れる時期に幸せを感じます。
昔はケープとかポンチョとか着てたらすごい目立ってたけど今はそうでもないのかな。しかし今10代だったら制服やら服やらほんと楽しかったろうな、とか、いやいや。いまも楽しいからいいんだ。
買い物に行くたびに服にかばんに靴に帽子にと目移りしまくりです。今年は物欲の秋なのか。
高認対策シリーズが一区切りついたら、これまでの勉強の過程で得た色々もぼちぼち書いていきたいと思います。中学生レベルから始めるので、現役の子でも読みやすいような……と考えると難しい。
そもそも読みやすい文章は、難しい文章を書くよりもはるかに難しいので、あんまりハードルを上げすぎると書けなくなるかなあ。
旅行疲れは思ったより残らなかったけど、歩きすぎが祟って腰が痛いです。日光の社寺めぐりは老人の方が元気でした。ばーちゃんの体力をなめてた。

片づけたり、物を探したりする必要が少しでもあると萎えてしまうので“座って1秒で勉強が開始出来る”机周りが必要だったというか、そもそも自分用の机が無かったのでそこから作る必要があったのでなかなか大変でした。
もう勉強することは無いと思っていたというか、勉強することを諦めたのがやっぱり裏目に出てしまったのですね。いや、諦め切れてなかったというべきか。
とにかくようやく環境が整ったので、やーっと服やら本が買えます。秋服だいすっきー。この微妙にあれこれ重ねて着れる時期に幸せを感じます。
昔はケープとかポンチョとか着てたらすごい目立ってたけど今はそうでもないのかな。しかし今10代だったら制服やら服やらほんと楽しかったろうな、とか、いやいや。いまも楽しいからいいんだ。
買い物に行くたびに服にかばんに靴に帽子にと目移りしまくりです。今年は物欲の秋なのか。
高認対策シリーズが一区切りついたら、これまでの勉強の過程で得た色々もぼちぼち書いていきたいと思います。中学生レベルから始めるので、現役の子でも読みやすいような……と考えると難しい。
そもそも読みやすい文章は、難しい文章を書くよりもはるかに難しいので、あんまりハードルを上げすぎると書けなくなるかなあ。
旅行疲れは思ったより残らなかったけど、歩きすぎが祟って腰が痛いです。日光の社寺めぐりは老人の方が元気でした。ばーちゃんの体力をなめてた。

高卒認定一ヶ月勉強法:英語
【高卒認定一ヶ月勉強法:目次はこちら】
(関連記事:中学英語を完成させる)
高認の英語は、他の大半の教科と同じように“高校に入らないと習わない”ものの割合はそれほど高くありません。というより、ほとんどが中学英語です。
高認から大学受験をするための中学英語についてはこちらの記事で書いているので、参考にしてください。
◆単語?文法?
単語・熟語帳については、高校受験用のものでもこの時点では大丈夫です。レベル別の場合、難関校(高校のね)対策までやって下さい。
とにかく、いきなりDuoや速読などに手を出すのはお勧めしません。よほど潜在的な能力が高ければそうでもないのかもしれないけど……。
もちろん高校に直前まで通っていたりしてそれまで使用しているものがある人は、それを使ってください。
高認の英語は難しくないので、ある程度やってきている人なら大丈夫です。
単語を一気に覚える!のもいいですが、中学からの“文法”は本当に大切です。
単語そのものはあとからでもついてくるので、どっちから手をつけたらいいのかな?という人は、文法から始めてみてください。
◆試験問題に合わせた対策を
全てマーク式であり、日本語→英語の問題は今のところ出ていません。
なので必要な能力は“英語→日本語”“英語→英語”なんですね。
つまり、英文を読んで、内容を把握して、英語か日本語の選択肢を選ぶことが出来ればいいんです。
もちろん最終的にはこの程度ではだめなのだけれど、大学受験の準備として「高認の英語で100点を取る」を最初の目標にするのも良いです。
高認の試験問題は、以下のように構成されています。
1:強勢
会話の中で協調するべき語句(単語)を選びます。
会話文なので、前後の流れから想像することが重要です。
……ふつうに考えて、会話の中で協調する語句は「わたし」「あなた」「物」「場所」「あれ」「それ」などですよね。
be動詞や前置詞はよほど特殊な場合で無い限り選ばれません。選ばれるとしたら、かなり特殊な状況です。こういうのが高認で出てくることはあんまり無いです。
前置詞ってなあに?という状態なのであれば、まずは単語帳などよりも簡単な英文法の本をやってください。
会話文の中身はたまに難しい構文があったりもしますが、単語のレベルは基本的に平易(もちろん、中学校程度という意味での平易)です。
どうしても迷ったら、「主語になりえるもの」を選んでください。
配点も低い(計6点)ので、ここで時間を使うのはもったいないです。
2:会話文(文補充)
会話の流れを掴み、それに沿った文章を選択します。
これもまた易しいです。何せ簡単な順に問題が並んでいるので、設問2で難しいようでは不合格者続出、試験の意味がありません(高認は『落とす』試験ではありません)。
設問のところに(電話で)(店で)(電車で)などシチュエーションが書いてあるのと(英語ですが)、空欄の直前、直後が大きなヒントになります。もちろんそこだけでわからなければ、会話文をすべて読んでじっくり考えます。
ここは配点が少し多い(計20点)ので、取りこぼさないこと。
3:並び替え
いわゆる文法問題。
そこまで難しくないものの、全て合っていないと正解にならないので細かいミスが響きます。
ある程度文法を理解したり熟語・構文を覚えているのなら単純な暗記や消去法でも正解できるのですが、覚えていない・わからない場合は辛いと思います。
見ただけでフリーズしてしまうほどわからないなら、まだ設問3ですが、この問題は思い切って捨てて(適当に埋めて)次に行ってもいいかもしれません。
ここだけの対策をするのは漢字と同じようにコストパフォーマンスが悪い(配点も全て正解してやっと16点)ので、長文や会話文などにあたっている時に「どうしてこの順なのかな?」「このtheは何を指してるんだ?」「ここでのwhichの役割は何だろう?」など、“この文章が並べ替えで問われたらどうしよう?”を意識しながらやってください。
もちろん、基本の『文法』を疎かにしてはいけないのですが……。
4:内容把握
短めのメッセージ文があり、送り手(書き手)の意図に沿ったものを選択する問題です。
選択肢が日本語なので、先に読んでから本文を読む方法が有効です。
選択肢に含まれている単語を本文でみつけることが出来れば、そこまで複雑な内容ではないので全訳出来なくても答えることが出来ます。
5:空欄補充
少し文章量が増えてくるものの、(日本語にして考えると)内容はそこまで複雑ではないです。
というか、1問目は大抵空欄についてひたすら説明してあったりするボーナス問題なので落としようがないかもしれません(英語がメタメタな人も、ここだけは頑張ってください)。
4と同じく、多少わからない部分があっても文脈が把握できれば解答できる問題です。名詞だけでなく接続詞や前置詞も(かなり基本的なものですが)問われるので、前後の繋がりはどうなっているか、は意識してください。
6,7:長文読解
内容把握・文補充の長文版。グラフ問題が出てくることもあります。
過去問などで“グラフについての説明でよく使われる単語”はしっかりと覚えておくのも重要です。
エッセイや投書(投書は大抵何らかの意思をもって書かれている)の場合、やはり細かい部分よりも内容を把握することが重要です。配点もとても多いです。
長文問題に慣れていない場合、一番の敵は“パニック”です。
長い・疲れた・わからない……となっていき、一文一文取り出せば読めたはずの文章も読めなくなってしまいます。
なので、まずは一番短い“設問文”“選択肢”を読み、その部分が英語ならば一通り訳し(出来る範囲で)、それから長文を読んで下さい。
ひとつの設問ごとに訳して長文に戻るより、設問を一気に訳して(日本語のメモを書いておく)から読むこと。
ここまできたら残りの時間は全て長文に使っていいので、本文をじっくり訳しても大丈夫です。
“パニック”のせいで大きく読み間違えてしまうこともあるので、焦って解くよりは時間をかけたほうが確実です。
◆参考書、オマケ
以下は一応おススメと言える参考書・問題集です。好みが分かれる単語帳と高認用なんたらはあえて外してあります。
(中学英語を完成させるも参考にしてください)
とりあえず、参考書を選ぶ時気をつけたいのが、“基礎”は大ウソであることが多いということ。
「はじめから」「超基礎」「中学校から」のようなキーワードがついているものを選んでください。
大岩のいちばんはじめの英文法―大学受験英語 (東進ブックス―気鋭の講師シリーズ)/大岩 秀樹

¥1,260
Amazon.co.jp
定番本。
大学入試英語長文ハイパートレーニングレベル1 超基礎編/安河内 哲也

¥1,418
Amazon.co.jp
高認の長文にレベルが近い。
やるとなったら書いてある通りの手順でじっくりやること。
総合英語Forest/墺 タカユキ
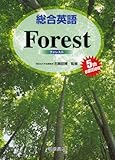
¥1,523
Amazon.co.jp
高認用としては、“全部やる”のではなく“確認する”ために使ってください。
“全部やる”のは、時間がある時に。
英単語イメージハンドブック/大西泰斗

¥1,890
Amazon.co.jp
正しい単語帳ではないし、文法書でもない――けれど、これを一通り読んでおくと少し“英語力”がつく。私が英語好きになる過程で読んだ本のひとつです。ただしある程度の文法知識は必要なので、オマケとして。
オマケと言えば、単語の覚え方でやっていることのひとつを。
・ホームセンターや文具店でノートサイズのホワイトボードを用意し、そこにデカデカと覚えたい単語を書く。語源などで色分けしてもいいが、一度に書くのは一つの単語のみ。
・じーっと見る。見て、網膜に焼き付ける。カメラのシャッターを押すような感覚を意識する。発音も同時にブツブツ呟く。動詞や名詞なら、その場面やモノ・匂い・音も想像する。が、実際に目に入るのはそのホワイトボードのみにし、実際に聞こえるのも自分の発音のみにする。
・消す
・もう一度書く(勿論、何も見ずに)
・もう一度じーっと見て、また消し、次の単語に移る。
最初は紙でやっていたが、もったいなくなったのとゴミが出て鬱陶しいのでホワイトボードにしました。単語帳がごちゃごちゃしていて覚えにくいと感じる人などはお試しあれ。
この方法が合っている場合、思い出そうとするとバ~ンとその単語が目の前に浮かぶようになります。コツは、一つの単語にあんまり時間をかけないことと、字を思いっきり書くこと。
英単語はゴロで、イメージで、語源で……一つの方法に囚われず、“憶えやすい方法”でとにかく憶えてしまうのがいいと思います。
あんまり単語ばっかりやるのはお勧めできませんが、単語の数・正確さが物を言うのも確かです。
↓高認関係のblogランキングです。(押すとこのblogへの応援になります)

にほんブログ村
【高卒認定一カ月勉強法:目次はこちら】
(関連記事:中学英語を完成させる)
高認の英語は、他の大半の教科と同じように“高校に入らないと習わない”ものの割合はそれほど高くありません。というより、ほとんどが中学英語です。
高認から大学受験をするための中学英語についてはこちらの記事で書いているので、参考にしてください。
◆単語?文法?
単語・熟語帳については、高校受験用のものでもこの時点では大丈夫です。レベル別の場合、難関校(高校のね)対策までやって下さい。
とにかく、いきなりDuoや速読などに手を出すのはお勧めしません。よほど潜在的な能力が高ければそうでもないのかもしれないけど……。
もちろん高校に直前まで通っていたりしてそれまで使用しているものがある人は、それを使ってください。
高認の英語は難しくないので、ある程度やってきている人なら大丈夫です。
単語を一気に覚える!のもいいですが、中学からの“文法”は本当に大切です。
単語そのものはあとからでもついてくるので、どっちから手をつけたらいいのかな?という人は、文法から始めてみてください。
◆試験問題に合わせた対策を
全てマーク式であり、日本語→英語の問題は今のところ出ていません。
なので必要な能力は“英語→日本語”“英語→英語”なんですね。
つまり、英文を読んで、内容を把握して、英語か日本語の選択肢を選ぶことが出来ればいいんです。
もちろん最終的にはこの程度ではだめなのだけれど、大学受験の準備として「高認の英語で100点を取る」を最初の目標にするのも良いです。
高認の試験問題は、以下のように構成されています。
1:強勢
会話の中で協調するべき語句(単語)を選びます。
会話文なので、前後の流れから想像することが重要です。
……ふつうに考えて、会話の中で協調する語句は「わたし」「あなた」「物」「場所」「あれ」「それ」などですよね。
be動詞や前置詞はよほど特殊な場合で無い限り選ばれません。選ばれるとしたら、かなり特殊な状況です。こういうのが高認で出てくることはあんまり無いです。
前置詞ってなあに?という状態なのであれば、まずは単語帳などよりも簡単な英文法の本をやってください。
会話文の中身はたまに難しい構文があったりもしますが、単語のレベルは基本的に平易(もちろん、中学校程度という意味での平易)です。
どうしても迷ったら、「主語になりえるもの」を選んでください。
配点も低い(計6点)ので、ここで時間を使うのはもったいないです。
2:会話文(文補充)
会話の流れを掴み、それに沿った文章を選択します。
これもまた易しいです。何せ簡単な順に問題が並んでいるので、設問2で難しいようでは不合格者続出、試験の意味がありません(高認は『落とす』試験ではありません)。
設問のところに(電話で)(店で)(電車で)などシチュエーションが書いてあるのと(英語ですが)、空欄の直前、直後が大きなヒントになります。もちろんそこだけでわからなければ、会話文をすべて読んでじっくり考えます。
ここは配点が少し多い(計20点)ので、取りこぼさないこと。
3:並び替え
いわゆる文法問題。
そこまで難しくないものの、全て合っていないと正解にならないので細かいミスが響きます。
ある程度文法を理解したり熟語・構文を覚えているのなら単純な暗記や消去法でも正解できるのですが、覚えていない・わからない場合は辛いと思います。
見ただけでフリーズしてしまうほどわからないなら、まだ設問3ですが、この問題は思い切って捨てて(適当に埋めて)次に行ってもいいかもしれません。
ここだけの対策をするのは漢字と同じようにコストパフォーマンスが悪い(配点も全て正解してやっと16点)ので、長文や会話文などにあたっている時に「どうしてこの順なのかな?」「このtheは何を指してるんだ?」「ここでのwhichの役割は何だろう?」など、“この文章が並べ替えで問われたらどうしよう?”を意識しながらやってください。
もちろん、基本の『文法』を疎かにしてはいけないのですが……。
4:内容把握
短めのメッセージ文があり、送り手(書き手)の意図に沿ったものを選択する問題です。
選択肢が日本語なので、先に読んでから本文を読む方法が有効です。
選択肢に含まれている単語を本文でみつけることが出来れば、そこまで複雑な内容ではないので全訳出来なくても答えることが出来ます。
5:空欄補充
少し文章量が増えてくるものの、(日本語にして考えると)内容はそこまで複雑ではないです。
というか、1問目は大抵空欄についてひたすら説明してあったりするボーナス問題なので落としようがないかもしれません(英語がメタメタな人も、ここだけは頑張ってください)。
4と同じく、多少わからない部分があっても文脈が把握できれば解答できる問題です。名詞だけでなく接続詞や前置詞も(かなり基本的なものですが)問われるので、前後の繋がりはどうなっているか、は意識してください。
6,7:長文読解
内容把握・文補充の長文版。グラフ問題が出てくることもあります。
過去問などで“グラフについての説明でよく使われる単語”はしっかりと覚えておくのも重要です。
エッセイや投書(投書は大抵何らかの意思をもって書かれている)の場合、やはり細かい部分よりも内容を把握することが重要です。配点もとても多いです。
長文問題に慣れていない場合、一番の敵は“パニック”です。
長い・疲れた・わからない……となっていき、一文一文取り出せば読めたはずの文章も読めなくなってしまいます。
なので、まずは一番短い“設問文”“選択肢”を読み、その部分が英語ならば一通り訳し(出来る範囲で)、それから長文を読んで下さい。
ひとつの設問ごとに訳して長文に戻るより、設問を一気に訳して(日本語のメモを書いておく)から読むこと。
ここまできたら残りの時間は全て長文に使っていいので、本文をじっくり訳しても大丈夫です。
“パニック”のせいで大きく読み間違えてしまうこともあるので、焦って解くよりは時間をかけたほうが確実です。
◆参考書、オマケ
以下は一応おススメと言える参考書・問題集です。好みが分かれる単語帳と高認用なんたらはあえて外してあります。
(中学英語を完成させるも参考にしてください)
とりあえず、参考書を選ぶ時気をつけたいのが、“基礎”は大ウソであることが多いということ。
「はじめから」「超基礎」「中学校から」のようなキーワードがついているものを選んでください。
大岩のいちばんはじめの英文法―大学受験英語 (東進ブックス―気鋭の講師シリーズ)/大岩 秀樹

¥1,260
Amazon.co.jp
定番本。
大学入試英語長文ハイパートレーニングレベル1 超基礎編/安河内 哲也

¥1,418
Amazon.co.jp
高認の長文にレベルが近い。
やるとなったら書いてある通りの手順でじっくりやること。
総合英語Forest/墺 タカユキ
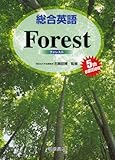
¥1,523
Amazon.co.jp
高認用としては、“全部やる”のではなく“確認する”ために使ってください。
“全部やる”のは、時間がある時に。
英単語イメージハンドブック/大西泰斗

¥1,890
Amazon.co.jp
正しい単語帳ではないし、文法書でもない――けれど、これを一通り読んでおくと少し“英語力”がつく。私が英語好きになる過程で読んだ本のひとつです。ただしある程度の文法知識は必要なので、オマケとして。
オマケと言えば、単語の覚え方でやっていることのひとつを。
・ホームセンターや文具店でノートサイズのホワイトボードを用意し、そこにデカデカと覚えたい単語を書く。語源などで色分けしてもいいが、一度に書くのは一つの単語のみ。
・じーっと見る。見て、網膜に焼き付ける。カメラのシャッターを押すような感覚を意識する。発音も同時にブツブツ呟く。動詞や名詞なら、その場面やモノ・匂い・音も想像する。が、実際に目に入るのはそのホワイトボードのみにし、実際に聞こえるのも自分の発音のみにする。
・消す
・もう一度書く(勿論、何も見ずに)
・もう一度じーっと見て、また消し、次の単語に移る。
最初は紙でやっていたが、もったいなくなったのとゴミが出て鬱陶しいのでホワイトボードにしました。単語帳がごちゃごちゃしていて覚えにくいと感じる人などはお試しあれ。
この方法が合っている場合、思い出そうとするとバ~ンとその単語が目の前に浮かぶようになります。コツは、一つの単語にあんまり時間をかけないことと、字を思いっきり書くこと。
英単語はゴロで、イメージで、語源で……一つの方法に囚われず、“憶えやすい方法”でとにかく憶えてしまうのがいいと思います。
あんまり単語ばっかりやるのはお勧めできませんが、単語の数・正確さが物を言うのも確かです。
↓高認関係のblogランキングです。(押すとこのblogへの応援になります)
にほんブログ村
【高卒認定一カ月勉強法:目次はこちら】