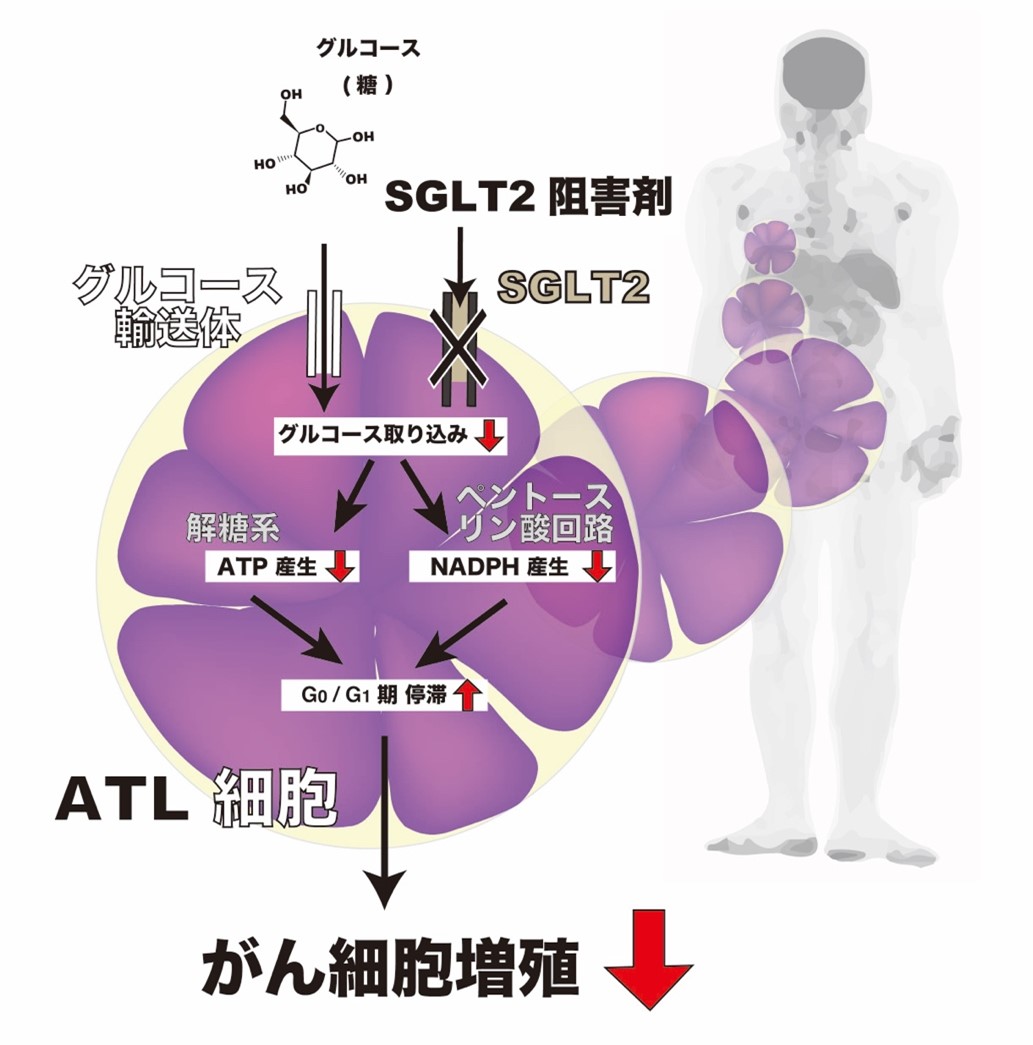私は来月で67歳になります。すでに世間一般では高齢者扱いとなり。いつ死んでもそれほどおかしくない歳です。二人の娘達もすでに独立し、夜ポツンと独りでいると、自分はこれまで何のために生きてきたのかな、などと思えてきます。ブログを書くことも虚しくなってきて、過去記事も大量に整理しました。もう完全に辞めようかとも思ったけど、どうせなら綺麗事ではなく、これまであまり触れなかった自分の本音を率直に書いてみようと思いました。
今から7年ほど前に、乳がん手術を終えたばかりのある女性が、私のブログによく来てくれました。そのころ彼女はまだ40代前半だったと思います。術後の経過はとても順調で、定期検査も毎回クリアして職場にも復帰し、私も安堵したものです。ところが手術から2年程過ぎた頃、彼女は風邪をひき、かなりこじらせてしまったのです。真面目な方だったので仕事も休まず無理したのでしょう。その風邪は一か月も長引き、さらに悪いことに続いてインフルエンザにも罹り、計2か月間も炎症状態が続いてしまったのです。するとそれまで順調だったはずのがんが肝臓や肺で突然再発し、すごい勢いで暴れ出し、最後は悲しい結果になってしまいました。せっかくあの時まで順調だったのに、なぜ急にあんなことになってしまったのか・・・私は長引いた風邪やインフルエンザか彼女の免疫状態を弱め、それまで抑えて込めていたがんが、いっきに噴き出してきたように思えてなりませんでした。もし、風邪のひき始めに大事を取って仕事を休んでいれば、あの時の再発はなかったのかもしれないのに・・と思うとすごく残念だったです。私が慢性炎症をできるだけ避けるように考えるようになったのはその頃からです。
私の職場には血液のがんで経過観察中の男性がいて、少し前に半年ごとの定期検査があったのです。ただタイミングが悪いことに、検査の数週間前に彼は風邪かコロナかわからない感染症で2週間ほど高熱が続き、仕事も休んだのです。彼は過去にきつい放射線治療も受けているので、感染症からの回復にも時間がかかるようです。ちょうどその頃、コロナに罹るとがんが再発しやすい、というニュースも流れたので、かなり気にしていたようです。でも私は彼に「2週間で治ったのならコロナだったとしても大丈夫だよ、一か月以上も長引いた場合がよくないんだよ」と言いました。そして検査の結果は予想通り全く問題なくクリアでした。私は彼に「言った通りだっただろう」というと彼は「そうですね」と答えました。彼は普段からとても御身大切にしていて、風邪などでもすぐに仕事を休むので、同僚からも評判が悪いようです。でもがん患者の場合は、そのくらい自分ファーストで良いのでしょう。
風邪やコロナを完全に防ぐことは無理です。でももし罹ってしまっても、早めに治せば免疫の疲弊(T細胞の機能低下)も起きないと思います。最近も次女の婿が職場でコロナを移され、次女の家族全員がコロナになったけど、一週間ほど職場を休んだら皆回復しました。味覚障害や嗅覚障害などの後遺症もないみたいです。喉の激しい痛みと回復には風邪より少し時間はかかるようですけど、後遺症の確率はかなり減ったようです。やはり慢性的な炎症を避けることがすごく重要と思います。