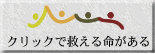今週は仕事に追われ、すっかりブログをさぼってしまいました。
新年句会に間に合うように…『漱石俳句かるた』を紹介しようと思っていたのに、まだ半ばです。
仕方ないので、ゆっくり紹介していきます。
そりばし ふよう かな
そ:反橋の小さく見ゆる芙蓉哉
An arch bridge
Looks smaller
Among the cotton roses.
明治29年、鏡子夫人を伴った北九州の旅の句。
前書は「大宰府天神」。
心字池に架かっている遠くの朱色の「反橋」と大きな花弁を持つ優雅な「芙蓉」との取り合わせが大宰府天満宮の美しくおごそかな境内の様子を表している。
季語「芙蓉」=秋
だいじじ さんもん あおた
た:大慈寺の山門長き青田かな
Along the long temple gate,
Far and wide spreads
A green rice field.
明治29年作。
熊本市南部にある曹洞宗の古刹大慈禅寺。
あたり一面の青田のなかに参道の長い「門」に焦点をあてることによって、「大慈寺」のたたずまいが見えてくる。「青田」の青と「山門」の色との対比も、「大慈寺」の風格あるさまをよく表現している。
季語「青田」=夏
ちくごじ
ち:筑後路や丸い山吹く春の風
The Chikugo route ―
Over the round hill,
Sprig wind.
明治30年、実家久留米に帰っていた親友菅虎雄(すがとらお)を見舞い、高良山(こうらやま)から発心公園(ほっしんこうえん)の桜を見学した折の作。
「丸い山」はやわらかな「春の風」が吹くのにふさわしく、この二語によって、山といってもそう高くない山が想像されて、筑後平野の風景の特色がみごとにとらえられている。
季語「春の風」=春
つ:月に行く漱石妻を忘れたり
Going up to the moon,
Soseki has forgotten
All about his wife.
明治30年作。
「妻を遺して独り肥後に下る」という前書によれば、「月に行く」は月の夜に熊本にもどるということである。月のあまりの美しさに妻を忘れてしまったという意味である。実際は流産した妻鏡子のことが気になっている句という。この逆説的な表現に、漱石の男のはにかみと“いき”あるさまが見られる。
季語「月」=秋
解説:永田満徳
英訳:西 忠温
男のはにかみ…言葉や態度と裏腹のちょっとした優しさ…。
こういうのっていいと思う。