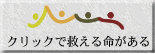日時 7月19日(土)
吟行地 館林市 田山花袋記念文学館
城沼(つつじが岡公園内)
句会場 日の出家(つつじが岡公園内)
参加者 9名
車を降りると、もやっと暑い空気に包まれた。これが館林の暑さである。いきなり気怠るさに襲われた。
―こんな暑い日に、よりによってこんな暑い街に来なくてもねぇ…。
この街にもう一度来ようと言った張本人が、こんなことを言う始末に、思わず笑みがこぼれたが、その笑い皺を伝って汗が流れた。
ここ数日の気温の上昇に、今日辺り「梅雨明け宣言」がでるだろうと朝のニュースで言っていたが、まだまだ湿った空気が立ち込めている。「風死す」…そんな季語がふとよぎった。
ともあれ、田山花袋記念文学館には冷房が効いており、館内に入るとほっとため息がこぼれたのだった。
田山花袋は、明治4年12月13日館林に生まれた。田山家は、旧館林藩主秋元家に仕える侍であり、その経緯もあり、少年時代から館林藩儒者吉田陋軒(ろうけん)に漢学を学んだ。こうして漢詩文などの文学に目覚めていったという。
壁に旧い館林のモノクローム写真のパネルが張られ、花袋の言葉が記されていた。
私の大きくなった町は平野の中の
摺鉢の底のような処にあった。
……(中略)
冬は赤城おろしが吹荒んで
日光連山の晴雪が
寒く街頭に光って見えた。
「幼き頃のスケッチ」より
ここ館林は、冬寒く風が吹き荒び、夏は暑く風も死する町なのだ。
風土的にも、関東平野の一角の摺鉢状の土地として、暑さで知られる埼玉の熊谷と気象的に似た条件になるのだろう。
花袋の文学は自然派に属する。『蒲団』では、明治後期の自由な空気に啓発された若い女性への主人公の赤裸々な感情が描かれている。訪れる前に読んでおいたが、当時の中年の…いわゆるオヤジの、純粋さは、ちょっとばかり呆れなくもないが、なかなか魅力的なものである。
『蒲団』口絵 小林鍾吉画(明治40年9月「新小説」)
こちらも応援クリック宜しくお願いします。