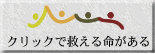今日も子規いろはかるたから…。
こ お こもり かたて
こ 子を負うて 子守まりつく 片手わざ 明治26年 新年
まりつきは、昔から正月の女の子の遊びで、丸めた綿を心にして、上を美しい色糸でかがった手まりを用いていました。手まり唄をうたいながら、上手に手まりをつく光景も、最近はあまり見かけませんが、みなさんはいかがでしょう。
えんばた つき む きゃく
え 縁端や 月に向いたる 客あるじ 明治25年 秋
俳句の世界では、単に「花」といえば桜の花をさし、春の季語、単に「月」といえば、秋の月をさし、秋の季語です。秋の夜、へやの明かりを消して、主人と客とが、ことば少なに縁端に座って、名月にじっと見とれているところでしょう。
て うち ほたるつめ ひかり
て 手の内に 螢冷たき 光かな 明治25年 夏
夏の夕暮れ時、清らかな小川のほとりで、笹やうちわを持って螢を追う―螢狩。みなさんは経験ありますか。捕えた螢を大切そうにやさしく手のひらに包み込んで、のぞいて見る青緑色のつめたい光。少年時代のすてきな経験です。
あか しろ みな
あ 赤きばら 白きばら皆 さみだるる 明治29年 夏
赤いばらも、白いばらも皆五月雨に打たれている、という意味でしょう。五月雨は、今の六月、つゆのころに降る雨のことです。この句をよむと、子規の弟子であった碧梧桐へきごとうの句、「赤い椿白い椿と落ちにけり」を思い出します。
さいせん お つばき
さ 賽銭の ひびきに落つる 椿かな 明治25年 春
いよずひこのみことじんじゃ
松山市の南の郊外にある伊予豆比古命神社は、一般には、椿神社と呼ばれ、旧暦一月八日の前後三日間行われるお祭りは、伊予三大祭りの一つで、「椿さん」と言って親しまれています。地元の人々は、「椿さん」が過ぎると暖かい春になると、そのお祭りを楽しみに待っているのです。
き だこ どうかんやま こ ゆ
き 切れ凧や 道灌山を 越えて行く 明治29年 春
道灌山は子規が住んでいた東京の根岸の近くにある小高い丘です。その山を糸の切れた凧が越えて行くのを見ての句でしょう。実はこの句の作られた前年の十二月、子規は後輩高浜虚子を誘って、この道灌山に上っています。その夏に病気が再発して、何度も血を吐き、自分の命の長くないことを感じていた子規は、自分のやりかけた俳句の仕事の後継者となってくれるように、この時虚子に頼んだのです。でも虚子は断わりました。子規は信じていたものに裏切られた絶望感におそわれながらも、命あるかぎり、ひとりでやろうと心に誓ったのです。そしてその年が明けて間もなくのころの、この句です。子規は切れ凧を見送りながら、虚子のことを考えていたのではないでしょうか。でも結果としては、虚子は子規の後をついで、俳句の仕事をりっぱに成し遂げています。
ゆ まち こうばいはや やどや
ゆ 温泉の町に 紅梅早き 宿屋かな 明治28年 春
一羽の白鷺が、傷ついた足をいやした伝えられる道後温泉は、歴史に残る日本最古の温泉で、今でも全国から数多くの観光客を集めています。明治31年、脊椎カリエスで寝たきりとなった子規は、「足なへの病いゆとふ伊予の湯に飛びても行かな鷺にあらませば」と歌にもよんで、二度と帰れぬ故郷の温泉のことを、せつないまでに思い浮かべています。
いっさくらい ぞうにもち
め めでたさも 一茶位や 雑煮餅 明治31年 新年
江戸時代の俳人小林一茶の句、「めでたさも中位なりおらが春」をふまえての作です。子規はこの年、新聞「日本」の文化欄担当の記者として月給四十円をもらっています。生活は母と妹の三人暮らしですが、自分の病気の薬代などに出費がかさんで、決して楽ではなかったようです。正月の祝いの雑煮餅を前にして、一茶の句をふと思い出したのでしょう。
解説は市村通泰氏のものをそのまま掲載させて頂いてます。
「こ」の句、片手でおんぶした赤子を支え、もう片手で手毬をする女の子の「わざ」を見事に描いてると思います。俳句は写生の「目」を養う…ここに句を作る一歩があります。ちょうど写真家が一瞬の美しい光景を撮影するように、言葉で描き取るのが俳句なのです。
こちらもクリックしていただけると励みになります