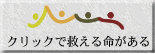そう いちど こども
れ れんげ草 われも一度は 子供なり 明治24年 春
春の田一面に咲いているれんげ草。暖かい春の日ざしの中で、手に持ちきれないほどたくさん摘んで、首飾りなどを作って遊んでいる子供たちを見て、子規も幼い時、それを摘んで、女の子にあげたことなど、懐かしく思い出したのでしょう。
そうせき き きょし き おおみそか
そ 漱石が来て 虚子が来て 大三十日 明治28年 冬
「坊ちゃん」や「吾輩は猫である」など数多くの小説を書いた明治の文豪夏目漱石は、子規にとって最も親しい友人の一人でした。また高浜虚子は、子規と同じ松山の出身で、子規に俳句を学び、病気の子規の世話をよくし、子規亡きあと、日本の俳句文学の世界でりっぱな仕事をした人です。この明治28年、漱石は、子規・虚子のふるさと松山の中学校で英語の教師をしており、まだ全く無名の人だったのです。
もの く ひるげ
つ つばくろの 物くわえ来る 昼食かな 明治31年 春
つばくろは、つばめのこと。つばくら、つばくらめとも呼ばれています。春、南の国から渡って来て、秋に帰ってゆきます。つばめの姿を見かけるようになると暖かくなった証拠で、俳句では春の季語です。「ひるげ」というのは、昼の食事のことです。みなさんの町でも、暖かくなったら、つばめの姿に注意してみてください。
ふみよ ひと はる くさ
ね ねころんで 書読む人や 春の草 明治18年 春
かんざんらくぼく
「寒山落木」という子規の句集は、明治18年から始まり、この句はその三句目のものです。子規はこのころから俳句を作り始め、三十六歳で亡くなるまで、実に二万三千程の句を残しています。いちばんたくさん作った年は、明治26年で、約四千八百句、一日平均十三句になります。自然の風景をただぼんやりながめていたのでは、俳句は生れてこないのです。
なつくさ ひととお
な 夏草や ベースボールの 人遠し 明治31年 夏
子規は、二十歳前後の頃、ベースボール(野球)に熱中し、随筆や短歌の中でも野球のことを書いています。四国松山に初めてベースボールを紹介したのも子規だと言われています。この句は、子規三十二歳の時、病床にあったころの作品ですから、「人遠し」ということばの中に、自らグラブを手にすることのできないさびしさが感じられます。
らん か おんなしうた し とうは
ら 蘭の香や 女詩歌う 詩は東坡 明治28年 秋
これは、子規が日清戦争の従軍記者として滞在していた時に見た光景でしょう。どこからとも知
れず蘭の花の香が漂って来る中で、中国の女性が漢詩を朗読している。その詩は蘇東坡(そとうは)という有名な詩人の詩なのです。もちろん耳馴れない中国語でうたわれ、子規は日本を遠く離れて、いかにも今、中国にいるのだという気分を強く味わったのでしょう。
むぎ きたとべやま
む 麦まきや 北砥部山の ふもとまで 明治28年 冬
松山の城山から、南の方を眺めると、石手川の松並木の堤防が東西に走り、そのずっと南に砥部焼で有名な砥部の山脈が、四国山脈に一段低く連なっているのが見渡せます。その砥部山の麓まで、今は住宅が建て混んでいますが、昔は、石手川から南は、田畑が一面に広がっていました。麦まきは冬の季語。初冬の風景です。
ひとみ なら か こ
う うっとりと 人見る 奈良の 鹿の子かな 明治28年 夏
鹿は秋の季語ですが、鹿の子(子鹿)は夏の季語です。奈良では、古いお寺の境内などに、たくさんの鹿が放し飼いにされていて、観光客にも人なつっこく近づいてきます。白い斑点のある子鹿が、やさしく澄んだ瞳で人を見上げている姿。静かで落ち着いた古都奈良の、夏の木立の下、暑さを忘れ、時間を忘れてたたずんでみたいものですね。
解説は、市村通泰氏のものをそのまま掲載させていただきました。
「ね」の句の解説…自分、まだまだ努力不足で脱帽です。