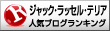だんだん日が長くなってきて、帰宅してもまだ明るかったので、久しぶりに平日夕方ドッグランに行ってみました。
週末は遠方から来る人が多く、残念ながらマナーの悪い飼い主が多いのですが、平日の夕方はほぼ常連さんなので安心して使えます。お話しながらも自分の犬から目を離すことはないし、犬たちが結構激しい遊びをしていても、止めた方がいいんじゃない?と思うイジメに発展することはありません。もしそんな雰囲気が感じられたら、すぐに飼い主さんが介入するからです。
週末のドッグランで、よく目にする、介入が必要と思われる犬の関わりを見ても飼い主が何もしないのは、多分犬の遊びスタイルを理解していないのだと思います。たまに来るドッグラン以外では、あまり他犬に関わることもなく、飼い主も犬も経験不足と言ったところでしょうか?
平日毎日のようにドッグランを利用する飼い主さんと犬は、経験からどれが健康的な遊びのスタイルかをなんとなくわかっているのだと思います。
私が注目するのは以下の4項目。遊びに参加している犬がお互いに対等に楽しく遊んでいることを確認するのに役に立ちます。
1.「これは遊びです」を示すボディランゲージ
遊びのお辞儀(プレイバウ)、弾むような動き、非効率的な動き、ニヤリと笑うような間抜けな表情をする遊びの顔が観察されます。
2. 定期的に変化する遊びスタイル
バランスの取れた遊びは、単なる遊びであることを伝えるためのボディランゲージで定期的に中断されるます。例えば、追いかけっこから、地面を転げ回るような遊びをするような変化をいいます。固執した一つの活動が一定時間続いている時は、それはもう遊びでない可能性があるので、一旦遊びを中断します(飼い主の介入)。
3. 逆転する役割
良い遊び仲間の間では、しばしば役割が逆転することがあります。ある犬は追いかけ、その後追いかけられ役になることがあります。レスリングでは、ある時は上にある時は下に、逆転が起こります。犬同士が遊ぶとき、常に完璧な役割の逆転があるわけではありません。レスリングで下になることを好む犬もいれば、追いかけられる側になることを好む犬もいる。それぞれの犬が自分の役割を楽しんでいるか、率先してその役割を演じているかよく観察する必要があります。
4. セルフハンディーキャップ
犬同士が健康的に遊ぶときは、遊び仲間を傷つけないように力の加減をします。あえて自らハンディーキャップを課するのです。上手に遊ぶ犬は、噛む、体をぶつけるなどの行動は、遊びを続けられるように自分でコントロールし、相手に害を与えることはありません。
やっぱり何より大事なのは、飼い主が自分の犬をしっかり観察して正しく判断すること。よく出くわすのが、犬が悲鳴をあげているのに「これもお勉強ですから」と大きな勘違いをしている人。
愛犬の苦悩が見えない飼い主にはなりたくないですよね![]()
いつもご愛読ありがとうございます。
訪問の印にポチッ![]() とお願いします!
とお願いします!