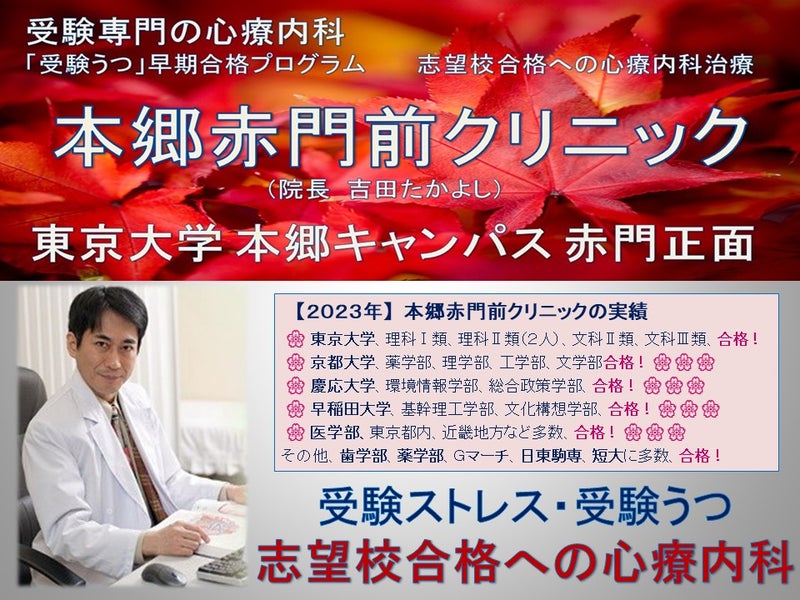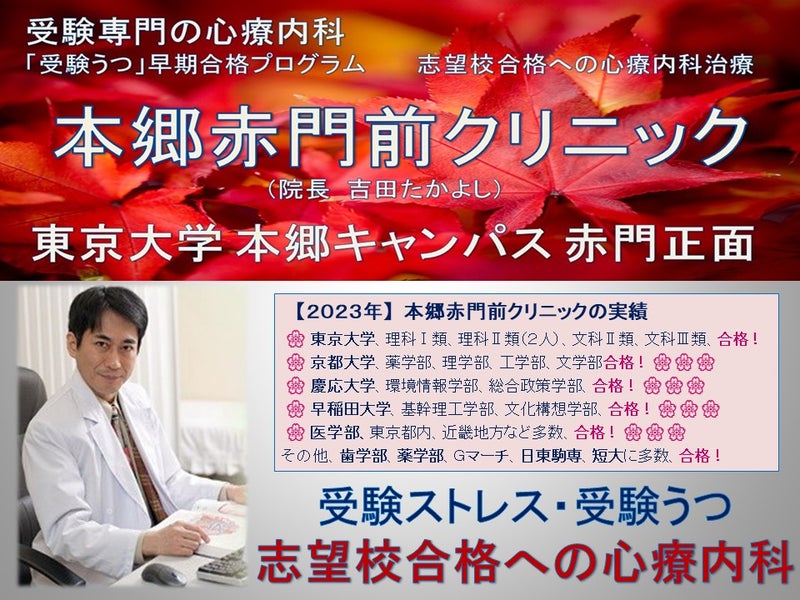受験の心療内科
不安感で脳の活動が高まる?メンタル医学で合格を勝ち取る方法

入試は合格する人と不合格になる人と、はっきりと結果に差が出るという厳しいものですので、多くの受験生が不安を感じて苦しい気分になってしまいます。
ただし、脳医学の上からは、合格を勝ち取る上で、不安が一概に悪い感情だとはいえません。
実は、認知機能を一時的に高める、つまり頭をよくするようなホルモンの状態になっている「良い不安」もあるのです。
その一方で、認知機能を低下させる、つまり頭を悪くするようなホルモンの状態になっている「悪い不安」ももちろんあります。
当然、志望校への合格を勝ち取るための対策も、この2種類のどちらであるのかで異なってきます。
受験生が合格を勝ち取るためには、ご自分が抱えている精神状態が、「良い不安」なのか「悪い不安」なのかを医学的に正しく見極めることが大事なのです。
入試に受かる「良い不安」と、入試に落ちる「悪い不安」は、具体的には何が違うのか?
それぞれ、志望校に合格するには、受験生は何を行えばいいのか?
受験生を志望校へ合格させることを専門に診療している心療内科医としての経験と専門知識をもとに、わかりますく解説します!


不安で低下する脳の5つの能力とは?
受験勉強を続ける中で、ほぼすべての受験生が、心の中で不安感と戦っていることでしょう。
不安感が一定限度に抑えられていればいいのですが、「不安で頭がいっぱい・・・」という受験生は、脳がとっても危険な状態です。
脳内で不安感が高まると、それに連動して、
①記銘力(新しいことを覚える力)
②想起力(記憶を思い出す力)
③論理的思考力
④創造力
⑤想像力
以上の5つの能力が低下することが、脳医学の研究で解明されているのです。
これらは、すべて入試を突破するのに不可欠な能力ですよね。
つまり、本当は合格するだけの学力がある受験生であっても、落ちるかもしれないという不安感が大きくなりすぎると、それによって本当に落ちるという現実を生み出してしまうということです。
これが、入試に落ちる「悪い不安」です。
もちろん、不安な受験生が、みんな落ちるわけではありません。
メンタル医学の上で大事なのは、「単なる心理的な不安」と、問題を解くための脳の機能が低下した状態で起こる「入試に落ちてしまう危険な受験不安」とをしっかりと区別することです。
合格を勝ち取るには、ぜひ、この違いを踏まえた上で、ご自分のメンタルの状態をチェックしていただきたいのです。
「単なる心理的な不安」は、本人にとっては辛いものですが、緊張感が脳を刺激し、情報処理のスピードが速くなるという側面もあります。
そのため、試験で点数を稼ぐには、メリットとデメリットが、けっこう微妙です。
少なくとも、不安感を自分でコントロールできている場合、具体的にいうと、「不安だからもっと頑張ろう」というポジティブなメンタルへの昇華ができている場合は、脳内で、デヒドロエピアンドロステロンといった脳の認知機能を高める物質が出てくれます。
そのため、不安感なしに、単なる穏やかな心理で受験する場合より、試験の点数はアップするわけです。
これが、むしろ入試に有利に働く「良い不安」なのです。
注意していただきたいのは、「入試に落ちてしまう危険な受験不安」です。
こちらは、コルチゾールなどストレス系の悪影響を脳や身体に及ぼすホルモンが増加します。
その影響もあり、脳内で理性を生み出す前頭前野の機能が低下してしまうために、大脳辺縁系が生み出す本能的な感情をコントロールできなくなって、入試に対する不安感が暴走する状態です。
不安感だけでも嫌なものですが、本当に怖いのは、前頭前野の機能が悪化しているため、先ほどご紹介した脳の5つの能力、つまり、①記銘力(新しいことを覚える力)、②想起力(記憶を思い出す力)、③論理的思考力、④創造力、⑤想像力が低下してしまうことです。
実際、模擬試験でこのような現象が生じ、思うように点数が取れなかった受験生も多かったはずです。
特に、応用問題は、②想起力(記憶を思い出す力)、③論理的思考力、④創造力を高度に使って、粘り強くじっくり考えて解かないと正解を出せないため、致命的な得点ダウンになってしまいます。
また、ケアレスミスを見つけだすのも前頭前野の機能を使いますので、本人はできたつもりでも、実はケアレスミスを連発していて、不合格になることも多いのです。
合格を勝ち取るには、「単なる心理的な不安」と「入試に落ちてしまう危険な受験不安」のどちらであるかを見極める必要があります。
私のクリニックのホームページの中で、「受験の不安」のページで、ご自分でセルフチェックができるように、くわしく症状を解説しています。
ぜひ、ご覧ください。
例のごとく、ページの冒頭だけ、こちらのブログでもご紹介しておきます。
興味のある方はホームページを見てください!
https://www.akamon-clinic.com/受験の不安/

✓ 「受験不安症(Exam anxiety disorder)」とは、入試や勉強に対する不安感が高まり、自分の理性でコントロールができなくなる精神障害です。
✓ 受験に対する精神的ストレスと勉強による脳疲労が脳内で化学反応を起こす結果、「受験不安症」が生じます。
✓ 「受験不安症」を発症すると、脳内で原始的な感情を作り出す扁桃体が過剰に刺激を受けるため、不安感の膨張だけにとどまらず、集中力、ヤル気、思考力など勉強をするための脳の認知機能の低下も生じます。
✓ 一般的な単なる受験や勉強の不安と、対処が必要な「受験不安症」の見極めが重要で、どなたもセルフチェックができる一覧表を掲載しています。
✓ 「受験不安症」の場合は、成績悪化が学力の低下によるものではないので、きちんと治療すれば、短期間のうちに成績が大幅に回復し、志望校への合格に直結します。
✓ 志望校への合格を勝ち取るため、ご自分でできる対策も解説します。
「受験不安症(Exam anxiety disorder)」とは
「受験不安症(Exam anxiety disorder)」とは、受験生が入試や試験に臨む際に過剰な不安や緊張を感じ、それを自分の理性で制御できなくなることが特徴の精神障害です。
受験生自身は集中力を高めて勉強に取り組みたいという意欲を持っているにも関わらず、その意志とは裏腹に、暴走する不安感のために勉強が進まず、それに対する焦燥感から、さらに症状が悪化する傾向があります。
また、「受験不安症」は試験が近づくにつれて悪化し、試験当日には身体的な症状やパニック症状が現れることが一般的です。
試験前には、頭痛、吐き気、嘔吐、めまい、動悸、息切れ、手足の震え、過剰な汗などの身体的な症状が現れることがあります。
また、パニック症状として、不安感や恐怖感、現実感喪失、過呼吸、胸痛、動悸、手足のしびれ感、発汗、吐き気、嘔吐などがあらわれることがあります。
続きを読む ⇒クリック!
https://www.akamon-clinic.com/受験の不安/