2012年
76冊目
「写楽 閉じた国の幻」
島田荘司
新潮社
- 写楽 閉じた国の幻/新潮社
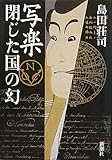
- ¥2,700
- Amazon.co.jp
わずか十ヵ月間の活躍、突然の消息不明。
写楽を知る同時代の絵師、版元の不可解な沈黙。
錯綜する諸説、乱立する矛盾。
歴史の点と線をつなぎ浮上する謎の言葉「命須照」、
見過ごされてきた「日記」、
辿り着いた古びた墓石。
史実と虚構のモザイクが完成する時、
美術史上最大の迷宮事件の「真犯人」が姿を現す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
に せ ん じ ゅ う に ね ん
とはいかなることか。
と思われるお歴々もあるかとは存じますが、
まあ、察してください。
しかし、2012年かぁ。
まだ、普通に記事更新してた頃だなぁ。
年、とったな・・・
いろいろ、変わっちまったな・・・
なんて遠い目をしてしまうほどではあるのですが、
涙をぬぐって(泣くほどだったのか・・・)
頑張って記事更新していきたいと思います。
ちなみに感想を書かなければならない本の
残数でも泣きそうです。
というか号泣です。
さて。
あらすじからも分かるように、この本のテーマは
「東州斎写楽とは何者だったのか」
です。
しかし、冒頭は現代日本。
語り部である美術史家(だったと思う。記憶が曖昧。
だって読んだのにせんじゅうn・・・もういいですかそうですか)
が小学生の息子と遊びに出掛けた際、
駐車場所を探す父と別行動をとった息子が
事故死してしまうところから始まります。
その後、事故の過失を巡って
なんやかんやあるのですが、
途中で舞台は江戸時代へと遡り、
蔦屋重三郎視点での物語へと転換。
当時の出版界のルールや時代背景なんかを
物語の流れとともに分かりやすく説明しながら、
様々な文献を提示し、
写楽が誰であったのかが語られていきます。
まあ正直言うと、ありえない話だとは思うんですが、
写楽を取り巻く不可解な事象や、
考証に使われた文献に残る記録が、
この説とうまい具合に符合するのも事実。
ありえないありえない、と否定していながら
ひょっとして、と思わせてもくれました。
このような証明の仕方は、
まさしく本格ミステリのよう。
流石は島田御大だなと言う感じです。
ただ。
流れ上端折ってしまいましたが、
美術史家の元に作者不明の肉筆画が送られてきて、
誰の作なのかを調査するのが現代パート。
蔦屋の視点で写楽の活躍を描くのが江戸時代パート。
こんな風にふたつの物語が交互に語られ、
筆者は島田荘司。
脳裏には、様々な名作が浮かび上がります。
徐々にふたつの物語が絡まり合っていき、
現代日本パートでも驚天動地の新事実!
肉筆画は誰のもの?
ひょっとして事故とも何か関わりが?
すべては繋がっていたのだ!
という流れを期待していたのですが、そうでもなく。
ある意味では逆に驚天動地でしたが・・・。
ただ、巻末あとがきによると、
本当はこの倍の分量ぐらいあったのに
出版社的に長すぎてムリと言われた、
という経緯があり、
続編の構想もあるそうなので、
期待して待ちたいと思います。
島田御大の推理小説だ!
と思って読むとがっかりするかも。
どっちかというと、
島田御大の研究発表・物語仕立て
という感じです。
歴史好きには良いと思いますです。